複数辞典一括検索+![]()
![]()
こ【子・児】🔗⭐🔉
こ 【子・児】
■一■ [0] (名)
(1)人間や動物から,生まれ出るもの。特に,生まれ出て間もないもの。
⇔親
「―を生む」「腹に―を持った鮭」「犬の―」
〔動物の場合「仔」とも書く〕
(2)まだ一人前になっていない人間。年少の男女。「都会の―は体力が劣る」「小さな女の―」
(3)両親の間に生まれた人。また,縁組により,その間に生まれたものと同じように養われている人。
⇔親
「―を思う親の心」「伯父夫婦の―になる」
(4)(親しみの気持ちで)若い女性をいう語。芸子をさす場合もある。「会社の女の―」「あの店はいい―がそろっている」
(5)キリスト教で,キリストのこと。みこ。
(6)もととなるものから分かれ出たもの。また,従属的なもの。「竹の―」「元も―もない」「―会社」
(7)愛する人。また,親しみを感ずる人。「はしきやし逢はぬ―故にいたづらに宇治川の瀬に裳裾濡らしつ/万葉 2429」「熊白檮(クマカシ)が葉を髻華(ウズ)に挿せその―/古事記(中)」
(8)鳥の卵。「あてなるもの…かりの―/枕草子 42」
■二■ (接尾)
上の語との間に促音が入ることもある。
(1)名詞や動詞の連用形に付いて,その仕事をしている人,そのことに当たる人,そのような状態の人,そのためのものなどの意を表す。「売り―」「売れっ―」「馬―」「振り―」「背負(シヨイ)―」
(2)特に女性のする動作や仕事に付けて,それをする人が若い娘であることを表す。「踊り―」「お針―」
(3)名詞に付いて,そのような状態・性質の子供である意を表す。「ひとりっ―」「いじめっ―」「だだっ―」
(4)小さなものに付けて,愛称とする。「ひよ―」「ひよっ―」「砂―」
(5)その場所や時代に生まれ育った人であることを表す。「江戸っ―」「団地っ―」「大正っ―」
(6)女性の名に付けて,それが女子であることを表す。平安時代以降,明治の頃までは身分の高い女性の名に用いた。「花―」「春―」
(7)人に対する親愛の気持ちを表す。古く人名や人を表す語に付けて,男女ともに用いた。「小野妹―」「我妹(ワギモ)―」「背―」
こ-くじら【小鯨・児鯨】🔗⭐🔉
こ-くじら ―クヂラ [2] 【小鯨・児鯨】
コククジラの別名。
こじま【児島】🔗⭐🔉
こじま 【児島】
岡山県倉敷市南部の地名。児島半島南西部を占める。南端の下津井は中世からの瀬戸内海の要港。学生服・ジーンズなど,縫製工業と,かつての製塩で知られる。
こじま-わん【児島湾】🔗⭐🔉
こじま-わん 【児島湾】
児島半島に抱かれた内湾。近世以降干拓が行われ,大部分が陸地化。
こじま【児島】🔗⭐🔉
こじま 【児島】
姓氏の一。
こじま-いけん【児島惟謙】🔗⭐🔉
こじま-いけん ― ケン 【児島惟謙】
(1837-1908) 明治時代の裁判官。宇和島藩出身。大審院長の時ロシア皇太子ニコライが襲われた大津事件の裁判にあたり,犯人津田三蔵の死刑を要求する政府の圧力をしりぞけて無期徒刑とし,司法権の独立を守った。
ケン 【児島惟謙】
(1837-1908) 明治時代の裁判官。宇和島藩出身。大審院長の時ロシア皇太子ニコライが襲われた大津事件の裁判にあたり,犯人津田三蔵の死刑を要求する政府の圧力をしりぞけて無期徒刑とし,司法権の独立を守った。
 ケン 【児島惟謙】
(1837-1908) 明治時代の裁判官。宇和島藩出身。大審院長の時ロシア皇太子ニコライが襲われた大津事件の裁判にあたり,犯人津田三蔵の死刑を要求する政府の圧力をしりぞけて無期徒刑とし,司法権の独立を守った。
ケン 【児島惟謙】
(1837-1908) 明治時代の裁判官。宇和島藩出身。大審院長の時ロシア皇太子ニコライが襲われた大津事件の裁判にあたり,犯人津田三蔵の死刑を要求する政府の圧力をしりぞけて無期徒刑とし,司法権の独立を守った。
こじま-きくお【児島喜久雄】🔗⭐🔉
こじま-きくお ―キクヲ 【児島喜久雄】
(1887-1950) 美術史家。東京生まれ。学習院・東北大・東大教授。主著「レオナルド研究」
こじま-ぜんざぶろう【児島善三郎】🔗⭐🔉
こじま-ぜんざぶろう ―ゼンザブラウ 【児島善三郎】
(1893-1962) 洋画家。福岡県生まれ。岡田三郎助に学ぶ。フォービスムの手法に日本画の装飾を加えた作品を描いた。代表作「アルプスへの道」
こじま-たかのり【児島高徳】🔗⭐🔉
こじま-たかのり 【児島高徳】
南北朝時代の武将。通称備後三郎。備前の人。「太平記」によれば,隠岐遷幸途中の後醍醐天皇を奪回しようとして失敗,天皇の宿所の桜木を削り「天莫 空
空 勾践
勾践 ,時非
,時非 無
無 范蠡
范蠡 」と記してその志を告げたという。天皇の隠岐脱出後,参陣。建武政権崩壊後も南朝方として各地を転戦。生没年未詳。
」と記してその志を告げたという。天皇の隠岐脱出後,参陣。建武政権崩壊後も南朝方として各地を転戦。生没年未詳。
 空
空 勾践
勾践 ,時非
,時非 無
無 范蠡
范蠡 」と記してその志を告げたという。天皇の隠岐脱出後,参陣。建武政権崩壊後も南朝方として各地を転戦。生没年未詳。
」と記してその志を告げたという。天皇の隠岐脱出後,参陣。建武政権崩壊後も南朝方として各地を転戦。生没年未詳。
こじま-とらじろう【児島虎次郎】🔗⭐🔉
こじま-とらじろう ―トラジラウ 【児島虎次郎】
(1881-1929) 洋画家。岡山県生まれ。印象派の画風を示し,「ベゴニヤの畠」「酒津の秋」などの作品を残す。大原孫三郎の委嘱を受けて渡欧,のちに大原美術館の基礎となる作品を収集した。
こだま【児玉】🔗⭐🔉
こだま 【児玉】
埼玉県北西部,児玉郡の町。鎌倉街道の宿場町・市場町として発展。塙(ハナワ)保己一(ホキイチ)の生地。
こだま【児玉】🔗⭐🔉
こだま 【児玉】
姓氏の一。
こだま-かがい【児玉花外】🔗⭐🔉
こだま-かがい ―クワグワイ 【児玉花外】
(1874-1943) 詩人。京都生まれ。本名,伝八。東京専門学校中退。キリスト教社会主義の立場から,「社会主義詩集」を発表,発売禁止となる。他に「花外詩集」「ゆく雲」など。
こだま-げんたろう【児玉源太郎】🔗⭐🔉
こだま-げんたろう ―ゲンタラウ 【児玉源太郎】
(1852-1906) 軍人。徳山藩出身。陸軍大将。陸軍大学校長・台湾総督・陸相などを経て,日露戦争の満州軍総参謀長。のち参謀総長となる。
このて-がしわ【児手柏・側柏】🔗⭐🔉
このて-がしわ ―ガシハ [4] 【児手柏・側柏】
ヒノキ科の常緑針葉小高木。中国原産。渡来は古く,庭園などに栽植する。枝は平らに分枝しててのひらを立てたように並び,裏表の区別がない鱗片葉を互生。先のとがった鱗片数対から成る球果をつける。漢方で葉と仁を薬に用いる。
児手柏
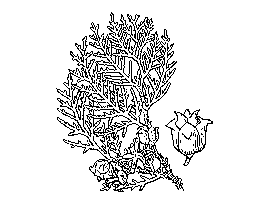 [図]
[図]
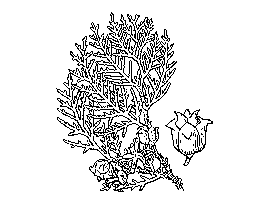 [図]
[図]
このてがしわ=のふた面(オモテ)🔗⭐🔉
――のふた面(オモテ)
〔コノテガシワの葉が表裏定めがたいことから〕
物事に両面あって,いずれとも定めがたいこと。「―,儘ならぬこそ恨みなれ/浄瑠璃・廿四孝」
こ-ら【子等・児等】🔗⭐🔉
こ-ら [1] 【子等・児等】
(1)子供たち。
(2)人を親しみをこめて呼んだ語。男女ともに用いたが,多くは男性から若い女性に対して用いた。「秋山のしたへる妹なよ竹のとをよる―は/万葉 217」
じ【児】🔗⭐🔉
じ [1] 【児】 (代)
一人称。親などに対して子供が自分のことをいう語。わたくし。「―は不幸にして未だ良師を得ません/魚玄機(鴎外)」
じ-ぎ【児戯】🔗⭐🔉
じ-ぎ [1] 【児戯】
子供の遊び。また,たわいないことにいう。
じぎ=に等し・い🔗⭐🔉
――に等し・い
たわいもないこと,価値のないことにいう語。児戯に類する。「―・い論評」
じ-し【児子】🔗⭐🔉
じ-し [1] 【児子】
子供。小児。
じ-じょ【児女】🔗⭐🔉
じ-じょ ―ヂヨ [1] 【児女】
(1)女の子。
(2)女子と子供。おんなこども。
(3)男の子と女の子。
じじょえいゆうでん【児女英雄伝】🔗⭐🔉
じじょえいゆうでん ジヂヨ― 【児女英雄伝】
中国,清代の白話体章回小説。文康作。四一回。1878年刊。侠女十三妹の活躍を描く。北京語で書かれる。別名「金玉縁」「日下親書」など。
じ-そん【児孫】🔗⭐🔉
じ-そん [1] 【児孫】
子供と孫。子孫。
じそん=のために美田(ビデン)を買わず🔗⭐🔉
――のために美田(ビデン)を買わず
〔西郷隆盛の詩にある言葉〕
子孫に財産を残すと,それに依存して安逸な生き方をするので,財産を残さない。
じ-どう【児童】🔗⭐🔉
じ-どう [1] 【児童】
身体・精神ともにまだ十分に発達していない者。普通,小学校に在学する者をさすが,児童福祉法では一八歳未満の者をいう。
じどう-いいん【児童委員】🔗⭐🔉
じどう-いいん ―
 ン [4] 【児童委員】
児童の生活環境の改善・福祉・保健など,児童福祉に関する援助・指導を行う民間奉仕者。厚生大臣より委嘱され,民生委員がこれを兼ねる。
ン [4] 【児童委員】
児童の生活環境の改善・福祉・保健など,児童福祉に関する援助・指導を行う民間奉仕者。厚生大臣より委嘱され,民生委員がこれを兼ねる。

 ン [4] 【児童委員】
児童の生活環境の改善・福祉・保健など,児童福祉に関する援助・指導を行う民間奉仕者。厚生大臣より委嘱され,民生委員がこれを兼ねる。
ン [4] 【児童委員】
児童の生活環境の改善・福祉・保健など,児童福祉に関する援助・指導を行う民間奉仕者。厚生大臣より委嘱され,民生委員がこれを兼ねる。
じどう-が【児童画】🔗⭐🔉
じどう-が ―グワ [0] 【児童画】
幼児・児童が描(カ)く絵画。
じどう-かん【児童館】🔗⭐🔉
じどう-かん ―クワン [2] 【児童館】
児童福祉法に基づく施設の一。学校外の教育機関として主として都市部に住む子供の健康増進を目的とし,児童厚生員の配置が義務づけられている。
じどう-き【児童期】🔗⭐🔉
じどう-き [2] 【児童期】
幼年期と青年期の間にあたる六,七歳から一二,三歳までの時期。後期には抽象的思考が可能となるなど知的発達が著しく,集団的行動をすることにより社会性も増大する。
じどう-ぎゃくたい-ぼうしほう【児童虐待防止法】🔗⭐🔉
じどう-ぎゃくたい-ぼうしほう ―バウシハフ 【児童虐待防止法】
一四歳未満の被虐待児童を保護・救済するための法律。地方長官による保護者に対する訓戒,諸施設への児童委託,また軽業・曲芸・芸妓(ゲイギ)の禁止などを規定。1933年(昭和8)制定。47年の児童福祉法に吸収。
じどう-げき【児童劇】🔗⭐🔉
じどう-げき [2] 【児童劇】
(1)児童が演ずる劇。自発的創造的な演劇活動を通して児童の人間形成に役立てようとするもの。欧米では一七世紀頃,日本では1921年(大正10)坪内逍遥が提唱。学校劇。
(2)児童を観客対象とする劇。
じどう-けんしょう【児童憲章】🔗⭐🔉
じどう-けんしょう ―シヤウ 【児童憲章】
児童に対する正しい観念を確立し,すべての児童の幸福と,よい環境の中で健全な成長を図るために定められた規定。児童福祉政策の根本理念を示すもの。1951年(昭和26)制定。
じどう-こうえん【児童公園】🔗⭐🔉
じどう-こうえん ― ン [4] 【児童公園】
都市公園法に基づき,児童の遊び・スポーツなどに供する公園施設。
ン [4] 【児童公園】
都市公園法に基づき,児童の遊び・スポーツなどに供する公園施設。
 ン [4] 【児童公園】
都市公園法に基づき,児童の遊び・スポーツなどに供する公園施設。
ン [4] 【児童公園】
都市公園法に基づき,児童の遊び・スポーツなどに供する公園施設。
じどう-しんりがく【児童心理学】🔗⭐🔉
じどう-しんりがく [6] 【児童心理学】
発達心理学の一分野。狭義には学童期の子供を,広義には出生から児童期終了までの子供を対象に,その知能・情緒・社会性などの発達過程を研究対象とする心理学。
じどう-そうだんじょ【児童相談所】🔗⭐🔉
じどう-そうだんじょ ―サウダン― [0][8] 【児童相談所】
児童の福祉増進のため,児童福祉法に基づいて都道府県に設置される機関。児童の生活全般に関して保護者や学校からの相談に応じ,児童や家庭について調査や判定を行なって,必要な指導や措置をとる。
じどう-ちゅうしん-しゅぎ【児童中心主義】🔗⭐🔉
じどう-ちゅうしん-しゅぎ [8] 【児童中心主義】
児童の人格を尊重し,内的成長力を信頼して,教育の目的・内容・方法を児童の立場に立って決めようとする考え方。二〇世紀前半における新教育運動の理論的基礎をなした。
じどう-てあて【児童手当】🔗⭐🔉
じどう-てあて [4] 【児童手当】
児童の養育にともなう家計負担の軽減を目的に国が支給する手当。児童の数・年齢および養育者の所得が給付要件となる。
じどう-の-けんり-じょうやく【児童の権利条約】🔗⭐🔉
じどう-の-けんり-じょうやく ―デウヤク 【児童の権利条約】
正式名称は「児童の権利に関する条約」。一八歳未満の子供を,保護の対象としてのみならず,権利の主体としてとらえ,具体的な権利内容を総合的に規定した条約。1989年国連総会で採択。日本は94年(平成6)承認,発効。通称「子どもの権利条約」。
じどう-ふくし-し【児童福祉司】🔗⭐🔉
じどう-ふくし-し [6] 【児童福祉司】
児童福祉法に基づき,児童および妊産婦の保護・保健その他福祉に関する事項について相談に応じ,必要な指導を行うなど,その福祉増進を図ることを職務として児童相談所に配置される地方公務員。
じどう-ふくし-しせつ【児童福祉施設】🔗⭐🔉
じどう-ふくし-しせつ [7] 【児童福祉施設】
児童福祉法に基づき,国または都道府県が設置するよう定められている,児童および妊産婦の福祉を図るための施設。助産施設・乳児院・母子寮・保育所・児童厚生施設・養護施設・精神薄弱児施設・精神薄弱児通園施設・盲聾唖児施設・虚弱児施設・肢体不自由児施設・重症心身障害児施設・情緒障害児短期治療施設・教護院の一四種の施設。
じどう-ふくしほう【児童福祉法】🔗⭐🔉
じどう-ふくしほう ―ハフ 【児童福祉法】
児童の出生・育成が健やかであり,かつその生活が保障愛護されることを理念とし,児童保護のための禁止行為や児童福祉司・児童相談所・児童福祉施設などの諸制度について定めた法律。1947年(昭和22)制定。
じどう-ふようてあて【児童扶養手当】🔗⭐🔉
じどう-ふようてあて ―フヤウ― [7] 【児童扶養手当】
児童扶養手当法に基づき,父親と生計を異にする児童の母または養育者に対して国が支給する手当。
じどう-ぶんか【児童文化】🔗⭐🔉
じどう-ぶんか ―クワ [4] 【児童文化】
子供のために作り出される文化の総称。児童文学・児童劇など。
じどう-ぶんがく【児童文学】🔗⭐🔉
じどう-ぶんがく [4] 【児童文学】
児童を読者対象として創作される文学作品。お伽話・童話・少年少女小説・童謡・児童劇など。
じどう-ろうどう【児童労働】🔗⭐🔉
じどう-ろうどう ―ラウ― [4] 【児童労働】
児童による労働。労働基準法は特定の場合を除き原則的に満一五歳未満の児童の使用を禁ずる。
じ-はい【児輩】🔗⭐🔉
じ-はい [1] 【児輩】
子供たち。
じ-はん【児斑】🔗⭐🔉
じ-はん [0] 【児斑】
⇒蒙古斑(モウコハン)
じらいや【自来也・児雷也】🔗⭐🔉
じらいや 【自来也・児雷也】
江戸時代の読本・草双紙・歌舞伎などに現れる怪盗。中国明代の小説に,門扉に「自来也」と書き残す我来也という盗賊があり,これの翻案による人物。蟇(ガマ)の妖術を使う。
ち-ご【稚児・児】🔗⭐🔉
ち-ご [1] 【稚児・児】
〔乳子の意〕
(1)神社・寺院の祭礼・法会(ホウエ)などで,天童に扮して行列に出る男女児。「―行道(ギヨウドウ)」
(2)男色の相手となる少年。
(3)赤ん坊。「―亡くなりたる産屋(ウブヤ)/枕草子 25」
(4)幼児。子供。「この―,養ふ程に,すくすくと大きになりまさる/竹取」
(5)公家・神社・寺院などに召し使われた少年。「養ひ君の,比叡山(ヒエノヤマ)に―にておはしますが/徒然 47」
やや【児・稚児】🔗⭐🔉
やや [1] 【児・稚児】
赤ん坊。ややこ。
やや-さん【児様】🔗⭐🔉
やや-さん [1] 【児様】
〔「ややさま」の転〕
他人を敬ってその赤子をいう語。
じぎ【児戯】(和英)🔗⭐🔉
じぎ【児戯】
(mere) child's play.〜に類する childish;→英和
like child's play.
じどう【児童】(和英)🔗⭐🔉
大辞林に「児」で始まるの検索結果 1-54。