複数辞典一括検索+![]()
![]()
しずく【滴・雫】🔗⭐🔉
しずく シヅク [3] 【滴・雫】 (名)スル
水などの液体がしたたり落ちること。また,その水など。「―に濡れる」「貫一は―する涙を払て/金色夜叉(紅葉)」
した-たら・す【滴らす】🔗⭐🔉
した-たら・す [4] 【滴らす】 (動サ五[四])
したたるようにする。したたらせる。「額から汗を―・す」
したたり【滴り・瀝り】🔗⭐🔉
したたり [0] 【滴り・瀝り】
(1)したたること。また,そのもの。しずく。「汗の―」「蝋の―」
(2)崖(ガケ)などからにじみ出たり,苔類を伝わって落ちる点滴。[季]夏。《―のあまたの音の一つ澄む/大橋桜坡子》
したたり=積もりて淵(フチ)となる🔗⭐🔉
――積もりて淵(フチ)となる
ごくわずかなものでも,多く集まれば,大きなものになる。塵(チリ)も積もれば山となる。
したた・る【滴る】🔗⭐🔉
したた・る [3] 【滴る】 (動ラ五[四])
〔近世初め頃まで「しただる」〕
(1)液体がしずくとなって落ちる。垂れる。「岩の割れ目から―・る水」「汗が―・り落ちる」
(2)みずみずしさなどがあふれるばかりである。「緑―・る若葉の候」
〔「滴(シタ)つ」に対する自動詞〕
[慣用] 水の―よう
した・つ【滴つ】🔗⭐🔉
した・つ 【滴つ】 (動タ下二)
〔「したづ」とも〕
したたらせる。「今共に心の血(マコト)を―・つ/日本書紀(孝徳訓)」
たらし【垂らし・滴し】🔗⭐🔉
たらし [3] 【垂らし・滴し】
〔動詞「垂らす」の連用形から〕
(1)液体などをたらすこと。したたり。たれ。「洟(ハナ)―」「一(ヒト)―」
(2)航海中荒天にあった船が,風浪に流されるのを防ぎ,かつ安全を保つために船首または船尾から曳かせる碇(イカリ)ないし碇綱。《垂》
→シー-アンカー
てき【滴】🔗⭐🔉
てき 【滴】 (接尾)
助数詞。数を表す漢語に付いて液体のしたたりの数を数えるのに用いる。「数―の露」
てき-か【滴下】🔗⭐🔉
てき-か [0] 【滴下】 (名)スル
しずくとなって落ちること。また,しずく状にして落とすこと。「試薬を―する」
てきちゅう-るい【滴虫類】🔗⭐🔉
てきちゅう-るい [3] 【滴虫類】
繊毛虫類の旧称。
てき-てい【滴定】🔗⭐🔉
てき-てい [0] 【滴定】 (名)スル
定量分析の操作の一。試料物質の溶液の一定体積をとり,これと反応する物質の濃度既知の標準溶液を加えていき,試料物質の全量が反応するのに要した標準溶液の体積から,試料物質の濃度,あるいは全量を求めること。用いる反応により中和滴定・酸化還元滴定・沈殿滴定などがある。
てき-てき【滴滴】🔗⭐🔉
てき-てき [0] 【滴滴】
■一■ (ト|タル)[文]形動タリ
(1)しずくがしたたり落ちるさま。ぽたぽた。「冷き飛沫(シブキ)の間に暗中―として熱き雫を感じた/良人の自白(尚江)」
(2)あちこちに散らばっているさま。「―と垣を蔽ふ連翹(レンギヨウ)の黄/虞美人草(漱石)」
■二■ (名)
しずくがしたたり落ちたような点々とした状態。したたり。「大きな銀杏に墨汁を点じた様な―の鳥が乱れてゐる/野分(漱石)」
てき-びん【滴瓶】🔗⭐🔉
てき-びん [0] 【滴瓶】
化学実験で,溶液を一滴ずつ滴下するためにつくられた小さなびん。指示薬などを入れておく。
滴瓶
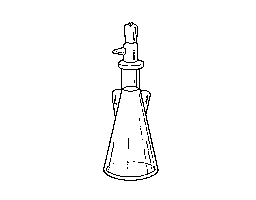 [図]
[図]
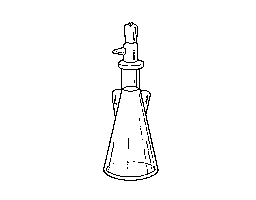 [図]
[図]
てき-れき【滴瀝】🔗⭐🔉
てき-れき [0] 【滴瀝】 (名)スル
水などがしたたること。また,そのしずく。したたり。「小懸泉の岩間に―するあり/日本風景論(重昂)」
したたり【滴り】(和英)🔗⭐🔉
したたる【滴る】(和英)🔗⭐🔉
大辞林に「滴」で始まるの検索結果 1-19。