複数辞典一括検索+![]()
![]()
さり【舎利】🔗⭐🔉
さり [1] 【舎利】
⇒しゃり(舎利)(1)
しゃえ【舎衛】🔗⭐🔉
しゃえ シヤ 【舎衛】
釈迦の時代,中インド,迦毘羅衛(カビラエ)国の西北にあった国。波斯匿(ハシノク)王が治世にあたっていた。祇園精舎はこの南にある。
【舎衛】
釈迦の時代,中インド,迦毘羅衛(カビラエ)国の西北にあった国。波斯匿(ハシノク)王が治世にあたっていた。祇園精舎はこの南にある。
 【舎衛】
釈迦の時代,中インド,迦毘羅衛(カビラエ)国の西北にあった国。波斯匿(ハシノク)王が治世にあたっていた。祇園精舎はこの南にある。
【舎衛】
釈迦の時代,中インド,迦毘羅衛(カビラエ)国の西北にあった国。波斯匿(ハシノク)王が治世にあたっていた。祇園精舎はこの南にある。
しゃ-えい【舎営】🔗⭐🔉
しゃ-えい [0] 【舎営】 (名)スル
軍隊が民間の家屋などで休養・宿泊すること。露営・野営に対していう。
しゃ-がい【舎飼い】🔗⭐🔉
しゃ-がい ―ガヒ [0] 【舎飼い】
家畜を畜舎で飼育すること。
しゃ-かん【舎監】🔗⭐🔉
しゃ-かん [0][1] 【舎監】
寄宿舎を管理・監督する人。
しゃ-じん【舎人】🔗⭐🔉
しゃ-じん 【舎人】
(1)召し使い。けらい。
(2)「とねり」に同じ。
しゃじん-かん【舎人監】🔗⭐🔉
しゃじん-かん 【舎人監】
⇒とねりのつかさ(舎人監)
しゃ-たく【舎宅】🔗⭐🔉
しゃ-たく 【舎宅】
家。家宅。「百姓の―を焼き払ふ/将門記」
しゃな【遮那・舎那】🔗⭐🔉
しゃな 【遮那・舎那】
〔仏〕 「毘盧遮那(ビルシヤナ)」の略。
しゃ-ひ【舎費】🔗⭐🔉
しゃ-ひ [1] 【舎費】
寄宿舎などの維持のため,居住者が払う費用。
しゃり【舎利】🔗⭐🔉
しゃり [1][0] 【舎利】
〔梵  ar
ar ra〕
(1)〔仏〕 遺骨。特に仏や聖人の遺骨をいう。仏舎利。さり。「―容器」
(2)白い米つぶ。また,米飯。「銀―」
(3)「おしゃり(御舎利)」に同じ。
ra〕
(1)〔仏〕 遺骨。特に仏や聖人の遺骨をいう。仏舎利。さり。「―容器」
(2)白い米つぶ。また,米飯。「銀―」
(3)「おしゃり(御舎利)」に同じ。
 ar
ar ra〕
(1)〔仏〕 遺骨。特に仏や聖人の遺骨をいう。仏舎利。さり。「―容器」
(2)白い米つぶ。また,米飯。「銀―」
(3)「おしゃり(御舎利)」に同じ。
ra〕
(1)〔仏〕 遺骨。特に仏や聖人の遺骨をいう。仏舎利。さり。「―容器」
(2)白い米つぶ。また,米飯。「銀―」
(3)「おしゃり(御舎利)」に同じ。
しゃり=が甲(コウ)にな・る🔗⭐🔉
――が甲(コウ)にな・る
「甲(コウ)が舎利になる」に同じ。
しゃり-え【舎利会】🔗⭐🔉
しゃり-え ― [2] 【舎利会】
仏の遺骨を供養する法会。舎利講会。舎利講。
[2] 【舎利会】
仏の遺骨を供養する法会。舎利講会。舎利講。
 [2] 【舎利会】
仏の遺骨を供養する法会。舎利講会。舎利講。
[2] 【舎利会】
仏の遺骨を供養する法会。舎利講会。舎利講。
しゃり-こう【舎利講】🔗⭐🔉
しゃり-こう ―カウ [0] 【舎利講】
⇒舎利会(シヤリエ)
しゃり-こうえ【舎利講会】🔗⭐🔉
しゃり-こうえ ―カウ [3] 【舎利講会】
⇒舎利会(シヤリエ)
[3] 【舎利講会】
⇒舎利会(シヤリエ)
 [3] 【舎利講会】
⇒舎利会(シヤリエ)
[3] 【舎利講会】
⇒舎利会(シヤリエ)
しゃり-でん【舎利殿】🔗⭐🔉
しゃり-でん [2] 【舎利殿】
仏の遺骨を安置する堂。中央に舎利塔を置く。
しゃり-とう【舎利塔】🔗⭐🔉
しゃり-とう ―タフ [0][2] 【舎利塔】
(1)寺院で,仏舎利を安置する小さな塔。骨塔。
(2)宝珠に火焔のあるもの。多く舎利塔の頂にあるのでいう。
舎利塔(1)
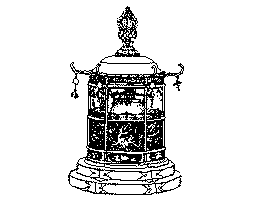 [図]
[図]
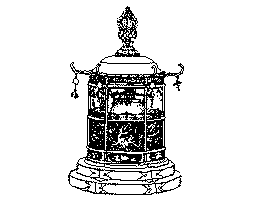 [図]
[図]
しゃり-ぶくろ【舎利袋】🔗⭐🔉
しゃり-ぶくろ [3] 【舎利袋】
仏舎利を入れる袋。
しゃり-ほう【舎利法】🔗⭐🔉
しゃり-ほう ―ホフ [2][0] 【舎利法】
仏舎利を本尊として行う密教の修法。
しゃり【舎利】🔗⭐🔉
しゃり 【舎利】
能の一。五番目物。旅僧が泉涌寺で仏舎利を拝しているところへ,里人が来て舎利のいわれを語る。里人は足疾鬼(ソクシツキ)と変じて舎利を奪って逃げるが,韋駄天(イダテン)が現れて舎利を取り戻す。
しゃりべつ【舎利別】🔗⭐🔉
しゃりべつ [2] 【舎利別】
〔(オランダ) siroop の中国での音訳か〕
シロップ。
しゃりほつ【舎利弗】🔗⭐🔉
しゃりほつ 【舎利弗】
〔梵 
 riputra〕
釈迦の十大弟子の一人。十六羅漢の一。懐疑論者の弟子だったが,のち仏弟子となり,智慧第一といわれた。舎利子。
riputra〕
釈迦の十大弟子の一人。十六羅漢の一。懐疑論者の弟子だったが,のち仏弟子となり,智慧第一といわれた。舎利子。 鷺子(シユウロシ)。
鷺子(シユウロシ)。

 riputra〕
釈迦の十大弟子の一人。十六羅漢の一。懐疑論者の弟子だったが,のち仏弟子となり,智慧第一といわれた。舎利子。
riputra〕
釈迦の十大弟子の一人。十六羅漢の一。懐疑論者の弟子だったが,のち仏弟子となり,智慧第一といわれた。舎利子。 鷺子(シユウロシ)。
鷺子(シユウロシ)。
セイミ-きょく【舎密局】🔗⭐🔉
セイミ-きょく 【舎密局】
明治初期の理化学研究教育機関。1869年(明治2)政府が大阪舎密局を開局。翌年大阪理学校,次いで大阪開成学校と改称,1972年廃校。京都にも府立の京都舎密局があった。
セイミかいそう【舎密開宗】🔗⭐🔉
セイミかいそう 【舎密開宗】
日本最初の化学書。宇田川榕庵著。内編一八巻,外編三巻。1837〜47年刊。イギリスのヘンリーの著書の独語訳の蘭語訳を原著とし,訳とともに自分の注釈・実験の結果を記載。
とねり【舎人】🔗⭐🔉
とねり [0][1] 【舎人】
(1)皇族・貴族に仕えて,雑務を行なった下級官人。律令制下には内舎人・大舎人・春宮舎人・中宮舎人などがあり,主に貴族・官人の子弟から選任された。舎人男。舎人子。
(2)平安時代,貴族の牛馬などを扱う従者。
(3)旧宮内省式部職に属した名誉官。式典に関する雑務に従事した。
とねり-おとこ【舎人男】🔗⭐🔉
とねり-おとこ ―ヲトコ 【舎人男】
「舎人{(1)}」に同じ。「うちひさす宮女(ミヤオミナ)さすたけの―も忍ぶらひ/万葉 3791」
とねり-の-つかさ【舎人監】🔗⭐🔉
とねり-の-つかさ 【舎人監】
律令制で,春宮坊(トウグウボウ)の役所であった三監の一。東宮の舎人の名帳・礼儀・分番の事を扱った。とねりつかさ。
とねり-べ【舎人部】🔗⭐🔉
とねり-べ [3] 【舎人部】
大化前代,天皇や皇族に直接仕え,雑役・警衛などにあたった部。
とねり-しんのう【舎人親王】🔗⭐🔉
とねり-しんのう ―シンワウ 【舎人親王】
(676?-735) 天武天皇の皇子。知太政官事。母は天智天皇の皇女新田部皇女。勅により日本書紀を編纂。死去に際し贈太政大臣。その子大炊王が即位して淳仁天皇となったので,崇道尽敬皇帝の追号がある。
−しゃ【舎】(和英)🔗⭐🔉
−しゃ【舎】
象(キリン)舎 an elephant (a giraffe) house.
しゃかん【舎監】(和英)🔗⭐🔉
しゃかん【舎監】
a dormitory superintendent.
大辞林に「舎」で始まるの検索結果 1-35。