複数辞典一括検索+![]()
![]()
かえる-また【蛙股・蟇股】🔗⭐🔉
かえる-また カヘル― [0] 【蛙股・蟇股】
〔蛙がまたを広げたような形から〕
(1)(「蟇股」と書く)社寺建築などで,頭貫(カシラヌキ)または梁(ハリ)の上,桁との間に置かれる山形の部材。本来は上部構造の重みを支えるもの。のちには単に装飾として,さまざまに彫刻して破風などにつけられた。厚い板でできた板蟇股と中を透かした本蟇股とがある。
(2)かんざしで,足が蛙のまたを広げた形になったもの。
(3)網地の結節の一。結び目が締まり,ずれにくいため,刺し網類に用いる。
蟇股(1)
 [図]
[図]
 [図]
[図]
ひき【蟇・蟾】🔗⭐🔉
ひき [2] 【蟇・蟾】
ヒキガエルの別名。[季]夏。《這出よかひやが下の―の声/芭蕉》
ひき-がえる【蟇・蟾蜍】🔗⭐🔉
ひき-がえる ―ガヘル [3] 【蟇・蟾蜍】
(1)カエル目ヒキガエル科の両生類の総称。
(2){(1)}の一種。体長は7〜15センチメートル。ずんぐりした体形で四肢は短く跳躍力は弱い。背面は暗褐色,腹面は淡黄褐色。耳腺がよく発達し,背には疣(イボ)がある。一般に地上性で,繁殖期以外はあまり水に入らない。ニホンヒキガエル。ヒキ。ガマ。ガマガエル。イボガエル。[季]夏。
ひき-はだ【蟇肌・引き膚】🔗⭐🔉
ひき-はだ [0] 【蟇肌・引き膚】
(1)「蟇肌革(ガワ)」の略。
(2)蟇肌革で作った刀剣の鞘袋(サヤブクロ)。「はきも習はぬ太刀の―(芭蕉)/ひさご」
ひきはだ-がわ【蟇肌革】🔗⭐🔉
ひきはだ-がわ ―ガハ [0] 【蟇肌革】
ヒキガエルの背のような,しわのある革。ひきはだ。
ひき-め【蟇目・引目】🔗⭐🔉
ひき-め [0] 【蟇目・引目】
〔「響き目」の転。また,その形がヒキガエルの目に似ているからともいう〕
紡錘形の先端をそいだ形の木製の鏑(カブラ)。また,それを付けた矢。朴(ホオ)・桐(キリ)などで作り,内部を刳(ク)り,数個の穴をあけてある。射ると音を立てて飛ぶことから降魔(ゴウマ)の法に用いられ,また,獲物に傷をつけないことから,笠懸(カサガケ)・犬追物(イヌオウモノ)などに使われた。ひきめかぶら。ひきめのかぶら。
蟇目
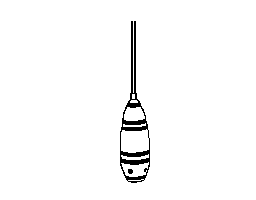 [図]
[図]
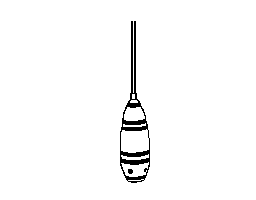 [図]
[図]
ひきめ-かぶら【蟇目鏑】🔗⭐🔉
ひきめ-かぶら [4] 【蟇目鏑】
「蟇目」に同じ。
ひきめ-がら【蟇目柄】🔗⭐🔉
ひきめ-がら [3][0] 【蟇目柄】
蟇目を付ける太く,長い矢柄。
ひきめ-くり【蟇目刳り】🔗⭐🔉
ひきめ-くり [3] 【蟇目刳り】
蟇目を作ること。また,その職人。
ひきめ-の-しんじ【蟇目の神事】🔗⭐🔉
ひきめ-の-しんじ 【蟇目の神事】
諸所の神社で,毎年2月4日(古くは陰暦正月四日)に行われる祭事。蟇目を射て邪を祓(ハラ)う神事。日光市の二荒山神社のものが有名。
ひきめ-の-ばん【蟇目の番】🔗⭐🔉
ひきめ-の-ばん 【蟇目の番】
蟇目を射て魔物を脅し,退散させる役目の侍。蟇目の当番。
ひきめ-の-ほう【蟇目の法】🔗⭐🔉
ひきめ-の-ほう ―ホフ 【蟇目の法】
妖魔降伏のため,蟇目を射ること。蟇目の式。
ひきめ-やく【蟇目役】🔗⭐🔉
ひきめ-やく [0] 【蟇目役】
貴人の出産の際,妖魔を降伏(ゴウブク)するために,蟇目を射る役。
ひきがえる【蟇】(和英)🔗⭐🔉
ひきがえる【蟇】
a toad.→英和
大辞林に「蟇」で始まるの検索結果 1-14。