複数辞典一括検索+![]()
![]()
○短兵直ちにたんぺいただちに🔗⭐🔉
○短兵直ちにたんぺいただちに
(→)「短兵急に」に同じ。
⇒たん‐ぺい【短兵】
だんべえ‐ぶね【団平船】
①近世、大坂で石を運送した川船。
②明治半ば以後、材木・石炭・土砂などを運搬した海船。
たん‐ぺき【丹碧】
赤色と青色。丹青。
たん‐ぺき【淡碧】
うすいあおいろ。
たん‐べつ【反別・段別】
①田畑を1反ごとに分けること。
②田畑の地積の称。
③反別割の略。
⇒たんべつ‐わり【反別割】
たんべつ‐わり【反別割】
田畑の反別を標準として賦課する租税。
⇒たん‐べつ【反別・段別】
ダン‐ベル【dumb-bell】
(→)亜鈴あれい。
タンペレ【Tampere】
フィンランド南西部にある工業都市。二つの湖に南北を囲まれ、両湖の水位差を利用した水力発電が盛ん。人口20万2千(2004)。
たん‐べん【単弁】
花弁のひとえのもの。ひとえ。↔重弁。
⇒たんべん‐か【単弁花】
たん‐ぺん【短編・短篇】
詩や文章・映画などで、長さの短い作品。「―小説」
だん‐ぺん【断片】
ちぎれた一ひら。きれはし。破片。「記憶の―」
⇒だんぺん‐てき【断片的】
だん‐ぺん【断編・断篇】
まとまった文章の、きれはし。
たんべん‐か【単弁花】‥クワ
花弁がひとえの花。↔重弁花
⇒たん‐べん【単弁】
だんぺん‐てき【断片的】
まとまりがなく、きれぎれであるさま。「―な知識」
⇒だん‐ぺん【断片】
たんぼ【田圃】
(「田圃」は当て字)田畑。田。
⇒たんぼ‐みち【田圃道】
たん‐ぼ【旦暮】
①あさゆう。あけくれ。謡曲、須磨源氏「これは須磨の浦に、―に釣を垂れ」
②(朝から暮までの意)ちょっとの間。
③時機の切迫したさま。旦夕。源平盛衰記20「老病身を侵して、余命―を待つ」
たんぽ
綿を丸めて革や布で包んだもの。稽古用の槍の頭につけ、また、墨などをふくませるのに用いる。
⇒たんぽ‐やり【たんぽ槍】
たん‐ぽ【担保】
①債務の履行を確保するため債権者に提供されるもの。抵当権や保証の類。→人的担保→物的担保。
②しちぐさ。抵当。ひきあて。
③不利益に備えてその補いとなるもの。「実効性を―する」
⇒たんぽ‐かけめ【担保掛目】
⇒たんぽ‐かしつけ【担保貸付】
⇒たんぽ‐せいきゅうけん【担保請求権】
⇒たんぽつき‐こうさい【担保付公債】
⇒たんぽつき‐しゃさい【担保付社債】
⇒たんぽ‐ぶつ【担保物】
⇒たんぽ‐ぶっけん【担保物権】
たん‐ぽ【湯婆】
(唐音)中に湯を入れて、腰・脚などをあたためるのに用いる金属製または陶製の器。ゆたんぽ。〈[季]冬〉
タンホイザー【Tannhäuser】
ワグナー作の歌劇。3幕。ミンネゼンガーの騎士タンホイザーの物語。1845年ドレスデンで初演。改訂して61年パリで上演。
ワグナー
提供:Lebrecht Music & Arts/APL
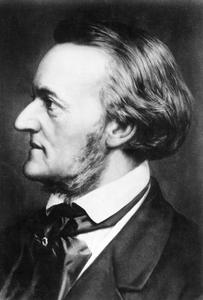 →歌劇「タンホイザー」序曲
提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
たん‐ぼいん【単母音】
一つの短母音または長母音が単一音節を成したもの。二重母音・三重母音に対していう。
たん‐ぼいん【短母音】
(short vowel)長さが1拍分(普通の長さ)の母音。みじかぼいん。↔長母音
たん‐ぼう【探訪】‥バウ
社会の出来事や事件の真相をさぐりに出向くこと。若松賤子、小公子「英国新聞は―の届く丈詳細に書き立て」。「―記事」
だん‐ぼう【暖房・煖房】‥バウ
①室内をあたためること。また、その装置。〈[季]冬〉。「―の効いた部屋」↔冷房。
②転宅の祝い。わたましのいわい。
だん‐ぽう【暖飽】‥パウ
(暖衣飽食の略)暖かに衣服を着、飽きるまで食物をとること。何の不足もなく生活すること。
だん‐ぽう【壇法】‥ポフ
〔仏〕修法しゅほうのときの壇を設ける方法。また、その修法。
だん‐ぽう【檀方・旦方】‥パウ
①檀家。檀徒。浄瑠璃、八百屋お七「お手前ばかりが―か不敵な差配と叱られて」
②転じて、仲間。知り合い。狂言、鈍太郎「それがしは―衆に長刀使ひを持つてゐるによつて」
たんほう‐ちょうよう【丹鳳朝陽】‥テウヤウ
(画題)朝日に丹色の鳳凰を描いたもの。瑞祥をあらわす。
だん‐ボール【段ボール】
包装用・運送用板紙の一つ。波状に成形した紙の片面または両面に厚紙を貼り合わせたもの。
たんぽ‐かけめ【担保掛目】
担保物件の時価にかけて、その評価額を決める比率。株式の信用取引などでは、これを変更することによって相場を調整する。率。掛目。
⇒たん‐ぽ【担保】
たんぽ‐かしつけ【担保貸付】
銀行の貸付で、担保品をとるもの。担保付貸付。
⇒たん‐ぽ【担保】
たん‐ぼく【淡墨】
うすい墨色。うすずみ。
たんぽ‐せいきゅうけん【担保請求権】‥キウ‥
担保の提供を請求しうる権利。
⇒たん‐ぽ【担保】
たんぽつき‐こうさい【担保付公債】
物的担保によりその元利金支払が保証されている公債。
⇒たん‐ぽ【担保】
たんぽつき‐しゃさい【担保付社債】
社債発行に際し、その元利金の支払を確実にさせるために、会社が特に担保を提供した社債。
⇒たん‐ぽ【担保】
たんぽ‐ぶつ【担保物】
担保として提供された物。抵当不動産・質物の類。
⇒たん‐ぽ【担保】
たんぽ‐ぶっけん【担保物権】
一定の債権の担保を目的とする物権。民法上、留置権・先取特権・質権・抵当権の四つに大別する。
⇒たん‐ぽ【担保】
たんぽぽ【蒲公英】
キク科タンポポ属の多年草の総称。全世界に広く分布。日本にはカンサイタンポポ・エゾタンポポ・シロバナタンポポ、また帰化植物のセイヨウタンポポなど10種以上あり、普通にはカントウタンポポをいう。根はゴボウ状。葉は土際に根生葉を作り、倒披針形で縁は羽裂。春、花茎を出し、舌状花だけから成る黄色の頭状花をつける。痩果は褐色で、冠毛は白色、風によって四散する。若葉は食用、帯根全体を乾燥したものが漢方生薬の蒲公英ほこうえいで健胃・催乳剤。たな。〈[季]春〉。文明本節用集「蒲公草、タンホホ」
カントウタンポポ
撮影:関戸 勇
→歌劇「タンホイザー」序曲
提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
たん‐ぼいん【単母音】
一つの短母音または長母音が単一音節を成したもの。二重母音・三重母音に対していう。
たん‐ぼいん【短母音】
(short vowel)長さが1拍分(普通の長さ)の母音。みじかぼいん。↔長母音
たん‐ぼう【探訪】‥バウ
社会の出来事や事件の真相をさぐりに出向くこと。若松賤子、小公子「英国新聞は―の届く丈詳細に書き立て」。「―記事」
だん‐ぼう【暖房・煖房】‥バウ
①室内をあたためること。また、その装置。〈[季]冬〉。「―の効いた部屋」↔冷房。
②転宅の祝い。わたましのいわい。
だん‐ぽう【暖飽】‥パウ
(暖衣飽食の略)暖かに衣服を着、飽きるまで食物をとること。何の不足もなく生活すること。
だん‐ぽう【壇法】‥ポフ
〔仏〕修法しゅほうのときの壇を設ける方法。また、その修法。
だん‐ぽう【檀方・旦方】‥パウ
①檀家。檀徒。浄瑠璃、八百屋お七「お手前ばかりが―か不敵な差配と叱られて」
②転じて、仲間。知り合い。狂言、鈍太郎「それがしは―衆に長刀使ひを持つてゐるによつて」
たんほう‐ちょうよう【丹鳳朝陽】‥テウヤウ
(画題)朝日に丹色の鳳凰を描いたもの。瑞祥をあらわす。
だん‐ボール【段ボール】
包装用・運送用板紙の一つ。波状に成形した紙の片面または両面に厚紙を貼り合わせたもの。
たんぽ‐かけめ【担保掛目】
担保物件の時価にかけて、その評価額を決める比率。株式の信用取引などでは、これを変更することによって相場を調整する。率。掛目。
⇒たん‐ぽ【担保】
たんぽ‐かしつけ【担保貸付】
銀行の貸付で、担保品をとるもの。担保付貸付。
⇒たん‐ぽ【担保】
たん‐ぼく【淡墨】
うすい墨色。うすずみ。
たんぽ‐せいきゅうけん【担保請求権】‥キウ‥
担保の提供を請求しうる権利。
⇒たん‐ぽ【担保】
たんぽつき‐こうさい【担保付公債】
物的担保によりその元利金支払が保証されている公債。
⇒たん‐ぽ【担保】
たんぽつき‐しゃさい【担保付社債】
社債発行に際し、その元利金の支払を確実にさせるために、会社が特に担保を提供した社債。
⇒たん‐ぽ【担保】
たんぽ‐ぶつ【担保物】
担保として提供された物。抵当不動産・質物の類。
⇒たん‐ぽ【担保】
たんぽ‐ぶっけん【担保物権】
一定の債権の担保を目的とする物権。民法上、留置権・先取特権・質権・抵当権の四つに大別する。
⇒たん‐ぽ【担保】
たんぽぽ【蒲公英】
キク科タンポポ属の多年草の総称。全世界に広く分布。日本にはカンサイタンポポ・エゾタンポポ・シロバナタンポポ、また帰化植物のセイヨウタンポポなど10種以上あり、普通にはカントウタンポポをいう。根はゴボウ状。葉は土際に根生葉を作り、倒披針形で縁は羽裂。春、花茎を出し、舌状花だけから成る黄色の頭状花をつける。痩果は褐色で、冠毛は白色、風によって四散する。若葉は食用、帯根全体を乾燥したものが漢方生薬の蒲公英ほこうえいで健胃・催乳剤。たな。〈[季]春〉。文明本節用集「蒲公草、タンホホ」
カントウタンポポ
撮影:関戸 勇
 シロバナタンポポ
撮影:関戸 勇
シロバナタンポポ
撮影:関戸 勇
 セイヨウタンポポ
撮影:関戸 勇
セイヨウタンポポ
撮影:関戸 勇
 タンポポ(実)
撮影:関戸 勇
タンポポ(実)
撮影:関戸 勇
 たんぼ‐みち【田圃道】
田畑の中を通っている道。
⇒たんぼ【田圃】
たんぽ‐やり【たんぽ槍】
柄の先にたんぽをつけた稽古用の槍。牡丹槍。
⇒たんぽ
タンボラ【Tambora】
インドネシア中部のスンバワ島にある活火山。1815年に、有史以来世界最大の噴火。爆発により山体を破壊、噴出物の量は100〜150立方キロメートルに及ぶ。噴火による直接の死者1万人、餓死・病死者8万2000人。
だんぼら‐ぼ
水中に大きな物を投げ入れた時の音。どんぶり。浄瑠璃、博多小女郎波枕「大勢かかつて―、辺ほとりも知れぬ海の中」
タンポン【Tampon ドイツ】
消毒した綿・ガーゼを円筒状あるいは球状にし、鼻腔・膣に挿入して止血または分泌液の吸収をさせるもの。綿球。止血栓。
たんほんい‐せい【単本位制】‥ヰ‥
本位貨幣が、単一の金属の一定純量と一定の関係を保つような本位制度。↔複本位制
たんま
(児童語)遊戯の中断。タイム。「―をかける」
たん‐まい【段米・反米】
中世、朝廷や幕府の行事に際し、段別に応じて臨時に賦課した税米。→段銭
だん‐まく【段幕】
紅白などの布を横に幾段にも縫い合わせた幕。
だん‐まく【弾幕】
敵の攻撃を防ぐため、横に砲列をしいてたくさんの弾丸を一度に発射すること。幕にたとえた言い方。「―を張る」
だんまく‐しゅぜん【断悪修善】
⇒だんあくしゅぜん
たん‐まつ【端末】
①物のはし。すえ。〈日葡辞書〉
②端末装置の略。
⇒たんまつ‐そうち【端末装置】
たんまつ‐そうち【端末装置】‥サウ‥
(terminal unit)コンピューター‐システムで、ホスト‐コンピューターとのデータのやりとりに特化した装置。
⇒たん‐まつ【端末】
だん‐まつま【断末魔・断末摩】
〔仏〕(末魔は、梵語marmanの音訳。支節・死穴と訳す。体の中にある特殊の急所で、他のものが触れれば劇痛を起こして必ず死ぬという)息を引き取るまぎわの苦痛。
ダンマパダ【Dhammapada パーリ】
〔仏〕(→)法句経ほっくきょうに同じ。
たんまり
〔副〕
①十分に。浮世風呂2「―と湯へもはいれません」
②金銭や物が満足できるほど十分であるさま。「―せしめる」
だんまり【黙り】
(ダマリの撥音化)
①だまっていること。無言。「返答に詰まって―をきめこむ」
②ことわらないこと。無断。
③歌舞伎で、登場人物が無言で闇中にさぐりあう動作を様式化したもの、またその場面。普通、時代狂言のものをいい、世話狂言のものは「世話だんまり」という。暗闘。暗争。
⇒だんまり‐ぼう【黙り坊】
だんまり‐ぼう【黙り坊】‥バウ
だまっている人。口かずの少ない人。だまりん坊。
⇒だんまり【黙り】
たん‐み【淡味・澹味】
①あわいあじ。
②あっさりとした趣味。
たん‐みん【
たんぼ‐みち【田圃道】
田畑の中を通っている道。
⇒たんぼ【田圃】
たんぽ‐やり【たんぽ槍】
柄の先にたんぽをつけた稽古用の槍。牡丹槍。
⇒たんぽ
タンボラ【Tambora】
インドネシア中部のスンバワ島にある活火山。1815年に、有史以来世界最大の噴火。爆発により山体を破壊、噴出物の量は100〜150立方キロメートルに及ぶ。噴火による直接の死者1万人、餓死・病死者8万2000人。
だんぼら‐ぼ
水中に大きな物を投げ入れた時の音。どんぶり。浄瑠璃、博多小女郎波枕「大勢かかつて―、辺ほとりも知れぬ海の中」
タンポン【Tampon ドイツ】
消毒した綿・ガーゼを円筒状あるいは球状にし、鼻腔・膣に挿入して止血または分泌液の吸収をさせるもの。綿球。止血栓。
たんほんい‐せい【単本位制】‥ヰ‥
本位貨幣が、単一の金属の一定純量と一定の関係を保つような本位制度。↔複本位制
たんま
(児童語)遊戯の中断。タイム。「―をかける」
たん‐まい【段米・反米】
中世、朝廷や幕府の行事に際し、段別に応じて臨時に賦課した税米。→段銭
だん‐まく【段幕】
紅白などの布を横に幾段にも縫い合わせた幕。
だん‐まく【弾幕】
敵の攻撃を防ぐため、横に砲列をしいてたくさんの弾丸を一度に発射すること。幕にたとえた言い方。「―を張る」
だんまく‐しゅぜん【断悪修善】
⇒だんあくしゅぜん
たん‐まつ【端末】
①物のはし。すえ。〈日葡辞書〉
②端末装置の略。
⇒たんまつ‐そうち【端末装置】
たんまつ‐そうち【端末装置】‥サウ‥
(terminal unit)コンピューター‐システムで、ホスト‐コンピューターとのデータのやりとりに特化した装置。
⇒たん‐まつ【端末】
だん‐まつま【断末魔・断末摩】
〔仏〕(末魔は、梵語marmanの音訳。支節・死穴と訳す。体の中にある特殊の急所で、他のものが触れれば劇痛を起こして必ず死ぬという)息を引き取るまぎわの苦痛。
ダンマパダ【Dhammapada パーリ】
〔仏〕(→)法句経ほっくきょうに同じ。
たんまり
〔副〕
①十分に。浮世風呂2「―と湯へもはいれません」
②金銭や物が満足できるほど十分であるさま。「―せしめる」
だんまり【黙り】
(ダマリの撥音化)
①だまっていること。無言。「返答に詰まって―をきめこむ」
②ことわらないこと。無断。
③歌舞伎で、登場人物が無言で闇中にさぐりあう動作を様式化したもの、またその場面。普通、時代狂言のものをいい、世話狂言のものは「世話だんまり」という。暗闘。暗争。
⇒だんまり‐ぼう【黙り坊】
だんまり‐ぼう【黙り坊】‥バウ
だまっている人。口かずの少ない人。だまりん坊。
⇒だんまり【黙り】
たん‐み【淡味・澹味】
①あわいあじ。
②あっさりとした趣味。
たん‐みん【 民】
中国南部の大河川や沿海地方の水上生活民を呼んだ称。漁業・水運などに従事。水上居民。
たん‐めい【旦明】
あけがた。よあけ。
たん‐めい【短命】
短いいのち。年若くて死ぬこと。わかじに。夭折ようせつ。「―に終わる」「―内閣」↔長命
たんめい‐てがた【単名手形】
手形債務者がただ一人である手形。裏書のない約束手形と引受け済みの自己あて為替手形をいう。
だん‐めつ【断滅】
絶え滅びること。また、絶やし滅ぼすこと。
たん‐めり
(完了の助動詞タリに推量の助動詞メリの付いた形の音便)…ているようだ。
たん‐めん【耽湎】
(「湎」は、おぼれる意)酒色にふけり、すさむこと。耽溺。たんべん。
たん‐めん【赧面】
恥じて顔をあからめること。赤面。
タンメン【湯麺】
(中国語)ゆでた中華そばにスープを加えるか、スープで煮る料理。汁そば。
だん‐めん【段免】
江戸時代、田地が地味によって分けられている場合、同じ等級であっても現実には作毛さくげの劣る田は、年貢率を1〜2段下げたこと。
だん‐めん【断面】
①もののきりくちの面。切断面。
②物事をある観点から見た時、そこに現れている状態。「社会の一―」
⇒だんめん‐ず【断面図】
だんめん‐ず【断面図】‥ヅ
物体をある平面で切ったと仮定して、その内部構造をえがいた図。
⇒だん‐めん【断面】
だん‐めんせき【断面積】
①図形や物体のある切断面における面積。
②〔理〕二つの粒子の散乱や反応の強さを表す量。面積の次元を持ち、現象が起こりやすいほど断面積が大きい。
たん‐もう【誕妄】‥マウ
うそ。いつわり。でたらめ。
たん‐もち【痰持ち】
痰の出る持病のある人。
たん‐もの【反物・段物】
①1反に仕上げてある織物。太物。↔疋物ひきもの。→たん(段・反)。
②一般に、呉服。「―屋」
だん‐もの【段物】
①能で、一曲の眼目とされるような謡いどころ、舞いどころのうち、曲くせ・狂くるいなどの定型に属さない一段。「三井寺」の鐘の段、「自然居士」のささらの段の類。
②義太夫節で、各段のうちの有名なあるいは特殊な一段。それを集めたものを正本・院本まるほんに対して「段物集」という。主として道行みちゆき・景事けいごとなどから選ぶ。
③常磐津や新内節で、義太夫節からの移入曲。短編の端物はものに対して、長編の曲を指す。
④日本舞踊で、常磐津・清元など浄瑠璃の伴奏による舞踊劇。
⑤箏曲そうきょくの曲種。歌のない器楽曲で、数段で一曲を構成する。各段の拍数は一定。速度は漸次急。八橋検校の「六段の調しらべ」など。しらべもの。
だん‐もよう【段模様】‥ヤウ
段々に染めた模様。段染めの模様。
たん‐もん【探問】
さぐりとうこと。
だん‐もん【断文】
断罪の命令文。断罪文。
たん‐や【短夜】
短い夜。夏の短い夜。みじかよ。↔長夜
たん‐や【鍛冶】
かじ。かぬち。
たん‐やく【丹薬】
不老不死の仙薬。道士の作った煉薬ねりやく。
だん‐やく【弾薬】
弾丸と、それを発射するための火薬の総称。たまぐすり。「―庫」
たん‐ゆう【胆勇】
大胆で勇気のあること。「―を備える」
たんゆう【探幽】‥イウ
⇒かのうたんゆう(狩野探幽)
だん‐ゆう【男優】‥イウ
男の俳優。↔女優
だん‐よ【談余】
はなしのついで。
たん‐よう【単葉】‥エフ
①葉身が小葉に分裂することがない葉。サクラ・ケヤキなどの葉。
②飛行機の主翼が1枚であること。↔複葉。
⇒たんよう‐き【単葉機】
たん‐よう【端陽】‥ヤウ
(→)端午たんごに同じ。
たんよう‐き【単葉機】‥エフ‥
主翼が1枚の飛行機。単葉飛行機。↔複葉機
⇒たん‐よう【単葉】
たん‐よく【貪欲】
欲が深いこと。どんよく。
たん‐らく【耽楽】
酒色にふけり楽しむこと。
たん‐らく【短絡】
①(short circuit)電気回路の2点間を小さい抵抗の導線で接続すること。また、電気回路の絶縁が破れるなどして、抵抗の非常に小さな回路を形成すること。ショート。
②(比喩的に)単純には結びつかない関係にある二つの物事を、直接・簡単に結びつけて論じること。
⇒たんらく‐しけん【短絡試験】
⇒たんらく‐てき【短絡的】
⇒たんらく‐はんのう【短絡反応】
だん‐らく【段落】
①長い文章中の大きな切れ目。段。
②転じて、物事のくぎり。「仕事が一―ついた」
たんらく‐しけん【短絡試験】
電気機器の端子間を短絡して行う試験。
⇒たん‐らく【短絡】
たんらく‐てき【短絡的】
筋道立てて考えずに物事を結びつけて論ずるさま。「―な思考」
⇒たん‐らく【短絡】
たんらく‐はんのう【短絡反応】‥オウ
〔心〕(→)近道反応に同じ。
⇒たん‐らく【短絡】
たん‐らん【貪婪】
きわめて欲が深いこと。どんらん。
だん‐らん【団欒】
①月などのまるいこと。まどか。
②集まって車座にすわること。まどい。
③集まってなごやかに楽しむこと。親密で楽しい会合。「一家―」
たん‐り【単利】
元金だけに対する利子。↔複利。
⇒たんり‐ほう【単利法】
たん‐り【単離】
〔化〕混合物中から一つの物質だけを純粋な形で取り出すこと。
たん‐り【貪吏】
欲が深く、人民の財をむさぼりとる官公吏。史記抄「―の様ににはかに盗取こそせねども」
たん‐り【貪利】
利益をむさぼること。あくまで利益を収めること。
たん‐り【短籬】
たけの低いまがき。
たん‐りつ【単立】
単独で設立されていること。「―宗教法人」
たん‐りつ【単律】
音楽で、呂・律の二つの音調に分けた時、律の音階だけが行われること。徒然草「唐土は呂の国なり。律の音なし。和国は、―の国にて、呂の音なし」
たんり‐ほう【単利法】‥ハフ
利息計算で、前期間の利息を元金に加算せず、元金のみに対し次期の利息を計算する法。↔複利法
⇒たん‐り【単利】
たん‐りゃく【胆略】
大胆で知略のあること。
たん‐りゅう【湍流】‥リウ
水勢の急な流れ。はやせ。急流。奔流。
だん‐りゅう【断流】‥リウ
川の水が河口まで届かず跡絶えてしまうこと。
だん‐りゅう【暖流】‥リウ
熱帯・亜熱帯の海域に源をもち、高緯度に向かって流れる海流。黒潮・湾流など。↔寒流
たんりゅう‐こうぞう【単粒構造】‥リフ‥ザウ
土壌を構成する土粒がそれぞれ独立して集積し、その間に何ら関係のない構造。ゆるい砂土や重粘な埴土はこの組織をなす。↔団粒構造
だんりゅう‐こうぞう【団粒構造】‥リフ‥ザウ
微細な土壌粒子が腐植や石灰などで膠着されて多孔質の肉眼で見える大きさの小粒をなすもの。通気・通水性が良好であるとともに、水分をよく保持し、一般に、植物の生育に適するので、土壌改善の目標とされる。↔単粒構造
たん‐りょ【短慮】
①考えが浅いこと。浅慮。毎月抄「更に―及び難くぞ覚え侍る」。「―を戒める」
②気みじか。せっかち。短気。浄瑠璃、嫗山姥こもちやまうば「世に便りなきうき節に、もし御―のこともやと」。「―な男」
⇒たんりょ‐じん【短慮人】
たん‐りょう【単寮】‥レウ
禅寺で、一人で住む寮舎。
たんりょう‐たい【単量体】‥リヤウ‥
(monomer)重合体を構成する基本単位物質。例えばエチレンはポリエチレンの単量体。モノマー。
たん‐りょく【胆力】
ものに恐れず臆しない気力。度胸。「―が据っている」「―を練る」
たん‐りょく【淡緑】
うすいみどり。
だん‐りょく【弾力】
①はずむ力。物体が変形に抗して、原形に復しようとする力。
②状況の変化に適応する柔軟性。「―的に考える」
⇒だんりょく‐せい【弾力性】
だんりょく‐せい【弾力性】
弾力のある性質。「規則に―をもたせる」
⇒だん‐りょく【弾力】
たんりょく‐ぼん【丹緑本】
⇒たんろくぼん
たんりょ‐じん【短慮人】
短気な人。怒りっぽい人。日葡辞書「ヒ(火)ヲフルヤウナタンリョジンヂャ」
⇒たん‐りょ【短慮】
たん‐りん【貪吝】
むさぼりとって出し惜しむこと。
だん‐りん【檀林・談林】
①(栴檀林の略)仏教の学問所。平安時代の檀林寺に始まるが、学問所を檀林と呼ぶようになったのは室町末期で、近世、各宗で設ける。関東十八檀林の類。学寮。
②寺の異称。
③談林風。
⇒だんりん‐は【談林派・檀林派】
⇒だんりん‐ふう【談林風・檀林風】
だんりん‐こうごう【檀林皇后】‥クワウ‥
橘嘉智子たちばなのかちこの異称。
だんりん‐じ【檀林寺】
京都の天竜寺付近にあった日本最古とされる禅院。承和(834〜848)年中、檀林皇后の願によって唐僧義空が開山。室町時代に再興して京都尼五山の一つとなったが廃絶。
だんりんとっぴゃくいん【談林十百韻】‥ヰン
俳諧集。2冊。田代松意編。1675年(延宝3)刊。宗因風を志向する江戸の俳人たちの百韻俳諧を10巻集めたもの。談林俳諧・談林風の称は本書題名による。
だんりん‐は【談林派・檀林派】
談林風を奉じた俳諧の流派。
⇒だん‐りん【檀林・談林】
だんりん‐ふう【談林風・檀林風】
江戸前期、延宝・天和(1673〜1684)頃に流行した俳諧の一風・一派。もとは江戸の田代松意の一派の結社を指すが、のち大坂の西山宗因を中心とする新風の汎称となる。伝統的・法式的な貞徳流に反抗して、軽妙な口語使用と滑稽な着想によって流行したが、蕉風しょうふうの興るに及んで衰えた。宗因風。
⇒だん‐りん【檀林・談林】
たん‐れい【淡麗】
日本酒の味や口当りに強い癖がなく、すっきりと滑らかである様子。
たん‐れい【貪戻】
むさぼって人の道にそむくこと。浄瑠璃、国性爺合戦「一人―なれば一国乱を起すといへり」
たん‐れい【端麗】
かたち・すがたがととのって、うるわしいこと。「容姿―」
だん‐れい‐ぼう【暖冷房】‥バウ
(→)冷暖房に同じ。
たん‐れつ【単列】
ひとならび。1列。
⇒たんれつ‐きかん【単列機関】
だん‐れつ【断裂】
断ち裂かれること。
たんれつ‐きかん【単列機関】‥クワン
シリンダーが1列に並んで1本のクランク軸によって動力を他へ伝動する機関。直列機関の1列のもの。
⇒たん‐れつ【単列】
たん‐れん【鍛練・鍛錬・鍛煉】
①金属をきたえねること。〈日葡辞書〉
②修養・訓練を積んで心身をきたえたり技能をみがいたりすること。浮世物語「通力あるが如くなる上手の―ある者」。「体を―する」
③酷吏が、罪のないものを罪に陥れること。
だん‐れん【団練】
中国で、住民による自衛武装組織。清代に盛行。→郷勇きょうゆう
たん‐れんが【短連歌】
前句と付句との2句の唱和から成る連歌。↔長連歌
たん‐ろ【坦路】
平らな路。坦道。
だん‐ろ【暖炉・煖炉】
火をたいて室内をあたためる炉。特に、壁に接して作ったもの。〈[季]冬〉
だんろ‐き【断路器】
送電線や配電線を切り離し、あるいは接続する装置。遮断器と異なり、電流が流れているときには操作できない。
たんろく‐ぼん【丹緑本】
江戸初期に刊行された御伽草子、仮名草子、舞の本、浄瑠璃本などの墨摺りの挿絵に手書きで彩色した本。丹(赤)・緑・黄・藍色などで、簡略に彩色する。丹と緑とが最も多く用いられたからいう。
だん‐ろん【談論】
談話と議論。
⇒だんろん‐ふうはつ【談論風発】
だんろん‐ふうはつ【談論風発】
いろいろな意見が活発にかわされること。
⇒だん‐ろん【談論】
だん‐わ【暖和】
気候があたたかくておだやかなこと。
だん‐わ【談話】
①はなし。ものがたり。会話。「炉辺の―」「―室」
②ある事柄についての見解などを述べた話。「首相―」
⇒だんわ‐たい【談話体】
だん‐わく【断惑】
(ダンナクとも)〔仏〕煩悩を断ち切ること。
⇒だんわく‐しょうり【断惑証理】
だんわく‐しょうり【断惑証理】
煩悩を断じて涅槃ねはんの真理を悟ること。
⇒だん‐わく【断惑】
だんわ‐たい【談話体】
日常の談話に近い言葉づかいの文体。福沢諭吉の「福翁自伝」など。
⇒だん‐わ【談話】
民】
中国南部の大河川や沿海地方の水上生活民を呼んだ称。漁業・水運などに従事。水上居民。
たん‐めい【旦明】
あけがた。よあけ。
たん‐めい【短命】
短いいのち。年若くて死ぬこと。わかじに。夭折ようせつ。「―に終わる」「―内閣」↔長命
たんめい‐てがた【単名手形】
手形債務者がただ一人である手形。裏書のない約束手形と引受け済みの自己あて為替手形をいう。
だん‐めつ【断滅】
絶え滅びること。また、絶やし滅ぼすこと。
たん‐めり
(完了の助動詞タリに推量の助動詞メリの付いた形の音便)…ているようだ。
たん‐めん【耽湎】
(「湎」は、おぼれる意)酒色にふけり、すさむこと。耽溺。たんべん。
たん‐めん【赧面】
恥じて顔をあからめること。赤面。
タンメン【湯麺】
(中国語)ゆでた中華そばにスープを加えるか、スープで煮る料理。汁そば。
だん‐めん【段免】
江戸時代、田地が地味によって分けられている場合、同じ等級であっても現実には作毛さくげの劣る田は、年貢率を1〜2段下げたこと。
だん‐めん【断面】
①もののきりくちの面。切断面。
②物事をある観点から見た時、そこに現れている状態。「社会の一―」
⇒だんめん‐ず【断面図】
だんめん‐ず【断面図】‥ヅ
物体をある平面で切ったと仮定して、その内部構造をえがいた図。
⇒だん‐めん【断面】
だん‐めんせき【断面積】
①図形や物体のある切断面における面積。
②〔理〕二つの粒子の散乱や反応の強さを表す量。面積の次元を持ち、現象が起こりやすいほど断面積が大きい。
たん‐もう【誕妄】‥マウ
うそ。いつわり。でたらめ。
たん‐もち【痰持ち】
痰の出る持病のある人。
たん‐もの【反物・段物】
①1反に仕上げてある織物。太物。↔疋物ひきもの。→たん(段・反)。
②一般に、呉服。「―屋」
だん‐もの【段物】
①能で、一曲の眼目とされるような謡いどころ、舞いどころのうち、曲くせ・狂くるいなどの定型に属さない一段。「三井寺」の鐘の段、「自然居士」のささらの段の類。
②義太夫節で、各段のうちの有名なあるいは特殊な一段。それを集めたものを正本・院本まるほんに対して「段物集」という。主として道行みちゆき・景事けいごとなどから選ぶ。
③常磐津や新内節で、義太夫節からの移入曲。短編の端物はものに対して、長編の曲を指す。
④日本舞踊で、常磐津・清元など浄瑠璃の伴奏による舞踊劇。
⑤箏曲そうきょくの曲種。歌のない器楽曲で、数段で一曲を構成する。各段の拍数は一定。速度は漸次急。八橋検校の「六段の調しらべ」など。しらべもの。
だん‐もよう【段模様】‥ヤウ
段々に染めた模様。段染めの模様。
たん‐もん【探問】
さぐりとうこと。
だん‐もん【断文】
断罪の命令文。断罪文。
たん‐や【短夜】
短い夜。夏の短い夜。みじかよ。↔長夜
たん‐や【鍛冶】
かじ。かぬち。
たん‐やく【丹薬】
不老不死の仙薬。道士の作った煉薬ねりやく。
だん‐やく【弾薬】
弾丸と、それを発射するための火薬の総称。たまぐすり。「―庫」
たん‐ゆう【胆勇】
大胆で勇気のあること。「―を備える」
たんゆう【探幽】‥イウ
⇒かのうたんゆう(狩野探幽)
だん‐ゆう【男優】‥イウ
男の俳優。↔女優
だん‐よ【談余】
はなしのついで。
たん‐よう【単葉】‥エフ
①葉身が小葉に分裂することがない葉。サクラ・ケヤキなどの葉。
②飛行機の主翼が1枚であること。↔複葉。
⇒たんよう‐き【単葉機】
たん‐よう【端陽】‥ヤウ
(→)端午たんごに同じ。
たんよう‐き【単葉機】‥エフ‥
主翼が1枚の飛行機。単葉飛行機。↔複葉機
⇒たん‐よう【単葉】
たん‐よく【貪欲】
欲が深いこと。どんよく。
たん‐らく【耽楽】
酒色にふけり楽しむこと。
たん‐らく【短絡】
①(short circuit)電気回路の2点間を小さい抵抗の導線で接続すること。また、電気回路の絶縁が破れるなどして、抵抗の非常に小さな回路を形成すること。ショート。
②(比喩的に)単純には結びつかない関係にある二つの物事を、直接・簡単に結びつけて論じること。
⇒たんらく‐しけん【短絡試験】
⇒たんらく‐てき【短絡的】
⇒たんらく‐はんのう【短絡反応】
だん‐らく【段落】
①長い文章中の大きな切れ目。段。
②転じて、物事のくぎり。「仕事が一―ついた」
たんらく‐しけん【短絡試験】
電気機器の端子間を短絡して行う試験。
⇒たん‐らく【短絡】
たんらく‐てき【短絡的】
筋道立てて考えずに物事を結びつけて論ずるさま。「―な思考」
⇒たん‐らく【短絡】
たんらく‐はんのう【短絡反応】‥オウ
〔心〕(→)近道反応に同じ。
⇒たん‐らく【短絡】
たん‐らん【貪婪】
きわめて欲が深いこと。どんらん。
だん‐らん【団欒】
①月などのまるいこと。まどか。
②集まって車座にすわること。まどい。
③集まってなごやかに楽しむこと。親密で楽しい会合。「一家―」
たん‐り【単利】
元金だけに対する利子。↔複利。
⇒たんり‐ほう【単利法】
たん‐り【単離】
〔化〕混合物中から一つの物質だけを純粋な形で取り出すこと。
たん‐り【貪吏】
欲が深く、人民の財をむさぼりとる官公吏。史記抄「―の様ににはかに盗取こそせねども」
たん‐り【貪利】
利益をむさぼること。あくまで利益を収めること。
たん‐り【短籬】
たけの低いまがき。
たん‐りつ【単立】
単独で設立されていること。「―宗教法人」
たん‐りつ【単律】
音楽で、呂・律の二つの音調に分けた時、律の音階だけが行われること。徒然草「唐土は呂の国なり。律の音なし。和国は、―の国にて、呂の音なし」
たんり‐ほう【単利法】‥ハフ
利息計算で、前期間の利息を元金に加算せず、元金のみに対し次期の利息を計算する法。↔複利法
⇒たん‐り【単利】
たん‐りゃく【胆略】
大胆で知略のあること。
たん‐りゅう【湍流】‥リウ
水勢の急な流れ。はやせ。急流。奔流。
だん‐りゅう【断流】‥リウ
川の水が河口まで届かず跡絶えてしまうこと。
だん‐りゅう【暖流】‥リウ
熱帯・亜熱帯の海域に源をもち、高緯度に向かって流れる海流。黒潮・湾流など。↔寒流
たんりゅう‐こうぞう【単粒構造】‥リフ‥ザウ
土壌を構成する土粒がそれぞれ独立して集積し、その間に何ら関係のない構造。ゆるい砂土や重粘な埴土はこの組織をなす。↔団粒構造
だんりゅう‐こうぞう【団粒構造】‥リフ‥ザウ
微細な土壌粒子が腐植や石灰などで膠着されて多孔質の肉眼で見える大きさの小粒をなすもの。通気・通水性が良好であるとともに、水分をよく保持し、一般に、植物の生育に適するので、土壌改善の目標とされる。↔単粒構造
たん‐りょ【短慮】
①考えが浅いこと。浅慮。毎月抄「更に―及び難くぞ覚え侍る」。「―を戒める」
②気みじか。せっかち。短気。浄瑠璃、嫗山姥こもちやまうば「世に便りなきうき節に、もし御―のこともやと」。「―な男」
⇒たんりょ‐じん【短慮人】
たん‐りょう【単寮】‥レウ
禅寺で、一人で住む寮舎。
たんりょう‐たい【単量体】‥リヤウ‥
(monomer)重合体を構成する基本単位物質。例えばエチレンはポリエチレンの単量体。モノマー。
たん‐りょく【胆力】
ものに恐れず臆しない気力。度胸。「―が据っている」「―を練る」
たん‐りょく【淡緑】
うすいみどり。
だん‐りょく【弾力】
①はずむ力。物体が変形に抗して、原形に復しようとする力。
②状況の変化に適応する柔軟性。「―的に考える」
⇒だんりょく‐せい【弾力性】
だんりょく‐せい【弾力性】
弾力のある性質。「規則に―をもたせる」
⇒だん‐りょく【弾力】
たんりょく‐ぼん【丹緑本】
⇒たんろくぼん
たんりょ‐じん【短慮人】
短気な人。怒りっぽい人。日葡辞書「ヒ(火)ヲフルヤウナタンリョジンヂャ」
⇒たん‐りょ【短慮】
たん‐りん【貪吝】
むさぼりとって出し惜しむこと。
だん‐りん【檀林・談林】
①(栴檀林の略)仏教の学問所。平安時代の檀林寺に始まるが、学問所を檀林と呼ぶようになったのは室町末期で、近世、各宗で設ける。関東十八檀林の類。学寮。
②寺の異称。
③談林風。
⇒だんりん‐は【談林派・檀林派】
⇒だんりん‐ふう【談林風・檀林風】
だんりん‐こうごう【檀林皇后】‥クワウ‥
橘嘉智子たちばなのかちこの異称。
だんりん‐じ【檀林寺】
京都の天竜寺付近にあった日本最古とされる禅院。承和(834〜848)年中、檀林皇后の願によって唐僧義空が開山。室町時代に再興して京都尼五山の一つとなったが廃絶。
だんりんとっぴゃくいん【談林十百韻】‥ヰン
俳諧集。2冊。田代松意編。1675年(延宝3)刊。宗因風を志向する江戸の俳人たちの百韻俳諧を10巻集めたもの。談林俳諧・談林風の称は本書題名による。
だんりん‐は【談林派・檀林派】
談林風を奉じた俳諧の流派。
⇒だん‐りん【檀林・談林】
だんりん‐ふう【談林風・檀林風】
江戸前期、延宝・天和(1673〜1684)頃に流行した俳諧の一風・一派。もとは江戸の田代松意の一派の結社を指すが、のち大坂の西山宗因を中心とする新風の汎称となる。伝統的・法式的な貞徳流に反抗して、軽妙な口語使用と滑稽な着想によって流行したが、蕉風しょうふうの興るに及んで衰えた。宗因風。
⇒だん‐りん【檀林・談林】
たん‐れい【淡麗】
日本酒の味や口当りに強い癖がなく、すっきりと滑らかである様子。
たん‐れい【貪戻】
むさぼって人の道にそむくこと。浄瑠璃、国性爺合戦「一人―なれば一国乱を起すといへり」
たん‐れい【端麗】
かたち・すがたがととのって、うるわしいこと。「容姿―」
だん‐れい‐ぼう【暖冷房】‥バウ
(→)冷暖房に同じ。
たん‐れつ【単列】
ひとならび。1列。
⇒たんれつ‐きかん【単列機関】
だん‐れつ【断裂】
断ち裂かれること。
たんれつ‐きかん【単列機関】‥クワン
シリンダーが1列に並んで1本のクランク軸によって動力を他へ伝動する機関。直列機関の1列のもの。
⇒たん‐れつ【単列】
たん‐れん【鍛練・鍛錬・鍛煉】
①金属をきたえねること。〈日葡辞書〉
②修養・訓練を積んで心身をきたえたり技能をみがいたりすること。浮世物語「通力あるが如くなる上手の―ある者」。「体を―する」
③酷吏が、罪のないものを罪に陥れること。
だん‐れん【団練】
中国で、住民による自衛武装組織。清代に盛行。→郷勇きょうゆう
たん‐れんが【短連歌】
前句と付句との2句の唱和から成る連歌。↔長連歌
たん‐ろ【坦路】
平らな路。坦道。
だん‐ろ【暖炉・煖炉】
火をたいて室内をあたためる炉。特に、壁に接して作ったもの。〈[季]冬〉
だんろ‐き【断路器】
送電線や配電線を切り離し、あるいは接続する装置。遮断器と異なり、電流が流れているときには操作できない。
たんろく‐ぼん【丹緑本】
江戸初期に刊行された御伽草子、仮名草子、舞の本、浄瑠璃本などの墨摺りの挿絵に手書きで彩色した本。丹(赤)・緑・黄・藍色などで、簡略に彩色する。丹と緑とが最も多く用いられたからいう。
だん‐ろん【談論】
談話と議論。
⇒だんろん‐ふうはつ【談論風発】
だんろん‐ふうはつ【談論風発】
いろいろな意見が活発にかわされること。
⇒だん‐ろん【談論】
だん‐わ【暖和】
気候があたたかくておだやかなこと。
だん‐わ【談話】
①はなし。ものがたり。会話。「炉辺の―」「―室」
②ある事柄についての見解などを述べた話。「首相―」
⇒だんわ‐たい【談話体】
だん‐わく【断惑】
(ダンナクとも)〔仏〕煩悩を断ち切ること。
⇒だんわく‐しょうり【断惑証理】
だんわく‐しょうり【断惑証理】
煩悩を断じて涅槃ねはんの真理を悟ること。
⇒だん‐わく【断惑】
だんわ‐たい【談話体】
日常の談話に近い言葉づかいの文体。福沢諭吉の「福翁自伝」など。
⇒だん‐わ【談話】
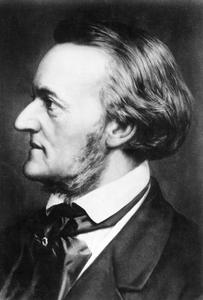 →歌劇「タンホイザー」序曲
提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
たん‐ぼいん【単母音】
一つの短母音または長母音が単一音節を成したもの。二重母音・三重母音に対していう。
たん‐ぼいん【短母音】
(short vowel)長さが1拍分(普通の長さ)の母音。みじかぼいん。↔長母音
たん‐ぼう【探訪】‥バウ
社会の出来事や事件の真相をさぐりに出向くこと。若松賤子、小公子「英国新聞は―の届く丈詳細に書き立て」。「―記事」
だん‐ぼう【暖房・煖房】‥バウ
①室内をあたためること。また、その装置。〈[季]冬〉。「―の効いた部屋」↔冷房。
②転宅の祝い。わたましのいわい。
だん‐ぽう【暖飽】‥パウ
(暖衣飽食の略)暖かに衣服を着、飽きるまで食物をとること。何の不足もなく生活すること。
だん‐ぽう【壇法】‥ポフ
〔仏〕修法しゅほうのときの壇を設ける方法。また、その修法。
だん‐ぽう【檀方・旦方】‥パウ
①檀家。檀徒。浄瑠璃、八百屋お七「お手前ばかりが―か不敵な差配と叱られて」
②転じて、仲間。知り合い。狂言、鈍太郎「それがしは―衆に長刀使ひを持つてゐるによつて」
たんほう‐ちょうよう【丹鳳朝陽】‥テウヤウ
(画題)朝日に丹色の鳳凰を描いたもの。瑞祥をあらわす。
だん‐ボール【段ボール】
包装用・運送用板紙の一つ。波状に成形した紙の片面または両面に厚紙を貼り合わせたもの。
たんぽ‐かけめ【担保掛目】
担保物件の時価にかけて、その評価額を決める比率。株式の信用取引などでは、これを変更することによって相場を調整する。率。掛目。
⇒たん‐ぽ【担保】
たんぽ‐かしつけ【担保貸付】
銀行の貸付で、担保品をとるもの。担保付貸付。
⇒たん‐ぽ【担保】
たん‐ぼく【淡墨】
うすい墨色。うすずみ。
たんぽ‐せいきゅうけん【担保請求権】‥キウ‥
担保の提供を請求しうる権利。
⇒たん‐ぽ【担保】
たんぽつき‐こうさい【担保付公債】
物的担保によりその元利金支払が保証されている公債。
⇒たん‐ぽ【担保】
たんぽつき‐しゃさい【担保付社債】
社債発行に際し、その元利金の支払を確実にさせるために、会社が特に担保を提供した社債。
⇒たん‐ぽ【担保】
たんぽ‐ぶつ【担保物】
担保として提供された物。抵当不動産・質物の類。
⇒たん‐ぽ【担保】
たんぽ‐ぶっけん【担保物権】
一定の債権の担保を目的とする物権。民法上、留置権・先取特権・質権・抵当権の四つに大別する。
⇒たん‐ぽ【担保】
たんぽぽ【蒲公英】
キク科タンポポ属の多年草の総称。全世界に広く分布。日本にはカンサイタンポポ・エゾタンポポ・シロバナタンポポ、また帰化植物のセイヨウタンポポなど10種以上あり、普通にはカントウタンポポをいう。根はゴボウ状。葉は土際に根生葉を作り、倒披針形で縁は羽裂。春、花茎を出し、舌状花だけから成る黄色の頭状花をつける。痩果は褐色で、冠毛は白色、風によって四散する。若葉は食用、帯根全体を乾燥したものが漢方生薬の蒲公英ほこうえいで健胃・催乳剤。たな。〈[季]春〉。文明本節用集「蒲公草、タンホホ」
カントウタンポポ
撮影:関戸 勇
→歌劇「タンホイザー」序曲
提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)
たん‐ぼいん【単母音】
一つの短母音または長母音が単一音節を成したもの。二重母音・三重母音に対していう。
たん‐ぼいん【短母音】
(short vowel)長さが1拍分(普通の長さ)の母音。みじかぼいん。↔長母音
たん‐ぼう【探訪】‥バウ
社会の出来事や事件の真相をさぐりに出向くこと。若松賤子、小公子「英国新聞は―の届く丈詳細に書き立て」。「―記事」
だん‐ぼう【暖房・煖房】‥バウ
①室内をあたためること。また、その装置。〈[季]冬〉。「―の効いた部屋」↔冷房。
②転宅の祝い。わたましのいわい。
だん‐ぽう【暖飽】‥パウ
(暖衣飽食の略)暖かに衣服を着、飽きるまで食物をとること。何の不足もなく生活すること。
だん‐ぽう【壇法】‥ポフ
〔仏〕修法しゅほうのときの壇を設ける方法。また、その修法。
だん‐ぽう【檀方・旦方】‥パウ
①檀家。檀徒。浄瑠璃、八百屋お七「お手前ばかりが―か不敵な差配と叱られて」
②転じて、仲間。知り合い。狂言、鈍太郎「それがしは―衆に長刀使ひを持つてゐるによつて」
たんほう‐ちょうよう【丹鳳朝陽】‥テウヤウ
(画題)朝日に丹色の鳳凰を描いたもの。瑞祥をあらわす。
だん‐ボール【段ボール】
包装用・運送用板紙の一つ。波状に成形した紙の片面または両面に厚紙を貼り合わせたもの。
たんぽ‐かけめ【担保掛目】
担保物件の時価にかけて、その評価額を決める比率。株式の信用取引などでは、これを変更することによって相場を調整する。率。掛目。
⇒たん‐ぽ【担保】
たんぽ‐かしつけ【担保貸付】
銀行の貸付で、担保品をとるもの。担保付貸付。
⇒たん‐ぽ【担保】
たん‐ぼく【淡墨】
うすい墨色。うすずみ。
たんぽ‐せいきゅうけん【担保請求権】‥キウ‥
担保の提供を請求しうる権利。
⇒たん‐ぽ【担保】
たんぽつき‐こうさい【担保付公債】
物的担保によりその元利金支払が保証されている公債。
⇒たん‐ぽ【担保】
たんぽつき‐しゃさい【担保付社債】
社債発行に際し、その元利金の支払を確実にさせるために、会社が特に担保を提供した社債。
⇒たん‐ぽ【担保】
たんぽ‐ぶつ【担保物】
担保として提供された物。抵当不動産・質物の類。
⇒たん‐ぽ【担保】
たんぽ‐ぶっけん【担保物権】
一定の債権の担保を目的とする物権。民法上、留置権・先取特権・質権・抵当権の四つに大別する。
⇒たん‐ぽ【担保】
たんぽぽ【蒲公英】
キク科タンポポ属の多年草の総称。全世界に広く分布。日本にはカンサイタンポポ・エゾタンポポ・シロバナタンポポ、また帰化植物のセイヨウタンポポなど10種以上あり、普通にはカントウタンポポをいう。根はゴボウ状。葉は土際に根生葉を作り、倒披針形で縁は羽裂。春、花茎を出し、舌状花だけから成る黄色の頭状花をつける。痩果は褐色で、冠毛は白色、風によって四散する。若葉は食用、帯根全体を乾燥したものが漢方生薬の蒲公英ほこうえいで健胃・催乳剤。たな。〈[季]春〉。文明本節用集「蒲公草、タンホホ」
カントウタンポポ
撮影:関戸 勇
 シロバナタンポポ
撮影:関戸 勇
シロバナタンポポ
撮影:関戸 勇
 セイヨウタンポポ
撮影:関戸 勇
セイヨウタンポポ
撮影:関戸 勇
 タンポポ(実)
撮影:関戸 勇
タンポポ(実)
撮影:関戸 勇
 たんぼ‐みち【田圃道】
田畑の中を通っている道。
⇒たんぼ【田圃】
たんぽ‐やり【たんぽ槍】
柄の先にたんぽをつけた稽古用の槍。牡丹槍。
⇒たんぽ
タンボラ【Tambora】
インドネシア中部のスンバワ島にある活火山。1815年に、有史以来世界最大の噴火。爆発により山体を破壊、噴出物の量は100〜150立方キロメートルに及ぶ。噴火による直接の死者1万人、餓死・病死者8万2000人。
だんぼら‐ぼ
水中に大きな物を投げ入れた時の音。どんぶり。浄瑠璃、博多小女郎波枕「大勢かかつて―、辺ほとりも知れぬ海の中」
タンポン【Tampon ドイツ】
消毒した綿・ガーゼを円筒状あるいは球状にし、鼻腔・膣に挿入して止血または分泌液の吸収をさせるもの。綿球。止血栓。
たんほんい‐せい【単本位制】‥ヰ‥
本位貨幣が、単一の金属の一定純量と一定の関係を保つような本位制度。↔複本位制
たんま
(児童語)遊戯の中断。タイム。「―をかける」
たん‐まい【段米・反米】
中世、朝廷や幕府の行事に際し、段別に応じて臨時に賦課した税米。→段銭
だん‐まく【段幕】
紅白などの布を横に幾段にも縫い合わせた幕。
だん‐まく【弾幕】
敵の攻撃を防ぐため、横に砲列をしいてたくさんの弾丸を一度に発射すること。幕にたとえた言い方。「―を張る」
だんまく‐しゅぜん【断悪修善】
⇒だんあくしゅぜん
たん‐まつ【端末】
①物のはし。すえ。〈日葡辞書〉
②端末装置の略。
⇒たんまつ‐そうち【端末装置】
たんまつ‐そうち【端末装置】‥サウ‥
(terminal unit)コンピューター‐システムで、ホスト‐コンピューターとのデータのやりとりに特化した装置。
⇒たん‐まつ【端末】
だん‐まつま【断末魔・断末摩】
〔仏〕(末魔は、梵語marmanの音訳。支節・死穴と訳す。体の中にある特殊の急所で、他のものが触れれば劇痛を起こして必ず死ぬという)息を引き取るまぎわの苦痛。
ダンマパダ【Dhammapada パーリ】
〔仏〕(→)法句経ほっくきょうに同じ。
たんまり
〔副〕
①十分に。浮世風呂2「―と湯へもはいれません」
②金銭や物が満足できるほど十分であるさま。「―せしめる」
だんまり【黙り】
(ダマリの撥音化)
①だまっていること。無言。「返答に詰まって―をきめこむ」
②ことわらないこと。無断。
③歌舞伎で、登場人物が無言で闇中にさぐりあう動作を様式化したもの、またその場面。普通、時代狂言のものをいい、世話狂言のものは「世話だんまり」という。暗闘。暗争。
⇒だんまり‐ぼう【黙り坊】
だんまり‐ぼう【黙り坊】‥バウ
だまっている人。口かずの少ない人。だまりん坊。
⇒だんまり【黙り】
たん‐み【淡味・澹味】
①あわいあじ。
②あっさりとした趣味。
たん‐みん【
たんぼ‐みち【田圃道】
田畑の中を通っている道。
⇒たんぼ【田圃】
たんぽ‐やり【たんぽ槍】
柄の先にたんぽをつけた稽古用の槍。牡丹槍。
⇒たんぽ
タンボラ【Tambora】
インドネシア中部のスンバワ島にある活火山。1815年に、有史以来世界最大の噴火。爆発により山体を破壊、噴出物の量は100〜150立方キロメートルに及ぶ。噴火による直接の死者1万人、餓死・病死者8万2000人。
だんぼら‐ぼ
水中に大きな物を投げ入れた時の音。どんぶり。浄瑠璃、博多小女郎波枕「大勢かかつて―、辺ほとりも知れぬ海の中」
タンポン【Tampon ドイツ】
消毒した綿・ガーゼを円筒状あるいは球状にし、鼻腔・膣に挿入して止血または分泌液の吸収をさせるもの。綿球。止血栓。
たんほんい‐せい【単本位制】‥ヰ‥
本位貨幣が、単一の金属の一定純量と一定の関係を保つような本位制度。↔複本位制
たんま
(児童語)遊戯の中断。タイム。「―をかける」
たん‐まい【段米・反米】
中世、朝廷や幕府の行事に際し、段別に応じて臨時に賦課した税米。→段銭
だん‐まく【段幕】
紅白などの布を横に幾段にも縫い合わせた幕。
だん‐まく【弾幕】
敵の攻撃を防ぐため、横に砲列をしいてたくさんの弾丸を一度に発射すること。幕にたとえた言い方。「―を張る」
だんまく‐しゅぜん【断悪修善】
⇒だんあくしゅぜん
たん‐まつ【端末】
①物のはし。すえ。〈日葡辞書〉
②端末装置の略。
⇒たんまつ‐そうち【端末装置】
たんまつ‐そうち【端末装置】‥サウ‥
(terminal unit)コンピューター‐システムで、ホスト‐コンピューターとのデータのやりとりに特化した装置。
⇒たん‐まつ【端末】
だん‐まつま【断末魔・断末摩】
〔仏〕(末魔は、梵語marmanの音訳。支節・死穴と訳す。体の中にある特殊の急所で、他のものが触れれば劇痛を起こして必ず死ぬという)息を引き取るまぎわの苦痛。
ダンマパダ【Dhammapada パーリ】
〔仏〕(→)法句経ほっくきょうに同じ。
たんまり
〔副〕
①十分に。浮世風呂2「―と湯へもはいれません」
②金銭や物が満足できるほど十分であるさま。「―せしめる」
だんまり【黙り】
(ダマリの撥音化)
①だまっていること。無言。「返答に詰まって―をきめこむ」
②ことわらないこと。無断。
③歌舞伎で、登場人物が無言で闇中にさぐりあう動作を様式化したもの、またその場面。普通、時代狂言のものをいい、世話狂言のものは「世話だんまり」という。暗闘。暗争。
⇒だんまり‐ぼう【黙り坊】
だんまり‐ぼう【黙り坊】‥バウ
だまっている人。口かずの少ない人。だまりん坊。
⇒だんまり【黙り】
たん‐み【淡味・澹味】
①あわいあじ。
②あっさりとした趣味。
たん‐みん【 民】
中国南部の大河川や沿海地方の水上生活民を呼んだ称。漁業・水運などに従事。水上居民。
たん‐めい【旦明】
あけがた。よあけ。
たん‐めい【短命】
短いいのち。年若くて死ぬこと。わかじに。夭折ようせつ。「―に終わる」「―内閣」↔長命
たんめい‐てがた【単名手形】
手形債務者がただ一人である手形。裏書のない約束手形と引受け済みの自己あて為替手形をいう。
だん‐めつ【断滅】
絶え滅びること。また、絶やし滅ぼすこと。
たん‐めり
(完了の助動詞タリに推量の助動詞メリの付いた形の音便)…ているようだ。
たん‐めん【耽湎】
(「湎」は、おぼれる意)酒色にふけり、すさむこと。耽溺。たんべん。
たん‐めん【赧面】
恥じて顔をあからめること。赤面。
タンメン【湯麺】
(中国語)ゆでた中華そばにスープを加えるか、スープで煮る料理。汁そば。
だん‐めん【段免】
江戸時代、田地が地味によって分けられている場合、同じ等級であっても現実には作毛さくげの劣る田は、年貢率を1〜2段下げたこと。
だん‐めん【断面】
①もののきりくちの面。切断面。
②物事をある観点から見た時、そこに現れている状態。「社会の一―」
⇒だんめん‐ず【断面図】
だんめん‐ず【断面図】‥ヅ
物体をある平面で切ったと仮定して、その内部構造をえがいた図。
⇒だん‐めん【断面】
だん‐めんせき【断面積】
①図形や物体のある切断面における面積。
②〔理〕二つの粒子の散乱や反応の強さを表す量。面積の次元を持ち、現象が起こりやすいほど断面積が大きい。
たん‐もう【誕妄】‥マウ
うそ。いつわり。でたらめ。
たん‐もち【痰持ち】
痰の出る持病のある人。
たん‐もの【反物・段物】
①1反に仕上げてある織物。太物。↔疋物ひきもの。→たん(段・反)。
②一般に、呉服。「―屋」
だん‐もの【段物】
①能で、一曲の眼目とされるような謡いどころ、舞いどころのうち、曲くせ・狂くるいなどの定型に属さない一段。「三井寺」の鐘の段、「自然居士」のささらの段の類。
②義太夫節で、各段のうちの有名なあるいは特殊な一段。それを集めたものを正本・院本まるほんに対して「段物集」という。主として道行みちゆき・景事けいごとなどから選ぶ。
③常磐津や新内節で、義太夫節からの移入曲。短編の端物はものに対して、長編の曲を指す。
④日本舞踊で、常磐津・清元など浄瑠璃の伴奏による舞踊劇。
⑤箏曲そうきょくの曲種。歌のない器楽曲で、数段で一曲を構成する。各段の拍数は一定。速度は漸次急。八橋検校の「六段の調しらべ」など。しらべもの。
だん‐もよう【段模様】‥ヤウ
段々に染めた模様。段染めの模様。
たん‐もん【探問】
さぐりとうこと。
だん‐もん【断文】
断罪の命令文。断罪文。
たん‐や【短夜】
短い夜。夏の短い夜。みじかよ。↔長夜
たん‐や【鍛冶】
かじ。かぬち。
たん‐やく【丹薬】
不老不死の仙薬。道士の作った煉薬ねりやく。
だん‐やく【弾薬】
弾丸と、それを発射するための火薬の総称。たまぐすり。「―庫」
たん‐ゆう【胆勇】
大胆で勇気のあること。「―を備える」
たんゆう【探幽】‥イウ
⇒かのうたんゆう(狩野探幽)
だん‐ゆう【男優】‥イウ
男の俳優。↔女優
だん‐よ【談余】
はなしのついで。
たん‐よう【単葉】‥エフ
①葉身が小葉に分裂することがない葉。サクラ・ケヤキなどの葉。
②飛行機の主翼が1枚であること。↔複葉。
⇒たんよう‐き【単葉機】
たん‐よう【端陽】‥ヤウ
(→)端午たんごに同じ。
たんよう‐き【単葉機】‥エフ‥
主翼が1枚の飛行機。単葉飛行機。↔複葉機
⇒たん‐よう【単葉】
たん‐よく【貪欲】
欲が深いこと。どんよく。
たん‐らく【耽楽】
酒色にふけり楽しむこと。
たん‐らく【短絡】
①(short circuit)電気回路の2点間を小さい抵抗の導線で接続すること。また、電気回路の絶縁が破れるなどして、抵抗の非常に小さな回路を形成すること。ショート。
②(比喩的に)単純には結びつかない関係にある二つの物事を、直接・簡単に結びつけて論じること。
⇒たんらく‐しけん【短絡試験】
⇒たんらく‐てき【短絡的】
⇒たんらく‐はんのう【短絡反応】
だん‐らく【段落】
①長い文章中の大きな切れ目。段。
②転じて、物事のくぎり。「仕事が一―ついた」
たんらく‐しけん【短絡試験】
電気機器の端子間を短絡して行う試験。
⇒たん‐らく【短絡】
たんらく‐てき【短絡的】
筋道立てて考えずに物事を結びつけて論ずるさま。「―な思考」
⇒たん‐らく【短絡】
たんらく‐はんのう【短絡反応】‥オウ
〔心〕(→)近道反応に同じ。
⇒たん‐らく【短絡】
たん‐らん【貪婪】
きわめて欲が深いこと。どんらん。
だん‐らん【団欒】
①月などのまるいこと。まどか。
②集まって車座にすわること。まどい。
③集まってなごやかに楽しむこと。親密で楽しい会合。「一家―」
たん‐り【単利】
元金だけに対する利子。↔複利。
⇒たんり‐ほう【単利法】
たん‐り【単離】
〔化〕混合物中から一つの物質だけを純粋な形で取り出すこと。
たん‐り【貪吏】
欲が深く、人民の財をむさぼりとる官公吏。史記抄「―の様ににはかに盗取こそせねども」
たん‐り【貪利】
利益をむさぼること。あくまで利益を収めること。
たん‐り【短籬】
たけの低いまがき。
たん‐りつ【単立】
単独で設立されていること。「―宗教法人」
たん‐りつ【単律】
音楽で、呂・律の二つの音調に分けた時、律の音階だけが行われること。徒然草「唐土は呂の国なり。律の音なし。和国は、―の国にて、呂の音なし」
たんり‐ほう【単利法】‥ハフ
利息計算で、前期間の利息を元金に加算せず、元金のみに対し次期の利息を計算する法。↔複利法
⇒たん‐り【単利】
たん‐りゃく【胆略】
大胆で知略のあること。
たん‐りゅう【湍流】‥リウ
水勢の急な流れ。はやせ。急流。奔流。
だん‐りゅう【断流】‥リウ
川の水が河口まで届かず跡絶えてしまうこと。
だん‐りゅう【暖流】‥リウ
熱帯・亜熱帯の海域に源をもち、高緯度に向かって流れる海流。黒潮・湾流など。↔寒流
たんりゅう‐こうぞう【単粒構造】‥リフ‥ザウ
土壌を構成する土粒がそれぞれ独立して集積し、その間に何ら関係のない構造。ゆるい砂土や重粘な埴土はこの組織をなす。↔団粒構造
だんりゅう‐こうぞう【団粒構造】‥リフ‥ザウ
微細な土壌粒子が腐植や石灰などで膠着されて多孔質の肉眼で見える大きさの小粒をなすもの。通気・通水性が良好であるとともに、水分をよく保持し、一般に、植物の生育に適するので、土壌改善の目標とされる。↔単粒構造
たん‐りょ【短慮】
①考えが浅いこと。浅慮。毎月抄「更に―及び難くぞ覚え侍る」。「―を戒める」
②気みじか。せっかち。短気。浄瑠璃、嫗山姥こもちやまうば「世に便りなきうき節に、もし御―のこともやと」。「―な男」
⇒たんりょ‐じん【短慮人】
たん‐りょう【単寮】‥レウ
禅寺で、一人で住む寮舎。
たんりょう‐たい【単量体】‥リヤウ‥
(monomer)重合体を構成する基本単位物質。例えばエチレンはポリエチレンの単量体。モノマー。
たん‐りょく【胆力】
ものに恐れず臆しない気力。度胸。「―が据っている」「―を練る」
たん‐りょく【淡緑】
うすいみどり。
だん‐りょく【弾力】
①はずむ力。物体が変形に抗して、原形に復しようとする力。
②状況の変化に適応する柔軟性。「―的に考える」
⇒だんりょく‐せい【弾力性】
だんりょく‐せい【弾力性】
弾力のある性質。「規則に―をもたせる」
⇒だん‐りょく【弾力】
たんりょく‐ぼん【丹緑本】
⇒たんろくぼん
たんりょ‐じん【短慮人】
短気な人。怒りっぽい人。日葡辞書「ヒ(火)ヲフルヤウナタンリョジンヂャ」
⇒たん‐りょ【短慮】
たん‐りん【貪吝】
むさぼりとって出し惜しむこと。
だん‐りん【檀林・談林】
①(栴檀林の略)仏教の学問所。平安時代の檀林寺に始まるが、学問所を檀林と呼ぶようになったのは室町末期で、近世、各宗で設ける。関東十八檀林の類。学寮。
②寺の異称。
③談林風。
⇒だんりん‐は【談林派・檀林派】
⇒だんりん‐ふう【談林風・檀林風】
だんりん‐こうごう【檀林皇后】‥クワウ‥
橘嘉智子たちばなのかちこの異称。
だんりん‐じ【檀林寺】
京都の天竜寺付近にあった日本最古とされる禅院。承和(834〜848)年中、檀林皇后の願によって唐僧義空が開山。室町時代に再興して京都尼五山の一つとなったが廃絶。
だんりんとっぴゃくいん【談林十百韻】‥ヰン
俳諧集。2冊。田代松意編。1675年(延宝3)刊。宗因風を志向する江戸の俳人たちの百韻俳諧を10巻集めたもの。談林俳諧・談林風の称は本書題名による。
だんりん‐は【談林派・檀林派】
談林風を奉じた俳諧の流派。
⇒だん‐りん【檀林・談林】
だんりん‐ふう【談林風・檀林風】
江戸前期、延宝・天和(1673〜1684)頃に流行した俳諧の一風・一派。もとは江戸の田代松意の一派の結社を指すが、のち大坂の西山宗因を中心とする新風の汎称となる。伝統的・法式的な貞徳流に反抗して、軽妙な口語使用と滑稽な着想によって流行したが、蕉風しょうふうの興るに及んで衰えた。宗因風。
⇒だん‐りん【檀林・談林】
たん‐れい【淡麗】
日本酒の味や口当りに強い癖がなく、すっきりと滑らかである様子。
たん‐れい【貪戻】
むさぼって人の道にそむくこと。浄瑠璃、国性爺合戦「一人―なれば一国乱を起すといへり」
たん‐れい【端麗】
かたち・すがたがととのって、うるわしいこと。「容姿―」
だん‐れい‐ぼう【暖冷房】‥バウ
(→)冷暖房に同じ。
たん‐れつ【単列】
ひとならび。1列。
⇒たんれつ‐きかん【単列機関】
だん‐れつ【断裂】
断ち裂かれること。
たんれつ‐きかん【単列機関】‥クワン
シリンダーが1列に並んで1本のクランク軸によって動力を他へ伝動する機関。直列機関の1列のもの。
⇒たん‐れつ【単列】
たん‐れん【鍛練・鍛錬・鍛煉】
①金属をきたえねること。〈日葡辞書〉
②修養・訓練を積んで心身をきたえたり技能をみがいたりすること。浮世物語「通力あるが如くなる上手の―ある者」。「体を―する」
③酷吏が、罪のないものを罪に陥れること。
だん‐れん【団練】
中国で、住民による自衛武装組織。清代に盛行。→郷勇きょうゆう
たん‐れんが【短連歌】
前句と付句との2句の唱和から成る連歌。↔長連歌
たん‐ろ【坦路】
平らな路。坦道。
だん‐ろ【暖炉・煖炉】
火をたいて室内をあたためる炉。特に、壁に接して作ったもの。〈[季]冬〉
だんろ‐き【断路器】
送電線や配電線を切り離し、あるいは接続する装置。遮断器と異なり、電流が流れているときには操作できない。
たんろく‐ぼん【丹緑本】
江戸初期に刊行された御伽草子、仮名草子、舞の本、浄瑠璃本などの墨摺りの挿絵に手書きで彩色した本。丹(赤)・緑・黄・藍色などで、簡略に彩色する。丹と緑とが最も多く用いられたからいう。
だん‐ろん【談論】
談話と議論。
⇒だんろん‐ふうはつ【談論風発】
だんろん‐ふうはつ【談論風発】
いろいろな意見が活発にかわされること。
⇒だん‐ろん【談論】
だん‐わ【暖和】
気候があたたかくておだやかなこと。
だん‐わ【談話】
①はなし。ものがたり。会話。「炉辺の―」「―室」
②ある事柄についての見解などを述べた話。「首相―」
⇒だんわ‐たい【談話体】
だん‐わく【断惑】
(ダンナクとも)〔仏〕煩悩を断ち切ること。
⇒だんわく‐しょうり【断惑証理】
だんわく‐しょうり【断惑証理】
煩悩を断じて涅槃ねはんの真理を悟ること。
⇒だん‐わく【断惑】
だんわ‐たい【談話体】
日常の談話に近い言葉づかいの文体。福沢諭吉の「福翁自伝」など。
⇒だん‐わ【談話】
民】
中国南部の大河川や沿海地方の水上生活民を呼んだ称。漁業・水運などに従事。水上居民。
たん‐めい【旦明】
あけがた。よあけ。
たん‐めい【短命】
短いいのち。年若くて死ぬこと。わかじに。夭折ようせつ。「―に終わる」「―内閣」↔長命
たんめい‐てがた【単名手形】
手形債務者がただ一人である手形。裏書のない約束手形と引受け済みの自己あて為替手形をいう。
だん‐めつ【断滅】
絶え滅びること。また、絶やし滅ぼすこと。
たん‐めり
(完了の助動詞タリに推量の助動詞メリの付いた形の音便)…ているようだ。
たん‐めん【耽湎】
(「湎」は、おぼれる意)酒色にふけり、すさむこと。耽溺。たんべん。
たん‐めん【赧面】
恥じて顔をあからめること。赤面。
タンメン【湯麺】
(中国語)ゆでた中華そばにスープを加えるか、スープで煮る料理。汁そば。
だん‐めん【段免】
江戸時代、田地が地味によって分けられている場合、同じ等級であっても現実には作毛さくげの劣る田は、年貢率を1〜2段下げたこと。
だん‐めん【断面】
①もののきりくちの面。切断面。
②物事をある観点から見た時、そこに現れている状態。「社会の一―」
⇒だんめん‐ず【断面図】
だんめん‐ず【断面図】‥ヅ
物体をある平面で切ったと仮定して、その内部構造をえがいた図。
⇒だん‐めん【断面】
だん‐めんせき【断面積】
①図形や物体のある切断面における面積。
②〔理〕二つの粒子の散乱や反応の強さを表す量。面積の次元を持ち、現象が起こりやすいほど断面積が大きい。
たん‐もう【誕妄】‥マウ
うそ。いつわり。でたらめ。
たん‐もち【痰持ち】
痰の出る持病のある人。
たん‐もの【反物・段物】
①1反に仕上げてある織物。太物。↔疋物ひきもの。→たん(段・反)。
②一般に、呉服。「―屋」
だん‐もの【段物】
①能で、一曲の眼目とされるような謡いどころ、舞いどころのうち、曲くせ・狂くるいなどの定型に属さない一段。「三井寺」の鐘の段、「自然居士」のささらの段の類。
②義太夫節で、各段のうちの有名なあるいは特殊な一段。それを集めたものを正本・院本まるほんに対して「段物集」という。主として道行みちゆき・景事けいごとなどから選ぶ。
③常磐津や新内節で、義太夫節からの移入曲。短編の端物はものに対して、長編の曲を指す。
④日本舞踊で、常磐津・清元など浄瑠璃の伴奏による舞踊劇。
⑤箏曲そうきょくの曲種。歌のない器楽曲で、数段で一曲を構成する。各段の拍数は一定。速度は漸次急。八橋検校の「六段の調しらべ」など。しらべもの。
だん‐もよう【段模様】‥ヤウ
段々に染めた模様。段染めの模様。
たん‐もん【探問】
さぐりとうこと。
だん‐もん【断文】
断罪の命令文。断罪文。
たん‐や【短夜】
短い夜。夏の短い夜。みじかよ。↔長夜
たん‐や【鍛冶】
かじ。かぬち。
たん‐やく【丹薬】
不老不死の仙薬。道士の作った煉薬ねりやく。
だん‐やく【弾薬】
弾丸と、それを発射するための火薬の総称。たまぐすり。「―庫」
たん‐ゆう【胆勇】
大胆で勇気のあること。「―を備える」
たんゆう【探幽】‥イウ
⇒かのうたんゆう(狩野探幽)
だん‐ゆう【男優】‥イウ
男の俳優。↔女優
だん‐よ【談余】
はなしのついで。
たん‐よう【単葉】‥エフ
①葉身が小葉に分裂することがない葉。サクラ・ケヤキなどの葉。
②飛行機の主翼が1枚であること。↔複葉。
⇒たんよう‐き【単葉機】
たん‐よう【端陽】‥ヤウ
(→)端午たんごに同じ。
たんよう‐き【単葉機】‥エフ‥
主翼が1枚の飛行機。単葉飛行機。↔複葉機
⇒たん‐よう【単葉】
たん‐よく【貪欲】
欲が深いこと。どんよく。
たん‐らく【耽楽】
酒色にふけり楽しむこと。
たん‐らく【短絡】
①(short circuit)電気回路の2点間を小さい抵抗の導線で接続すること。また、電気回路の絶縁が破れるなどして、抵抗の非常に小さな回路を形成すること。ショート。
②(比喩的に)単純には結びつかない関係にある二つの物事を、直接・簡単に結びつけて論じること。
⇒たんらく‐しけん【短絡試験】
⇒たんらく‐てき【短絡的】
⇒たんらく‐はんのう【短絡反応】
だん‐らく【段落】
①長い文章中の大きな切れ目。段。
②転じて、物事のくぎり。「仕事が一―ついた」
たんらく‐しけん【短絡試験】
電気機器の端子間を短絡して行う試験。
⇒たん‐らく【短絡】
たんらく‐てき【短絡的】
筋道立てて考えずに物事を結びつけて論ずるさま。「―な思考」
⇒たん‐らく【短絡】
たんらく‐はんのう【短絡反応】‥オウ
〔心〕(→)近道反応に同じ。
⇒たん‐らく【短絡】
たん‐らん【貪婪】
きわめて欲が深いこと。どんらん。
だん‐らん【団欒】
①月などのまるいこと。まどか。
②集まって車座にすわること。まどい。
③集まってなごやかに楽しむこと。親密で楽しい会合。「一家―」
たん‐り【単利】
元金だけに対する利子。↔複利。
⇒たんり‐ほう【単利法】
たん‐り【単離】
〔化〕混合物中から一つの物質だけを純粋な形で取り出すこと。
たん‐り【貪吏】
欲が深く、人民の財をむさぼりとる官公吏。史記抄「―の様ににはかに盗取こそせねども」
たん‐り【貪利】
利益をむさぼること。あくまで利益を収めること。
たん‐り【短籬】
たけの低いまがき。
たん‐りつ【単立】
単独で設立されていること。「―宗教法人」
たん‐りつ【単律】
音楽で、呂・律の二つの音調に分けた時、律の音階だけが行われること。徒然草「唐土は呂の国なり。律の音なし。和国は、―の国にて、呂の音なし」
たんり‐ほう【単利法】‥ハフ
利息計算で、前期間の利息を元金に加算せず、元金のみに対し次期の利息を計算する法。↔複利法
⇒たん‐り【単利】
たん‐りゃく【胆略】
大胆で知略のあること。
たん‐りゅう【湍流】‥リウ
水勢の急な流れ。はやせ。急流。奔流。
だん‐りゅう【断流】‥リウ
川の水が河口まで届かず跡絶えてしまうこと。
だん‐りゅう【暖流】‥リウ
熱帯・亜熱帯の海域に源をもち、高緯度に向かって流れる海流。黒潮・湾流など。↔寒流
たんりゅう‐こうぞう【単粒構造】‥リフ‥ザウ
土壌を構成する土粒がそれぞれ独立して集積し、その間に何ら関係のない構造。ゆるい砂土や重粘な埴土はこの組織をなす。↔団粒構造
だんりゅう‐こうぞう【団粒構造】‥リフ‥ザウ
微細な土壌粒子が腐植や石灰などで膠着されて多孔質の肉眼で見える大きさの小粒をなすもの。通気・通水性が良好であるとともに、水分をよく保持し、一般に、植物の生育に適するので、土壌改善の目標とされる。↔単粒構造
たん‐りょ【短慮】
①考えが浅いこと。浅慮。毎月抄「更に―及び難くぞ覚え侍る」。「―を戒める」
②気みじか。せっかち。短気。浄瑠璃、嫗山姥こもちやまうば「世に便りなきうき節に、もし御―のこともやと」。「―な男」
⇒たんりょ‐じん【短慮人】
たん‐りょう【単寮】‥レウ
禅寺で、一人で住む寮舎。
たんりょう‐たい【単量体】‥リヤウ‥
(monomer)重合体を構成する基本単位物質。例えばエチレンはポリエチレンの単量体。モノマー。
たん‐りょく【胆力】
ものに恐れず臆しない気力。度胸。「―が据っている」「―を練る」
たん‐りょく【淡緑】
うすいみどり。
だん‐りょく【弾力】
①はずむ力。物体が変形に抗して、原形に復しようとする力。
②状況の変化に適応する柔軟性。「―的に考える」
⇒だんりょく‐せい【弾力性】
だんりょく‐せい【弾力性】
弾力のある性質。「規則に―をもたせる」
⇒だん‐りょく【弾力】
たんりょく‐ぼん【丹緑本】
⇒たんろくぼん
たんりょ‐じん【短慮人】
短気な人。怒りっぽい人。日葡辞書「ヒ(火)ヲフルヤウナタンリョジンヂャ」
⇒たん‐りょ【短慮】
たん‐りん【貪吝】
むさぼりとって出し惜しむこと。
だん‐りん【檀林・談林】
①(栴檀林の略)仏教の学問所。平安時代の檀林寺に始まるが、学問所を檀林と呼ぶようになったのは室町末期で、近世、各宗で設ける。関東十八檀林の類。学寮。
②寺の異称。
③談林風。
⇒だんりん‐は【談林派・檀林派】
⇒だんりん‐ふう【談林風・檀林風】
だんりん‐こうごう【檀林皇后】‥クワウ‥
橘嘉智子たちばなのかちこの異称。
だんりん‐じ【檀林寺】
京都の天竜寺付近にあった日本最古とされる禅院。承和(834〜848)年中、檀林皇后の願によって唐僧義空が開山。室町時代に再興して京都尼五山の一つとなったが廃絶。
だんりんとっぴゃくいん【談林十百韻】‥ヰン
俳諧集。2冊。田代松意編。1675年(延宝3)刊。宗因風を志向する江戸の俳人たちの百韻俳諧を10巻集めたもの。談林俳諧・談林風の称は本書題名による。
だんりん‐は【談林派・檀林派】
談林風を奉じた俳諧の流派。
⇒だん‐りん【檀林・談林】
だんりん‐ふう【談林風・檀林風】
江戸前期、延宝・天和(1673〜1684)頃に流行した俳諧の一風・一派。もとは江戸の田代松意の一派の結社を指すが、のち大坂の西山宗因を中心とする新風の汎称となる。伝統的・法式的な貞徳流に反抗して、軽妙な口語使用と滑稽な着想によって流行したが、蕉風しょうふうの興るに及んで衰えた。宗因風。
⇒だん‐りん【檀林・談林】
たん‐れい【淡麗】
日本酒の味や口当りに強い癖がなく、すっきりと滑らかである様子。
たん‐れい【貪戻】
むさぼって人の道にそむくこと。浄瑠璃、国性爺合戦「一人―なれば一国乱を起すといへり」
たん‐れい【端麗】
かたち・すがたがととのって、うるわしいこと。「容姿―」
だん‐れい‐ぼう【暖冷房】‥バウ
(→)冷暖房に同じ。
たん‐れつ【単列】
ひとならび。1列。
⇒たんれつ‐きかん【単列機関】
だん‐れつ【断裂】
断ち裂かれること。
たんれつ‐きかん【単列機関】‥クワン
シリンダーが1列に並んで1本のクランク軸によって動力を他へ伝動する機関。直列機関の1列のもの。
⇒たん‐れつ【単列】
たん‐れん【鍛練・鍛錬・鍛煉】
①金属をきたえねること。〈日葡辞書〉
②修養・訓練を積んで心身をきたえたり技能をみがいたりすること。浮世物語「通力あるが如くなる上手の―ある者」。「体を―する」
③酷吏が、罪のないものを罪に陥れること。
だん‐れん【団練】
中国で、住民による自衛武装組織。清代に盛行。→郷勇きょうゆう
たん‐れんが【短連歌】
前句と付句との2句の唱和から成る連歌。↔長連歌
たん‐ろ【坦路】
平らな路。坦道。
だん‐ろ【暖炉・煖炉】
火をたいて室内をあたためる炉。特に、壁に接して作ったもの。〈[季]冬〉
だんろ‐き【断路器】
送電線や配電線を切り離し、あるいは接続する装置。遮断器と異なり、電流が流れているときには操作できない。
たんろく‐ぼん【丹緑本】
江戸初期に刊行された御伽草子、仮名草子、舞の本、浄瑠璃本などの墨摺りの挿絵に手書きで彩色した本。丹(赤)・緑・黄・藍色などで、簡略に彩色する。丹と緑とが最も多く用いられたからいう。
だん‐ろん【談論】
談話と議論。
⇒だんろん‐ふうはつ【談論風発】
だんろん‐ふうはつ【談論風発】
いろいろな意見が活発にかわされること。
⇒だん‐ろん【談論】
だん‐わ【暖和】
気候があたたかくておだやかなこと。
だん‐わ【談話】
①はなし。ものがたり。会話。「炉辺の―」「―室」
②ある事柄についての見解などを述べた話。「首相―」
⇒だんわ‐たい【談話体】
だん‐わく【断惑】
(ダンナクとも)〔仏〕煩悩を断ち切ること。
⇒だんわく‐しょうり【断惑証理】
だんわく‐しょうり【断惑証理】
煩悩を断じて涅槃ねはんの真理を悟ること。
⇒だん‐わく【断惑】
だんわ‐たい【談話体】
日常の談話に近い言葉づかいの文体。福沢諭吉の「福翁自伝」など。
⇒だん‐わ【談話】
広辞苑 ページ 12520 での【○短兵直ちに】単語。