複数辞典一括検索+![]()
![]()
○船端に刻むふなばたにきざむ🔗⭐🔉
○船端に刻むふなばたにきざむ
(→)刻舟こくしゅうに同じ。
⇒ふな‐ばた【船端・舷】
ふな‐はて【船泊て】
船が碇泊すること。ふなどまり。ふながかり。万葉集1「いづくにか―すらむ」
ふな‐ばら【船腹】
船の腹部。せんぷく。古事記中「年ごとに船並めて―乾ほさず、柂檝さおかじ乾さず」
⇒ふなばら‐そう【船腹草】
ふなばら‐そう【船腹草】‥サウ
ガガイモ科の多年草。山野に自生する。高さ約60センチメートル。茎に白毛がある。葉は楕円形。夏、暗紫色の花を数個ずつ開き、船の胴に似た果実をつける。根は漢方生薬の白薇はくびで、解熱・利尿薬。ロクエンソウ。
⇒ふな‐ばら【船腹】
ふな‐ばり【船梁】
和船の両舷側間に渡した多くの太い材。横からの水圧を防ぎ支え、船形を維持し、また、船の間仕切とする。〈日葡辞書〉
ふな‐ばんしょ【船番所】
(→)番所ばんしょ2に同じ。誹風柳多留11「三味線を握つて通る―」
ふな‐び【船日】
①船出するのによい日。浄瑠璃、双生隅田川「今日は三月十五日、上総の浦の―なれど」
②船の着くべき日。
ふな‐ひき【船引き】
船を綱で引くこと。また、その人。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「網引き―塩焼きあま人」
ふな‐ひじき【舟肘木】‥ヒヂ‥
〔建〕(形が川舟のような感じであるからいう)組物の一形式。柱上に肘木のみをのせて桁けたを支えるもの。
舟肘木
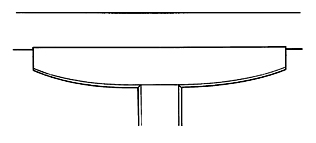 ふな‐びと【船人・舟人】
①船頭。ふなこ。万葉集15「朝なぎに船出をせむと―も水手かこも声よび」
②船客。土佐日記「―のよめる歌」
ふな‐びらき【船開き】
船が港から出帆すること。
ふな‐びん【船便】
船の便宜。便船。また、便船でものを送ること。〈日葡辞書〉。「―で送る」
ふな‐ぶぎょう【船奉行】‥ギヤウ
武家の職名。中世では水軍の指揮者、江戸幕府では船手頭ふなてがしらのこと。
フナフティ【Funafuti】
南太平洋、ツバルの首都。人口4千(1997)。
ふな‐ふな
ふらふらとふらつくさま。ふらふら。好色一代女6「―と腰も定めかね、息つぎせはしく」
ふな‐べ【船辺】
水に浮かんでいる船のあたり。
ふな‐べり【船縁・舷】
船のへり。船の側面。ふなばた。
ふなべんけい【船弁慶】
①能。観世信光作。大物浦だいもつのうらでの源義経と静御前の別れと、海上に現れた平知盛の怨霊を弁慶が祈り伏せることを描く。
②1によった長唄。
㋐2世杵屋勝三郎作曲。1870年(明治3)能役者日吉吉左衛門が三味線の地で演能を試みた。
㋑1885年(明治18)3世杵屋正治郎作曲、河竹黙阿弥作詞。新歌舞伎十八番の一つ。
ふな‐ま【舟間】
①舟の入港のとだえた間。また、そのため荷がとぎれること。洒落本、和漢同詠道行「地獄以もっての外のふけいきにて、弘誓ぐぜいの船の―なり」
②転じて、物の欠乏。払底。歌舞伎、文月恨鮫鞘「こいつア煙草が―だ」
ふな‐まく【船幕】
船上に張る幕。
ふな‐まち【船待ち】
船を待つこと。出船を待つこと。
ふな‐まど【船窓】
船のあかりとりのまど。
ふな‐まどい【船惑い】‥マドヒ
船が航路を見失うこと。是則集「何方か泊なるらむ山風のはらふ紅葉に―して」
ふな‐まわし【船回し】‥マハシ
船に積んで送り届けること。回漕。
ふな‐まんじゅう【船饅頭】‥ヂユウ
江戸の隅田川で、舟中で売春した下等の私娼。
ふな‐みち【船路】
船の通うみち。ふなじ。源氏物語夕顔「―のしわざとて少し黒みやつれたる旅姿」
ふな‐むし【船虫】
ワラジムシ目(等脚類)の甲殻類。体は長卵形、灰褐色で、体長約4センチメートル。第2触角は長い。胸脚はよく発達し、岩・船板などの上を群をなして走る。日本各地の海辺に分布。〈[季]夏〉
ふなむし
ふな‐びと【船人・舟人】
①船頭。ふなこ。万葉集15「朝なぎに船出をせむと―も水手かこも声よび」
②船客。土佐日記「―のよめる歌」
ふな‐びらき【船開き】
船が港から出帆すること。
ふな‐びん【船便】
船の便宜。便船。また、便船でものを送ること。〈日葡辞書〉。「―で送る」
ふな‐ぶぎょう【船奉行】‥ギヤウ
武家の職名。中世では水軍の指揮者、江戸幕府では船手頭ふなてがしらのこと。
フナフティ【Funafuti】
南太平洋、ツバルの首都。人口4千(1997)。
ふな‐ふな
ふらふらとふらつくさま。ふらふら。好色一代女6「―と腰も定めかね、息つぎせはしく」
ふな‐べ【船辺】
水に浮かんでいる船のあたり。
ふな‐べり【船縁・舷】
船のへり。船の側面。ふなばた。
ふなべんけい【船弁慶】
①能。観世信光作。大物浦だいもつのうらでの源義経と静御前の別れと、海上に現れた平知盛の怨霊を弁慶が祈り伏せることを描く。
②1によった長唄。
㋐2世杵屋勝三郎作曲。1870年(明治3)能役者日吉吉左衛門が三味線の地で演能を試みた。
㋑1885年(明治18)3世杵屋正治郎作曲、河竹黙阿弥作詞。新歌舞伎十八番の一つ。
ふな‐ま【舟間】
①舟の入港のとだえた間。また、そのため荷がとぎれること。洒落本、和漢同詠道行「地獄以もっての外のふけいきにて、弘誓ぐぜいの船の―なり」
②転じて、物の欠乏。払底。歌舞伎、文月恨鮫鞘「こいつア煙草が―だ」
ふな‐まく【船幕】
船上に張る幕。
ふな‐まち【船待ち】
船を待つこと。出船を待つこと。
ふな‐まど【船窓】
船のあかりとりのまど。
ふな‐まどい【船惑い】‥マドヒ
船が航路を見失うこと。是則集「何方か泊なるらむ山風のはらふ紅葉に―して」
ふな‐まわし【船回し】‥マハシ
船に積んで送り届けること。回漕。
ふな‐まんじゅう【船饅頭】‥ヂユウ
江戸の隅田川で、舟中で売春した下等の私娼。
ふな‐みち【船路】
船の通うみち。ふなじ。源氏物語夕顔「―のしわざとて少し黒みやつれたる旅姿」
ふな‐むし【船虫】
ワラジムシ目(等脚類)の甲殻類。体は長卵形、灰褐色で、体長約4センチメートル。第2触角は長い。胸脚はよく発達し、岩・船板などの上を群をなして走る。日本各地の海辺に分布。〈[季]夏〉
ふなむし
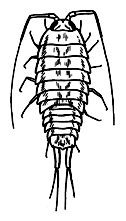 フナムシ
提供:東京動物園協会
フナムシ
提供:東京動物園協会
 ふな‐もぐり【船潜り】
漁場まで船で行き、比較的沖合の深所で仕事をする海女。通常、舟子と組みになって漁をする。本あま。→磯もぐり
ふな‐もち【船持】
船の持主。ふなぬし。
ふな‐もと【船許】
船の碇泊する所。〈日葡辞書〉
ふな‐もやい【舟舫い】‥モヤヒ
舟をつなぎとめること。
ふな‐もよい【船催い】‥モヨヒ
船出ふなでの準備。ふなよそい。孝範集「暁の―するあまの子の」
ふな‐もり【舟守】
舟の番をすること。また、舟の番人。
ふな‐もり【舟盛り】
伊勢えびの尾を高くはね上げ、船形にして盛ること。甲陽軍鑑16「―、小串こさし」
ふな‐や【船屋】
①池に張り出して建てた建物。あるいは釣殿と同じか。宇津保物語楼上下「かの池の―は、こたみはたけぞ高くなりにけり」
②(→)船小屋に同じ。
③(→)船屋形ふなやかたに同じ。
ふな‐やかた【船屋形】
船の屋形。船上の屋舎で、二階作り・三階作りなどもある。土佐日記「―の塵も散り」
ふな‐やく【船役】
船に課する税。
ふな‐やぐら【船矢倉】
船上に設けた矢倉。
ふな‐やど【船宿】
①漁港町などで、入港船の乗組員のための宿屋。漁具・食糧の世話をしたり、資金・資材を貸したりもする。
②船による運送を業とする家。
③遊船または釣漁などに貸船を仕立てるのを業とする家。成島柳北、柳橋新誌「―の各家いえごと其の家政を執り賓客に応接する者は其の妻也」
ふな‐やどり【船宿り】
船が碇泊すること。また、船中に宿泊すること。宇津保物語菊宴「見つつは過ぎじ―せむ」
ふな‐やまい【船病】‥ヤマヒ
ふなよい。ふなやもい。
ふな‐やもい【船病】‥ヤモヒ
(→)「ふなやまい」に同じ。〈倭名類聚鈔3〉
ふな‐ゆ【船湯・淦】
船の中に漏れて入った水。あか。
ふな‐ゆうれい【船幽霊】‥イウ‥
水中で死んだ人の幽霊。これに柄杓ひしゃくを貸すときは、その底を抜いて貸さないと船を沈められるという俗信がある。
ふな‐ゆさん【船遊山】
(→)「ふなあそび」に同じ。
ふな‐よい【船酔い】‥ヨヒ
船に乗った人が、船の揺れのため、気分のわるくなること。ふなえい。ふなあたり。〈文明本節用集〉
ふな‐よせ【船寄】
船を寄せること。また、その所。夫木和歌抄35「―の岸の上なるかどやより」
ふな‐よそ・う【船装ふ】‥ヨソフ
〔自四〕
出船の用意をする。万葉集20「押し照るや難波の津ゆり―・ひ吾あれは漕ぎぬと妹に告ぎこそ」
ふな‐よどみ【船淀み】
船の進行がとどこおること。堀河百首秋「渡守―すな」
ふな‐よばい【船呼ばい】‥ヨバヒ
船を呼び寄せること。また、その声。ふねよばい。源平盛衰記7「蘆屋の沖の―」
ふなら‐ふなら
力の抜けたさま。しょげたさま。浄瑠璃、唐船噺今国性爺「―と帰る犬獅子」
ふ‐なり【不成】
将棋で、敵陣に進んだ駒が成らないこと。ならず。
ぶ‐なり【不形】
形の整っていないこと。不恰好。浄瑠璃、双生隅田川「うなぎ・なまづは―なものよ」
ふ‐なれ【不馴れ】
馴れないこと。習熟しないこと。「―な仕事」
ふな‐わた【船綿】
船綿帽子の略。
⇒ふなわた‐ぼうし【船綿帽子】
ふな‐わたし【船渡し】
船で、荷物または人をわたすこと。また、その所。わたし。わたり。わたしば。風雅和歌集序「―する貢物たえずなりにければ」
ふなわたしむこ【船渡聟】
狂言。都の婿が酒を携えて舅しゅうとを訪ねる途中、船上で、船頭におどかされて酒を飲まれてしまう。
ふなわた‐ぼうし【船綿帽子】
綿帽子を細長くつぶして、舟の形にしたもの。てぼそ。古今綿。頬包。
⇒ふな‐わた【船綿】
ふな‐わたり【船渡り】
船でわたること。また、その所。源氏物語総角「―なども所せければ」
ふなん【扶南】
(bnam クメール語で山の意)紀元100年前後にコーチシナおよびカンボジア南部のメコン‐デルタ地域に拠ったクメール人の王国。大船を動かして海上貿易に従事、インド文化を受容して繁栄。7世紀前半、北方の真臘しんろうに併合された。
ぶ‐なん【無難】
①これといって特色はないが、また非難すべき点もないこと。平凡無事なさま。当り障りのないさま。「―の一生」「―にこなす」「その辺でやめておいた方が―だ」
②危ないことのないこと。無事。霧の屋主人、大川物語「倅ドウだ、お蔵は―か」
ふなんこぐい
(コグイは「凝り」の転訛という)ふなを昆布とともに、甘露煮にしたもの。佐賀県の郷土料理。ふなのこぐい。
ふ‐に【不二】
〔仏〕異ならないこと。差別のないこと。現象的に対立する二つのことが根底的には一体であること。大乗仏教において主張される。即。相即。「善悪―」「生死―」「凡聖―」
ふ‐に【膚膩】
皮膚のあぶら。また、あぶらづいたはだ。垢膩くに。
ふ‐にあい【不似合】‥アヒ
似合わないこと。似つかわしくないこと。「―な帽子」
ふな‐もぐり【船潜り】
漁場まで船で行き、比較的沖合の深所で仕事をする海女。通常、舟子と組みになって漁をする。本あま。→磯もぐり
ふな‐もち【船持】
船の持主。ふなぬし。
ふな‐もと【船許】
船の碇泊する所。〈日葡辞書〉
ふな‐もやい【舟舫い】‥モヤヒ
舟をつなぎとめること。
ふな‐もよい【船催い】‥モヨヒ
船出ふなでの準備。ふなよそい。孝範集「暁の―するあまの子の」
ふな‐もり【舟守】
舟の番をすること。また、舟の番人。
ふな‐もり【舟盛り】
伊勢えびの尾を高くはね上げ、船形にして盛ること。甲陽軍鑑16「―、小串こさし」
ふな‐や【船屋】
①池に張り出して建てた建物。あるいは釣殿と同じか。宇津保物語楼上下「かの池の―は、こたみはたけぞ高くなりにけり」
②(→)船小屋に同じ。
③(→)船屋形ふなやかたに同じ。
ふな‐やかた【船屋形】
船の屋形。船上の屋舎で、二階作り・三階作りなどもある。土佐日記「―の塵も散り」
ふな‐やく【船役】
船に課する税。
ふな‐やぐら【船矢倉】
船上に設けた矢倉。
ふな‐やど【船宿】
①漁港町などで、入港船の乗組員のための宿屋。漁具・食糧の世話をしたり、資金・資材を貸したりもする。
②船による運送を業とする家。
③遊船または釣漁などに貸船を仕立てるのを業とする家。成島柳北、柳橋新誌「―の各家いえごと其の家政を執り賓客に応接する者は其の妻也」
ふな‐やどり【船宿り】
船が碇泊すること。また、船中に宿泊すること。宇津保物語菊宴「見つつは過ぎじ―せむ」
ふな‐やまい【船病】‥ヤマヒ
ふなよい。ふなやもい。
ふな‐やもい【船病】‥ヤモヒ
(→)「ふなやまい」に同じ。〈倭名類聚鈔3〉
ふな‐ゆ【船湯・淦】
船の中に漏れて入った水。あか。
ふな‐ゆうれい【船幽霊】‥イウ‥
水中で死んだ人の幽霊。これに柄杓ひしゃくを貸すときは、その底を抜いて貸さないと船を沈められるという俗信がある。
ふな‐ゆさん【船遊山】
(→)「ふなあそび」に同じ。
ふな‐よい【船酔い】‥ヨヒ
船に乗った人が、船の揺れのため、気分のわるくなること。ふなえい。ふなあたり。〈文明本節用集〉
ふな‐よせ【船寄】
船を寄せること。また、その所。夫木和歌抄35「―の岸の上なるかどやより」
ふな‐よそ・う【船装ふ】‥ヨソフ
〔自四〕
出船の用意をする。万葉集20「押し照るや難波の津ゆり―・ひ吾あれは漕ぎぬと妹に告ぎこそ」
ふな‐よどみ【船淀み】
船の進行がとどこおること。堀河百首秋「渡守―すな」
ふな‐よばい【船呼ばい】‥ヨバヒ
船を呼び寄せること。また、その声。ふねよばい。源平盛衰記7「蘆屋の沖の―」
ふなら‐ふなら
力の抜けたさま。しょげたさま。浄瑠璃、唐船噺今国性爺「―と帰る犬獅子」
ふ‐なり【不成】
将棋で、敵陣に進んだ駒が成らないこと。ならず。
ぶ‐なり【不形】
形の整っていないこと。不恰好。浄瑠璃、双生隅田川「うなぎ・なまづは―なものよ」
ふ‐なれ【不馴れ】
馴れないこと。習熟しないこと。「―な仕事」
ふな‐わた【船綿】
船綿帽子の略。
⇒ふなわた‐ぼうし【船綿帽子】
ふな‐わたし【船渡し】
船で、荷物または人をわたすこと。また、その所。わたし。わたり。わたしば。風雅和歌集序「―する貢物たえずなりにければ」
ふなわたしむこ【船渡聟】
狂言。都の婿が酒を携えて舅しゅうとを訪ねる途中、船上で、船頭におどかされて酒を飲まれてしまう。
ふなわた‐ぼうし【船綿帽子】
綿帽子を細長くつぶして、舟の形にしたもの。てぼそ。古今綿。頬包。
⇒ふな‐わた【船綿】
ふな‐わたり【船渡り】
船でわたること。また、その所。源氏物語総角「―なども所せければ」
ふなん【扶南】
(bnam クメール語で山の意)紀元100年前後にコーチシナおよびカンボジア南部のメコン‐デルタ地域に拠ったクメール人の王国。大船を動かして海上貿易に従事、インド文化を受容して繁栄。7世紀前半、北方の真臘しんろうに併合された。
ぶ‐なん【無難】
①これといって特色はないが、また非難すべき点もないこと。平凡無事なさま。当り障りのないさま。「―の一生」「―にこなす」「その辺でやめておいた方が―だ」
②危ないことのないこと。無事。霧の屋主人、大川物語「倅ドウだ、お蔵は―か」
ふなんこぐい
(コグイは「凝り」の転訛という)ふなを昆布とともに、甘露煮にしたもの。佐賀県の郷土料理。ふなのこぐい。
ふ‐に【不二】
〔仏〕異ならないこと。差別のないこと。現象的に対立する二つのことが根底的には一体であること。大乗仏教において主張される。即。相即。「善悪―」「生死―」「凡聖―」
ふ‐に【膚膩】
皮膚のあぶら。また、あぶらづいたはだ。垢膩くに。
ふ‐にあい【不似合】‥アヒ
似合わないこと。似つかわしくないこと。「―な帽子」
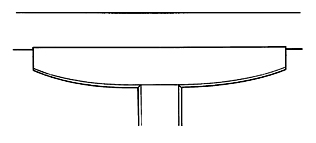 ふな‐びと【船人・舟人】
①船頭。ふなこ。万葉集15「朝なぎに船出をせむと―も水手かこも声よび」
②船客。土佐日記「―のよめる歌」
ふな‐びらき【船開き】
船が港から出帆すること。
ふな‐びん【船便】
船の便宜。便船。また、便船でものを送ること。〈日葡辞書〉。「―で送る」
ふな‐ぶぎょう【船奉行】‥ギヤウ
武家の職名。中世では水軍の指揮者、江戸幕府では船手頭ふなてがしらのこと。
フナフティ【Funafuti】
南太平洋、ツバルの首都。人口4千(1997)。
ふな‐ふな
ふらふらとふらつくさま。ふらふら。好色一代女6「―と腰も定めかね、息つぎせはしく」
ふな‐べ【船辺】
水に浮かんでいる船のあたり。
ふな‐べり【船縁・舷】
船のへり。船の側面。ふなばた。
ふなべんけい【船弁慶】
①能。観世信光作。大物浦だいもつのうらでの源義経と静御前の別れと、海上に現れた平知盛の怨霊を弁慶が祈り伏せることを描く。
②1によった長唄。
㋐2世杵屋勝三郎作曲。1870年(明治3)能役者日吉吉左衛門が三味線の地で演能を試みた。
㋑1885年(明治18)3世杵屋正治郎作曲、河竹黙阿弥作詞。新歌舞伎十八番の一つ。
ふな‐ま【舟間】
①舟の入港のとだえた間。また、そのため荷がとぎれること。洒落本、和漢同詠道行「地獄以もっての外のふけいきにて、弘誓ぐぜいの船の―なり」
②転じて、物の欠乏。払底。歌舞伎、文月恨鮫鞘「こいつア煙草が―だ」
ふな‐まく【船幕】
船上に張る幕。
ふな‐まち【船待ち】
船を待つこと。出船を待つこと。
ふな‐まど【船窓】
船のあかりとりのまど。
ふな‐まどい【船惑い】‥マドヒ
船が航路を見失うこと。是則集「何方か泊なるらむ山風のはらふ紅葉に―して」
ふな‐まわし【船回し】‥マハシ
船に積んで送り届けること。回漕。
ふな‐まんじゅう【船饅頭】‥ヂユウ
江戸の隅田川で、舟中で売春した下等の私娼。
ふな‐みち【船路】
船の通うみち。ふなじ。源氏物語夕顔「―のしわざとて少し黒みやつれたる旅姿」
ふな‐むし【船虫】
ワラジムシ目(等脚類)の甲殻類。体は長卵形、灰褐色で、体長約4センチメートル。第2触角は長い。胸脚はよく発達し、岩・船板などの上を群をなして走る。日本各地の海辺に分布。〈[季]夏〉
ふなむし
ふな‐びと【船人・舟人】
①船頭。ふなこ。万葉集15「朝なぎに船出をせむと―も水手かこも声よび」
②船客。土佐日記「―のよめる歌」
ふな‐びらき【船開き】
船が港から出帆すること。
ふな‐びん【船便】
船の便宜。便船。また、便船でものを送ること。〈日葡辞書〉。「―で送る」
ふな‐ぶぎょう【船奉行】‥ギヤウ
武家の職名。中世では水軍の指揮者、江戸幕府では船手頭ふなてがしらのこと。
フナフティ【Funafuti】
南太平洋、ツバルの首都。人口4千(1997)。
ふな‐ふな
ふらふらとふらつくさま。ふらふら。好色一代女6「―と腰も定めかね、息つぎせはしく」
ふな‐べ【船辺】
水に浮かんでいる船のあたり。
ふな‐べり【船縁・舷】
船のへり。船の側面。ふなばた。
ふなべんけい【船弁慶】
①能。観世信光作。大物浦だいもつのうらでの源義経と静御前の別れと、海上に現れた平知盛の怨霊を弁慶が祈り伏せることを描く。
②1によった長唄。
㋐2世杵屋勝三郎作曲。1870年(明治3)能役者日吉吉左衛門が三味線の地で演能を試みた。
㋑1885年(明治18)3世杵屋正治郎作曲、河竹黙阿弥作詞。新歌舞伎十八番の一つ。
ふな‐ま【舟間】
①舟の入港のとだえた間。また、そのため荷がとぎれること。洒落本、和漢同詠道行「地獄以もっての外のふけいきにて、弘誓ぐぜいの船の―なり」
②転じて、物の欠乏。払底。歌舞伎、文月恨鮫鞘「こいつア煙草が―だ」
ふな‐まく【船幕】
船上に張る幕。
ふな‐まち【船待ち】
船を待つこと。出船を待つこと。
ふな‐まど【船窓】
船のあかりとりのまど。
ふな‐まどい【船惑い】‥マドヒ
船が航路を見失うこと。是則集「何方か泊なるらむ山風のはらふ紅葉に―して」
ふな‐まわし【船回し】‥マハシ
船に積んで送り届けること。回漕。
ふな‐まんじゅう【船饅頭】‥ヂユウ
江戸の隅田川で、舟中で売春した下等の私娼。
ふな‐みち【船路】
船の通うみち。ふなじ。源氏物語夕顔「―のしわざとて少し黒みやつれたる旅姿」
ふな‐むし【船虫】
ワラジムシ目(等脚類)の甲殻類。体は長卵形、灰褐色で、体長約4センチメートル。第2触角は長い。胸脚はよく発達し、岩・船板などの上を群をなして走る。日本各地の海辺に分布。〈[季]夏〉
ふなむし
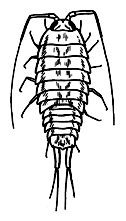 フナムシ
提供:東京動物園協会
フナムシ
提供:東京動物園協会
 ふな‐もぐり【船潜り】
漁場まで船で行き、比較的沖合の深所で仕事をする海女。通常、舟子と組みになって漁をする。本あま。→磯もぐり
ふな‐もち【船持】
船の持主。ふなぬし。
ふな‐もと【船許】
船の碇泊する所。〈日葡辞書〉
ふな‐もやい【舟舫い】‥モヤヒ
舟をつなぎとめること。
ふな‐もよい【船催い】‥モヨヒ
船出ふなでの準備。ふなよそい。孝範集「暁の―するあまの子の」
ふな‐もり【舟守】
舟の番をすること。また、舟の番人。
ふな‐もり【舟盛り】
伊勢えびの尾を高くはね上げ、船形にして盛ること。甲陽軍鑑16「―、小串こさし」
ふな‐や【船屋】
①池に張り出して建てた建物。あるいは釣殿と同じか。宇津保物語楼上下「かの池の―は、こたみはたけぞ高くなりにけり」
②(→)船小屋に同じ。
③(→)船屋形ふなやかたに同じ。
ふな‐やかた【船屋形】
船の屋形。船上の屋舎で、二階作り・三階作りなどもある。土佐日記「―の塵も散り」
ふな‐やく【船役】
船に課する税。
ふな‐やぐら【船矢倉】
船上に設けた矢倉。
ふな‐やど【船宿】
①漁港町などで、入港船の乗組員のための宿屋。漁具・食糧の世話をしたり、資金・資材を貸したりもする。
②船による運送を業とする家。
③遊船または釣漁などに貸船を仕立てるのを業とする家。成島柳北、柳橋新誌「―の各家いえごと其の家政を執り賓客に応接する者は其の妻也」
ふな‐やどり【船宿り】
船が碇泊すること。また、船中に宿泊すること。宇津保物語菊宴「見つつは過ぎじ―せむ」
ふな‐やまい【船病】‥ヤマヒ
ふなよい。ふなやもい。
ふな‐やもい【船病】‥ヤモヒ
(→)「ふなやまい」に同じ。〈倭名類聚鈔3〉
ふな‐ゆ【船湯・淦】
船の中に漏れて入った水。あか。
ふな‐ゆうれい【船幽霊】‥イウ‥
水中で死んだ人の幽霊。これに柄杓ひしゃくを貸すときは、その底を抜いて貸さないと船を沈められるという俗信がある。
ふな‐ゆさん【船遊山】
(→)「ふなあそび」に同じ。
ふな‐よい【船酔い】‥ヨヒ
船に乗った人が、船の揺れのため、気分のわるくなること。ふなえい。ふなあたり。〈文明本節用集〉
ふな‐よせ【船寄】
船を寄せること。また、その所。夫木和歌抄35「―の岸の上なるかどやより」
ふな‐よそ・う【船装ふ】‥ヨソフ
〔自四〕
出船の用意をする。万葉集20「押し照るや難波の津ゆり―・ひ吾あれは漕ぎぬと妹に告ぎこそ」
ふな‐よどみ【船淀み】
船の進行がとどこおること。堀河百首秋「渡守―すな」
ふな‐よばい【船呼ばい】‥ヨバヒ
船を呼び寄せること。また、その声。ふねよばい。源平盛衰記7「蘆屋の沖の―」
ふなら‐ふなら
力の抜けたさま。しょげたさま。浄瑠璃、唐船噺今国性爺「―と帰る犬獅子」
ふ‐なり【不成】
将棋で、敵陣に進んだ駒が成らないこと。ならず。
ぶ‐なり【不形】
形の整っていないこと。不恰好。浄瑠璃、双生隅田川「うなぎ・なまづは―なものよ」
ふ‐なれ【不馴れ】
馴れないこと。習熟しないこと。「―な仕事」
ふな‐わた【船綿】
船綿帽子の略。
⇒ふなわた‐ぼうし【船綿帽子】
ふな‐わたし【船渡し】
船で、荷物または人をわたすこと。また、その所。わたし。わたり。わたしば。風雅和歌集序「―する貢物たえずなりにければ」
ふなわたしむこ【船渡聟】
狂言。都の婿が酒を携えて舅しゅうとを訪ねる途中、船上で、船頭におどかされて酒を飲まれてしまう。
ふなわた‐ぼうし【船綿帽子】
綿帽子を細長くつぶして、舟の形にしたもの。てぼそ。古今綿。頬包。
⇒ふな‐わた【船綿】
ふな‐わたり【船渡り】
船でわたること。また、その所。源氏物語総角「―なども所せければ」
ふなん【扶南】
(bnam クメール語で山の意)紀元100年前後にコーチシナおよびカンボジア南部のメコン‐デルタ地域に拠ったクメール人の王国。大船を動かして海上貿易に従事、インド文化を受容して繁栄。7世紀前半、北方の真臘しんろうに併合された。
ぶ‐なん【無難】
①これといって特色はないが、また非難すべき点もないこと。平凡無事なさま。当り障りのないさま。「―の一生」「―にこなす」「その辺でやめておいた方が―だ」
②危ないことのないこと。無事。霧の屋主人、大川物語「倅ドウだ、お蔵は―か」
ふなんこぐい
(コグイは「凝り」の転訛という)ふなを昆布とともに、甘露煮にしたもの。佐賀県の郷土料理。ふなのこぐい。
ふ‐に【不二】
〔仏〕異ならないこと。差別のないこと。現象的に対立する二つのことが根底的には一体であること。大乗仏教において主張される。即。相即。「善悪―」「生死―」「凡聖―」
ふ‐に【膚膩】
皮膚のあぶら。また、あぶらづいたはだ。垢膩くに。
ふ‐にあい【不似合】‥アヒ
似合わないこと。似つかわしくないこと。「―な帽子」
ふな‐もぐり【船潜り】
漁場まで船で行き、比較的沖合の深所で仕事をする海女。通常、舟子と組みになって漁をする。本あま。→磯もぐり
ふな‐もち【船持】
船の持主。ふなぬし。
ふな‐もと【船許】
船の碇泊する所。〈日葡辞書〉
ふな‐もやい【舟舫い】‥モヤヒ
舟をつなぎとめること。
ふな‐もよい【船催い】‥モヨヒ
船出ふなでの準備。ふなよそい。孝範集「暁の―するあまの子の」
ふな‐もり【舟守】
舟の番をすること。また、舟の番人。
ふな‐もり【舟盛り】
伊勢えびの尾を高くはね上げ、船形にして盛ること。甲陽軍鑑16「―、小串こさし」
ふな‐や【船屋】
①池に張り出して建てた建物。あるいは釣殿と同じか。宇津保物語楼上下「かの池の―は、こたみはたけぞ高くなりにけり」
②(→)船小屋に同じ。
③(→)船屋形ふなやかたに同じ。
ふな‐やかた【船屋形】
船の屋形。船上の屋舎で、二階作り・三階作りなどもある。土佐日記「―の塵も散り」
ふな‐やく【船役】
船に課する税。
ふな‐やぐら【船矢倉】
船上に設けた矢倉。
ふな‐やど【船宿】
①漁港町などで、入港船の乗組員のための宿屋。漁具・食糧の世話をしたり、資金・資材を貸したりもする。
②船による運送を業とする家。
③遊船または釣漁などに貸船を仕立てるのを業とする家。成島柳北、柳橋新誌「―の各家いえごと其の家政を執り賓客に応接する者は其の妻也」
ふな‐やどり【船宿り】
船が碇泊すること。また、船中に宿泊すること。宇津保物語菊宴「見つつは過ぎじ―せむ」
ふな‐やまい【船病】‥ヤマヒ
ふなよい。ふなやもい。
ふな‐やもい【船病】‥ヤモヒ
(→)「ふなやまい」に同じ。〈倭名類聚鈔3〉
ふな‐ゆ【船湯・淦】
船の中に漏れて入った水。あか。
ふな‐ゆうれい【船幽霊】‥イウ‥
水中で死んだ人の幽霊。これに柄杓ひしゃくを貸すときは、その底を抜いて貸さないと船を沈められるという俗信がある。
ふな‐ゆさん【船遊山】
(→)「ふなあそび」に同じ。
ふな‐よい【船酔い】‥ヨヒ
船に乗った人が、船の揺れのため、気分のわるくなること。ふなえい。ふなあたり。〈文明本節用集〉
ふな‐よせ【船寄】
船を寄せること。また、その所。夫木和歌抄35「―の岸の上なるかどやより」
ふな‐よそ・う【船装ふ】‥ヨソフ
〔自四〕
出船の用意をする。万葉集20「押し照るや難波の津ゆり―・ひ吾あれは漕ぎぬと妹に告ぎこそ」
ふな‐よどみ【船淀み】
船の進行がとどこおること。堀河百首秋「渡守―すな」
ふな‐よばい【船呼ばい】‥ヨバヒ
船を呼び寄せること。また、その声。ふねよばい。源平盛衰記7「蘆屋の沖の―」
ふなら‐ふなら
力の抜けたさま。しょげたさま。浄瑠璃、唐船噺今国性爺「―と帰る犬獅子」
ふ‐なり【不成】
将棋で、敵陣に進んだ駒が成らないこと。ならず。
ぶ‐なり【不形】
形の整っていないこと。不恰好。浄瑠璃、双生隅田川「うなぎ・なまづは―なものよ」
ふ‐なれ【不馴れ】
馴れないこと。習熟しないこと。「―な仕事」
ふな‐わた【船綿】
船綿帽子の略。
⇒ふなわた‐ぼうし【船綿帽子】
ふな‐わたし【船渡し】
船で、荷物または人をわたすこと。また、その所。わたし。わたり。わたしば。風雅和歌集序「―する貢物たえずなりにければ」
ふなわたしむこ【船渡聟】
狂言。都の婿が酒を携えて舅しゅうとを訪ねる途中、船上で、船頭におどかされて酒を飲まれてしまう。
ふなわた‐ぼうし【船綿帽子】
綿帽子を細長くつぶして、舟の形にしたもの。てぼそ。古今綿。頬包。
⇒ふな‐わた【船綿】
ふな‐わたり【船渡り】
船でわたること。また、その所。源氏物語総角「―なども所せければ」
ふなん【扶南】
(bnam クメール語で山の意)紀元100年前後にコーチシナおよびカンボジア南部のメコン‐デルタ地域に拠ったクメール人の王国。大船を動かして海上貿易に従事、インド文化を受容して繁栄。7世紀前半、北方の真臘しんろうに併合された。
ぶ‐なん【無難】
①これといって特色はないが、また非難すべき点もないこと。平凡無事なさま。当り障りのないさま。「―の一生」「―にこなす」「その辺でやめておいた方が―だ」
②危ないことのないこと。無事。霧の屋主人、大川物語「倅ドウだ、お蔵は―か」
ふなんこぐい
(コグイは「凝り」の転訛という)ふなを昆布とともに、甘露煮にしたもの。佐賀県の郷土料理。ふなのこぐい。
ふ‐に【不二】
〔仏〕異ならないこと。差別のないこと。現象的に対立する二つのことが根底的には一体であること。大乗仏教において主張される。即。相即。「善悪―」「生死―」「凡聖―」
ふ‐に【膚膩】
皮膚のあぶら。また、あぶらづいたはだ。垢膩くに。
ふ‐にあい【不似合】‥アヒ
似合わないこと。似つかわしくないこと。「―な帽子」
広辞苑 ページ 17328 での【○船端に刻む】単語。