複数辞典一括検索+![]()
![]()
○海が涌くうみがわく🔗⭐🔉
○海が涌くうみがわく
(漁師語)魚群が海面に集まる。
⇒うみ【海】
うみ‐ぎり【海霧】
海上に発生する霧。主に移流霧をいう。
うみ‐ぎわ【海際】‥ギハ
陸の海と接する所。海のほとり。うみべ。謡曲、知章「いづくともなき―や」
うみ‐くさ【海草】
海藻および海草かいそうの総称。
うみぐも‐るい【海蜘蛛類】
節足動物のウミグモ綱の種の総称。体長1〜90ミリメートル。頭端に吻があって先端に口が開く。腹部は極めて小さく無節、付属肢の第1対は鋏肢、続く4対は長い歩脚となり、足だけの動物のように見える。浅海では石の下や海藻の間で生活。深海底の泥上にすむものもある。シマウミグモ・イトユメムシなど。夢虫。皆脚類。
うみ‐さそり【海蠍】
絶滅した節足動物。広翼亜綱を構成する。外形はサソリに似るが、系統上はカブトガニに近い。オルドビス紀からペルム紀まで、汎世界的に生息。最大の種類は体長1メートルに達する。
海蠍の化石
撮影:冨田幸光
 うみ‐さち【海幸】
①海の獲物を取る道具。つりばり。古事記上「―をもちて魚な釣らすに」
②海で得る獲物。海産物。神代紀下「兄…自づからに―有まします」↔山幸。
⇒うみさち‐やまさち【海幸山幸】
うみさち‐やまさち【海幸山幸】
日本神話の一つ。彦火火出見尊ひこほほでみのみこと(山幸彦)が兄の火照命ほでりのみこと(海幸彦)と猟具をとりかえて魚を釣りに出たが、釣針を失い、探し求めるため塩椎神しおつちのかみの教えにより海宮に赴き、海神の女むすめと結婚、釣針と潮盈珠しおみちのたま・潮乾珠しおひのたまを得て兄を降伏させたという話。天孫民族と隼人はやと族との闘争の神話化とも見られる。また仙郷滞留説話・神婚説話・浦島伝説の先駆をなすもの。
⇒うみ‐さち【海幸】
うみ‐サボテン【海サボテン】
八放サンゴ亜綱ウミエラ目ウミサボテン科の花虫類。棒状の群体を作り、ポリプはその周縁に配列、その姿がサボテンを思わせる。下端の細い柄部で海底に着生し、昼間は縮んで底に潜り、夜間は海中に伸び出して、長さ50センチメートルに達し、触ると燐光を発する。日本各地の浅海泥底に生息。
うみ‐ざりがに【海蝲蛄】
ロブスターのこと。
うみ‐じ【海路】‥ヂ
海上の舟の通う路。航路。船路。うなじ。万葉集3「いさな取り―に出でて」
うみ‐じ【産字・生字】
謡・浄瑠璃・長唄など日本の音曲で、1音節を長く延ばして歌う場合の延ばす母音の部分。「し」を「しいー」と延ばした時の「いー」の類。
うみ‐しか【海鹿】
アメフラシの別称。
うみ‐しだ【海羊歯】
ウミユリ綱ウミシダ亜目の棘皮きょくひ動物の総称。小さな円盤状の体の上面に口と肛門があり、周囲に10本から数十本の腕が出、各腕には細かな羽枝がある。外見が羊歯に類似するのでこの名がある。体の下面にある多数の巻枝で岩などにつかまり移動する。ニッポンウミシダ・オオバンウミシダ・アヤウミシダなど種類が多い。
うみ‐しる【膿汁】
うみ。のうじゅう。西大寺本最勝王経平安初期点「臭く穢けがれ膿ウミシル流れつつ」
うみ‐じるし【産印】
(四国地方で)痣あざ。
うみ‐す【産み巣】
子をはらむ腹。母胎。浄瑠璃、松風村雨束帯鑑「三人までの―とは、難じていはば子過ぎ腹」
うみすい‐いし【膿吸い石】‥スヒ‥
円く平たい小石状のもの。膿を吸わせる。竜骨の類か。→スランガステーン
うみ‐すずめ【海雀】
①ハコフグ科の海産の硬骨魚。全長約20センチメートル。体は箱状で亀甲型に仕切られた鱗甲を被り、頭部の左右に1対のとげが突出し、背にも1本のとげがある。本州中部以南の沿岸に産。スズメフグ。ハコフグ。スズメイオ。
②チドリ目ウミスズメ科の鳥の総称。北半球北部の海域に、約20種が分布。また、特にそのうち小形の約10種の総称。全長約25センチメートルのずんぐりした海鳥で、潜水して魚を捕る。日本では7種が記録され、カンムリウミスズメ・ウミスズメなどが繁殖。
③2の一種。太平洋北部に分布し、日本では北海道で繁殖。
うみすずめ(冬羽)
うみ‐さち【海幸】
①海の獲物を取る道具。つりばり。古事記上「―をもちて魚な釣らすに」
②海で得る獲物。海産物。神代紀下「兄…自づからに―有まします」↔山幸。
⇒うみさち‐やまさち【海幸山幸】
うみさち‐やまさち【海幸山幸】
日本神話の一つ。彦火火出見尊ひこほほでみのみこと(山幸彦)が兄の火照命ほでりのみこと(海幸彦)と猟具をとりかえて魚を釣りに出たが、釣針を失い、探し求めるため塩椎神しおつちのかみの教えにより海宮に赴き、海神の女むすめと結婚、釣針と潮盈珠しおみちのたま・潮乾珠しおひのたまを得て兄を降伏させたという話。天孫民族と隼人はやと族との闘争の神話化とも見られる。また仙郷滞留説話・神婚説話・浦島伝説の先駆をなすもの。
⇒うみ‐さち【海幸】
うみ‐サボテン【海サボテン】
八放サンゴ亜綱ウミエラ目ウミサボテン科の花虫類。棒状の群体を作り、ポリプはその周縁に配列、その姿がサボテンを思わせる。下端の細い柄部で海底に着生し、昼間は縮んで底に潜り、夜間は海中に伸び出して、長さ50センチメートルに達し、触ると燐光を発する。日本各地の浅海泥底に生息。
うみ‐ざりがに【海蝲蛄】
ロブスターのこと。
うみ‐じ【海路】‥ヂ
海上の舟の通う路。航路。船路。うなじ。万葉集3「いさな取り―に出でて」
うみ‐じ【産字・生字】
謡・浄瑠璃・長唄など日本の音曲で、1音節を長く延ばして歌う場合の延ばす母音の部分。「し」を「しいー」と延ばした時の「いー」の類。
うみ‐しか【海鹿】
アメフラシの別称。
うみ‐しだ【海羊歯】
ウミユリ綱ウミシダ亜目の棘皮きょくひ動物の総称。小さな円盤状の体の上面に口と肛門があり、周囲に10本から数十本の腕が出、各腕には細かな羽枝がある。外見が羊歯に類似するのでこの名がある。体の下面にある多数の巻枝で岩などにつかまり移動する。ニッポンウミシダ・オオバンウミシダ・アヤウミシダなど種類が多い。
うみ‐しる【膿汁】
うみ。のうじゅう。西大寺本最勝王経平安初期点「臭く穢けがれ膿ウミシル流れつつ」
うみ‐じるし【産印】
(四国地方で)痣あざ。
うみ‐す【産み巣】
子をはらむ腹。母胎。浄瑠璃、松風村雨束帯鑑「三人までの―とは、難じていはば子過ぎ腹」
うみすい‐いし【膿吸い石】‥スヒ‥
円く平たい小石状のもの。膿を吸わせる。竜骨の類か。→スランガステーン
うみ‐すずめ【海雀】
①ハコフグ科の海産の硬骨魚。全長約20センチメートル。体は箱状で亀甲型に仕切られた鱗甲を被り、頭部の左右に1対のとげが突出し、背にも1本のとげがある。本州中部以南の沿岸に産。スズメフグ。ハコフグ。スズメイオ。
②チドリ目ウミスズメ科の鳥の総称。北半球北部の海域に、約20種が分布。また、特にそのうち小形の約10種の総称。全長約25センチメートルのずんぐりした海鳥で、潜水して魚を捕る。日本では7種が記録され、カンムリウミスズメ・ウミスズメなどが繁殖。
③2の一種。太平洋北部に分布し、日本では北海道で繁殖。
うみすずめ(冬羽)
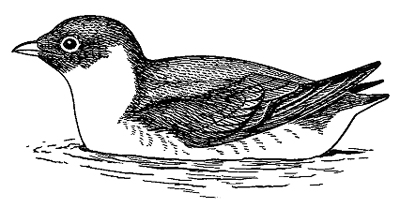 うみせん‐かわせん【海千河千】‥カハ‥
(海に千年河に千年住んだものの意)(→)海千山千に同じ。
うみせん‐やません【海千山千】
(海に千年山に千年住んだ蛇は竜になるという言い伝えから)せちがらい世の中の裏も表も知っていて、老獪ろうかいな人。「―の事業家」
うみ‐そ【績麻】
(→)「うみお」に同じ。
うみ‐ぞうめん【海索麺】‥ザウ‥
①アメフラシ・タツナミガイなどの卵塊の俗称。索麺の形をし、色は紅・黄・橙色など種々。膠質の紐の中に包み込まれている卵から幼生が孵化する。初夏、磯に見られる。
ウミゾウメン
提供:東京動物園協会
うみせん‐かわせん【海千河千】‥カハ‥
(海に千年河に千年住んだものの意)(→)海千山千に同じ。
うみせん‐やません【海千山千】
(海に千年山に千年住んだ蛇は竜になるという言い伝えから)せちがらい世の中の裏も表も知っていて、老獪ろうかいな人。「―の事業家」
うみ‐そ【績麻】
(→)「うみお」に同じ。
うみ‐ぞうめん【海索麺】‥ザウ‥
①アメフラシ・タツナミガイなどの卵塊の俗称。索麺の形をし、色は紅・黄・橙色など種々。膠質の紐の中に包み込まれている卵から幼生が孵化する。初夏、磯に見られる。
ウミゾウメン
提供:東京動物園協会
 ②海産の紅藻類。北海道・本州などで波の高い磯に付く。体は細長い紐状で、長さ10〜20センチメートル。濃紅茶色で粘性が強い。夏、採集して乾燥または塩漬とし、三杯酢で食べる。
うみ‐だか【海高】
江戸時代、海産の収穫を石高に見積もり、租税として米や金銀で納めさせたもの。海石うみこく。
うみ‐たけ‐がい【海筍貝・海笋貝】‥ガヒ
ニオガイ科の二枚貝。貝殻は白色で薄くてもろく、黒くて長い水管は殻長の2倍もある。食用となり、熨斗鮑のしあわびの代用。有明海・瀬戸内海など、内海の泥深い所に産する。ウミタケ。〈日葡辞書〉
うみ‐だ・す【生み出す・産み出す】
〔他五〕
①胎児または卵を生む。
②生み始める。
③新しく作り出す。「新企画を―・す」「財源を―・す」
うみ‐たなご【海鱮】
ウミタナゴ科の海産の硬骨魚。全長約25センチメートル。体は側扁し頭は小さい。鉄青色または銅赤色。日本各地の沿岸に産し、殊に内湾のアマモの生えているところに多く、卵胎生。地方によっては妊婦が食べるのを忌む。タナゴ。
ウミタナゴ
提供:東京動物園協会
②海産の紅藻類。北海道・本州などで波の高い磯に付く。体は細長い紐状で、長さ10〜20センチメートル。濃紅茶色で粘性が強い。夏、採集して乾燥または塩漬とし、三杯酢で食べる。
うみ‐だか【海高】
江戸時代、海産の収穫を石高に見積もり、租税として米や金銀で納めさせたもの。海石うみこく。
うみ‐たけ‐がい【海筍貝・海笋貝】‥ガヒ
ニオガイ科の二枚貝。貝殻は白色で薄くてもろく、黒くて長い水管は殻長の2倍もある。食用となり、熨斗鮑のしあわびの代用。有明海・瀬戸内海など、内海の泥深い所に産する。ウミタケ。〈日葡辞書〉
うみ‐だ・す【生み出す・産み出す】
〔他五〕
①胎児または卵を生む。
②生み始める。
③新しく作り出す。「新企画を―・す」「財源を―・す」
うみ‐たなご【海鱮】
ウミタナゴ科の海産の硬骨魚。全長約25センチメートル。体は側扁し頭は小さい。鉄青色または銅赤色。日本各地の沿岸に産し、殊に内湾のアマモの生えているところに多く、卵胎生。地方によっては妊婦が食べるのを忌む。タナゴ。
ウミタナゴ
提供:東京動物園協会
 うみ‐だぬき【海狸】
ビーバーのこと。かいり。
うみ‐たる【海樽】
原索動物門ウミタル科の海産プランクトンの一種。体長3〜6ミリメートルの透明なビヤ樽状。体壁の内側にある8個の環状筋を収縮して水を後端から噴出し、その反動で運動する。世界の温水域に分布し、大形回遊魚の天然飼料となる。
うみ‐ち【膿血】
膿汁に血のまじったもの。
うみ‐つか・れる【倦み疲れる】
〔自下一〕[文]うみつか・る(下二)
あきて疲れる。うんざりしてつかれる。
うみ‐づき【産み月】
胎児が生まれる予定の月。臨月。
うみ‐つ・ける【生み付ける・産み付ける】
〔他下一〕[文]うみつ・く(下二)
①卵を生んで物に付着させる。
②生んで、親の性質・外見などを受けさせる。
うみ‐つ‐じ【海路】‥ヂ
航路。うみじ。うなじ。万葉集9「―のなぎなむ時も渡らなむ」
うみ‐つばめ【海燕】
ミズナギドリ目ウミツバメ科の海鳥の総称。海面に遊泳し、また海面をかすめて飛ぶ。大きさはツグミまたはスズメぐらい。羽は主として暗褐色または蒼灰色。翼は長く、尾はツバメの尾と同じく二つに分かれるが短い。嘴端は鉤状、趾にみずかきがあり、孤島の地上に穴を穿って巣をつくる。
コシジロウミツバメ
撮影:小宮輝之
うみ‐だぬき【海狸】
ビーバーのこと。かいり。
うみ‐たる【海樽】
原索動物門ウミタル科の海産プランクトンの一種。体長3〜6ミリメートルの透明なビヤ樽状。体壁の内側にある8個の環状筋を収縮して水を後端から噴出し、その反動で運動する。世界の温水域に分布し、大形回遊魚の天然飼料となる。
うみ‐ち【膿血】
膿汁に血のまじったもの。
うみ‐つか・れる【倦み疲れる】
〔自下一〕[文]うみつか・る(下二)
あきて疲れる。うんざりしてつかれる。
うみ‐づき【産み月】
胎児が生まれる予定の月。臨月。
うみ‐つ・ける【生み付ける・産み付ける】
〔他下一〕[文]うみつ・く(下二)
①卵を生んで物に付着させる。
②生んで、親の性質・外見などを受けさせる。
うみ‐つ‐じ【海路】‥ヂ
航路。うみじ。うなじ。万葉集9「―のなぎなむ時も渡らなむ」
うみ‐つばめ【海燕】
ミズナギドリ目ウミツバメ科の海鳥の総称。海面に遊泳し、また海面をかすめて飛ぶ。大きさはツグミまたはスズメぐらい。羽は主として暗褐色または蒼灰色。翼は長く、尾はツバメの尾と同じく二つに分かれるが短い。嘴端は鉤状、趾にみずかきがあり、孤島の地上に穴を穿って巣をつくる。
コシジロウミツバメ
撮影:小宮輝之
 うみ‐づら【海面】
①海の面。海上。伊勢物語「伊勢、尾張のあはひの―を行くに」
②海に面した所。海べ。源氏物語若紫「少し奥まりたる山住みもせで、さる―に出でゐたる」
うみ‐づり【海釣り】
海でする釣り。
うみ‐つ・る【生み連る・産み連る】
〔他下二〕
生んで引き連れる。宇津保物語俊蔭「いかめしき雌熊・雄熊、子を―・れて棲むうつぼなりけり」
うみ‐て【海手】
海の方。↔山手
うみ‐とさか【海鶏頭・海鶏冠】
八放サンゴ亜綱ウミトサカ目、特にチヂミトサカ科の花虫類の総称。群体は柔軟な肉質で樹状に分岐、その先端に多くのポリプがある。縮んだ群体は、一般にカリフラワー状。岩礁上に着生。暖海に分布。ウミトサカ目はソフト‐コーラルとも呼ばれる。
うみ‐どじょう【海泥鰌】‥ドヂヤウ
①アシロ科の海産の硬骨魚。全長約25センチメートル。暗灰色でややギンポに似る。
②ギンポの別称。
③アユモドキの別称。
うみ‐どり【海鳥】
カモメ・グンカンドリなどもっぱら海洋で生活する鳥。海上を飛翔したり海面に浮游したりしている鳥を漠然と指すことが多い。かいちょう。
うみ‐ながし【産み流し】
①流産りゅうざん。増鏡「これも御―にて、俄にうせさせ給ひけりとぞ聞えし」
②生むだけで自分で世話しないこと。
うみ‐づら【海面】
①海の面。海上。伊勢物語「伊勢、尾張のあはひの―を行くに」
②海に面した所。海べ。源氏物語若紫「少し奥まりたる山住みもせで、さる―に出でゐたる」
うみ‐づり【海釣り】
海でする釣り。
うみ‐つ・る【生み連る・産み連る】
〔他下二〕
生んで引き連れる。宇津保物語俊蔭「いかめしき雌熊・雄熊、子を―・れて棲むうつぼなりけり」
うみ‐て【海手】
海の方。↔山手
うみ‐とさか【海鶏頭・海鶏冠】
八放サンゴ亜綱ウミトサカ目、特にチヂミトサカ科の花虫類の総称。群体は柔軟な肉質で樹状に分岐、その先端に多くのポリプがある。縮んだ群体は、一般にカリフラワー状。岩礁上に着生。暖海に分布。ウミトサカ目はソフト‐コーラルとも呼ばれる。
うみ‐どじょう【海泥鰌】‥ドヂヤウ
①アシロ科の海産の硬骨魚。全長約25センチメートル。暗灰色でややギンポに似る。
②ギンポの別称。
③アユモドキの別称。
うみ‐どり【海鳥】
カモメ・グンカンドリなどもっぱら海洋で生活する鳥。海上を飛翔したり海面に浮游したりしている鳥を漠然と指すことが多い。かいちょう。
うみ‐ながし【産み流し】
①流産りゅうざん。増鏡「これも御―にて、俄にうせさせ給ひけりとぞ聞えし」
②生むだけで自分で世話しないこと。
 うみ‐さち【海幸】
①海の獲物を取る道具。つりばり。古事記上「―をもちて魚な釣らすに」
②海で得る獲物。海産物。神代紀下「兄…自づからに―有まします」↔山幸。
⇒うみさち‐やまさち【海幸山幸】
うみさち‐やまさち【海幸山幸】
日本神話の一つ。彦火火出見尊ひこほほでみのみこと(山幸彦)が兄の火照命ほでりのみこと(海幸彦)と猟具をとりかえて魚を釣りに出たが、釣針を失い、探し求めるため塩椎神しおつちのかみの教えにより海宮に赴き、海神の女むすめと結婚、釣針と潮盈珠しおみちのたま・潮乾珠しおひのたまを得て兄を降伏させたという話。天孫民族と隼人はやと族との闘争の神話化とも見られる。また仙郷滞留説話・神婚説話・浦島伝説の先駆をなすもの。
⇒うみ‐さち【海幸】
うみ‐サボテン【海サボテン】
八放サンゴ亜綱ウミエラ目ウミサボテン科の花虫類。棒状の群体を作り、ポリプはその周縁に配列、その姿がサボテンを思わせる。下端の細い柄部で海底に着生し、昼間は縮んで底に潜り、夜間は海中に伸び出して、長さ50センチメートルに達し、触ると燐光を発する。日本各地の浅海泥底に生息。
うみ‐ざりがに【海蝲蛄】
ロブスターのこと。
うみ‐じ【海路】‥ヂ
海上の舟の通う路。航路。船路。うなじ。万葉集3「いさな取り―に出でて」
うみ‐じ【産字・生字】
謡・浄瑠璃・長唄など日本の音曲で、1音節を長く延ばして歌う場合の延ばす母音の部分。「し」を「しいー」と延ばした時の「いー」の類。
うみ‐しか【海鹿】
アメフラシの別称。
うみ‐しだ【海羊歯】
ウミユリ綱ウミシダ亜目の棘皮きょくひ動物の総称。小さな円盤状の体の上面に口と肛門があり、周囲に10本から数十本の腕が出、各腕には細かな羽枝がある。外見が羊歯に類似するのでこの名がある。体の下面にある多数の巻枝で岩などにつかまり移動する。ニッポンウミシダ・オオバンウミシダ・アヤウミシダなど種類が多い。
うみ‐しる【膿汁】
うみ。のうじゅう。西大寺本最勝王経平安初期点「臭く穢けがれ膿ウミシル流れつつ」
うみ‐じるし【産印】
(四国地方で)痣あざ。
うみ‐す【産み巣】
子をはらむ腹。母胎。浄瑠璃、松風村雨束帯鑑「三人までの―とは、難じていはば子過ぎ腹」
うみすい‐いし【膿吸い石】‥スヒ‥
円く平たい小石状のもの。膿を吸わせる。竜骨の類か。→スランガステーン
うみ‐すずめ【海雀】
①ハコフグ科の海産の硬骨魚。全長約20センチメートル。体は箱状で亀甲型に仕切られた鱗甲を被り、頭部の左右に1対のとげが突出し、背にも1本のとげがある。本州中部以南の沿岸に産。スズメフグ。ハコフグ。スズメイオ。
②チドリ目ウミスズメ科の鳥の総称。北半球北部の海域に、約20種が分布。また、特にそのうち小形の約10種の総称。全長約25センチメートルのずんぐりした海鳥で、潜水して魚を捕る。日本では7種が記録され、カンムリウミスズメ・ウミスズメなどが繁殖。
③2の一種。太平洋北部に分布し、日本では北海道で繁殖。
うみすずめ(冬羽)
うみ‐さち【海幸】
①海の獲物を取る道具。つりばり。古事記上「―をもちて魚な釣らすに」
②海で得る獲物。海産物。神代紀下「兄…自づからに―有まします」↔山幸。
⇒うみさち‐やまさち【海幸山幸】
うみさち‐やまさち【海幸山幸】
日本神話の一つ。彦火火出見尊ひこほほでみのみこと(山幸彦)が兄の火照命ほでりのみこと(海幸彦)と猟具をとりかえて魚を釣りに出たが、釣針を失い、探し求めるため塩椎神しおつちのかみの教えにより海宮に赴き、海神の女むすめと結婚、釣針と潮盈珠しおみちのたま・潮乾珠しおひのたまを得て兄を降伏させたという話。天孫民族と隼人はやと族との闘争の神話化とも見られる。また仙郷滞留説話・神婚説話・浦島伝説の先駆をなすもの。
⇒うみ‐さち【海幸】
うみ‐サボテン【海サボテン】
八放サンゴ亜綱ウミエラ目ウミサボテン科の花虫類。棒状の群体を作り、ポリプはその周縁に配列、その姿がサボテンを思わせる。下端の細い柄部で海底に着生し、昼間は縮んで底に潜り、夜間は海中に伸び出して、長さ50センチメートルに達し、触ると燐光を発する。日本各地の浅海泥底に生息。
うみ‐ざりがに【海蝲蛄】
ロブスターのこと。
うみ‐じ【海路】‥ヂ
海上の舟の通う路。航路。船路。うなじ。万葉集3「いさな取り―に出でて」
うみ‐じ【産字・生字】
謡・浄瑠璃・長唄など日本の音曲で、1音節を長く延ばして歌う場合の延ばす母音の部分。「し」を「しいー」と延ばした時の「いー」の類。
うみ‐しか【海鹿】
アメフラシの別称。
うみ‐しだ【海羊歯】
ウミユリ綱ウミシダ亜目の棘皮きょくひ動物の総称。小さな円盤状の体の上面に口と肛門があり、周囲に10本から数十本の腕が出、各腕には細かな羽枝がある。外見が羊歯に類似するのでこの名がある。体の下面にある多数の巻枝で岩などにつかまり移動する。ニッポンウミシダ・オオバンウミシダ・アヤウミシダなど種類が多い。
うみ‐しる【膿汁】
うみ。のうじゅう。西大寺本最勝王経平安初期点「臭く穢けがれ膿ウミシル流れつつ」
うみ‐じるし【産印】
(四国地方で)痣あざ。
うみ‐す【産み巣】
子をはらむ腹。母胎。浄瑠璃、松風村雨束帯鑑「三人までの―とは、難じていはば子過ぎ腹」
うみすい‐いし【膿吸い石】‥スヒ‥
円く平たい小石状のもの。膿を吸わせる。竜骨の類か。→スランガステーン
うみ‐すずめ【海雀】
①ハコフグ科の海産の硬骨魚。全長約20センチメートル。体は箱状で亀甲型に仕切られた鱗甲を被り、頭部の左右に1対のとげが突出し、背にも1本のとげがある。本州中部以南の沿岸に産。スズメフグ。ハコフグ。スズメイオ。
②チドリ目ウミスズメ科の鳥の総称。北半球北部の海域に、約20種が分布。また、特にそのうち小形の約10種の総称。全長約25センチメートルのずんぐりした海鳥で、潜水して魚を捕る。日本では7種が記録され、カンムリウミスズメ・ウミスズメなどが繁殖。
③2の一種。太平洋北部に分布し、日本では北海道で繁殖。
うみすずめ(冬羽)
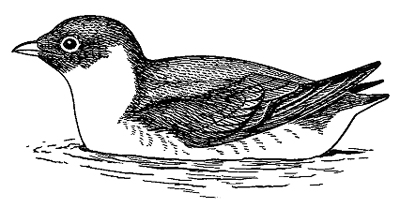 うみせん‐かわせん【海千河千】‥カハ‥
(海に千年河に千年住んだものの意)(→)海千山千に同じ。
うみせん‐やません【海千山千】
(海に千年山に千年住んだ蛇は竜になるという言い伝えから)せちがらい世の中の裏も表も知っていて、老獪ろうかいな人。「―の事業家」
うみ‐そ【績麻】
(→)「うみお」に同じ。
うみ‐ぞうめん【海索麺】‥ザウ‥
①アメフラシ・タツナミガイなどの卵塊の俗称。索麺の形をし、色は紅・黄・橙色など種々。膠質の紐の中に包み込まれている卵から幼生が孵化する。初夏、磯に見られる。
ウミゾウメン
提供:東京動物園協会
うみせん‐かわせん【海千河千】‥カハ‥
(海に千年河に千年住んだものの意)(→)海千山千に同じ。
うみせん‐やません【海千山千】
(海に千年山に千年住んだ蛇は竜になるという言い伝えから)せちがらい世の中の裏も表も知っていて、老獪ろうかいな人。「―の事業家」
うみ‐そ【績麻】
(→)「うみお」に同じ。
うみ‐ぞうめん【海索麺】‥ザウ‥
①アメフラシ・タツナミガイなどの卵塊の俗称。索麺の形をし、色は紅・黄・橙色など種々。膠質の紐の中に包み込まれている卵から幼生が孵化する。初夏、磯に見られる。
ウミゾウメン
提供:東京動物園協会
 ②海産の紅藻類。北海道・本州などで波の高い磯に付く。体は細長い紐状で、長さ10〜20センチメートル。濃紅茶色で粘性が強い。夏、採集して乾燥または塩漬とし、三杯酢で食べる。
うみ‐だか【海高】
江戸時代、海産の収穫を石高に見積もり、租税として米や金銀で納めさせたもの。海石うみこく。
うみ‐たけ‐がい【海筍貝・海笋貝】‥ガヒ
ニオガイ科の二枚貝。貝殻は白色で薄くてもろく、黒くて長い水管は殻長の2倍もある。食用となり、熨斗鮑のしあわびの代用。有明海・瀬戸内海など、内海の泥深い所に産する。ウミタケ。〈日葡辞書〉
うみ‐だ・す【生み出す・産み出す】
〔他五〕
①胎児または卵を生む。
②生み始める。
③新しく作り出す。「新企画を―・す」「財源を―・す」
うみ‐たなご【海鱮】
ウミタナゴ科の海産の硬骨魚。全長約25センチメートル。体は側扁し頭は小さい。鉄青色または銅赤色。日本各地の沿岸に産し、殊に内湾のアマモの生えているところに多く、卵胎生。地方によっては妊婦が食べるのを忌む。タナゴ。
ウミタナゴ
提供:東京動物園協会
②海産の紅藻類。北海道・本州などで波の高い磯に付く。体は細長い紐状で、長さ10〜20センチメートル。濃紅茶色で粘性が強い。夏、採集して乾燥または塩漬とし、三杯酢で食べる。
うみ‐だか【海高】
江戸時代、海産の収穫を石高に見積もり、租税として米や金銀で納めさせたもの。海石うみこく。
うみ‐たけ‐がい【海筍貝・海笋貝】‥ガヒ
ニオガイ科の二枚貝。貝殻は白色で薄くてもろく、黒くて長い水管は殻長の2倍もある。食用となり、熨斗鮑のしあわびの代用。有明海・瀬戸内海など、内海の泥深い所に産する。ウミタケ。〈日葡辞書〉
うみ‐だ・す【生み出す・産み出す】
〔他五〕
①胎児または卵を生む。
②生み始める。
③新しく作り出す。「新企画を―・す」「財源を―・す」
うみ‐たなご【海鱮】
ウミタナゴ科の海産の硬骨魚。全長約25センチメートル。体は側扁し頭は小さい。鉄青色または銅赤色。日本各地の沿岸に産し、殊に内湾のアマモの生えているところに多く、卵胎生。地方によっては妊婦が食べるのを忌む。タナゴ。
ウミタナゴ
提供:東京動物園協会
 うみ‐だぬき【海狸】
ビーバーのこと。かいり。
うみ‐たる【海樽】
原索動物門ウミタル科の海産プランクトンの一種。体長3〜6ミリメートルの透明なビヤ樽状。体壁の内側にある8個の環状筋を収縮して水を後端から噴出し、その反動で運動する。世界の温水域に分布し、大形回遊魚の天然飼料となる。
うみ‐ち【膿血】
膿汁に血のまじったもの。
うみ‐つか・れる【倦み疲れる】
〔自下一〕[文]うみつか・る(下二)
あきて疲れる。うんざりしてつかれる。
うみ‐づき【産み月】
胎児が生まれる予定の月。臨月。
うみ‐つ・ける【生み付ける・産み付ける】
〔他下一〕[文]うみつ・く(下二)
①卵を生んで物に付着させる。
②生んで、親の性質・外見などを受けさせる。
うみ‐つ‐じ【海路】‥ヂ
航路。うみじ。うなじ。万葉集9「―のなぎなむ時も渡らなむ」
うみ‐つばめ【海燕】
ミズナギドリ目ウミツバメ科の海鳥の総称。海面に遊泳し、また海面をかすめて飛ぶ。大きさはツグミまたはスズメぐらい。羽は主として暗褐色または蒼灰色。翼は長く、尾はツバメの尾と同じく二つに分かれるが短い。嘴端は鉤状、趾にみずかきがあり、孤島の地上に穴を穿って巣をつくる。
コシジロウミツバメ
撮影:小宮輝之
うみ‐だぬき【海狸】
ビーバーのこと。かいり。
うみ‐たる【海樽】
原索動物門ウミタル科の海産プランクトンの一種。体長3〜6ミリメートルの透明なビヤ樽状。体壁の内側にある8個の環状筋を収縮して水を後端から噴出し、その反動で運動する。世界の温水域に分布し、大形回遊魚の天然飼料となる。
うみ‐ち【膿血】
膿汁に血のまじったもの。
うみ‐つか・れる【倦み疲れる】
〔自下一〕[文]うみつか・る(下二)
あきて疲れる。うんざりしてつかれる。
うみ‐づき【産み月】
胎児が生まれる予定の月。臨月。
うみ‐つ・ける【生み付ける・産み付ける】
〔他下一〕[文]うみつ・く(下二)
①卵を生んで物に付着させる。
②生んで、親の性質・外見などを受けさせる。
うみ‐つ‐じ【海路】‥ヂ
航路。うみじ。うなじ。万葉集9「―のなぎなむ時も渡らなむ」
うみ‐つばめ【海燕】
ミズナギドリ目ウミツバメ科の海鳥の総称。海面に遊泳し、また海面をかすめて飛ぶ。大きさはツグミまたはスズメぐらい。羽は主として暗褐色または蒼灰色。翼は長く、尾はツバメの尾と同じく二つに分かれるが短い。嘴端は鉤状、趾にみずかきがあり、孤島の地上に穴を穿って巣をつくる。
コシジロウミツバメ
撮影:小宮輝之
 うみ‐づら【海面】
①海の面。海上。伊勢物語「伊勢、尾張のあはひの―を行くに」
②海に面した所。海べ。源氏物語若紫「少し奥まりたる山住みもせで、さる―に出でゐたる」
うみ‐づり【海釣り】
海でする釣り。
うみ‐つ・る【生み連る・産み連る】
〔他下二〕
生んで引き連れる。宇津保物語俊蔭「いかめしき雌熊・雄熊、子を―・れて棲むうつぼなりけり」
うみ‐て【海手】
海の方。↔山手
うみ‐とさか【海鶏頭・海鶏冠】
八放サンゴ亜綱ウミトサカ目、特にチヂミトサカ科の花虫類の総称。群体は柔軟な肉質で樹状に分岐、その先端に多くのポリプがある。縮んだ群体は、一般にカリフラワー状。岩礁上に着生。暖海に分布。ウミトサカ目はソフト‐コーラルとも呼ばれる。
うみ‐どじょう【海泥鰌】‥ドヂヤウ
①アシロ科の海産の硬骨魚。全長約25センチメートル。暗灰色でややギンポに似る。
②ギンポの別称。
③アユモドキの別称。
うみ‐どり【海鳥】
カモメ・グンカンドリなどもっぱら海洋で生活する鳥。海上を飛翔したり海面に浮游したりしている鳥を漠然と指すことが多い。かいちょう。
うみ‐ながし【産み流し】
①流産りゅうざん。増鏡「これも御―にて、俄にうせさせ給ひけりとぞ聞えし」
②生むだけで自分で世話しないこと。
うみ‐づら【海面】
①海の面。海上。伊勢物語「伊勢、尾張のあはひの―を行くに」
②海に面した所。海べ。源氏物語若紫「少し奥まりたる山住みもせで、さる―に出でゐたる」
うみ‐づり【海釣り】
海でする釣り。
うみ‐つ・る【生み連る・産み連る】
〔他下二〕
生んで引き連れる。宇津保物語俊蔭「いかめしき雌熊・雄熊、子を―・れて棲むうつぼなりけり」
うみ‐て【海手】
海の方。↔山手
うみ‐とさか【海鶏頭・海鶏冠】
八放サンゴ亜綱ウミトサカ目、特にチヂミトサカ科の花虫類の総称。群体は柔軟な肉質で樹状に分岐、その先端に多くのポリプがある。縮んだ群体は、一般にカリフラワー状。岩礁上に着生。暖海に分布。ウミトサカ目はソフト‐コーラルとも呼ばれる。
うみ‐どじょう【海泥鰌】‥ドヂヤウ
①アシロ科の海産の硬骨魚。全長約25センチメートル。暗灰色でややギンポに似る。
②ギンポの別称。
③アユモドキの別称。
うみ‐どり【海鳥】
カモメ・グンカンドリなどもっぱら海洋で生活する鳥。海上を飛翔したり海面に浮游したりしている鳥を漠然と指すことが多い。かいちょう。
うみ‐ながし【産み流し】
①流産りゅうざん。増鏡「これも御―にて、俄にうせさせ給ひけりとぞ聞えし」
②生むだけで自分で世話しないこと。
広辞苑 ページ 1947 での【○海が涌く】単語。