複数辞典一括検索+![]()
![]()
○槍が降ってもやりがふっても🔗⭐🔉
○槍が降ってもやりがふっても
どんな難事に出逢おうとも。槍が降ろうが。「火が降っても―」
⇒やり【槍・鎗・鑓】
やり‐がらみ【槍絡み】
槍ぶすまを作って敵軍にあたる一隊。
やり‐がんな【槍鉋・鐁】
古代の鉋。槍の穂先の反った形の身に柄をつけたもの。室町時代に現在の台鉋ができ、これに取って代わった。
槍鉋
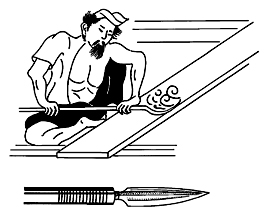 やり‐きず【槍疵・槍傷】
槍で突かれたきず。やりて。
やりきれ‐ない【遣り切れない】
①最後までやり遂げることができない。「期日までに―」
②がまんできない。たえられない。「暑くて―」
やり‐く【遣句】
連歌・俳諧で、前句がむつかしくて付句を付けにくい場合に、次の句を付けやすいよう軽く付けること。また、その句。俳諧では「逃句」とも。
やり‐くさ【槍草】
〔植〕(→)スズメノテッポウの別称。
やり‐ぐすね【槍薬煉】
手に唾つばをつけて槍を取ること。
やり‐くち【遣り口】
やりよう。しかた。手口。多く、公正・正当でない場合にいう。夏目漱石、吾輩は猫である「其熟練と器用な―にも一寸感心した」。「―がきたない」
やり‐くら【遣り競】
やりあうこと。競うこと。やりかたを競争すること。→競くら
やり‐くり【遣り繰り】
不十分な物事を種々に工夫して都合をつけること。どうにか繰り合わせること。好色一代女2「せはし男に気を付け―の後、やりて呼びて」。「家計の―」
⇒やりくり‐さんだん【遣り繰り算段】
⇒やりくり‐しんしょう【遣り繰り身上】
やりくり‐さんだん【遣り繰り算段】
いろいろとやりくりし工面すること。特に、金銭の都合に苦心すること。「―して資金を集める」
⇒やり‐くり【遣り繰り】
やりくり‐しんしょう【遣り繰り身上】‥シヤウ
やりくってようやく維持する世帯。
⇒やり‐くり【遣り繰り】
やり‐く・る【遣り繰る】
〔他五〕
やりくりをする。
やり‐ごえ【槍声】‥ゴヱ
鋭いとがり声。おこった声。
やり‐こな・す【遣り熟す】
〔他五〕
うまく処理できる。やってのける。「難事を―・す」
やり‐こ・める【遣り込める】
〔他下一〕[文]やりこ・む(下二)
論じつめて相手をだまらせる。言いこめる。言いふせる。「子供に―・められる」
やり‐さき【槍先】
①槍の先端。槍の穂先。物を突き刺すほどの勢いのある長いものにたとえていう。きっさき。ほこさき。好色一代女4「あたら―を都の島原陣の役にも立てず」
②喧嘩・合戦のしはじめ。〈日葡辞書〉
⇒やりさき‐の‐こうみょう【槍先の功名】
やりさき‐の‐こうみょう【槍先の功名】‥ミヤウ
戦場での功績。武功。
⇒やり‐さき【槍先】
やり‐さく【槍柵】
槍を柵のように多く立てならべること。また、そのもの。
やりさび【槍錆】
端唄・うた沢。「槍は錆びても」の略称。浪人となった丹波与作の心意気を歌ったもの。幕末に歌沢笹丸が「与作踊音頭」をもとに改作したという。歌舞伎で下座唄としても用いる。
やり‐し【槍師】
①槍の使い手。槍の名人。
②槍を作る人。
やり‐した【槍下】
槍で突き伏せること。日葡辞書「ヤリシタデクビヲトルハテガラデァ」
⇒やりした‐の‐こうみょう【槍下の高名】
やりした‐の‐こうみょう【槍下の高名】‥カウミヤウ
戦場で敵を突き伏せて首を取ること。
⇒やり‐した【槍下】
やり‐じるし【槍印】
戦陣または外出の時、槍の印付しるしづけの鐶かんにつけて、家名を明らかにした小帛こぎれ・白熊はぐまなどのしるし。
やり‐すぎ【遣り過ぎ】
限度以上にすること。しすぎること。「いくらなんでも―だ」
やり‐すご・す【遣り過ごす】
〔他五〕
①うしろから来たものを前へ行き過ぎさせる。「隊列を―・す」
②ある状態が経過するにまかせる。厄介な物事と関係を持たないですます。「この件を―・すことはできない」
③限度を超えてする。「酒を―・す」
やり‐そこない【遣り損い】‥ソコナヒ
やりそこなうこと。また、そのもの。しそんじ。
やり‐そこな・う【遣り損なう】‥ソコナフ
〔他五〕
①しようとして失敗する。しそんずる。やりそこねる。「あせって―・う」
②する機会をのがす。「遅刻して―・った」
やり‐ぞなえ【槍備え】‥ゾナヘ
槍を構えた隊列・陣形。
やり‐そんじ【遣り損じ】
やりそこなうこと。また、そのもの。しそんじ。
やり‐そん・じる【遣り損じる】
〔他上一〕
「遣り損ずる」に同じ。
やり‐そん・ずる【遣り損ずる】
〔他サ変〕[文]やりそん・ず(サ変)
①やりそこなう。
②乗物などを進めそこなう。
やりたい‐ほうだい【遣りたい放題】‥ハウ‥
(→)「したい放題」に同じ。
やり‐だし【遣出】
船の舳へさきから斜め前方に突き出した短い帆柱。小野寺篤謙、開成丸航海日誌「東方白む頃おひ―の帆を巻立、順風なれば真帆をも張て走り出す」
やり‐だ・す【遣り出す】
〔他五〕
①進め出す。押し出す。天草本平家物語「二位の入道車に乗り、一条大路おおみちへ―・させ実検せられた」
②しだす。しはじめる。
やり‐たなご【槍鱮】
コイ科の淡水産の硬骨魚。全長約10センチメートル。タナゴ類のなかでは体高がやや低い。本州・四国・九州北部の各地に分布。マタナゴ。ボテ。
やり‐だま【槍玉】
槍を手玉のように自由自在に扱うのにいう語。また、人を槍の穂先で突き刺すこと。
⇒槍玉に挙げる
やり‐きず【槍疵・槍傷】
槍で突かれたきず。やりて。
やりきれ‐ない【遣り切れない】
①最後までやり遂げることができない。「期日までに―」
②がまんできない。たえられない。「暑くて―」
やり‐く【遣句】
連歌・俳諧で、前句がむつかしくて付句を付けにくい場合に、次の句を付けやすいよう軽く付けること。また、その句。俳諧では「逃句」とも。
やり‐くさ【槍草】
〔植〕(→)スズメノテッポウの別称。
やり‐ぐすね【槍薬煉】
手に唾つばをつけて槍を取ること。
やり‐くち【遣り口】
やりよう。しかた。手口。多く、公正・正当でない場合にいう。夏目漱石、吾輩は猫である「其熟練と器用な―にも一寸感心した」。「―がきたない」
やり‐くら【遣り競】
やりあうこと。競うこと。やりかたを競争すること。→競くら
やり‐くり【遣り繰り】
不十分な物事を種々に工夫して都合をつけること。どうにか繰り合わせること。好色一代女2「せはし男に気を付け―の後、やりて呼びて」。「家計の―」
⇒やりくり‐さんだん【遣り繰り算段】
⇒やりくり‐しんしょう【遣り繰り身上】
やりくり‐さんだん【遣り繰り算段】
いろいろとやりくりし工面すること。特に、金銭の都合に苦心すること。「―して資金を集める」
⇒やり‐くり【遣り繰り】
やりくり‐しんしょう【遣り繰り身上】‥シヤウ
やりくってようやく維持する世帯。
⇒やり‐くり【遣り繰り】
やり‐く・る【遣り繰る】
〔他五〕
やりくりをする。
やり‐ごえ【槍声】‥ゴヱ
鋭いとがり声。おこった声。
やり‐こな・す【遣り熟す】
〔他五〕
うまく処理できる。やってのける。「難事を―・す」
やり‐こ・める【遣り込める】
〔他下一〕[文]やりこ・む(下二)
論じつめて相手をだまらせる。言いこめる。言いふせる。「子供に―・められる」
やり‐さき【槍先】
①槍の先端。槍の穂先。物を突き刺すほどの勢いのある長いものにたとえていう。きっさき。ほこさき。好色一代女4「あたら―を都の島原陣の役にも立てず」
②喧嘩・合戦のしはじめ。〈日葡辞書〉
⇒やりさき‐の‐こうみょう【槍先の功名】
やりさき‐の‐こうみょう【槍先の功名】‥ミヤウ
戦場での功績。武功。
⇒やり‐さき【槍先】
やり‐さく【槍柵】
槍を柵のように多く立てならべること。また、そのもの。
やりさび【槍錆】
端唄・うた沢。「槍は錆びても」の略称。浪人となった丹波与作の心意気を歌ったもの。幕末に歌沢笹丸が「与作踊音頭」をもとに改作したという。歌舞伎で下座唄としても用いる。
やり‐し【槍師】
①槍の使い手。槍の名人。
②槍を作る人。
やり‐した【槍下】
槍で突き伏せること。日葡辞書「ヤリシタデクビヲトルハテガラデァ」
⇒やりした‐の‐こうみょう【槍下の高名】
やりした‐の‐こうみょう【槍下の高名】‥カウミヤウ
戦場で敵を突き伏せて首を取ること。
⇒やり‐した【槍下】
やり‐じるし【槍印】
戦陣または外出の時、槍の印付しるしづけの鐶かんにつけて、家名を明らかにした小帛こぎれ・白熊はぐまなどのしるし。
やり‐すぎ【遣り過ぎ】
限度以上にすること。しすぎること。「いくらなんでも―だ」
やり‐すご・す【遣り過ごす】
〔他五〕
①うしろから来たものを前へ行き過ぎさせる。「隊列を―・す」
②ある状態が経過するにまかせる。厄介な物事と関係を持たないですます。「この件を―・すことはできない」
③限度を超えてする。「酒を―・す」
やり‐そこない【遣り損い】‥ソコナヒ
やりそこなうこと。また、そのもの。しそんじ。
やり‐そこな・う【遣り損なう】‥ソコナフ
〔他五〕
①しようとして失敗する。しそんずる。やりそこねる。「あせって―・う」
②する機会をのがす。「遅刻して―・った」
やり‐ぞなえ【槍備え】‥ゾナヘ
槍を構えた隊列・陣形。
やり‐そんじ【遣り損じ】
やりそこなうこと。また、そのもの。しそんじ。
やり‐そん・じる【遣り損じる】
〔他上一〕
「遣り損ずる」に同じ。
やり‐そん・ずる【遣り損ずる】
〔他サ変〕[文]やりそん・ず(サ変)
①やりそこなう。
②乗物などを進めそこなう。
やりたい‐ほうだい【遣りたい放題】‥ハウ‥
(→)「したい放題」に同じ。
やり‐だし【遣出】
船の舳へさきから斜め前方に突き出した短い帆柱。小野寺篤謙、開成丸航海日誌「東方白む頃おひ―の帆を巻立、順風なれば真帆をも張て走り出す」
やり‐だ・す【遣り出す】
〔他五〕
①進め出す。押し出す。天草本平家物語「二位の入道車に乗り、一条大路おおみちへ―・させ実検せられた」
②しだす。しはじめる。
やり‐たなご【槍鱮】
コイ科の淡水産の硬骨魚。全長約10センチメートル。タナゴ類のなかでは体高がやや低い。本州・四国・九州北部の各地に分布。マタナゴ。ボテ。
やり‐だま【槍玉】
槍を手玉のように自由自在に扱うのにいう語。また、人を槍の穂先で突き刺すこと。
⇒槍玉に挙げる
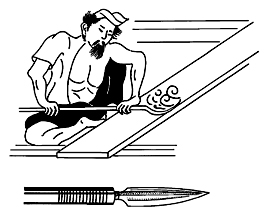 やり‐きず【槍疵・槍傷】
槍で突かれたきず。やりて。
やりきれ‐ない【遣り切れない】
①最後までやり遂げることができない。「期日までに―」
②がまんできない。たえられない。「暑くて―」
やり‐く【遣句】
連歌・俳諧で、前句がむつかしくて付句を付けにくい場合に、次の句を付けやすいよう軽く付けること。また、その句。俳諧では「逃句」とも。
やり‐くさ【槍草】
〔植〕(→)スズメノテッポウの別称。
やり‐ぐすね【槍薬煉】
手に唾つばをつけて槍を取ること。
やり‐くち【遣り口】
やりよう。しかた。手口。多く、公正・正当でない場合にいう。夏目漱石、吾輩は猫である「其熟練と器用な―にも一寸感心した」。「―がきたない」
やり‐くら【遣り競】
やりあうこと。競うこと。やりかたを競争すること。→競くら
やり‐くり【遣り繰り】
不十分な物事を種々に工夫して都合をつけること。どうにか繰り合わせること。好色一代女2「せはし男に気を付け―の後、やりて呼びて」。「家計の―」
⇒やりくり‐さんだん【遣り繰り算段】
⇒やりくり‐しんしょう【遣り繰り身上】
やりくり‐さんだん【遣り繰り算段】
いろいろとやりくりし工面すること。特に、金銭の都合に苦心すること。「―して資金を集める」
⇒やり‐くり【遣り繰り】
やりくり‐しんしょう【遣り繰り身上】‥シヤウ
やりくってようやく維持する世帯。
⇒やり‐くり【遣り繰り】
やり‐く・る【遣り繰る】
〔他五〕
やりくりをする。
やり‐ごえ【槍声】‥ゴヱ
鋭いとがり声。おこった声。
やり‐こな・す【遣り熟す】
〔他五〕
うまく処理できる。やってのける。「難事を―・す」
やり‐こ・める【遣り込める】
〔他下一〕[文]やりこ・む(下二)
論じつめて相手をだまらせる。言いこめる。言いふせる。「子供に―・められる」
やり‐さき【槍先】
①槍の先端。槍の穂先。物を突き刺すほどの勢いのある長いものにたとえていう。きっさき。ほこさき。好色一代女4「あたら―を都の島原陣の役にも立てず」
②喧嘩・合戦のしはじめ。〈日葡辞書〉
⇒やりさき‐の‐こうみょう【槍先の功名】
やりさき‐の‐こうみょう【槍先の功名】‥ミヤウ
戦場での功績。武功。
⇒やり‐さき【槍先】
やり‐さく【槍柵】
槍を柵のように多く立てならべること。また、そのもの。
やりさび【槍錆】
端唄・うた沢。「槍は錆びても」の略称。浪人となった丹波与作の心意気を歌ったもの。幕末に歌沢笹丸が「与作踊音頭」をもとに改作したという。歌舞伎で下座唄としても用いる。
やり‐し【槍師】
①槍の使い手。槍の名人。
②槍を作る人。
やり‐した【槍下】
槍で突き伏せること。日葡辞書「ヤリシタデクビヲトルハテガラデァ」
⇒やりした‐の‐こうみょう【槍下の高名】
やりした‐の‐こうみょう【槍下の高名】‥カウミヤウ
戦場で敵を突き伏せて首を取ること。
⇒やり‐した【槍下】
やり‐じるし【槍印】
戦陣または外出の時、槍の印付しるしづけの鐶かんにつけて、家名を明らかにした小帛こぎれ・白熊はぐまなどのしるし。
やり‐すぎ【遣り過ぎ】
限度以上にすること。しすぎること。「いくらなんでも―だ」
やり‐すご・す【遣り過ごす】
〔他五〕
①うしろから来たものを前へ行き過ぎさせる。「隊列を―・す」
②ある状態が経過するにまかせる。厄介な物事と関係を持たないですます。「この件を―・すことはできない」
③限度を超えてする。「酒を―・す」
やり‐そこない【遣り損い】‥ソコナヒ
やりそこなうこと。また、そのもの。しそんじ。
やり‐そこな・う【遣り損なう】‥ソコナフ
〔他五〕
①しようとして失敗する。しそんずる。やりそこねる。「あせって―・う」
②する機会をのがす。「遅刻して―・った」
やり‐ぞなえ【槍備え】‥ゾナヘ
槍を構えた隊列・陣形。
やり‐そんじ【遣り損じ】
やりそこなうこと。また、そのもの。しそんじ。
やり‐そん・じる【遣り損じる】
〔他上一〕
「遣り損ずる」に同じ。
やり‐そん・ずる【遣り損ずる】
〔他サ変〕[文]やりそん・ず(サ変)
①やりそこなう。
②乗物などを進めそこなう。
やりたい‐ほうだい【遣りたい放題】‥ハウ‥
(→)「したい放題」に同じ。
やり‐だし【遣出】
船の舳へさきから斜め前方に突き出した短い帆柱。小野寺篤謙、開成丸航海日誌「東方白む頃おひ―の帆を巻立、順風なれば真帆をも張て走り出す」
やり‐だ・す【遣り出す】
〔他五〕
①進め出す。押し出す。天草本平家物語「二位の入道車に乗り、一条大路おおみちへ―・させ実検せられた」
②しだす。しはじめる。
やり‐たなご【槍鱮】
コイ科の淡水産の硬骨魚。全長約10センチメートル。タナゴ類のなかでは体高がやや低い。本州・四国・九州北部の各地に分布。マタナゴ。ボテ。
やり‐だま【槍玉】
槍を手玉のように自由自在に扱うのにいう語。また、人を槍の穂先で突き刺すこと。
⇒槍玉に挙げる
やり‐きず【槍疵・槍傷】
槍で突かれたきず。やりて。
やりきれ‐ない【遣り切れない】
①最後までやり遂げることができない。「期日までに―」
②がまんできない。たえられない。「暑くて―」
やり‐く【遣句】
連歌・俳諧で、前句がむつかしくて付句を付けにくい場合に、次の句を付けやすいよう軽く付けること。また、その句。俳諧では「逃句」とも。
やり‐くさ【槍草】
〔植〕(→)スズメノテッポウの別称。
やり‐ぐすね【槍薬煉】
手に唾つばをつけて槍を取ること。
やり‐くち【遣り口】
やりよう。しかた。手口。多く、公正・正当でない場合にいう。夏目漱石、吾輩は猫である「其熟練と器用な―にも一寸感心した」。「―がきたない」
やり‐くら【遣り競】
やりあうこと。競うこと。やりかたを競争すること。→競くら
やり‐くり【遣り繰り】
不十分な物事を種々に工夫して都合をつけること。どうにか繰り合わせること。好色一代女2「せはし男に気を付け―の後、やりて呼びて」。「家計の―」
⇒やりくり‐さんだん【遣り繰り算段】
⇒やりくり‐しんしょう【遣り繰り身上】
やりくり‐さんだん【遣り繰り算段】
いろいろとやりくりし工面すること。特に、金銭の都合に苦心すること。「―して資金を集める」
⇒やり‐くり【遣り繰り】
やりくり‐しんしょう【遣り繰り身上】‥シヤウ
やりくってようやく維持する世帯。
⇒やり‐くり【遣り繰り】
やり‐く・る【遣り繰る】
〔他五〕
やりくりをする。
やり‐ごえ【槍声】‥ゴヱ
鋭いとがり声。おこった声。
やり‐こな・す【遣り熟す】
〔他五〕
うまく処理できる。やってのける。「難事を―・す」
やり‐こ・める【遣り込める】
〔他下一〕[文]やりこ・む(下二)
論じつめて相手をだまらせる。言いこめる。言いふせる。「子供に―・められる」
やり‐さき【槍先】
①槍の先端。槍の穂先。物を突き刺すほどの勢いのある長いものにたとえていう。きっさき。ほこさき。好色一代女4「あたら―を都の島原陣の役にも立てず」
②喧嘩・合戦のしはじめ。〈日葡辞書〉
⇒やりさき‐の‐こうみょう【槍先の功名】
やりさき‐の‐こうみょう【槍先の功名】‥ミヤウ
戦場での功績。武功。
⇒やり‐さき【槍先】
やり‐さく【槍柵】
槍を柵のように多く立てならべること。また、そのもの。
やりさび【槍錆】
端唄・うた沢。「槍は錆びても」の略称。浪人となった丹波与作の心意気を歌ったもの。幕末に歌沢笹丸が「与作踊音頭」をもとに改作したという。歌舞伎で下座唄としても用いる。
やり‐し【槍師】
①槍の使い手。槍の名人。
②槍を作る人。
やり‐した【槍下】
槍で突き伏せること。日葡辞書「ヤリシタデクビヲトルハテガラデァ」
⇒やりした‐の‐こうみょう【槍下の高名】
やりした‐の‐こうみょう【槍下の高名】‥カウミヤウ
戦場で敵を突き伏せて首を取ること。
⇒やり‐した【槍下】
やり‐じるし【槍印】
戦陣または外出の時、槍の印付しるしづけの鐶かんにつけて、家名を明らかにした小帛こぎれ・白熊はぐまなどのしるし。
やり‐すぎ【遣り過ぎ】
限度以上にすること。しすぎること。「いくらなんでも―だ」
やり‐すご・す【遣り過ごす】
〔他五〕
①うしろから来たものを前へ行き過ぎさせる。「隊列を―・す」
②ある状態が経過するにまかせる。厄介な物事と関係を持たないですます。「この件を―・すことはできない」
③限度を超えてする。「酒を―・す」
やり‐そこない【遣り損い】‥ソコナヒ
やりそこなうこと。また、そのもの。しそんじ。
やり‐そこな・う【遣り損なう】‥ソコナフ
〔他五〕
①しようとして失敗する。しそんずる。やりそこねる。「あせって―・う」
②する機会をのがす。「遅刻して―・った」
やり‐ぞなえ【槍備え】‥ゾナヘ
槍を構えた隊列・陣形。
やり‐そんじ【遣り損じ】
やりそこなうこと。また、そのもの。しそんじ。
やり‐そん・じる【遣り損じる】
〔他上一〕
「遣り損ずる」に同じ。
やり‐そん・ずる【遣り損ずる】
〔他サ変〕[文]やりそん・ず(サ変)
①やりそこなう。
②乗物などを進めそこなう。
やりたい‐ほうだい【遣りたい放題】‥ハウ‥
(→)「したい放題」に同じ。
やり‐だし【遣出】
船の舳へさきから斜め前方に突き出した短い帆柱。小野寺篤謙、開成丸航海日誌「東方白む頃おひ―の帆を巻立、順風なれば真帆をも張て走り出す」
やり‐だ・す【遣り出す】
〔他五〕
①進め出す。押し出す。天草本平家物語「二位の入道車に乗り、一条大路おおみちへ―・させ実検せられた」
②しだす。しはじめる。
やり‐たなご【槍鱮】
コイ科の淡水産の硬骨魚。全長約10センチメートル。タナゴ類のなかでは体高がやや低い。本州・四国・九州北部の各地に分布。マタナゴ。ボテ。
やり‐だま【槍玉】
槍を手玉のように自由自在に扱うのにいう語。また、人を槍の穂先で突き刺すこと。
⇒槍玉に挙げる
広辞苑 ページ 19917 での【○槍が降っても】単語。