複数辞典一括検索+![]()
![]()
○明日は明日の風が吹くあしたはあしたのかぜがふく🔗⭐🔉
○明日は明日の風が吹くあしたはあしたのかぜがふく
明日はまた別のなりゆきになる。世の中は何とかなるもので、先を思い煩うことはない。
⇒あした【朝・明日】
あしだ‐ひとし【芦田均】
政治家。京都府出身。東大卒。外交官を経て代議士。民主党総裁。1948年首相在任中、昭電事件の責任を理由に政界を引退。著「芦田日記」。(1887〜1959)
芦田均
撮影:田村 茂
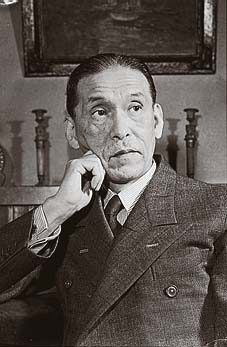 ⇒あしだ【芦田】
あし‐だま【足玉】
足首の飾りにつけた玉。万葉集10「―も手玉ただまもゆらに織るはたを」
あし‐だまり【足溜り】
①しばらく足をとどめる所。転じて、ある行動のための根拠地。
②足をかけるところ。あしがかり。
あしたれ‐ぼし【足垂星】
二十八宿の一つ。蠍座さそりざの南東部。尾宿。尾び。
あ‐ジチオンさん‐ナトリウム【亜ジチオン酸ナトリウム】
(sodium dithionite)化学式Na2S2O4 無色の結晶。強力な還元剤。染料合成原料・染色助剤・漂白剤などに用いる。ハイドロサルファイト・ヒドロ亜硫酸ナトリウムは誤称。
あし‐ついで【足序で】
歩きついで。出かけたついで。
あし‐つ‐お【足つ緒】‥ヲ
①琴の弦の端を結びかがった糸。
②太い綱。差縄。
あし‐づかい【足遣い】‥ヅカヒ
①足のつかいかた。あしどり。あしつき。
②人形浄瑠璃の三人遣いで、両足の操作を担当する人。
あし‐つき【足付】
①歩く時の足の様子。歩きかた。あしどり。「よろよろした―」
②器に足をつけたもの。
③足付折敷の略。
⇒あしつき‐おしき【足付折敷】
あし‐つき【葦付】
淡水に生えるジュズモなどの藍藻類。葦または石に付着。食用。あしつきのり。万葉集17「―採ると瀬に立たすらし」
あし‐つぎ【足継ぎ】
高くて手のとどかない場合に用いる台。ふみだい。ふみつぎ。
あしつき‐おしき【足付折敷】‥ヲ‥
板製の足が底の左右についた折敷。普通は白木を用いる。あしうちおしき。あしうち。木具きぐ。
⇒あし‐つき【足付】
あし‐つけ【足付】
足をつけた盆。あしつき。醒睡笑「芋を―の上へおとし」
あじ‐つけ【味付け】アヂ‥
味をつけること。また、その具合。「塩で―する」
⇒あじつけ‐のり【味付海苔】
⇒あじつけ‐めし【味付飯】
あじつけ‐のり【味付海苔】アヂ‥
乾海苔ほしのりの一種。調味液を付けあぶって乾燥させたもの。
⇒あじ‐つけ【味付け】
あじつけ‐めし【味付飯】アヂ‥
味つけをした飯。茶飯ちゃめし・ごもくめしなどの類。
⇒あじ‐つけ【味付け】
あし‐づつ【葦筒】
葦の茎の内側にあるあま皮。
⇒あしづつ‐の【葦筒の】
あしづつ‐の【葦筒の】
〔枕〕
「ひとへ(一重)」「薄し」にかかる。
⇒あし‐づつ【葦筒】
あし‐づの【葦角】
葦の新芽。葦の角。あしかび。古今和歌集六帖6「―の生ひ出し時に」
あし‐て【足手】
足と手。てあし。また、身体。
⇒あして‐かぎり【足手限り】
⇒あして‐かげ【足手影】
⇒あして‐がらみ【足手搦み】
⇒あして‐そくさい【足手息災】
⇒あして‐まとい【足手纏い】
あし‐で【悪手】
下手な書。悪筆。
あし‐で【葦手】
①平安時代に行われた文字の戯書ざれがき。水辺に葦などの生えた風景に草・岩・松・水鳥などの形を仮名・漢字で絵画化して書いたもの。水手みずで。あしでがき。
葦手
⇒あしだ【芦田】
あし‐だま【足玉】
足首の飾りにつけた玉。万葉集10「―も手玉ただまもゆらに織るはたを」
あし‐だまり【足溜り】
①しばらく足をとどめる所。転じて、ある行動のための根拠地。
②足をかけるところ。あしがかり。
あしたれ‐ぼし【足垂星】
二十八宿の一つ。蠍座さそりざの南東部。尾宿。尾び。
あ‐ジチオンさん‐ナトリウム【亜ジチオン酸ナトリウム】
(sodium dithionite)化学式Na2S2O4 無色の結晶。強力な還元剤。染料合成原料・染色助剤・漂白剤などに用いる。ハイドロサルファイト・ヒドロ亜硫酸ナトリウムは誤称。
あし‐ついで【足序で】
歩きついで。出かけたついで。
あし‐つ‐お【足つ緒】‥ヲ
①琴の弦の端を結びかがった糸。
②太い綱。差縄。
あし‐づかい【足遣い】‥ヅカヒ
①足のつかいかた。あしどり。あしつき。
②人形浄瑠璃の三人遣いで、両足の操作を担当する人。
あし‐つき【足付】
①歩く時の足の様子。歩きかた。あしどり。「よろよろした―」
②器に足をつけたもの。
③足付折敷の略。
⇒あしつき‐おしき【足付折敷】
あし‐つき【葦付】
淡水に生えるジュズモなどの藍藻類。葦または石に付着。食用。あしつきのり。万葉集17「―採ると瀬に立たすらし」
あし‐つぎ【足継ぎ】
高くて手のとどかない場合に用いる台。ふみだい。ふみつぎ。
あしつき‐おしき【足付折敷】‥ヲ‥
板製の足が底の左右についた折敷。普通は白木を用いる。あしうちおしき。あしうち。木具きぐ。
⇒あし‐つき【足付】
あし‐つけ【足付】
足をつけた盆。あしつき。醒睡笑「芋を―の上へおとし」
あじ‐つけ【味付け】アヂ‥
味をつけること。また、その具合。「塩で―する」
⇒あじつけ‐のり【味付海苔】
⇒あじつけ‐めし【味付飯】
あじつけ‐のり【味付海苔】アヂ‥
乾海苔ほしのりの一種。調味液を付けあぶって乾燥させたもの。
⇒あじ‐つけ【味付け】
あじつけ‐めし【味付飯】アヂ‥
味つけをした飯。茶飯ちゃめし・ごもくめしなどの類。
⇒あじ‐つけ【味付け】
あし‐づつ【葦筒】
葦の茎の内側にあるあま皮。
⇒あしづつ‐の【葦筒の】
あしづつ‐の【葦筒の】
〔枕〕
「ひとへ(一重)」「薄し」にかかる。
⇒あし‐づつ【葦筒】
あし‐づの【葦角】
葦の新芽。葦の角。あしかび。古今和歌集六帖6「―の生ひ出し時に」
あし‐て【足手】
足と手。てあし。また、身体。
⇒あして‐かぎり【足手限り】
⇒あして‐かげ【足手影】
⇒あして‐がらみ【足手搦み】
⇒あして‐そくさい【足手息災】
⇒あして‐まとい【足手纏い】
あし‐で【悪手】
下手な書。悪筆。
あし‐で【葦手】
①平安時代に行われた文字の戯書ざれがき。水辺に葦などの生えた風景に草・岩・松・水鳥などの形を仮名・漢字で絵画化して書いたもの。水手みずで。あしでがき。
葦手
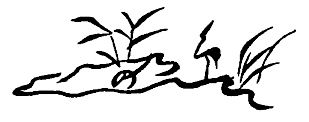 ②散らし書き。
⇒あしで‐え【葦手絵】
⇒あしで‐がき【葦手書】
⇒あしで‐がた【葦手形】
⇒あしで‐の‐けん【葦手の剣】
⇒あしで‐もじ【葦手文字】
あしで‐え【葦手絵】‥ヱ
葦手1を取り入れた絵画。歌絵うたえの一種となる場合もあるが、多くは料紙の下絵や蒔絵の文様として装飾的に用いられた。
⇒あし‐で【葦手】
アジテーション【agitation】
煽動せんどう。アジ。
アジテーター【agitator】
煽動者。
あしで‐がき【葦手書】
葦手に書くこと。また、書いたもの。あしで。
⇒あし‐で【葦手】
あして‐かぎり【足手限り】
足と手との力の続く限り。
⇒あし‐て【足手】
あして‐かげ【足手影】
①すがた。おもかげ。謡曲、隅田川「都の人の―もなつかしう候へば」
②人の往来のはげしい所。西鶴織留3「諸国の城下、又は入舟の湊などは、人の―にて」
⇒あし‐て【足手】
②散らし書き。
⇒あしで‐え【葦手絵】
⇒あしで‐がき【葦手書】
⇒あしで‐がた【葦手形】
⇒あしで‐の‐けん【葦手の剣】
⇒あしで‐もじ【葦手文字】
あしで‐え【葦手絵】‥ヱ
葦手1を取り入れた絵画。歌絵うたえの一種となる場合もあるが、多くは料紙の下絵や蒔絵の文様として装飾的に用いられた。
⇒あし‐で【葦手】
アジテーション【agitation】
煽動せんどう。アジ。
アジテーター【agitator】
煽動者。
あしで‐がき【葦手書】
葦手に書くこと。また、書いたもの。あしで。
⇒あし‐で【葦手】
あして‐かぎり【足手限り】
足と手との力の続く限り。
⇒あし‐て【足手】
あして‐かげ【足手影】
①すがた。おもかげ。謡曲、隅田川「都の人の―もなつかしう候へば」
②人の往来のはげしい所。西鶴織留3「諸国の城下、又は入舟の湊などは、人の―にて」
⇒あし‐て【足手】
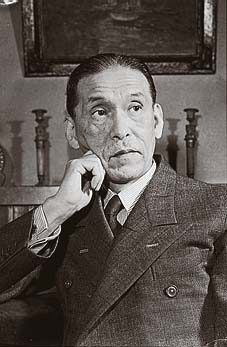 ⇒あしだ【芦田】
あし‐だま【足玉】
足首の飾りにつけた玉。万葉集10「―も手玉ただまもゆらに織るはたを」
あし‐だまり【足溜り】
①しばらく足をとどめる所。転じて、ある行動のための根拠地。
②足をかけるところ。あしがかり。
あしたれ‐ぼし【足垂星】
二十八宿の一つ。蠍座さそりざの南東部。尾宿。尾び。
あ‐ジチオンさん‐ナトリウム【亜ジチオン酸ナトリウム】
(sodium dithionite)化学式Na2S2O4 無色の結晶。強力な還元剤。染料合成原料・染色助剤・漂白剤などに用いる。ハイドロサルファイト・ヒドロ亜硫酸ナトリウムは誤称。
あし‐ついで【足序で】
歩きついで。出かけたついで。
あし‐つ‐お【足つ緒】‥ヲ
①琴の弦の端を結びかがった糸。
②太い綱。差縄。
あし‐づかい【足遣い】‥ヅカヒ
①足のつかいかた。あしどり。あしつき。
②人形浄瑠璃の三人遣いで、両足の操作を担当する人。
あし‐つき【足付】
①歩く時の足の様子。歩きかた。あしどり。「よろよろした―」
②器に足をつけたもの。
③足付折敷の略。
⇒あしつき‐おしき【足付折敷】
あし‐つき【葦付】
淡水に生えるジュズモなどの藍藻類。葦または石に付着。食用。あしつきのり。万葉集17「―採ると瀬に立たすらし」
あし‐つぎ【足継ぎ】
高くて手のとどかない場合に用いる台。ふみだい。ふみつぎ。
あしつき‐おしき【足付折敷】‥ヲ‥
板製の足が底の左右についた折敷。普通は白木を用いる。あしうちおしき。あしうち。木具きぐ。
⇒あし‐つき【足付】
あし‐つけ【足付】
足をつけた盆。あしつき。醒睡笑「芋を―の上へおとし」
あじ‐つけ【味付け】アヂ‥
味をつけること。また、その具合。「塩で―する」
⇒あじつけ‐のり【味付海苔】
⇒あじつけ‐めし【味付飯】
あじつけ‐のり【味付海苔】アヂ‥
乾海苔ほしのりの一種。調味液を付けあぶって乾燥させたもの。
⇒あじ‐つけ【味付け】
あじつけ‐めし【味付飯】アヂ‥
味つけをした飯。茶飯ちゃめし・ごもくめしなどの類。
⇒あじ‐つけ【味付け】
あし‐づつ【葦筒】
葦の茎の内側にあるあま皮。
⇒あしづつ‐の【葦筒の】
あしづつ‐の【葦筒の】
〔枕〕
「ひとへ(一重)」「薄し」にかかる。
⇒あし‐づつ【葦筒】
あし‐づの【葦角】
葦の新芽。葦の角。あしかび。古今和歌集六帖6「―の生ひ出し時に」
あし‐て【足手】
足と手。てあし。また、身体。
⇒あして‐かぎり【足手限り】
⇒あして‐かげ【足手影】
⇒あして‐がらみ【足手搦み】
⇒あして‐そくさい【足手息災】
⇒あして‐まとい【足手纏い】
あし‐で【悪手】
下手な書。悪筆。
あし‐で【葦手】
①平安時代に行われた文字の戯書ざれがき。水辺に葦などの生えた風景に草・岩・松・水鳥などの形を仮名・漢字で絵画化して書いたもの。水手みずで。あしでがき。
葦手
⇒あしだ【芦田】
あし‐だま【足玉】
足首の飾りにつけた玉。万葉集10「―も手玉ただまもゆらに織るはたを」
あし‐だまり【足溜り】
①しばらく足をとどめる所。転じて、ある行動のための根拠地。
②足をかけるところ。あしがかり。
あしたれ‐ぼし【足垂星】
二十八宿の一つ。蠍座さそりざの南東部。尾宿。尾び。
あ‐ジチオンさん‐ナトリウム【亜ジチオン酸ナトリウム】
(sodium dithionite)化学式Na2S2O4 無色の結晶。強力な還元剤。染料合成原料・染色助剤・漂白剤などに用いる。ハイドロサルファイト・ヒドロ亜硫酸ナトリウムは誤称。
あし‐ついで【足序で】
歩きついで。出かけたついで。
あし‐つ‐お【足つ緒】‥ヲ
①琴の弦の端を結びかがった糸。
②太い綱。差縄。
あし‐づかい【足遣い】‥ヅカヒ
①足のつかいかた。あしどり。あしつき。
②人形浄瑠璃の三人遣いで、両足の操作を担当する人。
あし‐つき【足付】
①歩く時の足の様子。歩きかた。あしどり。「よろよろした―」
②器に足をつけたもの。
③足付折敷の略。
⇒あしつき‐おしき【足付折敷】
あし‐つき【葦付】
淡水に生えるジュズモなどの藍藻類。葦または石に付着。食用。あしつきのり。万葉集17「―採ると瀬に立たすらし」
あし‐つぎ【足継ぎ】
高くて手のとどかない場合に用いる台。ふみだい。ふみつぎ。
あしつき‐おしき【足付折敷】‥ヲ‥
板製の足が底の左右についた折敷。普通は白木を用いる。あしうちおしき。あしうち。木具きぐ。
⇒あし‐つき【足付】
あし‐つけ【足付】
足をつけた盆。あしつき。醒睡笑「芋を―の上へおとし」
あじ‐つけ【味付け】アヂ‥
味をつけること。また、その具合。「塩で―する」
⇒あじつけ‐のり【味付海苔】
⇒あじつけ‐めし【味付飯】
あじつけ‐のり【味付海苔】アヂ‥
乾海苔ほしのりの一種。調味液を付けあぶって乾燥させたもの。
⇒あじ‐つけ【味付け】
あじつけ‐めし【味付飯】アヂ‥
味つけをした飯。茶飯ちゃめし・ごもくめしなどの類。
⇒あじ‐つけ【味付け】
あし‐づつ【葦筒】
葦の茎の内側にあるあま皮。
⇒あしづつ‐の【葦筒の】
あしづつ‐の【葦筒の】
〔枕〕
「ひとへ(一重)」「薄し」にかかる。
⇒あし‐づつ【葦筒】
あし‐づの【葦角】
葦の新芽。葦の角。あしかび。古今和歌集六帖6「―の生ひ出し時に」
あし‐て【足手】
足と手。てあし。また、身体。
⇒あして‐かぎり【足手限り】
⇒あして‐かげ【足手影】
⇒あして‐がらみ【足手搦み】
⇒あして‐そくさい【足手息災】
⇒あして‐まとい【足手纏い】
あし‐で【悪手】
下手な書。悪筆。
あし‐で【葦手】
①平安時代に行われた文字の戯書ざれがき。水辺に葦などの生えた風景に草・岩・松・水鳥などの形を仮名・漢字で絵画化して書いたもの。水手みずで。あしでがき。
葦手
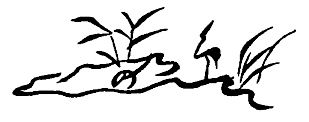 ②散らし書き。
⇒あしで‐え【葦手絵】
⇒あしで‐がき【葦手書】
⇒あしで‐がた【葦手形】
⇒あしで‐の‐けん【葦手の剣】
⇒あしで‐もじ【葦手文字】
あしで‐え【葦手絵】‥ヱ
葦手1を取り入れた絵画。歌絵うたえの一種となる場合もあるが、多くは料紙の下絵や蒔絵の文様として装飾的に用いられた。
⇒あし‐で【葦手】
アジテーション【agitation】
煽動せんどう。アジ。
アジテーター【agitator】
煽動者。
あしで‐がき【葦手書】
葦手に書くこと。また、書いたもの。あしで。
⇒あし‐で【葦手】
あして‐かぎり【足手限り】
足と手との力の続く限り。
⇒あし‐て【足手】
あして‐かげ【足手影】
①すがた。おもかげ。謡曲、隅田川「都の人の―もなつかしう候へば」
②人の往来のはげしい所。西鶴織留3「諸国の城下、又は入舟の湊などは、人の―にて」
⇒あし‐て【足手】
②散らし書き。
⇒あしで‐え【葦手絵】
⇒あしで‐がき【葦手書】
⇒あしで‐がた【葦手形】
⇒あしで‐の‐けん【葦手の剣】
⇒あしで‐もじ【葦手文字】
あしで‐え【葦手絵】‥ヱ
葦手1を取り入れた絵画。歌絵うたえの一種となる場合もあるが、多くは料紙の下絵や蒔絵の文様として装飾的に用いられた。
⇒あし‐で【葦手】
アジテーション【agitation】
煽動せんどう。アジ。
アジテーター【agitator】
煽動者。
あしで‐がき【葦手書】
葦手に書くこと。また、書いたもの。あしで。
⇒あし‐で【葦手】
あして‐かぎり【足手限り】
足と手との力の続く限り。
⇒あし‐て【足手】
あして‐かげ【足手影】
①すがた。おもかげ。謡曲、隅田川「都の人の―もなつかしう候へば」
②人の往来のはげしい所。西鶴織留3「諸国の城下、又は入舟の湊などは、人の―にて」
⇒あし‐て【足手】
広辞苑 ページ 329 での【○明日は明日の風が吹く】単語。