複数辞典一括検索+![]()
![]()
○空足を踏むからあしをふむ🔗⭐🔉
○空足を踏むからあしをふむ
階段の上り下りなどで、高さを誤って足が空くうを踏むこと。
⇒から‐あし【空足】
カラー‐スキャナー【colo(u)r scanner】
カラー原稿を走査して色分解し、電気信号として出力する装置。
⇒カラー【colo(u)r】
カラー‐チャート【colo(u)r chart】
色見本帳。色見本を系統的に配列した表。特に、写真・印刷・テレビなどで色の再現性を調べるために用いるもの。
⇒カラー【colo(u)r】
カラー‐テレビ
(colo(u)r television)色彩をもつ画面を送るテレビジョン。また、その受信装置。
⇒カラー【colo(u)r】
カラード【colo(u)red】
有色人種。特に、南アフリカで有色人種と白色人種との混血の人を指す。
カラー‐ネガ‐フィルム【colo(u)r negative film】
被写体の明暗が逆で、色彩が補色の画像を作るカラー‐フィルム。これをカラー印画紙に焼き付けて、正しい色のカラー‐プリントを作る。
⇒カラー【colo(u)r】
カラー‐フィルム【colo(u)r film】
①カラー写真用のフィルム。1枚のフィルム上に、青・緑・赤の光に感じ、それぞれ黄・マゼンタ・シアンに発色する3種の写真乳剤を塗布したもの。カラー‐ネガ‐フィルムとカラー‐リバーサル‐フィルムに大別。
②カラー映画。
⇒カラー【colo(u)r】
カラー‐プリント【colo(u)r print】
カラー写真印画。普通には、カラー‐ネガ‐フィルムをカラー印画紙に焼き付け、現像処理して得られる。
⇒カラー【colo(u)r】
カラー‐ボール
(和製語colo(u)r ball)防犯用品の一つ。逃げる犯人に投げつけて中の塗料を付着させ、追跡の目印とするボール。
⇒カラー【colo(u)r】
カラー‐マッチング【colo(u)r matching】
(印刷用語)コンピューター製版で、色合せ。
⇒カラー【colo(u)r】
カラー‐マネージメント【colo(u)r management】
どの機器を使っても同じ色が再現されるように色を管理すること。CMS
⇒カラー【colo(u)r】
から‐あや【唐綾】
唐織の綾。中国から伝わった浮織の綾。綸子りんずの類。源氏物語若菜下「―の表うえの袴」
⇒からあや‐おどし【唐綾縅】
からあや‐おどし【唐綾縅】‥ヲドシ
鎧よろいの縅の一種。唐綾を細く裁ち、内に麻を入れて畳んでおどしたもの。白・黒・紺・朽葉色など種々ある。
⇒から‐あや【唐綾】
カラー‐リバーサル‐フィルム【colo(u)r reversal film】
反転現像処理により、直接透明陽画を作る写真用カラー‐フィルム。スライド用・印刷用原稿に適する。
⇒カラー【colo(u)r】
がら‐あわせ【柄合せ】‥アハセ
衣服を仕立てるとき、前後左右の柄がうまく合うように裁ち合わせること。
からい【柄井】‥ヰ
姓氏の一つ。
⇒からい‐せんりゅう【柄井川柳】
から‐い【涸井】‥ヰ
水の涸かれた井戸。
か‐らい【渦雷】クワ‥
台風や低気圧の中心部で、渦に伴う上昇気流によって生じる雷。
から・い【辛い】
〔形〕[文]から・し(ク)
①激しく舌を刺激するような味である。
㋐唐がらし・わさび・しょうがなどの味にいう。ひりひりする。古今和歌集六帖6「みな月の河原に生ふる八穂蓼の―・しや人に逢はぬ心は」
㋑(「鹹い」と書く)塩味が強い。しおからい。しょっぱい。万葉集17「焼く塩の―・き恋をも吾はするかも」
㋒酸味が強い。すっぱい。〈新撰字鏡4〉
㋓こくがあって甘味の少ない酒の味にいう。〈新撰字鏡4〉
②心身に強い刺激を与える状態、または心身に強く感ずるさまである。
㋐やり方や仕打ちがきびしくひどい。過酷である。容赦がない。武烈紀「酷刑からきのり」。源氏物語空蝉「さて今宵もやかへしてむとする。いとあさましう―・うこそあべけれ」。「点が―・い」「自分に―・い」
㋑つらい。せつない。苦しい。悲痛である。万葉集15「昔よりいひけることの唐国の―・くもここにわかれするかも」。日葡辞書「カライメニワウ」。「―・い目をみる」
㋒いやだ。気に染まない。堤中納言物語「―・くや。眉はしもかはむしだちためり」
㋓あやうい。あぶない。平家物語4「わが身手負ひ、―・き命をいきつつ本宮へこそ逃げのぼりけれ」。「―・くも難を逃れた」
㋔(連用形を副詞的に使って)必死に。懸命に。土佐日記「男女―・く神仏をいのりて、この水門を渡りぬ」
㋕(連用形を副詞的に使って)大変ひどく。大鏡道長「けしうはあらぬ歌よみなれど、―・う劣りにしことぞかし」
から‐いけ【空生け・空活け】
生花の一技法。水を用いずに若松などを生ける法。
から‐いしき【唐居敷】‥ヰ‥
門柱の下に敷き、門扉の軸受とする石または木の厚板。古事談2「門の―に立たしめ」
からい‐せんりゅう【柄井川柳】‥ヰ‥リウ
江戸中期の前句付まえくづけ点者。江戸浅草の人。1757年(宝暦7)「川柳評万句合」を発行、他の点者を圧倒する名声を得た。その撰句を川柳点、のちには単に川柳と称した。(1718〜1790)→川柳
⇒からい【柄井】
から‐いた【空板】
講釈師の前座が、客寄せのために見台を張扇でむやみに叩くこと。
から‐いと【唐糸】
①中国から渡来した糸。
②唐糸織の略。
③(糸を引くからいう)納豆なっとう。
⇒からいと‐おり【唐糸織】
⇒からいと‐そう【唐糸草】
から‐いと【可良糸】
よりをかけた糸。よりいと。
⇒からいと‐おり【可良糸織】
からいと‐おり【唐糸織】
唐糸で織った織物。
⇒から‐いと【唐糸】
からいと‐おり【可良糸織】
甲府付近から製出する糸織。下等な繭まゆから手取りにした諸撚糸もろよりいとを用いて地厚・重めのものとしたもの。
⇒から‐いと【可良糸】
からいと‐そう【唐糸草】‥サウ
バラ科の多年草。本州中部の高山草地に生える。地下の根茎は太く、横に走る。根生葉は5〜6対の小葉を持つ羽状複葉で長柄がある。夏に茎頂に大きな花穂を出し、紅紫色の雄しべが目立つ小花を密集する。花穂は先端部の花から順次開花する。
⇒から‐いと【唐糸】
から‐いぬ【唐犬】
中国産の犬。また、外国産の犬。こまいぬ。
から‐いばり【空威張り】‥ヰ‥
実力がないのに、表面ばかりえらそうに、また強そうにすること。虚勢を張ること。「酔うと―する」
から‐いも【唐薯】
①(もと中国から渡来したからいう)「さつまいも」の別称。
②「きくいも」の別称。
から‐いり【乾煎り】
食物を水を加えずに煎ること。また、そうした食物。
から‐いり【殻煎り】
豆腐のからを煎って味をつけたもの。卯の花いり。
から・う
〔他五〕
(熊本県ほかで)背負う。
カラヴァッジオ【Michelangelo Merisi da Caravaggio】
イタリアの画家。宗教画に写実性とコントラストの強い明暗法を導入、バロック美術に大きな影響を与えた。作「聖マタイの召命」「キリストの埋葬」など。(1573〜1610)
カラヴァッジオ
提供:Photos12/APL
 から‐うす【唐臼・碓】
臼を地に埋め、横木にのせた杵きねの一端をふみ、放すと他の端が落ちて臼の中の穀類などをつく装置。ふみうす。万葉集16「―に舂つき」→添水そうず。
唐臼
から‐うす【唐臼・碓】
臼を地に埋め、横木にのせた杵きねの一端をふみ、放すと他の端が落ちて臼の中の穀類などをつく装置。ふみうす。万葉集16「―に舂つき」→添水そうず。
唐臼
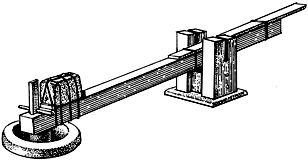 ⇒からうす‐びょうし【唐臼拍子】
から‐うず【唐櫃】‥ウヅ
カラビツの音便。
からうす‐びょうし【唐臼拍子】‥ビヤウ‥
両方同時にはうまく運ばないことのたとえ。
⇒から‐うす【唐臼・碓】
から‐うそ【空嘘】
全くのうそ。あかうそ。
から‐うた【唐歌】
漢詩。土佐日記「―声あげていひけり」↔大和歌やまとうた
から‐うち【唐打】
糸をあやに組むこと。また、その糸。
から‐うど【唐櫃】
⇒かろうど
から‐うま【空馬】
人や荷物をのせていない馬。
⇒空馬に怪我なし
から‐うま【唐馬】
中国産の馬。また、外国産の馬。
⇒からうす‐びょうし【唐臼拍子】
から‐うず【唐櫃】‥ウヅ
カラビツの音便。
からうす‐びょうし【唐臼拍子】‥ビヤウ‥
両方同時にはうまく運ばないことのたとえ。
⇒から‐うす【唐臼・碓】
から‐うそ【空嘘】
全くのうそ。あかうそ。
から‐うた【唐歌】
漢詩。土佐日記「―声あげていひけり」↔大和歌やまとうた
から‐うち【唐打】
糸をあやに組むこと。また、その糸。
から‐うど【唐櫃】
⇒かろうど
から‐うま【空馬】
人や荷物をのせていない馬。
⇒空馬に怪我なし
から‐うま【唐馬】
中国産の馬。また、外国産の馬。
 から‐うす【唐臼・碓】
臼を地に埋め、横木にのせた杵きねの一端をふみ、放すと他の端が落ちて臼の中の穀類などをつく装置。ふみうす。万葉集16「―に舂つき」→添水そうず。
唐臼
から‐うす【唐臼・碓】
臼を地に埋め、横木にのせた杵きねの一端をふみ、放すと他の端が落ちて臼の中の穀類などをつく装置。ふみうす。万葉集16「―に舂つき」→添水そうず。
唐臼
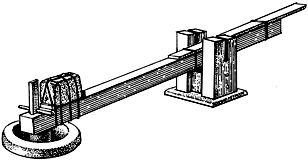 ⇒からうす‐びょうし【唐臼拍子】
から‐うず【唐櫃】‥ウヅ
カラビツの音便。
からうす‐びょうし【唐臼拍子】‥ビヤウ‥
両方同時にはうまく運ばないことのたとえ。
⇒から‐うす【唐臼・碓】
から‐うそ【空嘘】
全くのうそ。あかうそ。
から‐うた【唐歌】
漢詩。土佐日記「―声あげていひけり」↔大和歌やまとうた
から‐うち【唐打】
糸をあやに組むこと。また、その糸。
から‐うど【唐櫃】
⇒かろうど
から‐うま【空馬】
人や荷物をのせていない馬。
⇒空馬に怪我なし
から‐うま【唐馬】
中国産の馬。また、外国産の馬。
⇒からうす‐びょうし【唐臼拍子】
から‐うず【唐櫃】‥ウヅ
カラビツの音便。
からうす‐びょうし【唐臼拍子】‥ビヤウ‥
両方同時にはうまく運ばないことのたとえ。
⇒から‐うす【唐臼・碓】
から‐うそ【空嘘】
全くのうそ。あかうそ。
から‐うた【唐歌】
漢詩。土佐日記「―声あげていひけり」↔大和歌やまとうた
から‐うち【唐打】
糸をあやに組むこと。また、その糸。
から‐うど【唐櫃】
⇒かろうど
から‐うま【空馬】
人や荷物をのせていない馬。
⇒空馬に怪我なし
から‐うま【唐馬】
中国産の馬。また、外国産の馬。
広辞苑 ページ 4181 での【○空足を踏む】単語。