複数辞典一括検索+![]()
![]()
○苦は楽の種くはらくのたね🔗⭐🔉
○苦は楽の種くはらくのたね
現在の苦労は後日の幸福のもととなる。「楽は苦の種―」
⇒く【苦】
くはら‐ふさのすけ【久原房之助】
政治家・実業家。萩生れ。慶応義塾卒。久原鉱業を創立し日立製作所の基礎を築く。政友会に入り、逓相。二‐二六事件に連座、のち政友会総裁。(1869〜1965)
久原房之助
撮影:田沼武能
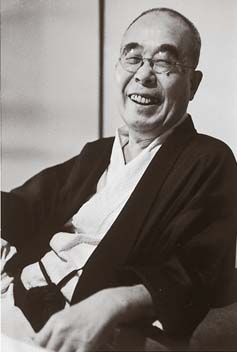 ⇒くはら【久原】
くばり【配り・賦り】
①くばること。くばった位置。「字―」「心―」
②生花で、木の叉またなどを筒の中に入れて花を支えること。また、その木の叉など。
⇒くばり‐だて【配り立て】
⇒くばり‐なっとう【配り納豆】
⇒くばり‐ばんづけ【配り番付】
⇒くばり‐ふだ【配り札】
⇒くばり‐へい【配り幣】
⇒くばり‐もの【配り物】
⇒くばりわけ‐ぶぎょう【賦別奉行】
くばり‐だて【配り立て】
方々に人手を分けて備えをすること。てくばり。
⇒くばり【配り・賦り】
くばり‐ちら・す【配り散らす】
〔他五〕
誰彼となくやたらにくばる。方々へくばる。
くばり‐なっとう【配り納豆】
年末または年始に、寺から檀家へくばる寺納豆。
⇒くばり【配り・賦り】
くばり‐ばんづけ【配り番付】
(ひいき先にも配ったからいう)芝居番付の一つ。狂言の外題・役割・料金などを一枚刷にして辻々に貼り出す番付。札番付。櫓下やぐらした番付。配り札。
⇒くばり【配り・賦り】
くばり‐ふだ【配り札】
①劇場からひいき筋に贈る招待券。
②(→)「配り番付」に同じ。
⇒くばり【配り・賦り】
くばり‐へい【配り幣】
諸神に奉るべき幣帛へいはくを一つに束ね、両段再拝の後、束を解いて各座の神に配り供えること。
⇒くばり【配り・賦り】
くばり‐もの【配り物】
祝儀・挨拶・謝礼として人々に分け贈る物。
⇒くばり【配り・賦り】
くばりわけ‐ぶぎょう【賦別奉行】‥ギヤウ
鎌倉・室町幕府の職名。訴状を受け取って、年月日および氏名を記し、引付方各番へくばり分ける職。問注所役人の勤務。賦奉行ふぶぎょう。
⇒くばり【配り・賦り】
くば・る【配る・賦る】
〔他五〕
①物を割り当てて渡す。分配する。源氏物語葵「誠にかの御形見なるべき物など…、皆―・らせ給ひけり」。「新聞を―・る」
②注意や心遣いを行きわたらせる。宇津保物語梅花笠「あまたに―・りし心を、只一所になりたりかし」。「目を―・る」「気を―・る」
③結婚させる。縁づける。源氏物語東屋「はじめの腹の二三人は、皆さまざまに―・りておとなびさせたり」
④それぞれ適当な所におく。配置する。「短冊に字を―・る」「要所要所に人を―・る」
⑤(隠語)非常警戒線を張る。
くば・る【焼る】
〔自四〕
火の中にはいって燃える。浄瑠璃、女殺油地獄「火に―・らうが、うぬが三昧」
ぐはん‐しょうねん【虞犯少年】‥セウ‥
一定の事由があって、その性格・環境に照らし、将来、罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をする虞おそれのある少年。少年法により家庭裁判所の審判に付される。
くばんだ【鳩槃荼】
(梵語Kumbhāṇḍa)人の精気を吸い、動作速く、さまざまに変化する悪神。鳩槃荼夜叉神。
く‐ひ【句碑】
俳句を彫りつけた石碑。「芭蕉の―」
くび【首・頸】
①脊椎動物の頭と胴とをつなぐ部分。頸部。万葉集4「わが恋は千引の石を七ばかり―にかけむも神の諸伏もろふし」
②衣服の、くびに当たる部分。
③物の、くびの形をした部分。「手―」「徳利の―」
㋐琴きんの狭くくびれている2部分のうち、本の方の部分。末の方は腰という。
㋑琵琶の胴の上部の細くなった部分。鹿頸ししくび。俗に棹さおという。
㋒薩摩琵琶の撥ばちのくびれている所。
④身体のくびより上の部分。かしら。あたま。こうべ。「―をはねる」
⑤解雇すること。馘首かくしゅ。「会社を―になった」
⑥顔。容貌。
⇒首が繋がる
⇒首が飛ぶ
⇒首が回らない
⇒首になる
⇒首に縄を付ける
⇒首の皮一枚
⇒首の座へ直る
⇒首振り三年
⇒首を洗って待つ
⇒首を傾げる
⇒首を切る
⇒首をすくめる
⇒首を挿げ替える
⇒首を縦に振る
⇒首を突っ込む
⇒首を長くする
⇒首を捻る
⇒首を横に振る
くび【鵠】
(→)「くぐい」に同じ。古事記中「さ渡る―」
ぐ‐ひ【具否】
備わっているかいないか。ぐふ。
ぐ‐び【具備】
必要なものが十分に備わっていること。「条件を―した書類」
くび‐いた【首板】
軍陣で、敵の首をのせる板。
くび‐うま【首馬・頸馬】
①鞍くらの前輪まえわに乗ること。
②肩車かたぐるま。首子乗り。
くび‐おおい【頸被い】‥オホヒ
牛馬の頸をおおう布。〈倭名類聚鈔11〉
くび‐おけ【首桶】‥ヲケ
討ちとった首を入れる桶。首入れ。
くび‐がけ【首賭け】
首を賭けて誓うこと。また、首を賭けて勝負すること。浄瑠璃、傾城反魂香「あつちへ遣るかこつちへ取るか―の博奕」
くびかけ‐しばい【頸掛芝居】‥ヰ
人形を入れた箱を頸にかけ、その上で人形を操り、大道で見せたもの。くぐつまわし。山猫まわし。箱芝居。→傀儡師かいらいし(図)
くび‐かざり【首飾り・頸飾り】
首にかける装飾品。宝石・貴金属類などをつないで輪にしたもの。ネックレス。「真珠の―」
くび‐かし【首枷・頸枷】
(→)「くびかせ」1に同じ。孝徳紀「枷くびかしを着はけ反縛しりえでにしばれり」
くび‐かせ【首枷・頸枷】
①罪人の首にはめ、自由に動けないようにする鉄または木製の刑具。太平記2「―・手枷を入れられ」
②自由を束縛するもの。係累。きずな。謡曲、天鼓「親子は三界の―と」
くび‐がってん【首合点】
首を上下にふって承諾の意を表すこと。
⇒くはら【久原】
くばり【配り・賦り】
①くばること。くばった位置。「字―」「心―」
②生花で、木の叉またなどを筒の中に入れて花を支えること。また、その木の叉など。
⇒くばり‐だて【配り立て】
⇒くばり‐なっとう【配り納豆】
⇒くばり‐ばんづけ【配り番付】
⇒くばり‐ふだ【配り札】
⇒くばり‐へい【配り幣】
⇒くばり‐もの【配り物】
⇒くばりわけ‐ぶぎょう【賦別奉行】
くばり‐だて【配り立て】
方々に人手を分けて備えをすること。てくばり。
⇒くばり【配り・賦り】
くばり‐ちら・す【配り散らす】
〔他五〕
誰彼となくやたらにくばる。方々へくばる。
くばり‐なっとう【配り納豆】
年末または年始に、寺から檀家へくばる寺納豆。
⇒くばり【配り・賦り】
くばり‐ばんづけ【配り番付】
(ひいき先にも配ったからいう)芝居番付の一つ。狂言の外題・役割・料金などを一枚刷にして辻々に貼り出す番付。札番付。櫓下やぐらした番付。配り札。
⇒くばり【配り・賦り】
くばり‐ふだ【配り札】
①劇場からひいき筋に贈る招待券。
②(→)「配り番付」に同じ。
⇒くばり【配り・賦り】
くばり‐へい【配り幣】
諸神に奉るべき幣帛へいはくを一つに束ね、両段再拝の後、束を解いて各座の神に配り供えること。
⇒くばり【配り・賦り】
くばり‐もの【配り物】
祝儀・挨拶・謝礼として人々に分け贈る物。
⇒くばり【配り・賦り】
くばりわけ‐ぶぎょう【賦別奉行】‥ギヤウ
鎌倉・室町幕府の職名。訴状を受け取って、年月日および氏名を記し、引付方各番へくばり分ける職。問注所役人の勤務。賦奉行ふぶぎょう。
⇒くばり【配り・賦り】
くば・る【配る・賦る】
〔他五〕
①物を割り当てて渡す。分配する。源氏物語葵「誠にかの御形見なるべき物など…、皆―・らせ給ひけり」。「新聞を―・る」
②注意や心遣いを行きわたらせる。宇津保物語梅花笠「あまたに―・りし心を、只一所になりたりかし」。「目を―・る」「気を―・る」
③結婚させる。縁づける。源氏物語東屋「はじめの腹の二三人は、皆さまざまに―・りておとなびさせたり」
④それぞれ適当な所におく。配置する。「短冊に字を―・る」「要所要所に人を―・る」
⑤(隠語)非常警戒線を張る。
くば・る【焼る】
〔自四〕
火の中にはいって燃える。浄瑠璃、女殺油地獄「火に―・らうが、うぬが三昧」
ぐはん‐しょうねん【虞犯少年】‥セウ‥
一定の事由があって、その性格・環境に照らし、将来、罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をする虞おそれのある少年。少年法により家庭裁判所の審判に付される。
くばんだ【鳩槃荼】
(梵語Kumbhāṇḍa)人の精気を吸い、動作速く、さまざまに変化する悪神。鳩槃荼夜叉神。
く‐ひ【句碑】
俳句を彫りつけた石碑。「芭蕉の―」
くび【首・頸】
①脊椎動物の頭と胴とをつなぐ部分。頸部。万葉集4「わが恋は千引の石を七ばかり―にかけむも神の諸伏もろふし」
②衣服の、くびに当たる部分。
③物の、くびの形をした部分。「手―」「徳利の―」
㋐琴きんの狭くくびれている2部分のうち、本の方の部分。末の方は腰という。
㋑琵琶の胴の上部の細くなった部分。鹿頸ししくび。俗に棹さおという。
㋒薩摩琵琶の撥ばちのくびれている所。
④身体のくびより上の部分。かしら。あたま。こうべ。「―をはねる」
⑤解雇すること。馘首かくしゅ。「会社を―になった」
⑥顔。容貌。
⇒首が繋がる
⇒首が飛ぶ
⇒首が回らない
⇒首になる
⇒首に縄を付ける
⇒首の皮一枚
⇒首の座へ直る
⇒首振り三年
⇒首を洗って待つ
⇒首を傾げる
⇒首を切る
⇒首をすくめる
⇒首を挿げ替える
⇒首を縦に振る
⇒首を突っ込む
⇒首を長くする
⇒首を捻る
⇒首を横に振る
くび【鵠】
(→)「くぐい」に同じ。古事記中「さ渡る―」
ぐ‐ひ【具否】
備わっているかいないか。ぐふ。
ぐ‐び【具備】
必要なものが十分に備わっていること。「条件を―した書類」
くび‐いた【首板】
軍陣で、敵の首をのせる板。
くび‐うま【首馬・頸馬】
①鞍くらの前輪まえわに乗ること。
②肩車かたぐるま。首子乗り。
くび‐おおい【頸被い】‥オホヒ
牛馬の頸をおおう布。〈倭名類聚鈔11〉
くび‐おけ【首桶】‥ヲケ
討ちとった首を入れる桶。首入れ。
くび‐がけ【首賭け】
首を賭けて誓うこと。また、首を賭けて勝負すること。浄瑠璃、傾城反魂香「あつちへ遣るかこつちへ取るか―の博奕」
くびかけ‐しばい【頸掛芝居】‥ヰ
人形を入れた箱を頸にかけ、その上で人形を操り、大道で見せたもの。くぐつまわし。山猫まわし。箱芝居。→傀儡師かいらいし(図)
くび‐かざり【首飾り・頸飾り】
首にかける装飾品。宝石・貴金属類などをつないで輪にしたもの。ネックレス。「真珠の―」
くび‐かし【首枷・頸枷】
(→)「くびかせ」1に同じ。孝徳紀「枷くびかしを着はけ反縛しりえでにしばれり」
くび‐かせ【首枷・頸枷】
①罪人の首にはめ、自由に動けないようにする鉄または木製の刑具。太平記2「―・手枷を入れられ」
②自由を束縛するもの。係累。きずな。謡曲、天鼓「親子は三界の―と」
くび‐がってん【首合点】
首を上下にふって承諾の意を表すこと。
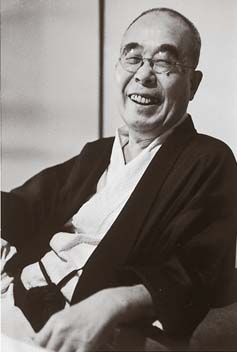 ⇒くはら【久原】
くばり【配り・賦り】
①くばること。くばった位置。「字―」「心―」
②生花で、木の叉またなどを筒の中に入れて花を支えること。また、その木の叉など。
⇒くばり‐だて【配り立て】
⇒くばり‐なっとう【配り納豆】
⇒くばり‐ばんづけ【配り番付】
⇒くばり‐ふだ【配り札】
⇒くばり‐へい【配り幣】
⇒くばり‐もの【配り物】
⇒くばりわけ‐ぶぎょう【賦別奉行】
くばり‐だて【配り立て】
方々に人手を分けて備えをすること。てくばり。
⇒くばり【配り・賦り】
くばり‐ちら・す【配り散らす】
〔他五〕
誰彼となくやたらにくばる。方々へくばる。
くばり‐なっとう【配り納豆】
年末または年始に、寺から檀家へくばる寺納豆。
⇒くばり【配り・賦り】
くばり‐ばんづけ【配り番付】
(ひいき先にも配ったからいう)芝居番付の一つ。狂言の外題・役割・料金などを一枚刷にして辻々に貼り出す番付。札番付。櫓下やぐらした番付。配り札。
⇒くばり【配り・賦り】
くばり‐ふだ【配り札】
①劇場からひいき筋に贈る招待券。
②(→)「配り番付」に同じ。
⇒くばり【配り・賦り】
くばり‐へい【配り幣】
諸神に奉るべき幣帛へいはくを一つに束ね、両段再拝の後、束を解いて各座の神に配り供えること。
⇒くばり【配り・賦り】
くばり‐もの【配り物】
祝儀・挨拶・謝礼として人々に分け贈る物。
⇒くばり【配り・賦り】
くばりわけ‐ぶぎょう【賦別奉行】‥ギヤウ
鎌倉・室町幕府の職名。訴状を受け取って、年月日および氏名を記し、引付方各番へくばり分ける職。問注所役人の勤務。賦奉行ふぶぎょう。
⇒くばり【配り・賦り】
くば・る【配る・賦る】
〔他五〕
①物を割り当てて渡す。分配する。源氏物語葵「誠にかの御形見なるべき物など…、皆―・らせ給ひけり」。「新聞を―・る」
②注意や心遣いを行きわたらせる。宇津保物語梅花笠「あまたに―・りし心を、只一所になりたりかし」。「目を―・る」「気を―・る」
③結婚させる。縁づける。源氏物語東屋「はじめの腹の二三人は、皆さまざまに―・りておとなびさせたり」
④それぞれ適当な所におく。配置する。「短冊に字を―・る」「要所要所に人を―・る」
⑤(隠語)非常警戒線を張る。
くば・る【焼る】
〔自四〕
火の中にはいって燃える。浄瑠璃、女殺油地獄「火に―・らうが、うぬが三昧」
ぐはん‐しょうねん【虞犯少年】‥セウ‥
一定の事由があって、その性格・環境に照らし、将来、罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をする虞おそれのある少年。少年法により家庭裁判所の審判に付される。
くばんだ【鳩槃荼】
(梵語Kumbhāṇḍa)人の精気を吸い、動作速く、さまざまに変化する悪神。鳩槃荼夜叉神。
く‐ひ【句碑】
俳句を彫りつけた石碑。「芭蕉の―」
くび【首・頸】
①脊椎動物の頭と胴とをつなぐ部分。頸部。万葉集4「わが恋は千引の石を七ばかり―にかけむも神の諸伏もろふし」
②衣服の、くびに当たる部分。
③物の、くびの形をした部分。「手―」「徳利の―」
㋐琴きんの狭くくびれている2部分のうち、本の方の部分。末の方は腰という。
㋑琵琶の胴の上部の細くなった部分。鹿頸ししくび。俗に棹さおという。
㋒薩摩琵琶の撥ばちのくびれている所。
④身体のくびより上の部分。かしら。あたま。こうべ。「―をはねる」
⑤解雇すること。馘首かくしゅ。「会社を―になった」
⑥顔。容貌。
⇒首が繋がる
⇒首が飛ぶ
⇒首が回らない
⇒首になる
⇒首に縄を付ける
⇒首の皮一枚
⇒首の座へ直る
⇒首振り三年
⇒首を洗って待つ
⇒首を傾げる
⇒首を切る
⇒首をすくめる
⇒首を挿げ替える
⇒首を縦に振る
⇒首を突っ込む
⇒首を長くする
⇒首を捻る
⇒首を横に振る
くび【鵠】
(→)「くぐい」に同じ。古事記中「さ渡る―」
ぐ‐ひ【具否】
備わっているかいないか。ぐふ。
ぐ‐び【具備】
必要なものが十分に備わっていること。「条件を―した書類」
くび‐いた【首板】
軍陣で、敵の首をのせる板。
くび‐うま【首馬・頸馬】
①鞍くらの前輪まえわに乗ること。
②肩車かたぐるま。首子乗り。
くび‐おおい【頸被い】‥オホヒ
牛馬の頸をおおう布。〈倭名類聚鈔11〉
くび‐おけ【首桶】‥ヲケ
討ちとった首を入れる桶。首入れ。
くび‐がけ【首賭け】
首を賭けて誓うこと。また、首を賭けて勝負すること。浄瑠璃、傾城反魂香「あつちへ遣るかこつちへ取るか―の博奕」
くびかけ‐しばい【頸掛芝居】‥ヰ
人形を入れた箱を頸にかけ、その上で人形を操り、大道で見せたもの。くぐつまわし。山猫まわし。箱芝居。→傀儡師かいらいし(図)
くび‐かざり【首飾り・頸飾り】
首にかける装飾品。宝石・貴金属類などをつないで輪にしたもの。ネックレス。「真珠の―」
くび‐かし【首枷・頸枷】
(→)「くびかせ」1に同じ。孝徳紀「枷くびかしを着はけ反縛しりえでにしばれり」
くび‐かせ【首枷・頸枷】
①罪人の首にはめ、自由に動けないようにする鉄または木製の刑具。太平記2「―・手枷を入れられ」
②自由を束縛するもの。係累。きずな。謡曲、天鼓「親子は三界の―と」
くび‐がってん【首合点】
首を上下にふって承諾の意を表すこと。
⇒くはら【久原】
くばり【配り・賦り】
①くばること。くばった位置。「字―」「心―」
②生花で、木の叉またなどを筒の中に入れて花を支えること。また、その木の叉など。
⇒くばり‐だて【配り立て】
⇒くばり‐なっとう【配り納豆】
⇒くばり‐ばんづけ【配り番付】
⇒くばり‐ふだ【配り札】
⇒くばり‐へい【配り幣】
⇒くばり‐もの【配り物】
⇒くばりわけ‐ぶぎょう【賦別奉行】
くばり‐だて【配り立て】
方々に人手を分けて備えをすること。てくばり。
⇒くばり【配り・賦り】
くばり‐ちら・す【配り散らす】
〔他五〕
誰彼となくやたらにくばる。方々へくばる。
くばり‐なっとう【配り納豆】
年末または年始に、寺から檀家へくばる寺納豆。
⇒くばり【配り・賦り】
くばり‐ばんづけ【配り番付】
(ひいき先にも配ったからいう)芝居番付の一つ。狂言の外題・役割・料金などを一枚刷にして辻々に貼り出す番付。札番付。櫓下やぐらした番付。配り札。
⇒くばり【配り・賦り】
くばり‐ふだ【配り札】
①劇場からひいき筋に贈る招待券。
②(→)「配り番付」に同じ。
⇒くばり【配り・賦り】
くばり‐へい【配り幣】
諸神に奉るべき幣帛へいはくを一つに束ね、両段再拝の後、束を解いて各座の神に配り供えること。
⇒くばり【配り・賦り】
くばり‐もの【配り物】
祝儀・挨拶・謝礼として人々に分け贈る物。
⇒くばり【配り・賦り】
くばりわけ‐ぶぎょう【賦別奉行】‥ギヤウ
鎌倉・室町幕府の職名。訴状を受け取って、年月日および氏名を記し、引付方各番へくばり分ける職。問注所役人の勤務。賦奉行ふぶぎょう。
⇒くばり【配り・賦り】
くば・る【配る・賦る】
〔他五〕
①物を割り当てて渡す。分配する。源氏物語葵「誠にかの御形見なるべき物など…、皆―・らせ給ひけり」。「新聞を―・る」
②注意や心遣いを行きわたらせる。宇津保物語梅花笠「あまたに―・りし心を、只一所になりたりかし」。「目を―・る」「気を―・る」
③結婚させる。縁づける。源氏物語東屋「はじめの腹の二三人は、皆さまざまに―・りておとなびさせたり」
④それぞれ適当な所におく。配置する。「短冊に字を―・る」「要所要所に人を―・る」
⑤(隠語)非常警戒線を張る。
くば・る【焼る】
〔自四〕
火の中にはいって燃える。浄瑠璃、女殺油地獄「火に―・らうが、うぬが三昧」
ぐはん‐しょうねん【虞犯少年】‥セウ‥
一定の事由があって、その性格・環境に照らし、将来、罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をする虞おそれのある少年。少年法により家庭裁判所の審判に付される。
くばんだ【鳩槃荼】
(梵語Kumbhāṇḍa)人の精気を吸い、動作速く、さまざまに変化する悪神。鳩槃荼夜叉神。
く‐ひ【句碑】
俳句を彫りつけた石碑。「芭蕉の―」
くび【首・頸】
①脊椎動物の頭と胴とをつなぐ部分。頸部。万葉集4「わが恋は千引の石を七ばかり―にかけむも神の諸伏もろふし」
②衣服の、くびに当たる部分。
③物の、くびの形をした部分。「手―」「徳利の―」
㋐琴きんの狭くくびれている2部分のうち、本の方の部分。末の方は腰という。
㋑琵琶の胴の上部の細くなった部分。鹿頸ししくび。俗に棹さおという。
㋒薩摩琵琶の撥ばちのくびれている所。
④身体のくびより上の部分。かしら。あたま。こうべ。「―をはねる」
⑤解雇すること。馘首かくしゅ。「会社を―になった」
⑥顔。容貌。
⇒首が繋がる
⇒首が飛ぶ
⇒首が回らない
⇒首になる
⇒首に縄を付ける
⇒首の皮一枚
⇒首の座へ直る
⇒首振り三年
⇒首を洗って待つ
⇒首を傾げる
⇒首を切る
⇒首をすくめる
⇒首を挿げ替える
⇒首を縦に振る
⇒首を突っ込む
⇒首を長くする
⇒首を捻る
⇒首を横に振る
くび【鵠】
(→)「くぐい」に同じ。古事記中「さ渡る―」
ぐ‐ひ【具否】
備わっているかいないか。ぐふ。
ぐ‐び【具備】
必要なものが十分に備わっていること。「条件を―した書類」
くび‐いた【首板】
軍陣で、敵の首をのせる板。
くび‐うま【首馬・頸馬】
①鞍くらの前輪まえわに乗ること。
②肩車かたぐるま。首子乗り。
くび‐おおい【頸被い】‥オホヒ
牛馬の頸をおおう布。〈倭名類聚鈔11〉
くび‐おけ【首桶】‥ヲケ
討ちとった首を入れる桶。首入れ。
くび‐がけ【首賭け】
首を賭けて誓うこと。また、首を賭けて勝負すること。浄瑠璃、傾城反魂香「あつちへ遣るかこつちへ取るか―の博奕」
くびかけ‐しばい【頸掛芝居】‥ヰ
人形を入れた箱を頸にかけ、その上で人形を操り、大道で見せたもの。くぐつまわし。山猫まわし。箱芝居。→傀儡師かいらいし(図)
くび‐かざり【首飾り・頸飾り】
首にかける装飾品。宝石・貴金属類などをつないで輪にしたもの。ネックレス。「真珠の―」
くび‐かし【首枷・頸枷】
(→)「くびかせ」1に同じ。孝徳紀「枷くびかしを着はけ反縛しりえでにしばれり」
くび‐かせ【首枷・頸枷】
①罪人の首にはめ、自由に動けないようにする鉄または木製の刑具。太平記2「―・手枷を入れられ」
②自由を束縛するもの。係累。きずな。謡曲、天鼓「親子は三界の―と」
くび‐がってん【首合点】
首を上下にふって承諾の意を表すこと。
広辞苑 ページ 5719 での【○苦は楽の種】単語。