複数辞典一括検索+![]()
![]()
たちはき‐せんじょう【帯刀先生】‥ジヤウ🔗⭐🔉
たちはき‐せんじょう【帯刀先生】‥ジヤウ
帯刀の筆頭者。源・平二氏の武士が次第に多くなった。
⇒たち‐はき【帯刀】
たちはき‐とねり【帯刀舎人】🔗⭐🔉
たちはき‐とねり【帯刀舎人】
(→)「たちはき」に同じ。
⇒たち‐はき【帯刀】
たちはき‐の‐じん【帯刀の陣】‥ヂン🔗⭐🔉
たちはき‐の‐じん【帯刀の陣】‥ヂン
たちはきの詰所。古今和歌集春「春宮の―にて」
⇒たち‐はき【帯刀】
たちはき‐の‐やく【帯刀役・帯剣役】🔗⭐🔉
たちはき‐の‐やく【帯刀役・帯剣役】
鎌倉・室町幕府の職名。将軍の参内・社参などに太刀を帯びて供奉した役。
⇒たち‐はき【帯刀】
たち‐ばさみ【裁ち鋏】🔗⭐🔉
たち‐ばさみ【裁ち鋏】
布地を裁断するのに用いる鋏。
たち‐はし・る【立ち走る】🔗⭐🔉
たち‐はし・る【立ち走る】
〔自四〕
立って走る。また、走りまわる。万葉集9「―・り叫び袖振り」
たち‐はずし【裁ち外し】‥ハヅシ🔗⭐🔉
たち‐はずし【裁ち外し】‥ハヅシ
布などのたちくず。
たち‐はずれ【裁ち外れ】‥ハヅレ🔗⭐🔉
たち‐はずれ【裁ち外れ】‥ハヅレ
(→)「たちはずし」に同じ。狂言、夷毘沙門「絹の―、布の―などをきて」
たち‐はだか・る【立ちはだかる】🔗⭐🔉
たち‐はだか・る【立ちはだかる】
〔自五〕
立ちふさがって邪魔をする。手足を広げて立ってさえぎる。「行く手に―・る難関」
たち‐はたら・く【立ち働く】🔗⭐🔉
たち‐はたら・く【立ち働く】
〔自五〕
動きまわって働く。いろいろとよく働く。「こまめに―・く」
たちばな【橘】🔗⭐🔉
たちばな【橘】
①食用柑橘かんきつ類の総称。ときじくのかくのこのみ。〈[季]秋〉。万葉集6「―は実さへ花さへその葉さへ枝えに霜降れどいや常葉とこはの樹」。「右近の―」
②ニホンタチバナの別称。〈[季]秋〉
③カラタチバナの別称。
④襲かさねの色目。表は朽葉くちば、裏は黄。また、表は白、裏は青。
⑤紋所の名。橘の葉と果実とをとりあわせて描いたもの。橘・丸に橘・杏葉ぎょうよう橘・枝橘・向むこう橘・三橘など。
橘
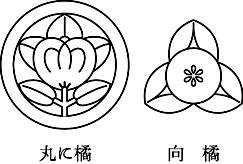 ⑥香銘。木所きどころは真那賀まなか。→香木。
⇒たちばな‐づき【橘月】
⇒たちばな‐どり【橘鳥】
⇒たちばな‐もどき【橘擬き】
⇒たちばな‐やき【橘焼】
⇒たちばな‐を【橘を】
⑥香銘。木所きどころは真那賀まなか。→香木。
⇒たちばな‐づき【橘月】
⇒たちばな‐どり【橘鳥】
⇒たちばな‐もどき【橘擬き】
⇒たちばな‐やき【橘焼】
⇒たちばな‐を【橘を】
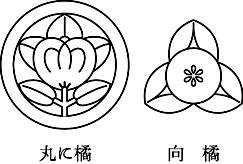 ⑥香銘。木所きどころは真那賀まなか。→香木。
⇒たちばな‐づき【橘月】
⇒たちばな‐どり【橘鳥】
⇒たちばな‐もどき【橘擬き】
⇒たちばな‐やき【橘焼】
⇒たちばな‐を【橘を】
⑥香銘。木所きどころは真那賀まなか。→香木。
⇒たちばな‐づき【橘月】
⇒たちばな‐どり【橘鳥】
⇒たちばな‐もどき【橘擬き】
⇒たちばな‐やき【橘焼】
⇒たちばな‐を【橘を】
広辞苑 ページ 12193。