複数辞典一括検索+![]()
![]()
のき‐ひらがわら【軒平瓦】‥ガハラ🔗⭐🔉
のき‐ひらがわら【軒平瓦】‥ガハラ
軒先に葺ふく平瓦。多く唐草模様をつけるので唐草瓦とも。軒瓦。↔軒丸瓦
のぎ‐へん【ノ木偏・禾偏】🔗⭐🔉
のぎ‐へん【ノ木偏・禾偏】
漢字の偏の一つ。「稲」「秋」などの偏の「禾」の称。
のき‐まるがわら【軒丸瓦】‥ガハラ🔗⭐🔉
のき‐まるがわら【軒丸瓦】‥ガハラ
軒先に葺ふく丸瓦。古くは蓮華文が多い。後にほとんど巴ともえ文となったので巴瓦とも。鐙瓦あぶみがわら。花瓦はながわら。↔軒平瓦
軒丸瓦
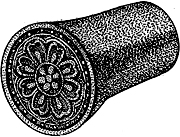
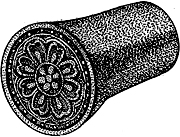
のぎ‐まれすけ【乃木希典】🔗⭐🔉
のぎ‐まれすけ【乃木希典】
軍人。陸軍大将。長州藩士。日露戦争に第三軍司令官として旅順を攻略。後に学習院長。明治天皇の大葬当日、自邸で妻静子とともに殉死。(1849〜1912)
乃木希典
提供:毎日新聞社
 ⇒のぎ【乃木】
⇒のぎ【乃木】
 ⇒のぎ【乃木】
⇒のぎ【乃木】
のぎ‐め【芒目】🔗⭐🔉
のぎ‐め【芒目】
陶器や鉱物などの肌にある芒のような文理きめ。
の‐ぎわ【野際】‥ギハ🔗⭐🔉
の‐ぎわ【野際】‥ギハ
野のあたり。のべ。万代和歌集春「あだち野の―の真葛もえにけり」
のき‐わり【軒割】🔗⭐🔉
のき‐わり【軒割】
戸数に応じて割り当てること。金銭の寄付などにいう。戸数割。→株割かぶわり→高割たかわり
○軒を争うのきをあらそう
軒と軒とが相接して家が建てこんでいるさまにいう。軒を並べる。軒を連ねる。方丈記「軒を争ひし人のすまひ」
⇒のき【軒・簷・檐・宇】
○軒を連ねるのきをつらねる
(→)「軒を争う」に同じ。
⇒のき【軒・簷・檐・宇】
の・く【仰く】🔗⭐🔉
の・く【仰く】
[一]〔他下二〕
上を向くようにする。あおむけにする。
[二]〔自四〕
上を向く。あおむけになる。
の・く【退く】🔗⭐🔉
の・く【退く】
[一]〔自五〕
①いる場所から引きさがる。立ち去る。避けて離れる。源氏物語手習「つつみもあへず、物ぐるはしきまで、けはひ聞えぬべければ、―・きぬ」。おらが春「雀の子そこ―・けそこ―・け御馬が通る」。「借家を―・く」
②逃げる。退却する。平家物語11「渚なぎさに百騎ばかりありける者ども、しばしもこらへず、二町ばかりざつと引いてぞ―・きにける」
③離れて居る。間が隔たっている。平家物語11「判官叶はじとや思はれけん、長刀脇にかい挟み、御方みかたの船の二丈ばかり―・いたりけるに、ゆらりととび乗り給ひぬ」
④その地位を離れる。しりぞく。大鏡頼忠「一条院位につかせ給ひしかば、よそ人にて、関白―・かせ給ひにき」。「会長職を―・く」
⑤今までの関係を離れる。縁を切る。源氏物語浮舟「この宮の御具にてはいとよきあはひなりと、思ひもゆづりつべく―・く心地し給へど」。浮世草子、好色敗毒散「色里に遊ぶ人は興に乗じて女郎にあひ、興尽きて―・きたいとて、心まかせに―・かする事にあらず」
⑥仲間・集まりなどからぬけ出る。「組合を―・く」
[二]〔他下二〕
⇒のける(下一)
⇒退けば他人
広辞苑 ページ 15379。