複数辞典一括検索+![]()
![]()
かがみ‐の‐まつ【鏡の松】🔗⭐🔉
かがみ‐の‐まつ【鏡の松】
能舞台正面の鏡板に描いた老松。
⇒かがみ【鏡】
かがみ‐ばこ【鏡匣・鏡箱】🔗⭐🔉
かがみ‐ばこ【鏡匣・鏡箱】
①鏡を入れておく箱。
②平安時代以後、寝殿に置いた調度で、鏡・領巾ひれ・汗手巾あせたのごいなどを入れる箱。鷺足さぎあしの台に載せ、唐櫛笥からくしげと並べて置く。鏡の家。
鏡匣
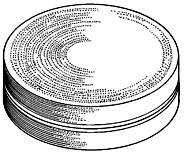 ⇒かがみ【鏡】
⇒かがみ【鏡】
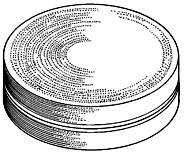 ⇒かがみ【鏡】
⇒かがみ【鏡】
かがみ‐はだ【鏡肌】🔗⭐🔉
かがみ‐はだ【鏡肌】
〔地〕断層によって岩盤や鉱床がずれ動いたために、磨かれて鏡のように光る断層面。
⇒かがみ【鏡】
かがみ‐ばり【鏡張り】🔗⭐🔉
かがみ‐ばり【鏡張り】
鏡板を張ること。また、張ったもの。
⇒かがみ【鏡】
かがみ‐びらき【鏡開き】🔗⭐🔉
かがみ‐びらき【鏡開き】
(「開き」は「割り」の忌み詞)
①正月11日ごろ鏡餅を下げて雑煮・汁粉にして食べる行事。近世、武家で、正月に男は具足餅を、女は鏡台に供えた餅を正月20日(のち11日)に割って食べたのに始まる。鏡割り。〈[季]新年〉
②祝い事に酒樽のふたを開くこと。鏡抜き。
⇒かがみ【鏡】
かがみ‐ぶくろ【鏡袋】🔗⭐🔉
かがみ‐ぶくろ【鏡袋】
懐中鏡を入れておく袋。金銭も入れた。好色一代男4「―より一包とり出だして」
⇒かがみ【鏡】
かがみ‐ぶた【鏡蓋】🔗⭐🔉
かがみ‐ぶた【鏡蓋】
根付ねつけの一種。鏡のふたをかたどったものか。仮名垣魯文、安愚楽鍋「根付けは象牙の―にて」
⇒かがみ【鏡】
かがみ‐ぶとん【鏡蒲団】🔗⭐🔉
かがみ‐ぶとん【鏡蒲団】
裏の布を表に折りかえして額縁のように縁をとった蒲団。
⇒かがみ【鏡】
かがみ‐まくら【鏡枕】🔗⭐🔉
かがみ‐まくら【鏡枕】
柱や鏡台に鏡を掛ける時、鏡の角度を安定させるために鏡の下に置く筒状のもの。
⇒かがみ【鏡】
広辞苑 ページ 3430。