複数辞典一括検索+![]()
![]()
あばた【痘痕】🔗⭐🔉
○痘痕も靨あばたもえくぼ🔗⭐🔉
○痘痕も靨あばたもえくぼ
好きになると欠点まで好ましく見える意。
⇒あばた【痘痕】
アバダン【Abadan】
イラン南西部の港湾都市。ペルシア湾頭に臨み、大精油所があり、同国南部の油田地帯とパイプラインで結ばれる。人口27万8千(2003)。
アパッシュ【apache フランス】
無頼漢。ならず者。
アパッチ【Apache】
アメリカ先住民のアサバスカン諸族のうち、南下を繰り返して南西部のニュー‐メキシコ州・アリゾナ州にかけて居住する諸民族の総称。東部アパッチは特に機動力と武勇とで知られ、その一民族のリーダー、ジェロニモは有名。
アパテイア【apatheia ギリシア】
〔哲〕情感によって乱されず、欲情によって支配されない心の状態。この心境に達することをストア学派は哲学的訓練の究極目的とみなした。アパシー。
アパトサウルス【Apatosaurus ラテン】
ジュラ紀の北アメリカに生息した恐竜で、竜脚類の一つ。全長約21メートル。頭は小さく、首と尾が細長い。植物食性。ブロントサウルス。雷竜かみなりりゅう。
アパトサウルス
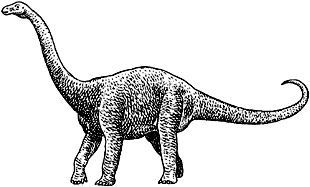 あ‐はなち【畔放ち】
天つ罪の一つ。田のあぜを崩すこと。祝詞、大祓詞「―、溝埋み」
あはは
口を大きく開けて笑う声。
あ‐はや【足速】
足の速いこと。移動の速度が速いこと。万葉集7「島伝ふ―の小舟」
あば‐よ
(「さあらばよ」からか)ふつう男性が使う、別れの時のぞんざいな挨拶。さようなら。
あばら【肋】
(荒あばらの意)「あばらぼね」の略。
⇒あばら‐きん【肋筋】
⇒あばら‐ぼね【肋骨】
あばら【荒】
①荒れはててすきまの多いさま。伊勢物語「―なる板敷」。日葡辞書「カキ、カベアバラニシテアメ、カゼタマラヌ」
②「あばらや」の略。
③「あばらすど」の略。
⇒あばら‐しょうじ【荒障子】
⇒あばら‐すど【荒簾戸】
⇒あばら‐や【荒屋】
あばら【疎】
(→)「まばら」に同じ。
あばら‐きん【肋筋】
鉄筋コンクリート梁の主筋に直交する形で巻いた鉄筋。剪断に対する補強と主筋の位置の保持のために付ける。
⇒あばら【肋】
あばら‐しょうじ【荒障子】‥シヤウ‥
紙の破れた障子。
⇒あばら【荒】
あばら‐すど【荒簾戸】
①破れた簾戸。
②戸のない家。あばら。
⇒あばら【荒】
アパラチア‐さんみゃく【アパラチア山脈】
(Appalachian mountains)アメリカ合衆国の東部にある古い褶曲山脈。長さ約2600キロメートル。北端はカナダに達する。最高点2037メートル。山脈中に何本もの縦谷が走る。
あばら‐ぼね【肋骨】
肋骨ろっこつのこと。
⇒あばら【肋】
あばら‐や【荒屋】
①荒れはてた家。自分の家の謙称としても用いる。源氏物語澪標「人知れぬ―に」
②休憩所として設けた四方の囲いのない小さな建物。四阿あずまや。亭ちん。あばら。
⇒あばら【荒】
アバランシュ【avalanche フランス】
(登山用語)なだれ。アバランチ。
あ‐ばり【網針】
あみばり。
あば・る【荒る】
〔自下二〕
荒れはてる。荒れくずれる。こわれる。宇津保物語楼上上「一丁なれどいみじう―・れて」。日葡辞書「イエハカゼニアバレ、アメニク(朽)ツル」
あば・る【暴る】
〔自下二〕
⇒あばれる(下一)
アパルトヘイト【apartheid アフリカーンス】
(もと隔離の意)南アフリカ共和国の有色人種差別政策。1991年法的に全廃。
アパルトマン【appartement フランス】
(→)アパートに同じ。
あばれ【暴れ】
①あばれること。浄瑠璃、女殺油地獄「鼠の―は静まりぬ」
②「あばれ食い」の略。
③歌舞伎囃子の一つ。荒事に用い、太鼓を主奏楽器とする。
⇒あばれ‐うま【暴れ馬】
⇒あばれ‐がわ【暴れ川】
⇒あばれ‐ぐい【暴れ食い】
⇒あばれ‐たんぜん【暴れ丹前】
⇒あばれ‐もの【暴れ者】
あばれ‐うま【暴れ馬】
あばれくるう馬。
⇒あばれ【暴れ】
あばれ‐がわ【暴れ川】‥ガハ
たびたび氾濫する川。
⇒あばれ【暴れ】
あばれ‐ぐい【暴れ食い】‥グヒ
むやみに食うこと。
⇒あばれ【暴れ】
あばれ‐たんぜん【暴れ丹前】
①歌舞伎の丹前3のうち、乱暴者に扮する俳優が演ずるもの。また、そのような暴れ者の役。
②下座音楽の一つ。1の出場に笛と太鼓を主とするはやし。
⇒あばれ【暴れ】
あばれ‐まわ・る【暴れ回る】‥マハル
〔自五〕
①いたる所で乱暴なふるまいをする。「街道を―・った盗賊」
②思う存分、力を発揮し活躍する。
あばれ‐もの【暴れ者】
乱暴な人。
⇒あばれ【暴れ】
あば・れる【暴れる】
〔自下一〕[文]あば・る(下二)
①乱暴する。暴力を振るうなど無法なことをする。日葡辞書「コノワランベガアバレテタマラヌ」「ネズミガアバルル」。「酔って―・れる」
②転じて、勇ましく大胆なふるまいをする。「若い時は大いに―・れたものだ」
③暴飲暴食をする。西鶴織留3「釣りたるはぜを丸焼にして数食ふ事を手柄におのおの―・れける中にも」
アパレル【apparel】
衣服、特に既製服のこと。転じて既製服業界・ファッション衣料の製造業者などを指す。「―産業」
あばれん‐ぼう【暴れん坊】‥バウ
思うままに振る舞う人。あばれもの。「政界の―」
アバン‐ギャルド【avant-garde フランス】
(前衛の意)
①軍隊用語で、本隊に先がけて偵察・先制攻撃を行う小隊。
②レーニンによる1の革命運動への転用。大衆の自然発生的反抗を組織する革命家集団・政党。
③2の芸術分野への転用で、20世紀初め以来ヨーロッパでの、既成の通念を否定し未知の表現領域を開拓しようとする芸術家・芸術運動(立体派・表現派・ダダイスム・抽象派・超現実派など)を指す。1970年代、大衆社会の爛熟のなかで衰退。前衛派。
アバン‐ゲール【avant-guerre フランス】
(戦前の意)
①第一次・第二次両大戦は、ともに芸術を一変させようとする戦後派を生んだが、それから見て、戦前の通念に固執する傾向を指していう語。
②転じて、第二次大戦前の思想・生活態度などを保持する人。戦前派。
↔アプレ‐ゲール
アバンチュール【aventure フランス】
(冒険の意)冒険味をおびた恋愛。恋の火遊び。
あび【阿比】
アビ目アビ科の鳥。大きさはカモメぐらい。体は鵜うに似て潜水が巧み。背面は黒褐色、頭・頸・背面に白斑が散在する。魚群を追って集まる習性があり、漁業に有益。夏は北極付近で繁殖、日本には冬に渡来し、海洋に広く群棲。古名かずくとり。平家鳥。
あび【阿鼻】
〔仏〕(梵語Avīci 無間むけんと訳す)八大地獄の第8。五逆・謗法の大悪を犯した者が、ここに生まれ、間断なく剣樹・刀山・鑊湯かくとうなどの苦しみを受ける、諸地獄中で最も苦しい地獄。阿鼻地獄。無間地獄。阿鼻叫喚地獄。阿鼻大城。
アピア【Apia】
南太平洋、サモアの首都。ウポル島の北岸に位置する。人口3万9千(2001)。アーピア。
アピール【appeal】
①主張などを世論や他人に訴えること。また、その訴え。「平和への―」「自分の長所を―する」
②心を引きつける力。魅力。「セックス‐―」
③運動競技で、審判の判定に異議を申し立てること。
⇒アピール‐ポイント
アピール‐ポイント
(和製語appeal point)自分や自社の製品などを相手に訴えかける上で、特に強調する長所・要点。
⇒アピール【appeal】
あびき
①(漁村語)汽船などが通る際に起こす波のこと。単に大浪のことをもいう。汽船波。
②湾内の異常に大きい潮位変動。長崎湾が最も有名。
あ‐びき【網引】
①網をひいて魚をとること。万葉集3「―すと網子あご調ととのふる海人あまの呼び声」
②大膳職だいぜんしきの品部しなべの一つ。網を用いて魚をとって貢した者。
あび‐きょうかん【阿鼻叫喚】‥ケウクワン
〔仏〕
①阿鼻地獄の苦に堪えられないで泣き叫ぶさま。
②転じて、甚だしい惨状を形容する語。「―の巷と化す」
あ‐び・く【網引く】
〔自四〕
網をひく。神楽歌、朝倉「朝倉やをめの湊に―・きせば」
あびこ【我孫子】
千葉県北西部、手賀沼と利根川に挟まれた市。近世、水戸街道の宿駅・河港として発達。近年は宅地造成が盛ん。東京の衛星都市化が進む。人口13万1千。
あびこ【阿毘古・阿弭古・我孫】
古代の姓かばね、または氏うじの一種。一説に、もとは官名。広く行われ、地名として残る。
あ‐ひさん【亜砒酸】
①無水亜ヒ酸、すなわち三酸化二ヒ素が水に溶けた時、溶液中に存在する弱酸。水溶液としてのみ存在。
②三酸化二ヒ素の俗称。→酸化ヒ素1
あび‐じごく【阿鼻地獄】‥ヂ‥
〔仏〕(→)「あび(阿鼻)」に同じ。
アビシニア【Abyssinia】
エチオピアの旧称。
アビシニアン【Abyssinian】
ネコの一品種。エチオピア原産。体は筋肉質で短毛。毛は1本1本が根元の方から2〜4色に分かれる。イエネコの中では最古の品種といわれる。
アビジャン【Abidjan】
コート‐ディヴォアールの南部、ギニア湾に臨む港湾都市。1983年まで首都。自動車・食品工業が盛んで、西アフリカの経済・文化の中心の一つ。人口192万9千(1988)。
アビジャン
撮影:小松義夫
あ‐はなち【畔放ち】
天つ罪の一つ。田のあぜを崩すこと。祝詞、大祓詞「―、溝埋み」
あはは
口を大きく開けて笑う声。
あ‐はや【足速】
足の速いこと。移動の速度が速いこと。万葉集7「島伝ふ―の小舟」
あば‐よ
(「さあらばよ」からか)ふつう男性が使う、別れの時のぞんざいな挨拶。さようなら。
あばら【肋】
(荒あばらの意)「あばらぼね」の略。
⇒あばら‐きん【肋筋】
⇒あばら‐ぼね【肋骨】
あばら【荒】
①荒れはててすきまの多いさま。伊勢物語「―なる板敷」。日葡辞書「カキ、カベアバラニシテアメ、カゼタマラヌ」
②「あばらや」の略。
③「あばらすど」の略。
⇒あばら‐しょうじ【荒障子】
⇒あばら‐すど【荒簾戸】
⇒あばら‐や【荒屋】
あばら【疎】
(→)「まばら」に同じ。
あばら‐きん【肋筋】
鉄筋コンクリート梁の主筋に直交する形で巻いた鉄筋。剪断に対する補強と主筋の位置の保持のために付ける。
⇒あばら【肋】
あばら‐しょうじ【荒障子】‥シヤウ‥
紙の破れた障子。
⇒あばら【荒】
あばら‐すど【荒簾戸】
①破れた簾戸。
②戸のない家。あばら。
⇒あばら【荒】
アパラチア‐さんみゃく【アパラチア山脈】
(Appalachian mountains)アメリカ合衆国の東部にある古い褶曲山脈。長さ約2600キロメートル。北端はカナダに達する。最高点2037メートル。山脈中に何本もの縦谷が走る。
あばら‐ぼね【肋骨】
肋骨ろっこつのこと。
⇒あばら【肋】
あばら‐や【荒屋】
①荒れはてた家。自分の家の謙称としても用いる。源氏物語澪標「人知れぬ―に」
②休憩所として設けた四方の囲いのない小さな建物。四阿あずまや。亭ちん。あばら。
⇒あばら【荒】
アバランシュ【avalanche フランス】
(登山用語)なだれ。アバランチ。
あ‐ばり【網針】
あみばり。
あば・る【荒る】
〔自下二〕
荒れはてる。荒れくずれる。こわれる。宇津保物語楼上上「一丁なれどいみじう―・れて」。日葡辞書「イエハカゼニアバレ、アメニク(朽)ツル」
あば・る【暴る】
〔自下二〕
⇒あばれる(下一)
アパルトヘイト【apartheid アフリカーンス】
(もと隔離の意)南アフリカ共和国の有色人種差別政策。1991年法的に全廃。
アパルトマン【appartement フランス】
(→)アパートに同じ。
あばれ【暴れ】
①あばれること。浄瑠璃、女殺油地獄「鼠の―は静まりぬ」
②「あばれ食い」の略。
③歌舞伎囃子の一つ。荒事に用い、太鼓を主奏楽器とする。
⇒あばれ‐うま【暴れ馬】
⇒あばれ‐がわ【暴れ川】
⇒あばれ‐ぐい【暴れ食い】
⇒あばれ‐たんぜん【暴れ丹前】
⇒あばれ‐もの【暴れ者】
あばれ‐うま【暴れ馬】
あばれくるう馬。
⇒あばれ【暴れ】
あばれ‐がわ【暴れ川】‥ガハ
たびたび氾濫する川。
⇒あばれ【暴れ】
あばれ‐ぐい【暴れ食い】‥グヒ
むやみに食うこと。
⇒あばれ【暴れ】
あばれ‐たんぜん【暴れ丹前】
①歌舞伎の丹前3のうち、乱暴者に扮する俳優が演ずるもの。また、そのような暴れ者の役。
②下座音楽の一つ。1の出場に笛と太鼓を主とするはやし。
⇒あばれ【暴れ】
あばれ‐まわ・る【暴れ回る】‥マハル
〔自五〕
①いたる所で乱暴なふるまいをする。「街道を―・った盗賊」
②思う存分、力を発揮し活躍する。
あばれ‐もの【暴れ者】
乱暴な人。
⇒あばれ【暴れ】
あば・れる【暴れる】
〔自下一〕[文]あば・る(下二)
①乱暴する。暴力を振るうなど無法なことをする。日葡辞書「コノワランベガアバレテタマラヌ」「ネズミガアバルル」。「酔って―・れる」
②転じて、勇ましく大胆なふるまいをする。「若い時は大いに―・れたものだ」
③暴飲暴食をする。西鶴織留3「釣りたるはぜを丸焼にして数食ふ事を手柄におのおの―・れける中にも」
アパレル【apparel】
衣服、特に既製服のこと。転じて既製服業界・ファッション衣料の製造業者などを指す。「―産業」
あばれん‐ぼう【暴れん坊】‥バウ
思うままに振る舞う人。あばれもの。「政界の―」
アバン‐ギャルド【avant-garde フランス】
(前衛の意)
①軍隊用語で、本隊に先がけて偵察・先制攻撃を行う小隊。
②レーニンによる1の革命運動への転用。大衆の自然発生的反抗を組織する革命家集団・政党。
③2の芸術分野への転用で、20世紀初め以来ヨーロッパでの、既成の通念を否定し未知の表現領域を開拓しようとする芸術家・芸術運動(立体派・表現派・ダダイスム・抽象派・超現実派など)を指す。1970年代、大衆社会の爛熟のなかで衰退。前衛派。
アバン‐ゲール【avant-guerre フランス】
(戦前の意)
①第一次・第二次両大戦は、ともに芸術を一変させようとする戦後派を生んだが、それから見て、戦前の通念に固執する傾向を指していう語。
②転じて、第二次大戦前の思想・生活態度などを保持する人。戦前派。
↔アプレ‐ゲール
アバンチュール【aventure フランス】
(冒険の意)冒険味をおびた恋愛。恋の火遊び。
あび【阿比】
アビ目アビ科の鳥。大きさはカモメぐらい。体は鵜うに似て潜水が巧み。背面は黒褐色、頭・頸・背面に白斑が散在する。魚群を追って集まる習性があり、漁業に有益。夏は北極付近で繁殖、日本には冬に渡来し、海洋に広く群棲。古名かずくとり。平家鳥。
あび【阿鼻】
〔仏〕(梵語Avīci 無間むけんと訳す)八大地獄の第8。五逆・謗法の大悪を犯した者が、ここに生まれ、間断なく剣樹・刀山・鑊湯かくとうなどの苦しみを受ける、諸地獄中で最も苦しい地獄。阿鼻地獄。無間地獄。阿鼻叫喚地獄。阿鼻大城。
アピア【Apia】
南太平洋、サモアの首都。ウポル島の北岸に位置する。人口3万9千(2001)。アーピア。
アピール【appeal】
①主張などを世論や他人に訴えること。また、その訴え。「平和への―」「自分の長所を―する」
②心を引きつける力。魅力。「セックス‐―」
③運動競技で、審判の判定に異議を申し立てること。
⇒アピール‐ポイント
アピール‐ポイント
(和製語appeal point)自分や自社の製品などを相手に訴えかける上で、特に強調する長所・要点。
⇒アピール【appeal】
あびき
①(漁村語)汽船などが通る際に起こす波のこと。単に大浪のことをもいう。汽船波。
②湾内の異常に大きい潮位変動。長崎湾が最も有名。
あ‐びき【網引】
①網をひいて魚をとること。万葉集3「―すと網子あご調ととのふる海人あまの呼び声」
②大膳職だいぜんしきの品部しなべの一つ。網を用いて魚をとって貢した者。
あび‐きょうかん【阿鼻叫喚】‥ケウクワン
〔仏〕
①阿鼻地獄の苦に堪えられないで泣き叫ぶさま。
②転じて、甚だしい惨状を形容する語。「―の巷と化す」
あ‐び・く【網引く】
〔自四〕
網をひく。神楽歌、朝倉「朝倉やをめの湊に―・きせば」
あびこ【我孫子】
千葉県北西部、手賀沼と利根川に挟まれた市。近世、水戸街道の宿駅・河港として発達。近年は宅地造成が盛ん。東京の衛星都市化が進む。人口13万1千。
あびこ【阿毘古・阿弭古・我孫】
古代の姓かばね、または氏うじの一種。一説に、もとは官名。広く行われ、地名として残る。
あ‐ひさん【亜砒酸】
①無水亜ヒ酸、すなわち三酸化二ヒ素が水に溶けた時、溶液中に存在する弱酸。水溶液としてのみ存在。
②三酸化二ヒ素の俗称。→酸化ヒ素1
あび‐じごく【阿鼻地獄】‥ヂ‥
〔仏〕(→)「あび(阿鼻)」に同じ。
アビシニア【Abyssinia】
エチオピアの旧称。
アビシニアン【Abyssinian】
ネコの一品種。エチオピア原産。体は筋肉質で短毛。毛は1本1本が根元の方から2〜4色に分かれる。イエネコの中では最古の品種といわれる。
アビジャン【Abidjan】
コート‐ディヴォアールの南部、ギニア湾に臨む港湾都市。1983年まで首都。自動車・食品工業が盛んで、西アフリカの経済・文化の中心の一つ。人口192万9千(1988)。
アビジャン
撮影:小松義夫
 あび・す【浴びす】
〔他下二〕
⇒あびせる(下一)
あびせ‐か・ける【浴びせ掛ける】
〔他下一〕
①水などを勢いよく掛ける。「泥水を―・ける」
②激しい調子の言葉を投げ掛ける。「非難を―・ける」
あびせ‐たおし【浴せ倒し】‥タフシ
相撲の手の一つ。相手が堪こらえるのを上からのしかかって押しつぶすように倒すもの。
あび・せる【浴びせる】
〔他下一〕[文]あび・す(下二)
①湯・水などを他人や物に注ぎかける。宇治拾遺物語(一本)「念仏の僧に湯わかして―・せたてまつらんとて」
②相手に対して物事を勢いよく、あるいは続けざまにしかける。「一太刀ひとたち―・せる」「罵声を―・せる」
アビタシオン【habitation フランス】
(住宅の意)主に中高層の集合住宅の俗称。
あびだつま【阿毘達磨】
〔仏〕(梵語abhidharma)仏の教説を理論的にまとめたもの。主に部派仏教の論書を指す。三蔵の一つ。論。阿毘曇。アビダルマ。「―倶舎論」
アビトゥア【Abitur ドイツ】
ドイツの中等教育修了・大学入学資格試験。
アビラ【Avila】
スペイン中部、旧カスティリア地方の都市。イサベル女王および聖女テレサの生地。
あびらうんけん【阿毘羅吽欠】
〔仏〕(梵語a vi ra hūṃ khaṃ)密教で、胎蔵界大日如来の真言。地・水・火・風・空の五大を象徴する。この真言を唱えると一切のことが成就するという。前に「唵おん」(oṃ)を、後に「蘇婆訶そわか」(svāhā)をつけて唱えることが多い。
アビリティー【ability】
能力。才能。手腕。
アビリンピック
(abilityとOlympicとを合わせた語)身体障害者の全国技能競技大会。1972年、第1回を開いたのに始まる。
あひる【家鴨・鶩】
カモ目カモ科の家禽。マガモの飼養品種で、種類が多い。肉や卵をとり、羽毛は羽ぶとんに使用。
アヒル(1)
撮影:小宮輝之
あび・す【浴びす】
〔他下二〕
⇒あびせる(下一)
あびせ‐か・ける【浴びせ掛ける】
〔他下一〕
①水などを勢いよく掛ける。「泥水を―・ける」
②激しい調子の言葉を投げ掛ける。「非難を―・ける」
あびせ‐たおし【浴せ倒し】‥タフシ
相撲の手の一つ。相手が堪こらえるのを上からのしかかって押しつぶすように倒すもの。
あび・せる【浴びせる】
〔他下一〕[文]あび・す(下二)
①湯・水などを他人や物に注ぎかける。宇治拾遺物語(一本)「念仏の僧に湯わかして―・せたてまつらんとて」
②相手に対して物事を勢いよく、あるいは続けざまにしかける。「一太刀ひとたち―・せる」「罵声を―・せる」
アビタシオン【habitation フランス】
(住宅の意)主に中高層の集合住宅の俗称。
あびだつま【阿毘達磨】
〔仏〕(梵語abhidharma)仏の教説を理論的にまとめたもの。主に部派仏教の論書を指す。三蔵の一つ。論。阿毘曇。アビダルマ。「―倶舎論」
アビトゥア【Abitur ドイツ】
ドイツの中等教育修了・大学入学資格試験。
アビラ【Avila】
スペイン中部、旧カスティリア地方の都市。イサベル女王および聖女テレサの生地。
あびらうんけん【阿毘羅吽欠】
〔仏〕(梵語a vi ra hūṃ khaṃ)密教で、胎蔵界大日如来の真言。地・水・火・風・空の五大を象徴する。この真言を唱えると一切のことが成就するという。前に「唵おん」(oṃ)を、後に「蘇婆訶そわか」(svāhā)をつけて唱えることが多い。
アビリティー【ability】
能力。才能。手腕。
アビリンピック
(abilityとOlympicとを合わせた語)身体障害者の全国技能競技大会。1972年、第1回を開いたのに始まる。
あひる【家鴨・鶩】
カモ目カモ科の家禽。マガモの飼養品種で、種類が多い。肉や卵をとり、羽毛は羽ぶとんに使用。
アヒル(1)
撮影:小宮輝之
 アヒル(2)
撮影:小宮輝之
アヒル(2)
撮影:小宮輝之
 ペキンダック
撮影:小宮輝之
ペキンダック
撮影:小宮輝之
 ▷脚が短く尻を振る歩き方から、時にそのようなさまのあざけり語として使われた。
⇒あひる‐げた【家鴨下駄】
⇒あひる‐の‐きゃはん【家鴨の脚絆】
⇒家鴨が文庫を背負うたよう
⇒家鴨の火事見舞い
あ・びる【浴びる】
〔他上一〕[文]あ・ぶ(上二)
①湯・水などを体にかぶる。湯・水などにつかる。「シャワーを―・びる」「一風呂―・びる」
②身の回りに物をたくさん受ける。また一般に、受ける。こうむる。「日光を―・びる」「埃ほこりを―・びる」「集中砲火を―・びる」「賞賛を―・びる」
③(酒などを)大いに飲む。
▷脚が短く尻を振る歩き方から、時にそのようなさまのあざけり語として使われた。
⇒あひる‐げた【家鴨下駄】
⇒あひる‐の‐きゃはん【家鴨の脚絆】
⇒家鴨が文庫を背負うたよう
⇒家鴨の火事見舞い
あ・びる【浴びる】
〔他上一〕[文]あ・ぶ(上二)
①湯・水などを体にかぶる。湯・水などにつかる。「シャワーを―・びる」「一風呂―・びる」
②身の回りに物をたくさん受ける。また一般に、受ける。こうむる。「日光を―・びる」「埃ほこりを―・びる」「集中砲火を―・びる」「賞賛を―・びる」
③(酒などを)大いに飲む。
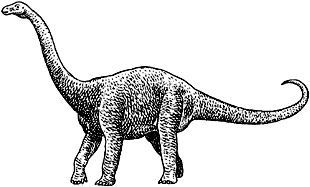 あ‐はなち【畔放ち】
天つ罪の一つ。田のあぜを崩すこと。祝詞、大祓詞「―、溝埋み」
あはは
口を大きく開けて笑う声。
あ‐はや【足速】
足の速いこと。移動の速度が速いこと。万葉集7「島伝ふ―の小舟」
あば‐よ
(「さあらばよ」からか)ふつう男性が使う、別れの時のぞんざいな挨拶。さようなら。
あばら【肋】
(荒あばらの意)「あばらぼね」の略。
⇒あばら‐きん【肋筋】
⇒あばら‐ぼね【肋骨】
あばら【荒】
①荒れはててすきまの多いさま。伊勢物語「―なる板敷」。日葡辞書「カキ、カベアバラニシテアメ、カゼタマラヌ」
②「あばらや」の略。
③「あばらすど」の略。
⇒あばら‐しょうじ【荒障子】
⇒あばら‐すど【荒簾戸】
⇒あばら‐や【荒屋】
あばら【疎】
(→)「まばら」に同じ。
あばら‐きん【肋筋】
鉄筋コンクリート梁の主筋に直交する形で巻いた鉄筋。剪断に対する補強と主筋の位置の保持のために付ける。
⇒あばら【肋】
あばら‐しょうじ【荒障子】‥シヤウ‥
紙の破れた障子。
⇒あばら【荒】
あばら‐すど【荒簾戸】
①破れた簾戸。
②戸のない家。あばら。
⇒あばら【荒】
アパラチア‐さんみゃく【アパラチア山脈】
(Appalachian mountains)アメリカ合衆国の東部にある古い褶曲山脈。長さ約2600キロメートル。北端はカナダに達する。最高点2037メートル。山脈中に何本もの縦谷が走る。
あばら‐ぼね【肋骨】
肋骨ろっこつのこと。
⇒あばら【肋】
あばら‐や【荒屋】
①荒れはてた家。自分の家の謙称としても用いる。源氏物語澪標「人知れぬ―に」
②休憩所として設けた四方の囲いのない小さな建物。四阿あずまや。亭ちん。あばら。
⇒あばら【荒】
アバランシュ【avalanche フランス】
(登山用語)なだれ。アバランチ。
あ‐ばり【網針】
あみばり。
あば・る【荒る】
〔自下二〕
荒れはてる。荒れくずれる。こわれる。宇津保物語楼上上「一丁なれどいみじう―・れて」。日葡辞書「イエハカゼニアバレ、アメニク(朽)ツル」
あば・る【暴る】
〔自下二〕
⇒あばれる(下一)
アパルトヘイト【apartheid アフリカーンス】
(もと隔離の意)南アフリカ共和国の有色人種差別政策。1991年法的に全廃。
アパルトマン【appartement フランス】
(→)アパートに同じ。
あばれ【暴れ】
①あばれること。浄瑠璃、女殺油地獄「鼠の―は静まりぬ」
②「あばれ食い」の略。
③歌舞伎囃子の一つ。荒事に用い、太鼓を主奏楽器とする。
⇒あばれ‐うま【暴れ馬】
⇒あばれ‐がわ【暴れ川】
⇒あばれ‐ぐい【暴れ食い】
⇒あばれ‐たんぜん【暴れ丹前】
⇒あばれ‐もの【暴れ者】
あばれ‐うま【暴れ馬】
あばれくるう馬。
⇒あばれ【暴れ】
あばれ‐がわ【暴れ川】‥ガハ
たびたび氾濫する川。
⇒あばれ【暴れ】
あばれ‐ぐい【暴れ食い】‥グヒ
むやみに食うこと。
⇒あばれ【暴れ】
あばれ‐たんぜん【暴れ丹前】
①歌舞伎の丹前3のうち、乱暴者に扮する俳優が演ずるもの。また、そのような暴れ者の役。
②下座音楽の一つ。1の出場に笛と太鼓を主とするはやし。
⇒あばれ【暴れ】
あばれ‐まわ・る【暴れ回る】‥マハル
〔自五〕
①いたる所で乱暴なふるまいをする。「街道を―・った盗賊」
②思う存分、力を発揮し活躍する。
あばれ‐もの【暴れ者】
乱暴な人。
⇒あばれ【暴れ】
あば・れる【暴れる】
〔自下一〕[文]あば・る(下二)
①乱暴する。暴力を振るうなど無法なことをする。日葡辞書「コノワランベガアバレテタマラヌ」「ネズミガアバルル」。「酔って―・れる」
②転じて、勇ましく大胆なふるまいをする。「若い時は大いに―・れたものだ」
③暴飲暴食をする。西鶴織留3「釣りたるはぜを丸焼にして数食ふ事を手柄におのおの―・れける中にも」
アパレル【apparel】
衣服、特に既製服のこと。転じて既製服業界・ファッション衣料の製造業者などを指す。「―産業」
あばれん‐ぼう【暴れん坊】‥バウ
思うままに振る舞う人。あばれもの。「政界の―」
アバン‐ギャルド【avant-garde フランス】
(前衛の意)
①軍隊用語で、本隊に先がけて偵察・先制攻撃を行う小隊。
②レーニンによる1の革命運動への転用。大衆の自然発生的反抗を組織する革命家集団・政党。
③2の芸術分野への転用で、20世紀初め以来ヨーロッパでの、既成の通念を否定し未知の表現領域を開拓しようとする芸術家・芸術運動(立体派・表現派・ダダイスム・抽象派・超現実派など)を指す。1970年代、大衆社会の爛熟のなかで衰退。前衛派。
アバン‐ゲール【avant-guerre フランス】
(戦前の意)
①第一次・第二次両大戦は、ともに芸術を一変させようとする戦後派を生んだが、それから見て、戦前の通念に固執する傾向を指していう語。
②転じて、第二次大戦前の思想・生活態度などを保持する人。戦前派。
↔アプレ‐ゲール
アバンチュール【aventure フランス】
(冒険の意)冒険味をおびた恋愛。恋の火遊び。
あび【阿比】
アビ目アビ科の鳥。大きさはカモメぐらい。体は鵜うに似て潜水が巧み。背面は黒褐色、頭・頸・背面に白斑が散在する。魚群を追って集まる習性があり、漁業に有益。夏は北極付近で繁殖、日本には冬に渡来し、海洋に広く群棲。古名かずくとり。平家鳥。
あび【阿鼻】
〔仏〕(梵語Avīci 無間むけんと訳す)八大地獄の第8。五逆・謗法の大悪を犯した者が、ここに生まれ、間断なく剣樹・刀山・鑊湯かくとうなどの苦しみを受ける、諸地獄中で最も苦しい地獄。阿鼻地獄。無間地獄。阿鼻叫喚地獄。阿鼻大城。
アピア【Apia】
南太平洋、サモアの首都。ウポル島の北岸に位置する。人口3万9千(2001)。アーピア。
アピール【appeal】
①主張などを世論や他人に訴えること。また、その訴え。「平和への―」「自分の長所を―する」
②心を引きつける力。魅力。「セックス‐―」
③運動競技で、審判の判定に異議を申し立てること。
⇒アピール‐ポイント
アピール‐ポイント
(和製語appeal point)自分や自社の製品などを相手に訴えかける上で、特に強調する長所・要点。
⇒アピール【appeal】
あびき
①(漁村語)汽船などが通る際に起こす波のこと。単に大浪のことをもいう。汽船波。
②湾内の異常に大きい潮位変動。長崎湾が最も有名。
あ‐びき【網引】
①網をひいて魚をとること。万葉集3「―すと網子あご調ととのふる海人あまの呼び声」
②大膳職だいぜんしきの品部しなべの一つ。網を用いて魚をとって貢した者。
あび‐きょうかん【阿鼻叫喚】‥ケウクワン
〔仏〕
①阿鼻地獄の苦に堪えられないで泣き叫ぶさま。
②転じて、甚だしい惨状を形容する語。「―の巷と化す」
あ‐び・く【網引く】
〔自四〕
網をひく。神楽歌、朝倉「朝倉やをめの湊に―・きせば」
あびこ【我孫子】
千葉県北西部、手賀沼と利根川に挟まれた市。近世、水戸街道の宿駅・河港として発達。近年は宅地造成が盛ん。東京の衛星都市化が進む。人口13万1千。
あびこ【阿毘古・阿弭古・我孫】
古代の姓かばね、または氏うじの一種。一説に、もとは官名。広く行われ、地名として残る。
あ‐ひさん【亜砒酸】
①無水亜ヒ酸、すなわち三酸化二ヒ素が水に溶けた時、溶液中に存在する弱酸。水溶液としてのみ存在。
②三酸化二ヒ素の俗称。→酸化ヒ素1
あび‐じごく【阿鼻地獄】‥ヂ‥
〔仏〕(→)「あび(阿鼻)」に同じ。
アビシニア【Abyssinia】
エチオピアの旧称。
アビシニアン【Abyssinian】
ネコの一品種。エチオピア原産。体は筋肉質で短毛。毛は1本1本が根元の方から2〜4色に分かれる。イエネコの中では最古の品種といわれる。
アビジャン【Abidjan】
コート‐ディヴォアールの南部、ギニア湾に臨む港湾都市。1983年まで首都。自動車・食品工業が盛んで、西アフリカの経済・文化の中心の一つ。人口192万9千(1988)。
アビジャン
撮影:小松義夫
あ‐はなち【畔放ち】
天つ罪の一つ。田のあぜを崩すこと。祝詞、大祓詞「―、溝埋み」
あはは
口を大きく開けて笑う声。
あ‐はや【足速】
足の速いこと。移動の速度が速いこと。万葉集7「島伝ふ―の小舟」
あば‐よ
(「さあらばよ」からか)ふつう男性が使う、別れの時のぞんざいな挨拶。さようなら。
あばら【肋】
(荒あばらの意)「あばらぼね」の略。
⇒あばら‐きん【肋筋】
⇒あばら‐ぼね【肋骨】
あばら【荒】
①荒れはててすきまの多いさま。伊勢物語「―なる板敷」。日葡辞書「カキ、カベアバラニシテアメ、カゼタマラヌ」
②「あばらや」の略。
③「あばらすど」の略。
⇒あばら‐しょうじ【荒障子】
⇒あばら‐すど【荒簾戸】
⇒あばら‐や【荒屋】
あばら【疎】
(→)「まばら」に同じ。
あばら‐きん【肋筋】
鉄筋コンクリート梁の主筋に直交する形で巻いた鉄筋。剪断に対する補強と主筋の位置の保持のために付ける。
⇒あばら【肋】
あばら‐しょうじ【荒障子】‥シヤウ‥
紙の破れた障子。
⇒あばら【荒】
あばら‐すど【荒簾戸】
①破れた簾戸。
②戸のない家。あばら。
⇒あばら【荒】
アパラチア‐さんみゃく【アパラチア山脈】
(Appalachian mountains)アメリカ合衆国の東部にある古い褶曲山脈。長さ約2600キロメートル。北端はカナダに達する。最高点2037メートル。山脈中に何本もの縦谷が走る。
あばら‐ぼね【肋骨】
肋骨ろっこつのこと。
⇒あばら【肋】
あばら‐や【荒屋】
①荒れはてた家。自分の家の謙称としても用いる。源氏物語澪標「人知れぬ―に」
②休憩所として設けた四方の囲いのない小さな建物。四阿あずまや。亭ちん。あばら。
⇒あばら【荒】
アバランシュ【avalanche フランス】
(登山用語)なだれ。アバランチ。
あ‐ばり【網針】
あみばり。
あば・る【荒る】
〔自下二〕
荒れはてる。荒れくずれる。こわれる。宇津保物語楼上上「一丁なれどいみじう―・れて」。日葡辞書「イエハカゼニアバレ、アメニク(朽)ツル」
あば・る【暴る】
〔自下二〕
⇒あばれる(下一)
アパルトヘイト【apartheid アフリカーンス】
(もと隔離の意)南アフリカ共和国の有色人種差別政策。1991年法的に全廃。
アパルトマン【appartement フランス】
(→)アパートに同じ。
あばれ【暴れ】
①あばれること。浄瑠璃、女殺油地獄「鼠の―は静まりぬ」
②「あばれ食い」の略。
③歌舞伎囃子の一つ。荒事に用い、太鼓を主奏楽器とする。
⇒あばれ‐うま【暴れ馬】
⇒あばれ‐がわ【暴れ川】
⇒あばれ‐ぐい【暴れ食い】
⇒あばれ‐たんぜん【暴れ丹前】
⇒あばれ‐もの【暴れ者】
あばれ‐うま【暴れ馬】
あばれくるう馬。
⇒あばれ【暴れ】
あばれ‐がわ【暴れ川】‥ガハ
たびたび氾濫する川。
⇒あばれ【暴れ】
あばれ‐ぐい【暴れ食い】‥グヒ
むやみに食うこと。
⇒あばれ【暴れ】
あばれ‐たんぜん【暴れ丹前】
①歌舞伎の丹前3のうち、乱暴者に扮する俳優が演ずるもの。また、そのような暴れ者の役。
②下座音楽の一つ。1の出場に笛と太鼓を主とするはやし。
⇒あばれ【暴れ】
あばれ‐まわ・る【暴れ回る】‥マハル
〔自五〕
①いたる所で乱暴なふるまいをする。「街道を―・った盗賊」
②思う存分、力を発揮し活躍する。
あばれ‐もの【暴れ者】
乱暴な人。
⇒あばれ【暴れ】
あば・れる【暴れる】
〔自下一〕[文]あば・る(下二)
①乱暴する。暴力を振るうなど無法なことをする。日葡辞書「コノワランベガアバレテタマラヌ」「ネズミガアバルル」。「酔って―・れる」
②転じて、勇ましく大胆なふるまいをする。「若い時は大いに―・れたものだ」
③暴飲暴食をする。西鶴織留3「釣りたるはぜを丸焼にして数食ふ事を手柄におのおの―・れける中にも」
アパレル【apparel】
衣服、特に既製服のこと。転じて既製服業界・ファッション衣料の製造業者などを指す。「―産業」
あばれん‐ぼう【暴れん坊】‥バウ
思うままに振る舞う人。あばれもの。「政界の―」
アバン‐ギャルド【avant-garde フランス】
(前衛の意)
①軍隊用語で、本隊に先がけて偵察・先制攻撃を行う小隊。
②レーニンによる1の革命運動への転用。大衆の自然発生的反抗を組織する革命家集団・政党。
③2の芸術分野への転用で、20世紀初め以来ヨーロッパでの、既成の通念を否定し未知の表現領域を開拓しようとする芸術家・芸術運動(立体派・表現派・ダダイスム・抽象派・超現実派など)を指す。1970年代、大衆社会の爛熟のなかで衰退。前衛派。
アバン‐ゲール【avant-guerre フランス】
(戦前の意)
①第一次・第二次両大戦は、ともに芸術を一変させようとする戦後派を生んだが、それから見て、戦前の通念に固執する傾向を指していう語。
②転じて、第二次大戦前の思想・生活態度などを保持する人。戦前派。
↔アプレ‐ゲール
アバンチュール【aventure フランス】
(冒険の意)冒険味をおびた恋愛。恋の火遊び。
あび【阿比】
アビ目アビ科の鳥。大きさはカモメぐらい。体は鵜うに似て潜水が巧み。背面は黒褐色、頭・頸・背面に白斑が散在する。魚群を追って集まる習性があり、漁業に有益。夏は北極付近で繁殖、日本には冬に渡来し、海洋に広く群棲。古名かずくとり。平家鳥。
あび【阿鼻】
〔仏〕(梵語Avīci 無間むけんと訳す)八大地獄の第8。五逆・謗法の大悪を犯した者が、ここに生まれ、間断なく剣樹・刀山・鑊湯かくとうなどの苦しみを受ける、諸地獄中で最も苦しい地獄。阿鼻地獄。無間地獄。阿鼻叫喚地獄。阿鼻大城。
アピア【Apia】
南太平洋、サモアの首都。ウポル島の北岸に位置する。人口3万9千(2001)。アーピア。
アピール【appeal】
①主張などを世論や他人に訴えること。また、その訴え。「平和への―」「自分の長所を―する」
②心を引きつける力。魅力。「セックス‐―」
③運動競技で、審判の判定に異議を申し立てること。
⇒アピール‐ポイント
アピール‐ポイント
(和製語appeal point)自分や自社の製品などを相手に訴えかける上で、特に強調する長所・要点。
⇒アピール【appeal】
あびき
①(漁村語)汽船などが通る際に起こす波のこと。単に大浪のことをもいう。汽船波。
②湾内の異常に大きい潮位変動。長崎湾が最も有名。
あ‐びき【網引】
①網をひいて魚をとること。万葉集3「―すと網子あご調ととのふる海人あまの呼び声」
②大膳職だいぜんしきの品部しなべの一つ。網を用いて魚をとって貢した者。
あび‐きょうかん【阿鼻叫喚】‥ケウクワン
〔仏〕
①阿鼻地獄の苦に堪えられないで泣き叫ぶさま。
②転じて、甚だしい惨状を形容する語。「―の巷と化す」
あ‐び・く【網引く】
〔自四〕
網をひく。神楽歌、朝倉「朝倉やをめの湊に―・きせば」
あびこ【我孫子】
千葉県北西部、手賀沼と利根川に挟まれた市。近世、水戸街道の宿駅・河港として発達。近年は宅地造成が盛ん。東京の衛星都市化が進む。人口13万1千。
あびこ【阿毘古・阿弭古・我孫】
古代の姓かばね、または氏うじの一種。一説に、もとは官名。広く行われ、地名として残る。
あ‐ひさん【亜砒酸】
①無水亜ヒ酸、すなわち三酸化二ヒ素が水に溶けた時、溶液中に存在する弱酸。水溶液としてのみ存在。
②三酸化二ヒ素の俗称。→酸化ヒ素1
あび‐じごく【阿鼻地獄】‥ヂ‥
〔仏〕(→)「あび(阿鼻)」に同じ。
アビシニア【Abyssinia】
エチオピアの旧称。
アビシニアン【Abyssinian】
ネコの一品種。エチオピア原産。体は筋肉質で短毛。毛は1本1本が根元の方から2〜4色に分かれる。イエネコの中では最古の品種といわれる。
アビジャン【Abidjan】
コート‐ディヴォアールの南部、ギニア湾に臨む港湾都市。1983年まで首都。自動車・食品工業が盛んで、西アフリカの経済・文化の中心の一つ。人口192万9千(1988)。
アビジャン
撮影:小松義夫
 あび・す【浴びす】
〔他下二〕
⇒あびせる(下一)
あびせ‐か・ける【浴びせ掛ける】
〔他下一〕
①水などを勢いよく掛ける。「泥水を―・ける」
②激しい調子の言葉を投げ掛ける。「非難を―・ける」
あびせ‐たおし【浴せ倒し】‥タフシ
相撲の手の一つ。相手が堪こらえるのを上からのしかかって押しつぶすように倒すもの。
あび・せる【浴びせる】
〔他下一〕[文]あび・す(下二)
①湯・水などを他人や物に注ぎかける。宇治拾遺物語(一本)「念仏の僧に湯わかして―・せたてまつらんとて」
②相手に対して物事を勢いよく、あるいは続けざまにしかける。「一太刀ひとたち―・せる」「罵声を―・せる」
アビタシオン【habitation フランス】
(住宅の意)主に中高層の集合住宅の俗称。
あびだつま【阿毘達磨】
〔仏〕(梵語abhidharma)仏の教説を理論的にまとめたもの。主に部派仏教の論書を指す。三蔵の一つ。論。阿毘曇。アビダルマ。「―倶舎論」
アビトゥア【Abitur ドイツ】
ドイツの中等教育修了・大学入学資格試験。
アビラ【Avila】
スペイン中部、旧カスティリア地方の都市。イサベル女王および聖女テレサの生地。
あびらうんけん【阿毘羅吽欠】
〔仏〕(梵語a vi ra hūṃ khaṃ)密教で、胎蔵界大日如来の真言。地・水・火・風・空の五大を象徴する。この真言を唱えると一切のことが成就するという。前に「唵おん」(oṃ)を、後に「蘇婆訶そわか」(svāhā)をつけて唱えることが多い。
アビリティー【ability】
能力。才能。手腕。
アビリンピック
(abilityとOlympicとを合わせた語)身体障害者の全国技能競技大会。1972年、第1回を開いたのに始まる。
あひる【家鴨・鶩】
カモ目カモ科の家禽。マガモの飼養品種で、種類が多い。肉や卵をとり、羽毛は羽ぶとんに使用。
アヒル(1)
撮影:小宮輝之
あび・す【浴びす】
〔他下二〕
⇒あびせる(下一)
あびせ‐か・ける【浴びせ掛ける】
〔他下一〕
①水などを勢いよく掛ける。「泥水を―・ける」
②激しい調子の言葉を投げ掛ける。「非難を―・ける」
あびせ‐たおし【浴せ倒し】‥タフシ
相撲の手の一つ。相手が堪こらえるのを上からのしかかって押しつぶすように倒すもの。
あび・せる【浴びせる】
〔他下一〕[文]あび・す(下二)
①湯・水などを他人や物に注ぎかける。宇治拾遺物語(一本)「念仏の僧に湯わかして―・せたてまつらんとて」
②相手に対して物事を勢いよく、あるいは続けざまにしかける。「一太刀ひとたち―・せる」「罵声を―・せる」
アビタシオン【habitation フランス】
(住宅の意)主に中高層の集合住宅の俗称。
あびだつま【阿毘達磨】
〔仏〕(梵語abhidharma)仏の教説を理論的にまとめたもの。主に部派仏教の論書を指す。三蔵の一つ。論。阿毘曇。アビダルマ。「―倶舎論」
アビトゥア【Abitur ドイツ】
ドイツの中等教育修了・大学入学資格試験。
アビラ【Avila】
スペイン中部、旧カスティリア地方の都市。イサベル女王および聖女テレサの生地。
あびらうんけん【阿毘羅吽欠】
〔仏〕(梵語a vi ra hūṃ khaṃ)密教で、胎蔵界大日如来の真言。地・水・火・風・空の五大を象徴する。この真言を唱えると一切のことが成就するという。前に「唵おん」(oṃ)を、後に「蘇婆訶そわか」(svāhā)をつけて唱えることが多い。
アビリティー【ability】
能力。才能。手腕。
アビリンピック
(abilityとOlympicとを合わせた語)身体障害者の全国技能競技大会。1972年、第1回を開いたのに始まる。
あひる【家鴨・鶩】
カモ目カモ科の家禽。マガモの飼養品種で、種類が多い。肉や卵をとり、羽毛は羽ぶとんに使用。
アヒル(1)
撮影:小宮輝之
 アヒル(2)
撮影:小宮輝之
アヒル(2)
撮影:小宮輝之
 ペキンダック
撮影:小宮輝之
ペキンダック
撮影:小宮輝之
 ▷脚が短く尻を振る歩き方から、時にそのようなさまのあざけり語として使われた。
⇒あひる‐げた【家鴨下駄】
⇒あひる‐の‐きゃはん【家鴨の脚絆】
⇒家鴨が文庫を背負うたよう
⇒家鴨の火事見舞い
あ・びる【浴びる】
〔他上一〕[文]あ・ぶ(上二)
①湯・水などを体にかぶる。湯・水などにつかる。「シャワーを―・びる」「一風呂―・びる」
②身の回りに物をたくさん受ける。また一般に、受ける。こうむる。「日光を―・びる」「埃ほこりを―・びる」「集中砲火を―・びる」「賞賛を―・びる」
③(酒などを)大いに飲む。
▷脚が短く尻を振る歩き方から、時にそのようなさまのあざけり語として使われた。
⇒あひる‐げた【家鴨下駄】
⇒あひる‐の‐きゃはん【家鴨の脚絆】
⇒家鴨が文庫を背負うたよう
⇒家鴨の火事見舞い
あ・びる【浴びる】
〔他上一〕[文]あ・ぶ(上二)
①湯・水などを体にかぶる。湯・水などにつかる。「シャワーを―・びる」「一風呂―・びる」
②身の回りに物をたくさん受ける。また一般に、受ける。こうむる。「日光を―・びる」「埃ほこりを―・びる」「集中砲火を―・びる」「賞賛を―・びる」
③(酒などを)大いに飲む。
広辞苑に「あばた」で始まるの検索結果 1-2。