複数辞典一括検索+![]()
![]()
おう‐へい【横柄】ワウ‥🔗⭐🔉
おう‐へい【横柄】ワウ‥
(「押柄おしから」の音読「押柄おうへい」から。「大柄」とも書く)おごりたかぶって無礼なこと。そうした態度。尊大。狂言、入間川「あの様に―に申す者はござらぬ」。「―な口をきく」
⇒横柄を捌く
○横柄を捌くおうへいをさばく🔗⭐🔉
○横柄を捌くおうへいをさばく
横柄にふるまう。狂言、祢宜山伏「只今某にあうて、大柄を捌きをるが」
⇒おう‐へい【横柄】
おう‐へん【応変】
[晋書孫楚伝「変に応じ窮すること無し」]情況に応じて適宜に処置すること。「臨機―」
おう‐へん【往返・往反】ワウ‥
行きと帰り。行き来。往復。おうばん。平家物語1「京中に満ち満ちて―しけり」
おうへん‐まい【黄変米】ワウ‥
カビの寄生によって黄色に変質した有毒米。カビの種類により肝障害・腎障害・神経障害・貧血等の中毒をおこす。
おう‐ぼ【王母】ワウ‥
祖母の尊敬語。多く故人にいう。また、帝王の母。↔王父
おう‐ぼ【応募】
募集に応ずること。「コンテストに―する」
⇒おうぼ‐かかく【応募価格】
⇒おうぼしゃ‐りまわり【応募者利回り】
おう‐ほう【王法】ワウハフ
①国王の法令。
②王たるものの道。→おうぼう
おうほう【応保】
[書経]平安後期、二条天皇朝の年号。永暦2年9月4日(1161年9月24日)改元、応保3年3月29日(1163年5月4日)長寛に改元。
おう‐ほう【応報】
〔仏〕善悪の行いに応じて吉凶・禍福のむくいを受けること。果報。「因果―」
⇒おうほうけい‐しゅぎ【応報刑主義】
おう‐ほう【往訪】ワウハウ
人をたずねて行くこと。訪問。↔来訪
おう‐ほう【押妨】アフハウ
(オウボウとも)押し入って乱暴したり、不当な課税をしたりすること。平家物語1「入部の―をとどめよ」
おう‐ほう【枉法】ワウハフ
私意を以て法の正理をまげて適用すること。
おう‐ほう【黄袍】ワウハウ
無位の者の着用する袍。こうほう。
おう‐ぼう【王法】ワウボフ
仏教で国王の法令を称する語。また、仏法に対して政治をいう語。
おう‐ぼう【横暴】ワウ‥
わがままで乱暴なこと。「―な振舞い」
おうほうけい‐しゅぎ【応報刑主義】
刑罰は犯罪により生じた害悪に対する応報であると考える立場。いわゆる旧派・古典学派。↔目的刑主義
⇒おう‐ほう【応報】
おうぼ‐かかく【応募価格】
公債・社債・株式などを募集する際、引受(応募)者が実際に払い込む金額。額面価格とは異なる。
⇒おう‐ぼ【応募】
おうぼしゃ‐りまわり【応募者利回り】‥マハリ
新規発行債券を発行価格で購入し、償還まで保有した場合の利回り。→発行者利回り
⇒おう‐ぼ【応募】
おう‐ぼつ【王勃】ワウ‥
初唐の詩人。字は子安。隋末の王通の孫。詩賦に秀で、「滕王閣序」が名高い。初唐の四傑の一人。著「王子安集」。(650〜676)
お‐うま【牡馬・雄馬】ヲ‥
おすの馬。
おう‐ま【黄麻】ワウ‥
(コウマとも)
①ツナソ(綱麻)の別称。
②(唐代に、黄麻紙に詔勅を書いたからいう)詔書。勅書。
⇒おうま‐し【黄麻紙】
おうま‐が‐とき【逢魔が時】アフ‥
(オオマガトキ(大禍時)の転。禍いの起こる時刻の意)夕方の薄暗い時。たそがれ。おまんがとき。おうまどき。
おうま‐し【黄麻紙】ワウ‥
ツナソの皮を原料にして漉すいた紙。写経に多く用いた。
⇒おう‐ま【黄麻】
おうみ【近江・淡海】アフミ
(アハウミの転。淡水湖の意で琵琶湖を指す)旧国名。今の滋賀県。江州。
⇒おうみ‐あきんど【近江商人】
⇒おうみ‐おんな【近江女】
⇒おうみ‐げんじ【近江源氏】
⇒おうみげんじ‐せんじんやかた【近江源氏先陣館】
⇒おうみ‐さるがく【近江猿楽】
⇒おうみ‐しょうにん【近江商人】
⇒おうみ‐じんぐう【近江神宮】
⇒おうみ‐せいじん【近江聖人】
⇒おうみ‐の‐うみ【近江の海】
⇒おうみ‐の‐おおつ‐の‐みや【近江大津宮】
⇒おうみ‐の‐おかね【近江のお兼】
⇒おうみ‐はちまん【近江八幡】
⇒おうみ‐はっけい【近江八景】
⇒おうみ‐ぶし【近江節】
⇒おうみ‐ぶな【近江鮒】
⇒おうみ‐ぼんち【近江盆地】
⇒おうみ‐りょう【近江令】
⇒近江泥棒伊勢乞食
おうみ【淡海】アフミ
姓氏の一つ。
⇒おうみ‐の‐みふね【淡海三船】
お‐うみ【苧績み】ヲ‥
苧の繊維をよりあわせて糸にすること。
⇒おうみ‐やど【苧績宿】
おうみ‐あきんど【近江商人】アフミ‥
近江出身の商人。室町時代に東海・北陸方面と京都を結ぶ商業活動を中心に発祥し、江戸時代には伊勢商人と共に多くの成功者を出した。江商ごうしょう。
⇒おうみ【近江・淡海】
おうみ‐おんな【近江女】アフミヲンナ
能面。やや卑俗であだっぽい女面。
近江女
撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)
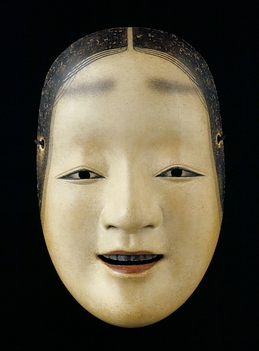 ⇒おうみ【近江・淡海】
おうみ‐げんじ【近江源氏】アフミ‥
宇多天皇から4代目の鎮守府将軍源成頼の子孫。近江国蒲生郡佐々木荘を本拠とした。佐々木高綱が最も有名。六角氏・京極氏もこの流。
⇒おうみ【近江・淡海】
おうみげんじ‐せんじんやかた【近江源氏先陣館】アフミ‥ヂン‥
浄瑠璃。近松半二ほか合作の時代物。1769年(明和6)初演。大坂冬の陣を鎌倉時代に仮託し、大坂城を近江城、真田信幸を佐々木盛綱、同幸村を高綱、千姫を時姫、秀頼を頼家に擬して脚色。8段目「盛綱陣屋」が有名。後に歌舞伎化。
⇒おうみ【近江・淡海】
おうみ‐さるがく【近江猿楽】アフミ‥
南北朝・室町時代に、近江の日吉神社に奉仕した6座の猿楽。山階・下坂・日吉の上3座、敏満寺みまじ・大森・酒人さかうどの下3座から成る。
⇒おうみ【近江・淡海】
おうみ‐しま【青海島】アヲミ‥
山口県の日本海沿岸、長門市仙崎の北方にある島。面積約15平方キロメートル。青海大橋によって本州とつながる。海食崖が発達。
青海島
撮影:佐藤 尚
⇒おうみ【近江・淡海】
おうみ‐げんじ【近江源氏】アフミ‥
宇多天皇から4代目の鎮守府将軍源成頼の子孫。近江国蒲生郡佐々木荘を本拠とした。佐々木高綱が最も有名。六角氏・京極氏もこの流。
⇒おうみ【近江・淡海】
おうみげんじ‐せんじんやかた【近江源氏先陣館】アフミ‥ヂン‥
浄瑠璃。近松半二ほか合作の時代物。1769年(明和6)初演。大坂冬の陣を鎌倉時代に仮託し、大坂城を近江城、真田信幸を佐々木盛綱、同幸村を高綱、千姫を時姫、秀頼を頼家に擬して脚色。8段目「盛綱陣屋」が有名。後に歌舞伎化。
⇒おうみ【近江・淡海】
おうみ‐さるがく【近江猿楽】アフミ‥
南北朝・室町時代に、近江の日吉神社に奉仕した6座の猿楽。山階・下坂・日吉の上3座、敏満寺みまじ・大森・酒人さかうどの下3座から成る。
⇒おうみ【近江・淡海】
おうみ‐しま【青海島】アヲミ‥
山口県の日本海沿岸、長門市仙崎の北方にある島。面積約15平方キロメートル。青海大橋によって本州とつながる。海食崖が発達。
青海島
撮影:佐藤 尚
 おうみ‐しょうにん【近江商人】アフミシヤウ‥
⇒おうみあきんど。
⇒おうみ【近江・淡海】
おうみ‐じんぐう【近江神宮】アフミ‥
滋賀県大津市にある元官幣大社。祭神は天智天皇。1940年(昭和15)の創建。
近江神宮
撮影:的場 啓
おうみ‐しょうにん【近江商人】アフミシヤウ‥
⇒おうみあきんど。
⇒おうみ【近江・淡海】
おうみ‐じんぐう【近江神宮】アフミ‥
滋賀県大津市にある元官幣大社。祭神は天智天皇。1940年(昭和15)の創建。
近江神宮
撮影:的場 啓
 ⇒おうみ【近江・淡海】
おうみ‐せいじん【近江聖人】アフミ‥
中江藤樹の敬称。
⇒おうみ【近江・淡海】
⇒おうみ【近江・淡海】
おうみ‐せいじん【近江聖人】アフミ‥
中江藤樹の敬称。
⇒おうみ【近江・淡海】
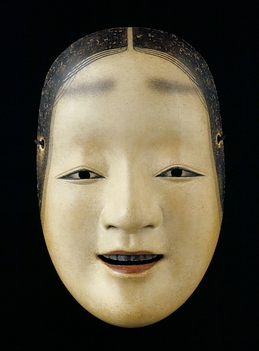 ⇒おうみ【近江・淡海】
おうみ‐げんじ【近江源氏】アフミ‥
宇多天皇から4代目の鎮守府将軍源成頼の子孫。近江国蒲生郡佐々木荘を本拠とした。佐々木高綱が最も有名。六角氏・京極氏もこの流。
⇒おうみ【近江・淡海】
おうみげんじ‐せんじんやかた【近江源氏先陣館】アフミ‥ヂン‥
浄瑠璃。近松半二ほか合作の時代物。1769年(明和6)初演。大坂冬の陣を鎌倉時代に仮託し、大坂城を近江城、真田信幸を佐々木盛綱、同幸村を高綱、千姫を時姫、秀頼を頼家に擬して脚色。8段目「盛綱陣屋」が有名。後に歌舞伎化。
⇒おうみ【近江・淡海】
おうみ‐さるがく【近江猿楽】アフミ‥
南北朝・室町時代に、近江の日吉神社に奉仕した6座の猿楽。山階・下坂・日吉の上3座、敏満寺みまじ・大森・酒人さかうどの下3座から成る。
⇒おうみ【近江・淡海】
おうみ‐しま【青海島】アヲミ‥
山口県の日本海沿岸、長門市仙崎の北方にある島。面積約15平方キロメートル。青海大橋によって本州とつながる。海食崖が発達。
青海島
撮影:佐藤 尚
⇒おうみ【近江・淡海】
おうみ‐げんじ【近江源氏】アフミ‥
宇多天皇から4代目の鎮守府将軍源成頼の子孫。近江国蒲生郡佐々木荘を本拠とした。佐々木高綱が最も有名。六角氏・京極氏もこの流。
⇒おうみ【近江・淡海】
おうみげんじ‐せんじんやかた【近江源氏先陣館】アフミ‥ヂン‥
浄瑠璃。近松半二ほか合作の時代物。1769年(明和6)初演。大坂冬の陣を鎌倉時代に仮託し、大坂城を近江城、真田信幸を佐々木盛綱、同幸村を高綱、千姫を時姫、秀頼を頼家に擬して脚色。8段目「盛綱陣屋」が有名。後に歌舞伎化。
⇒おうみ【近江・淡海】
おうみ‐さるがく【近江猿楽】アフミ‥
南北朝・室町時代に、近江の日吉神社に奉仕した6座の猿楽。山階・下坂・日吉の上3座、敏満寺みまじ・大森・酒人さかうどの下3座から成る。
⇒おうみ【近江・淡海】
おうみ‐しま【青海島】アヲミ‥
山口県の日本海沿岸、長門市仙崎の北方にある島。面積約15平方キロメートル。青海大橋によって本州とつながる。海食崖が発達。
青海島
撮影:佐藤 尚
 おうみ‐しょうにん【近江商人】アフミシヤウ‥
⇒おうみあきんど。
⇒おうみ【近江・淡海】
おうみ‐じんぐう【近江神宮】アフミ‥
滋賀県大津市にある元官幣大社。祭神は天智天皇。1940年(昭和15)の創建。
近江神宮
撮影:的場 啓
おうみ‐しょうにん【近江商人】アフミシヤウ‥
⇒おうみあきんど。
⇒おうみ【近江・淡海】
おうみ‐じんぐう【近江神宮】アフミ‥
滋賀県大津市にある元官幣大社。祭神は天智天皇。1940年(昭和15)の創建。
近江神宮
撮影:的場 啓
 ⇒おうみ【近江・淡海】
おうみ‐せいじん【近江聖人】アフミ‥
中江藤樹の敬称。
⇒おうみ【近江・淡海】
⇒おうみ【近江・淡海】
おうみ‐せいじん【近江聖人】アフミ‥
中江藤樹の敬称。
⇒おうみ【近江・淡海】
広辞苑に「横柄」で始まるの検索結果 1-2。