複数辞典一括検索+![]()
![]()
ふく‐とく【福徳】🔗⭐🔉
ふく‐とく【福徳】
①善行およびそれによって得る福利。今昔物語集1「舎利弗は大智・―ましまして、国の中に供養を受け給ふに最もよし」
②財物にめぐまれること。幸福と利益。日葡辞書「フクトクニウマレタヒト」
⇒ふくとく‐えんまん【福徳円満】
⇒福徳の三年目
ふくとく【福徳】(年号)🔗⭐🔉
ふくとく【福徳】
私年号の一つ。1489年〜92年頃に用いられた。→私年号(表)
ふくとく‐えんまん【福徳円満】‥ヱン‥🔗⭐🔉
ふくとく‐えんまん【福徳円満】‥ヱン‥
幸福・利益に恵まれて、満ち足りていること。
⇒ふく‐とく【福徳】
○福徳の三年目ふくとくのさんねんめ
めったにない幸運に出会うこと。強めて「福徳の百年目」ともいう。
⇒ふく‐とく【福徳】
○福徳の三年目ふくとくのさんねんめ🔗⭐🔉
○福徳の三年目ふくとくのさんねんめ
めったにない幸運に出会うこと。強めて「福徳の百年目」ともいう。
⇒ふく‐とく【福徳】
ふく‐どくほん【副読本】
主となる教科書にそえて、補助的に用いる学習書。
ふくと‐じる【河豚汁】
(→)「ふぐじる」に同じ。〈[季]冬〉。「あら何ともなやきのふは過て―」(芭蕉)
⇒ふくと【河豚魚】
ふく‐としん【副都心】
大都市の中心部にある在来の都心に対して、その周辺に発生した副次的中心。東京における新宿・池袋・渋谷など。
ふく‐とみ【福富】
(→)富籤とみくじに同じ。
ふくとみぞうし【福富草子】‥ザウ‥
室町時代の御伽草子。絵巻物としても伝わる。作者不詳。放屁を特技とする男が富み栄えたのを、隣家の男がまねて失敗する物羨み説話。福富長者物語。
→文献資料[福富草子]
ぶく‐なおし【服直し】‥ナホシ
喪に服していた人が、喪を果たして通常の衣服に着かえること。ぶくぬぎ。源氏物語少女「御―の程などにも」
ふくなが【福永】
姓氏の一つ。
⇒ふくなが‐たけひこ【福永武彦】
ふくなが‐たけひこ【福永武彦】
小説家。福岡県生れ。東大仏文科卒。内部世界の真実を知的抒情で織りなす作風で登場。小説「風土」「草の花」「死の島」、評論「ゴーギャンの世界」など。(1918〜1979)
福永武彦
撮影:田沼武能
 ⇒ふくなが【福永】
ふく‐にち【復日】
暦注で、その月に配する五行と、その日の五行とが重なる日。吉事に用いるときは善いことが重なるが、嫁取り・葬送などは忌むという。重喪日。
ふく‐にん【復任】
①再びもとの官職に任ぜられること。
②父母の喪にあって官を解かれたものが、喪が明けて原職に復すること。↔服解ぶくげ
ぶく‐ぬぎ【服脱ぎ】
(→)「ぶくなおし」に同じ。
ふく‐の‐かみ【福の神】
福を授けるという神。ふくじん。七福神。「―が舞い込む」
ふくのかみ【福の神】
狂言。脇狂言。福の神が供えの御酒みきに満足して、富貴になる心得を教える。
福の神
撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)
⇒ふくなが【福永】
ふく‐にち【復日】
暦注で、その月に配する五行と、その日の五行とが重なる日。吉事に用いるときは善いことが重なるが、嫁取り・葬送などは忌むという。重喪日。
ふく‐にん【復任】
①再びもとの官職に任ぜられること。
②父母の喪にあって官を解かれたものが、喪が明けて原職に復すること。↔服解ぶくげ
ぶく‐ぬぎ【服脱ぎ】
(→)「ぶくなおし」に同じ。
ふく‐の‐かみ【福の神】
福を授けるという神。ふくじん。七福神。「―が舞い込む」
ふくのかみ【福の神】
狂言。脇狂言。福の神が供えの御酒みきに満足して、富貴になる心得を教える。
福の神
撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)
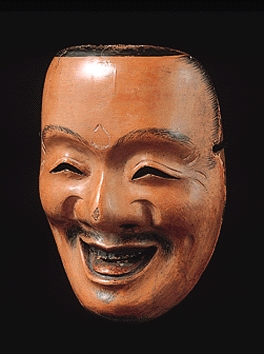 ふくの‐じま【福野縞】
富山県西部、南砺市福野付近で製する縞木綿織物。文政(1818〜1830)年間に始まるという。
ふく‐ば【副馬】
必要に応じて主とする馬に代用するため、添えてひくうま。
ふく‐はい【伏拝】
ひれ伏しておがむこと。
ふく‐はい【復配】
配当を復活すること。
ふく‐はい【腹背】
①はらとせ。前面と背面。まえうしろ。「―に敵を受ける」
②心の中で背くこと。「面従―」
ふく‐はい【覆敗】
くつがえりやぶれること。
ふくの‐じま【福野縞】
富山県西部、南砺市福野付近で製する縞木綿織物。文政(1818〜1830)年間に始まるという。
ふく‐ば【副馬】
必要に応じて主とする馬に代用するため、添えてひくうま。
ふく‐はい【伏拝】
ひれ伏しておがむこと。
ふく‐はい【復配】
配当を復活すること。
ふく‐はい【腹背】
①はらとせ。前面と背面。まえうしろ。「―に敵を受ける」
②心の中で背くこと。「面従―」
ふく‐はい【覆敗】
くつがえりやぶれること。
 ⇒ふくなが【福永】
ふく‐にち【復日】
暦注で、その月に配する五行と、その日の五行とが重なる日。吉事に用いるときは善いことが重なるが、嫁取り・葬送などは忌むという。重喪日。
ふく‐にん【復任】
①再びもとの官職に任ぜられること。
②父母の喪にあって官を解かれたものが、喪が明けて原職に復すること。↔服解ぶくげ
ぶく‐ぬぎ【服脱ぎ】
(→)「ぶくなおし」に同じ。
ふく‐の‐かみ【福の神】
福を授けるという神。ふくじん。七福神。「―が舞い込む」
ふくのかみ【福の神】
狂言。脇狂言。福の神が供えの御酒みきに満足して、富貴になる心得を教える。
福の神
撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)
⇒ふくなが【福永】
ふく‐にち【復日】
暦注で、その月に配する五行と、その日の五行とが重なる日。吉事に用いるときは善いことが重なるが、嫁取り・葬送などは忌むという。重喪日。
ふく‐にん【復任】
①再びもとの官職に任ぜられること。
②父母の喪にあって官を解かれたものが、喪が明けて原職に復すること。↔服解ぶくげ
ぶく‐ぬぎ【服脱ぎ】
(→)「ぶくなおし」に同じ。
ふく‐の‐かみ【福の神】
福を授けるという神。ふくじん。七福神。「―が舞い込む」
ふくのかみ【福の神】
狂言。脇狂言。福の神が供えの御酒みきに満足して、富貴になる心得を教える。
福の神
撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)
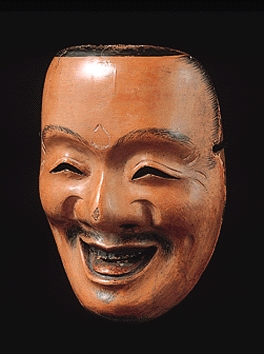 ふくの‐じま【福野縞】
富山県西部、南砺市福野付近で製する縞木綿織物。文政(1818〜1830)年間に始まるという。
ふく‐ば【副馬】
必要に応じて主とする馬に代用するため、添えてひくうま。
ふく‐はい【伏拝】
ひれ伏しておがむこと。
ふく‐はい【復配】
配当を復活すること。
ふく‐はい【腹背】
①はらとせ。前面と背面。まえうしろ。「―に敵を受ける」
②心の中で背くこと。「面従―」
ふく‐はい【覆敗】
くつがえりやぶれること。
ふくの‐じま【福野縞】
富山県西部、南砺市福野付近で製する縞木綿織物。文政(1818〜1830)年間に始まるという。
ふく‐ば【副馬】
必要に応じて主とする馬に代用するため、添えてひくうま。
ふく‐はい【伏拝】
ひれ伏しておがむこと。
ふく‐はい【復配】
配当を復活すること。
ふく‐はい【腹背】
①はらとせ。前面と背面。まえうしろ。「―に敵を受ける」
②心の中で背くこと。「面従―」
ふく‐はい【覆敗】
くつがえりやぶれること。
広辞苑に「福徳」で始まるの検索結果 1-4。