複数辞典一括検索+![]()
![]()
うす【薄】🔗⭐🔉
うす【薄】
①(ある語に冠して)
㋐厚さ・濃度・密度の小さいこと。「―紙」「―紫」「―味」「―曇り」
㋑きわだってではないが、何となくその感じがして好ましくないこと。「―ぎたない」
②(ある語の後に付けて)少ししかないこと。「品―」「望み―」「気乗り―」
うす‐あお【薄襖】‥アヲ🔗⭐🔉
うす‐あお【薄襖】‥アヲ
薄い地質で仕立てた狩衣かりぎぬ。
うす・い【薄い・淡い】🔗⭐🔉
うす・い【薄い・淡い】
〔形〕[文]うす・し(ク)
①《薄》厚みが少ない。万葉集6「吾背子が着ける衣きぬ―・し佐保風はいたくな吹きそ家に至るまで」。「―・いふとん」「皮を―・くむく」
②物の密度・濃度が少ない。
㋐液体・霧などの密度(濃度)が少ない。風雅和歌集秋「霧―・き秋の日影の山の端にほのぼの見ゆるかりの一つら」。「コーヒーを―・くいれる」
㋑物の色合いで、その色けが少ない。あわい。古今和歌集秋「さほ山のははその色は―・けれど秋は深くもなりにけるかな」。「―・い墨」
㋒まばらである。炭俵「平地の寺の―・き藪垣」(芭蕉)。「髪が―・い」
㋓物の味(からさ・あまさ)が濃くない。淡泊だ。「―・い醤油しょうゆ」
③物事の程度が強く(深く・烈しく)ない。量が少ない。
㋐(愛情・交際・関心などが)深くない。万葉集20「薄氷うすらびの―・き心をわが思はなくに」。「馴染みが―・い」「情が―・い」
㋑浅い。軽微だ。徒然草「この世の濁りも―・く、仏道をつとむる心もまめやかならざらん」。「―・く化粧する」
㋒光が強くない。あわい。風雅和歌集秋「鳴く声も高き梢のせみのはの―・き日影にあきぞちかづく」
㋓弱い。つたない。浄瑠璃、曾我扇八景「運の―・い御人や」。駿台雑話「武の心がけ―・き故に候」
㋔乏しい。貧しい。狂言、伯母が酒「私の在所は、―・う広い所でござるが」
㋕利益・効果・可能性などが少ない。「もうけが―・い」「合格の見込みは―・い」
うす‐うす【薄薄】🔗⭐🔉
うす‐うす【薄薄】
〔副〕
①ほのかに。かすかに。好色一代女6「人顔の―見えし夕暮を」
②ぼんやりとではあるが分かるさま。「―察していた」
うす‐がき【薄柿】🔗⭐🔉
うす‐がき【薄柿】
柿渋で染めたうすい渋色。薄柿色。浮世風呂4「―の団七じまのかたびら」
Munsell color system: 2R7.5/5.5
うす‐がすみ【薄霞】🔗⭐🔉
うす‐がすみ【薄霞】
薄くたなびいているかすみ。〈[季]春〉。野ざらし紀行「春なれや名もなき山の―」
うす‐かね【薄金】🔗⭐🔉
うす‐かね【薄金】
鎧よろいの札さねに薄い鉄を使用したもの。源氏八領中のものは著名。太平記16「義貞は―といふ甲よろいに」
うす‐がみ【薄紙】🔗⭐🔉
うす‐がみ【薄紙】
薄い紙。貫之集「桜の花を―に包みて」
⇒薄紙を剥ぐよう
○薄紙を剥ぐよううすがみをはぐよう
病気が少しずつよくなるさまの形容。
⇒うす‐がみ【薄紙】
○臼から杵うすからきね
(臼は女、杵は男を象徴する。女から男に働きかけるのは逆であるの意で)事が逆であるさまにいう。
⇒うす【臼・舂・碓】
うす‐ぎたな・い【薄穢い・薄汚い】🔗⭐🔉
うす‐ぎたな・い【薄穢い・薄汚い】
〔形〕
なんとなくきたない。「―・い下着」「―・いやり方」
うす‐ぎぬ【薄衣】🔗⭐🔉
うす‐ぎぬ【薄衣】
地の薄いきもの。薄ごろも。
うす‐ぎぬ【薄帛・薄絹】🔗⭐🔉
うす‐ぎぬ【薄帛・薄絹】
地の薄い絹織物。紗しゃ・絽ろなど。
うす‐きみわる・い【薄気味悪い】🔗⭐🔉
うす‐きみわる・い【薄気味悪い】
〔形〕
なんとなく気味がわるい。「暗くて―・い部屋だ」
うす‐くち【薄口】🔗⭐🔉
うす‐くち【薄口】
①吸物や煮物などの料理の味付けが薄めのもの。「―に煮る」
②薄口醤油の略。↔濃口こいくち。
③陶器などで、薄手に仕上げてあるもの。「―の茶碗」
⇒うすくち‐しょうゆ【薄口醤油】
うすくち‐しょうゆ【薄口醤油】‥シヤウ‥🔗⭐🔉
うすくち‐しょうゆ【薄口醤油】‥シヤウ‥
色が薄い醤油。味・香りともにあっさりしているが、塩分は多く含む。関西で多く使用。↔濃口醤油
⇒うす‐くち【薄口】
うすくも【薄雲】🔗⭐🔉
うすくも【薄雲】
平家重代の鎧よろいの一つ。
うす‐ぐも【薄雲】🔗⭐🔉
うす‐ぐも【薄雲】
①薄くかかった雲。
薄雲
撮影:高橋健司
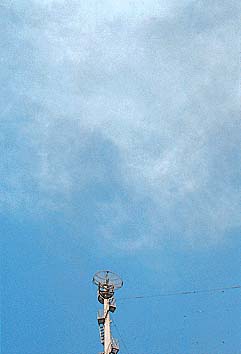 ②源氏物語の巻名。藤壺の死、および冷泉帝が光源氏を実父と知ることが描かれる。
⇒うすぐも‐の‐にょういん【薄雲の女院】
②源氏物語の巻名。藤壺の死、および冷泉帝が光源氏を実父と知ることが描かれる。
⇒うすぐも‐の‐にょういん【薄雲の女院】
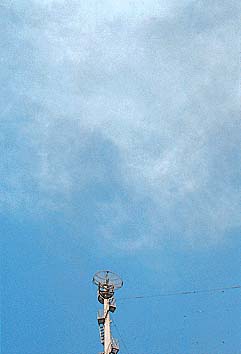 ②源氏物語の巻名。藤壺の死、および冷泉帝が光源氏を実父と知ることが描かれる。
⇒うすぐも‐の‐にょういん【薄雲の女院】
②源氏物語の巻名。藤壺の死、および冷泉帝が光源氏を実父と知ることが描かれる。
⇒うすぐも‐の‐にょういん【薄雲の女院】
うすぐも‐の‐にょういん【薄雲の女院】‥ヰン🔗⭐🔉
うすぐも‐の‐にょういん【薄雲の女院】‥ヰン
源氏物語中の女性藤壺のこと。「薄雲」の巻にその崩御のことを記すからいう。
⇒うす‐ぐも【薄雲】
うす‐ぐら・い【薄暗い】🔗⭐🔉
うす‐ぐら・い【薄暗い】
〔形〕[文]うすぐら・し(ク)
光が薄くて、まっくらではないが、暗い。ほのぐらい。「―・い部屋」
うす‐くらがり【薄暗がり】🔗⭐🔉
うす‐くらがり【薄暗がり】
少し暗いこと。また、その場所。「植込みの―に隠れる」
うす‐くりげ【薄栗毛】🔗⭐🔉
うす‐くりげ【薄栗毛】
馬の毛色の、黄色を帯びた栗毛で、たてがみの黒いもの。
うす‐くれない【薄紅】‥クレナヰ🔗⭐🔉
うす‐くれない【薄紅】‥クレナヰ
薄いくれない色。淡紅。
うす‐ぐろ・い【薄黒い】🔗⭐🔉
うす‐ぐろ・い【薄黒い】
〔形〕
少しばかり黒い。黒ずんでいる。
うす‐げしょう【薄化粧】‥シヤウ🔗⭐🔉
うす‐げしょう【薄化粧】‥シヤウ
あっさりと化粧すること。「―して外出する」「雪で―した山」↔厚化粧
うす‐こうばい【薄紅梅】🔗⭐🔉
うす‐こうばい【薄紅梅】
①紅梅の花の色の薄いもの。
②紅梅色の薄いもの。枕草子50「馬は…―の毛にて」
Munsell color system: 5RP7/8
③襲かさねの色目。紅梅襲の表裏とも薄いもの。
うす‐ざいしき【薄彩色】🔗⭐🔉
うす‐ざいしき【薄彩色】
薄く施した彩色。墨絵の上に藍・代赭たいしゃなどで薄く着色したもの。〈日葡辞書〉
うす‐ざくら【薄桜】🔗⭐🔉
うす‐ざくら【薄桜】
①桜の花の色のうすいもの。
②襲かさねの色目。表は白、裏は紅で、一重梅ひとえうめと異名同色。(蛙抄)
⇒うすざくら‐もえぎ【薄桜萌葱】
うすざくら‐もえぎ【薄桜萌葱】🔗⭐🔉
うすざくら‐もえぎ【薄桜萌葱】
襲かさねの色目。山科流では、表は薄青、裏も同じ、または薄紅。また、表は青、裏は蘇芳すおうとも。
⇒うす‐ざくら【薄桜】
うす‐さむ・い【薄寒い】🔗⭐🔉
うす‐さむ・い【薄寒い】
〔形〕[文]うすさむ・し(ク)
(主として明治期に用いた語)なんとなく寒い。少し寒く感じられる。うそさむい。
うす・し【薄し・淡し】🔗⭐🔉
うす・し【薄し・淡し】
〔形ク〕
⇒うすい
うす‐じお【薄塩】‥ジホ🔗⭐🔉
うす‐じお【薄塩】‥ジホ
塩加減の薄いこと。また、薄い塩加減に調理してあること。甘塩。日葡辞書「ウスジヲノウヲ」
うす‐したじ【薄下地】‥ヂ🔗⭐🔉
うす‐したじ【薄下地】‥ヂ
塩加減を薄くした醤油。上方料理に用いる。浮世風呂2「―で吸物ぢやさかい」
うす‐ず・む【薄ずむ】🔗⭐🔉
うす‐ず・む【薄ずむ】
〔自四〕
薄く黒ずんで見える。薄くかすんで見える。夫木和歌抄13「朝霧のそことしるしはなけれども―・み渡る三輪の杉むら」
うす‐だみ【薄彩み】🔗⭐🔉
うす‐だみ【薄彩み】
薄くいろどること。日葡辞書「ウスダミノエ」
うす‐だ・む【薄彩む】🔗⭐🔉
うす‐だ・む【薄彩む】
〔他四〕
薄くいろどる。正治百首「―・みわたる夕霞かな」
うす‐づきよ【薄月夜】🔗⭐🔉
うす‐づきよ【薄月夜】
月の光のほのかにさす夜。おぼろづきよ。
うす‐づくり【薄造り・薄作り】🔗⭐🔉
うす‐づくり【薄造り・薄作り】
刺身で、ごく薄くそぎ切りにしたもの。フグ・ヒラメなどに適する。
うすっ‐ぺら【薄っぺら】🔗⭐🔉
うすっ‐ぺら【薄っぺら】
薄くぺらぺらしていること。転じて、物の見方や人柄が奥深くないこと。浅薄。「―な用紙」「―な人間」
うす‐どろ【薄どろ】🔗⭐🔉
うす‐どろ【薄どろ】
歌舞伎囃子の一つ。どろどろを薄く(弱く)打つもの。幽霊の出る時などに用いる。→どろどろ2
うす‐どろどろ【薄どろどろ】🔗⭐🔉
うす‐どろどろ【薄どろどろ】
(→)「うすどろ」に同じ。歌舞伎、東海道四谷怪談ト書「この時、―たて、障子へタラタラと血かかる途端に」
うすば‐かげろう【薄羽蜉蝣】‥カゲロフ🔗⭐🔉
うすば‐かげろう【薄羽蜉蝣】‥カゲロフ
アミメカゲロウ目ウスバカゲロウ科の昆虫の総称。また、その一種。一見トンボに似る。翅は透明、細かな脈がある。開張約8センチメートル。幼虫は「ありじごく」。〈[季]夏〉
ウスバカゲロウ
提供:ネイチャー・プロダクション


うすば‐きとんぼ【薄羽黄蜻蛉】🔗⭐🔉
うすば‐きとんぼ【薄羽黄蜻蛉】
トンボ科の一種。中形。体は黄色。毎年、南方から渡って来る。5月頃南九州に現れ、夏の終り頃北海道に達する。道や畑の上を群れて飛ぶ。
ウスバキトンボ
提供:ネイチャー・プロダクション


うす‐はた【薄繒・薄機】🔗⭐🔉
うす‐はた【薄繒・薄機】
(→)「うすもの」1に同じ。推古紀「五色の綾―を用ゐる」
うす‐はないろ【薄花色】🔗⭐🔉
うす‐はないろ【薄花色】
薄いはなだ色。
Munsell color system: 2.5PB5.5/5.5
うす‐はなごころ【薄花心】🔗⭐🔉
うす‐はなごころ【薄花心】
情が浅くて移りやすい心。続千載和歌集恋「月草の―いかがたのまむ」
うす‐はなごろも【薄花衣】🔗⭐🔉
うす‐はなごろも【薄花衣】
薄花色に染めた衣服。
うす‐はなざくら【薄花桜】🔗⭐🔉
うす‐はなざくら【薄花桜】
①花の色の薄い桜。うすざくら。
②襲かさねの色目。表は白、裏は紅。
③うすはないろ。
Munsell color system: 6PB5/9.5
うす‐はなぞめ【薄花染】🔗⭐🔉
うす‐はなぞめ【薄花染】
薄いはなだ色に染めたもの。新千載和歌集恋「紅の―の色に出づらん」
うす‐びたい【薄額】‥ビタヒ🔗⭐🔉
うす‐びたい【薄額】‥ビタヒ
前額部の縁へりを低くつくった冠。近世のもの。↔厚額
うす‐べった・い【薄べったい】🔗⭐🔉
うす‐べった・い【薄べったい】
〔形〕
うすくてひらたい。中身が少ない感じである。
うす‐べに【薄紅】🔗⭐🔉
うす‐べに【薄紅】
①薄いべにいろ。また、その顔料。
②薄くつけた化粧用の紅べに。「―をさす」
うす‐べり【薄縁】🔗⭐🔉
うす‐べり【薄縁】
裏をつけ、縁をつけた筵むしろで、家の中や縁側に敷くもの。
うす‐ぼんやり【薄ぼんやり】🔗⭐🔉
うす‐ぼんやり【薄ぼんやり】
①あまりはっきりしないさま。少しぼやけたさま。「―と霞んで見える」
②(→)薄鈍うすのろに同じ。
うすま・る【薄まる】🔗⭐🔉
うすま・る【薄まる】
〔自五〕
色・味などがうすくなる。
うす・める【薄める】🔗⭐🔉
うす・める【薄める】
〔他下一〕[文]うす・む(下二)
色・味などをうすくする。濃度・密度を低くする。「水で―・める」
うす‐もとで【薄元手】🔗⭐🔉
うす‐もとで【薄元手】
ごくわずかな資本。浄瑠璃、心中天の網島「漆漉しほどな―で」
うす‐やみ【薄闇】🔗⭐🔉
うす‐やみ【薄闇】
完全な闇ではなく、何とか物の見分けが付く程度の暗さ。
うす‐よご・れる【薄汚れる】🔗⭐🔉
うす‐よご・れる【薄汚れる】
〔自下一〕
どことなく汚くなる。「―・れた顔」
うす‐ら【薄ら】🔗⭐🔉
うす‐ら【薄ら】
厚み・色合い・程度などが、うすいさま。名詞・形容詞の上に付いて、「うすい」「なんとなく」「少しばかり」の意味をそえる。
⇒うすら‐ごろも【薄ら衣】
⇒うすら‐さむ・い【薄ら寒い】
⇒うすら‐ひ【薄ら氷】
⇒うすら‐び【薄ら日・薄ら陽】
⇒うすら‐わらい【薄ら笑い】
うす‐らか【薄らか】🔗⭐🔉
うす‐らか【薄らか】
見た目に薄い感じであるさま。うっすらとしているさま。淡泊なさま。
うす‐ら・ぐ【薄らぐ】🔗⭐🔉
うす‐ら・ぐ【薄らぐ】
〔自五〕
薄くなる。軽くなる。減ってゆく。源氏物語賢木「あざやかなる方の覚えも―・ぐものなり」。「痛みが―・ぐ」「記憶が―・ぐ」
うすら‐ごろも【薄ら衣】🔗⭐🔉
うすら‐ごろも【薄ら衣】
薄い衣服。うすぎぬ。
⇒うす‐ら【薄ら】
うすら‐さむ・い【薄ら寒い】🔗⭐🔉
うすら‐さむ・い【薄ら寒い】
〔形〕[文]うすらさむ・し(ク)
なんとなく寒い。夏の末から秋の初めにかけてのほのかに感じられる寒さなどにいう。うそさむい。
⇒うす‐ら【薄ら】
うすら‐ひ【薄ら氷】🔗⭐🔉
うすら‐ひ【薄ら氷】
(古くはウスラビ)薄く張った氷。特に、春さきの氷。うすごおり。うすらい。〈[季]春〉
⇒うす‐ら【薄ら】
うすら‐び【薄ら日・薄ら陽】🔗⭐🔉
うすら‐び【薄ら日・薄ら陽】
うすく弱々しい日ざし。
⇒うす‐ら【薄ら】
うすら‐わらい【薄ら笑い】‥ワラヒ🔗⭐🔉
うすら‐わらい【薄ら笑い】‥ワラヒ
相手を見くだしたような感じで、かすかに笑うこと。うすわらい。「―を浮かべる」
⇒うす‐ら【薄ら】
うすれ‐び【薄れ日】🔗⭐🔉
うすれ‐び【薄れ日】
弱くなった日ざし。うすび。
うす・れる【薄れる】🔗⭐🔉
うす・れる【薄れる】
〔自下一〕[文]うす・る(下二)
薄くなる。うすらぐ。衰える。軽くなる。和泉式部集「たづのたちどの氷―・れて」。「色が―・れる」「興味が―・れる」
うす‐ろ・ぐ【薄ろぐ】🔗⭐🔉
うす‐ろ・ぐ【薄ろぐ】
〔自四〕
(→)「うすらぐ」に同じ。
うっすら【薄ら】🔗⭐🔉
うっすら【薄ら】
〔副〕
量や程度がわずかで薄いさま。かすかに。ほのかに。「―雪が積もる」「―と覚えている」
うっすり【薄り】🔗⭐🔉
うっすり【薄り】
〔副〕
「うっすら」に同じ。
すすき【薄・芒】🔗⭐🔉
すすき【薄・芒】
①むらがって生える草の総称。万葉集7「妹等がりわが行く道のしの―」
②イネ科の多年草。土手・荒地などにしばしば大群落を作る。毎年、宿根から新芽を生じ、高さ2メートルに達する。秋、花穂は十数枝を分かち、黄褐色を呈する。小穂の下部に絹糸様の白毛がある。「尾花」と称し、秋の七草の一つ。茎葉は屋根を葺くのに用いる。シマススキなど、観賞用の園芸品種もある。袖振草。〈[季]秋〉。万葉集10「さ男鹿の入野の―初尾花」
すすき
 ススキ
撮影:関戸 勇
ススキ
撮影:関戸 勇
 ススキ(花)
撮影:関戸 勇
ススキ(花)
撮影:関戸 勇
 ⇒すすき‐の‐き【薄の木】
⇒すすき‐の‐まる【薄の丸】
⇒すすき‐みみずく【薄木
⇒すすき‐の‐き【薄の木】
⇒すすき‐の‐まる【薄の丸】
⇒すすき‐みみずく【薄木 】
⇒薄の穂にも怖じる
】
⇒薄の穂にも怖じる
 ススキ
撮影:関戸 勇
ススキ
撮影:関戸 勇
 ススキ(花)
撮影:関戸 勇
ススキ(花)
撮影:関戸 勇
 ⇒すすき‐の‐き【薄の木】
⇒すすき‐の‐まる【薄の丸】
⇒すすき‐みみずく【薄木
⇒すすき‐の‐き【薄の木】
⇒すすき‐の‐まる【薄の丸】
⇒すすき‐みみずく【薄木 】
⇒薄の穂にも怖じる
】
⇒薄の穂にも怖じる
すすき‐の‐き【薄の木】🔗⭐🔉
○薄の穂にも怖じるすすきのほにもおじる🔗⭐🔉
○薄の穂にも怖じるすすきのほにもおじる
心が落ち着かず、わずかな事にもおじけ恐れるさま。「落武者は―」
⇒すすき【薄・芒】
すすき‐の‐まる【薄の丸】
紋所の名。薄を輪わとして穂と葉を内側に描いたもの。
⇒すすき【薄・芒】
すずき‐はるのぶ【鈴木春信】
江戸中期の浮世絵師。江戸の人。絵暦えごよみの制作を契機に多色刷木版画の技術を開発、錦絵を完成。見立ての趣向をきかせた抒情的な美人画に独自の境地を開く。(1725〜1770)
⇒すずき【鈴木】
すずき‐ぶんじ【鈴木文治】‥ヂ
労働運動家。宮城県生れ。東大卒業後、友愛会(のち日本労働総同盟)を創立、労働組合運動に尽力。社会民衆党代議士。(1885〜1946)
⇒すずき【鈴木】
すずきぼうちょう【鱸庖丁】‥バウチヤウ
狂言。伯父に鯉をおくる約束をした甥が、鯉は獺うそが食ったといってだます。伯父はその仕返しに、甥に鱸を馳走するといって料理の話を長々とした末、鱸は北条(「庖丁」の音通、虚言の意)が食ったという。
すずき‐ぼくし【鈴木牧之】
江戸後期の文人。越後の人。本名、儀三治。牧之は俳号。著「北越雪譜」など。(1770〜1842)
⇒すずき【鈴木】
すずき‐まさひさ【鈴木正久】
日本基督教団牧師。千葉県生れ。バルト研究を推進。1967年、「第二次大戦下における日本基督教団の責任についての告白」を教団議長名で発表、戦争責任を認めた。(1912〜1969)
⇒すずき【鈴木】
すずき‐みえきち【鈴木三重吉】‥ミヘ‥
作家。広島県生れ。東大英文科出身で夏目漱石門下。短編「千鳥」により文壇に出た。ほかに「小鳥の巣」「桑の実」など、抒情的傾向が強い。のち童話作家として活動、雑誌「赤い鳥」を創刊して児童文学に貢献。(1882〜1936)
鈴木三重吉
提供:岩波書店
 ⇒すずき【鈴木】
すすき‐みみずく【薄木
⇒すずき【鈴木】
すすき‐みみずく【薄木 】‥ヅク
東京都豊島区の雑司ヶ谷にある鬼子母神境内で売られる、ススキで作ったミミズクの玩具。
⇒すすき【薄・芒】
すずき‐もさぶろう【鈴木茂三郎】‥ラウ
政治家。愛知県生れ。早大卒。労農派の理論家。第二次大戦後、日本社会党結成に参加。党内左派の中心となり、1951〜60年党委員長。(1893〜1970)
鈴木茂三郎
撮影:田村 茂
】‥ヅク
東京都豊島区の雑司ヶ谷にある鬼子母神境内で売られる、ススキで作ったミミズクの玩具。
⇒すすき【薄・芒】
すずき‐もさぶろう【鈴木茂三郎】‥ラウ
政治家。愛知県生れ。早大卒。労農派の理論家。第二次大戦後、日本社会党結成に参加。党内左派の中心となり、1951〜60年党委員長。(1893〜1970)
鈴木茂三郎
撮影:田村 茂
 ⇒すずき【鈴木】
すずき‐もんど【鈴木主水】
江戸後期の武士。また、主水を主人公とする歌舞伎の通称。鈴木主水と江戸内藤新宿橋本屋の宿場女郎白糸との情死事件は、幕末期の流行歌謡に歌われて流布。これに鏡山の筋を合わせた「隅田川対高賀紋すみだがわついのかがもん」(3世桜田治助作)以後、同材を扱った歌舞伎脚本が作られた。( 〜1801)
⇒すずき【鈴木】
すずき‐よねわか【寿々木米若】
浪曲家。本名、藤田松平。新潟県生れ。当り芸「佐渡情話」は浪曲に民謡を取り入れ、最初の浪曲トーキー映画にもなった。(1899〜1979)
すす・ぐ【濯ぐ・洒ぐ・滌ぐ・漱ぐ】
〔他五〕
(古くは清音)
①水で洗い清める。万葉集16「机の島の小螺しただみを…早川に洗ひ―・き」。源氏物語橋姫「所せき人の御移香にて、えも―・ぎ捨てぬぞあまりなるや」。「洗濯物を―・ぐ」
②《漱》口をゆすぐ。うがいする。〈日本霊異記中訓釈〉。日葡辞書「クチヲススグ」
③けがれをきよめる。源氏物語槿「よろづに罪かろげなりし御有様ながら、この一つ事にてぞこの世のにごりを―・ぎ給はざらむ」。日葡辞書「ミミヲススイダ」
④(「雪ぐ」とも書く)汚名を除き払う。源氏物語夕霧「かの一夜ばかりの御うらみ文を、とらへ所にかこちて、えしも―・ぎ果て給はじと頼もしかりけり」。「恥を―・ぐ」
すず‐くしろ【鈴釧】
銅の腕輪の周縁に小鈴をつけたもの。古墳時代後期の遺物。
すず‐ぐち【鈴口】
①大名の屋敷などで、表と奥との境に赤い組緒のついた鈴を掛け、鈴をひき鳴らして用事を通ずる所。→鈴の間。
②亀頭の異称。
すず‐くら【篶倉】
篠竹すずたけで葺いた倉。散木奇歌集「―にふるきほしひぞつきもせぬ」
ずず‐ぐり【数珠繰り】
(→)「数珠子ずずご釣り」に同じ。
すずくれ‐ぐさ【涼暮草】
松の雅称。
すずくれ‐づき【涼暮月】
陰暦6月の異称。
すすけ【煤け】
すすけること。煤けて黒くなること。「―紙」
すす・ける【煤ける】
〔自下一〕[文]すす・く(下二)
①煤に染みて黒くなる。宇津保物語蔵開下「火桶の―・けたるに火わづかにおこしたるに」
②古ぼけて煤色になる。汚れて黒くなる。源氏物語末摘花「白き衣のいひしらず―・けたるに」
すず‐こ
(→)筋子すじこに同じ。
ずず‐ご【数珠子】
①ジュズダマの別称。
②数珠子釣りに用いる、ミミズなどをいくつも糸に通した餌。輪にして釣竿の先に結ぶ。
⇒ずずご‐づり【数珠子釣り】
ずずご‐づり【数珠子釣り】
数珠子2を用いてウナギ・ハゼなどを釣ること。ずずぐり。ずずぶし。千つなぎ。
⇒ずず‐ご【数珠子】
すす‐ごもり【煤籠り】
すすはきの時、病人・老人などが別室に移りこもること。〈[季]冬〉
すずこん‐しき【錫婚式】
(tin wedding)結婚10年記念祝賀の式。→結婚記念日(表)
すず‐さいこ【鈴柴胡】
ガガイモ科イケマ属の多年草。アジアの温帯に広く分布し、日本の山野にも自生する。高さ数十センチメートル。葉は対生し披針ひしん状線形。夏、葉腋に花序を出し、淡黄緑色の小花を多数つける。古名、ヒメカガミ。
すす‐さだけ【煤さ竹】
(→)煤男すすおとこに同じ。
すすし
(山陰地方で)(→)「すずき」に同じ。
すずし【生絹】
生糸きいとの織物で、練っていないもの。軽く薄くて紗しゃに似る。源氏物語空蝉「―なるひとへ」。日葡辞書「ススシ」↔練絹ねりぎぬ
すず‐し【錫師】
錫・鉛で茶壺・鉢などの器具を造る職人。
すずし・い【涼しい】
〔形〕[文]すず・し(シク)
①ほどよく冷やかである。暑苦しくなくすがすがしい。ひんやりして気持よい。〈[季]夏〉。万葉集10「秋風は―・しくなりぬ」。源氏物語若紫「すこし―・しき水の流れ」。「―・い風が吹く」
②物のさまがさわやかである。すっきりしている。澄んで清い。源氏物語常夏「秋の夜の月影―・しき程」。源氏物語蓬生「遣水かき払ひ、前栽のもとだちも―・しうしなしなどして」。日葡辞書「スズシュウ(立派に礼儀正しく)マウス」。好色一代男2「目のうち―・しく、おもくさ繁く見えて、どこともなうこのもし」。「―・い目もと」
③心がさわやかである。煩いがない。さっぱりしている。源氏物語若菜下「身を捨てむも惜しかるまじき齢どもになりにたるを、やうやう―・しく思ひ侍る」
④いさぎよい。太平記25「事の賾おぎろ、実に思ひ切つたる体かなと、先づ―・しくぞ見えたりける」
⑤厳としたさまである。きっぱりしている。恨之介「いづれも―・しく申されけるは、さも頼もしく聞えけり」
⑥潔白である。無関係である。浄瑠璃、淀鯉出世滝徳「恐らく―・しい此の新七に無い難つけて暇出させ」
⇒涼しい顔
⇒涼しき方
⇒涼しき道
⇒すずき【鈴木】
すずき‐もんど【鈴木主水】
江戸後期の武士。また、主水を主人公とする歌舞伎の通称。鈴木主水と江戸内藤新宿橋本屋の宿場女郎白糸との情死事件は、幕末期の流行歌謡に歌われて流布。これに鏡山の筋を合わせた「隅田川対高賀紋すみだがわついのかがもん」(3世桜田治助作)以後、同材を扱った歌舞伎脚本が作られた。( 〜1801)
⇒すずき【鈴木】
すずき‐よねわか【寿々木米若】
浪曲家。本名、藤田松平。新潟県生れ。当り芸「佐渡情話」は浪曲に民謡を取り入れ、最初の浪曲トーキー映画にもなった。(1899〜1979)
すす・ぐ【濯ぐ・洒ぐ・滌ぐ・漱ぐ】
〔他五〕
(古くは清音)
①水で洗い清める。万葉集16「机の島の小螺しただみを…早川に洗ひ―・き」。源氏物語橋姫「所せき人の御移香にて、えも―・ぎ捨てぬぞあまりなるや」。「洗濯物を―・ぐ」
②《漱》口をゆすぐ。うがいする。〈日本霊異記中訓釈〉。日葡辞書「クチヲススグ」
③けがれをきよめる。源氏物語槿「よろづに罪かろげなりし御有様ながら、この一つ事にてぞこの世のにごりを―・ぎ給はざらむ」。日葡辞書「ミミヲススイダ」
④(「雪ぐ」とも書く)汚名を除き払う。源氏物語夕霧「かの一夜ばかりの御うらみ文を、とらへ所にかこちて、えしも―・ぎ果て給はじと頼もしかりけり」。「恥を―・ぐ」
すず‐くしろ【鈴釧】
銅の腕輪の周縁に小鈴をつけたもの。古墳時代後期の遺物。
すず‐ぐち【鈴口】
①大名の屋敷などで、表と奥との境に赤い組緒のついた鈴を掛け、鈴をひき鳴らして用事を通ずる所。→鈴の間。
②亀頭の異称。
すず‐くら【篶倉】
篠竹すずたけで葺いた倉。散木奇歌集「―にふるきほしひぞつきもせぬ」
ずず‐ぐり【数珠繰り】
(→)「数珠子ずずご釣り」に同じ。
すずくれ‐ぐさ【涼暮草】
松の雅称。
すずくれ‐づき【涼暮月】
陰暦6月の異称。
すすけ【煤け】
すすけること。煤けて黒くなること。「―紙」
すす・ける【煤ける】
〔自下一〕[文]すす・く(下二)
①煤に染みて黒くなる。宇津保物語蔵開下「火桶の―・けたるに火わづかにおこしたるに」
②古ぼけて煤色になる。汚れて黒くなる。源氏物語末摘花「白き衣のいひしらず―・けたるに」
すず‐こ
(→)筋子すじこに同じ。
ずず‐ご【数珠子】
①ジュズダマの別称。
②数珠子釣りに用いる、ミミズなどをいくつも糸に通した餌。輪にして釣竿の先に結ぶ。
⇒ずずご‐づり【数珠子釣り】
ずずご‐づり【数珠子釣り】
数珠子2を用いてウナギ・ハゼなどを釣ること。ずずぐり。ずずぶし。千つなぎ。
⇒ずず‐ご【数珠子】
すす‐ごもり【煤籠り】
すすはきの時、病人・老人などが別室に移りこもること。〈[季]冬〉
すずこん‐しき【錫婚式】
(tin wedding)結婚10年記念祝賀の式。→結婚記念日(表)
すず‐さいこ【鈴柴胡】
ガガイモ科イケマ属の多年草。アジアの温帯に広く分布し、日本の山野にも自生する。高さ数十センチメートル。葉は対生し披針ひしん状線形。夏、葉腋に花序を出し、淡黄緑色の小花を多数つける。古名、ヒメカガミ。
すす‐さだけ【煤さ竹】
(→)煤男すすおとこに同じ。
すすし
(山陰地方で)(→)「すずき」に同じ。
すずし【生絹】
生糸きいとの織物で、練っていないもの。軽く薄くて紗しゃに似る。源氏物語空蝉「―なるひとへ」。日葡辞書「ススシ」↔練絹ねりぎぬ
すず‐し【錫師】
錫・鉛で茶壺・鉢などの器具を造る職人。
すずし・い【涼しい】
〔形〕[文]すず・し(シク)
①ほどよく冷やかである。暑苦しくなくすがすがしい。ひんやりして気持よい。〈[季]夏〉。万葉集10「秋風は―・しくなりぬ」。源氏物語若紫「すこし―・しき水の流れ」。「―・い風が吹く」
②物のさまがさわやかである。すっきりしている。澄んで清い。源氏物語常夏「秋の夜の月影―・しき程」。源氏物語蓬生「遣水かき払ひ、前栽のもとだちも―・しうしなしなどして」。日葡辞書「スズシュウ(立派に礼儀正しく)マウス」。好色一代男2「目のうち―・しく、おもくさ繁く見えて、どこともなうこのもし」。「―・い目もと」
③心がさわやかである。煩いがない。さっぱりしている。源氏物語若菜下「身を捨てむも惜しかるまじき齢どもになりにたるを、やうやう―・しく思ひ侍る」
④いさぎよい。太平記25「事の賾おぎろ、実に思ひ切つたる体かなと、先づ―・しくぞ見えたりける」
⑤厳としたさまである。きっぱりしている。恨之介「いづれも―・しく申されけるは、さも頼もしく聞えけり」
⑥潔白である。無関係である。浄瑠璃、淀鯉出世滝徳「恐らく―・しい此の新七に無い難つけて暇出させ」
⇒涼しい顔
⇒涼しき方
⇒涼しき道
 ⇒すずき【鈴木】
すすき‐みみずく【薄木
⇒すずき【鈴木】
すすき‐みみずく【薄木 】‥ヅク
東京都豊島区の雑司ヶ谷にある鬼子母神境内で売られる、ススキで作ったミミズクの玩具。
⇒すすき【薄・芒】
すずき‐もさぶろう【鈴木茂三郎】‥ラウ
政治家。愛知県生れ。早大卒。労農派の理論家。第二次大戦後、日本社会党結成に参加。党内左派の中心となり、1951〜60年党委員長。(1893〜1970)
鈴木茂三郎
撮影:田村 茂
】‥ヅク
東京都豊島区の雑司ヶ谷にある鬼子母神境内で売られる、ススキで作ったミミズクの玩具。
⇒すすき【薄・芒】
すずき‐もさぶろう【鈴木茂三郎】‥ラウ
政治家。愛知県生れ。早大卒。労農派の理論家。第二次大戦後、日本社会党結成に参加。党内左派の中心となり、1951〜60年党委員長。(1893〜1970)
鈴木茂三郎
撮影:田村 茂
 ⇒すずき【鈴木】
すずき‐もんど【鈴木主水】
江戸後期の武士。また、主水を主人公とする歌舞伎の通称。鈴木主水と江戸内藤新宿橋本屋の宿場女郎白糸との情死事件は、幕末期の流行歌謡に歌われて流布。これに鏡山の筋を合わせた「隅田川対高賀紋すみだがわついのかがもん」(3世桜田治助作)以後、同材を扱った歌舞伎脚本が作られた。( 〜1801)
⇒すずき【鈴木】
すずき‐よねわか【寿々木米若】
浪曲家。本名、藤田松平。新潟県生れ。当り芸「佐渡情話」は浪曲に民謡を取り入れ、最初の浪曲トーキー映画にもなった。(1899〜1979)
すす・ぐ【濯ぐ・洒ぐ・滌ぐ・漱ぐ】
〔他五〕
(古くは清音)
①水で洗い清める。万葉集16「机の島の小螺しただみを…早川に洗ひ―・き」。源氏物語橋姫「所せき人の御移香にて、えも―・ぎ捨てぬぞあまりなるや」。「洗濯物を―・ぐ」
②《漱》口をゆすぐ。うがいする。〈日本霊異記中訓釈〉。日葡辞書「クチヲススグ」
③けがれをきよめる。源氏物語槿「よろづに罪かろげなりし御有様ながら、この一つ事にてぞこの世のにごりを―・ぎ給はざらむ」。日葡辞書「ミミヲススイダ」
④(「雪ぐ」とも書く)汚名を除き払う。源氏物語夕霧「かの一夜ばかりの御うらみ文を、とらへ所にかこちて、えしも―・ぎ果て給はじと頼もしかりけり」。「恥を―・ぐ」
すず‐くしろ【鈴釧】
銅の腕輪の周縁に小鈴をつけたもの。古墳時代後期の遺物。
すず‐ぐち【鈴口】
①大名の屋敷などで、表と奥との境に赤い組緒のついた鈴を掛け、鈴をひき鳴らして用事を通ずる所。→鈴の間。
②亀頭の異称。
すず‐くら【篶倉】
篠竹すずたけで葺いた倉。散木奇歌集「―にふるきほしひぞつきもせぬ」
ずず‐ぐり【数珠繰り】
(→)「数珠子ずずご釣り」に同じ。
すずくれ‐ぐさ【涼暮草】
松の雅称。
すずくれ‐づき【涼暮月】
陰暦6月の異称。
すすけ【煤け】
すすけること。煤けて黒くなること。「―紙」
すす・ける【煤ける】
〔自下一〕[文]すす・く(下二)
①煤に染みて黒くなる。宇津保物語蔵開下「火桶の―・けたるに火わづかにおこしたるに」
②古ぼけて煤色になる。汚れて黒くなる。源氏物語末摘花「白き衣のいひしらず―・けたるに」
すず‐こ
(→)筋子すじこに同じ。
ずず‐ご【数珠子】
①ジュズダマの別称。
②数珠子釣りに用いる、ミミズなどをいくつも糸に通した餌。輪にして釣竿の先に結ぶ。
⇒ずずご‐づり【数珠子釣り】
ずずご‐づり【数珠子釣り】
数珠子2を用いてウナギ・ハゼなどを釣ること。ずずぐり。ずずぶし。千つなぎ。
⇒ずず‐ご【数珠子】
すす‐ごもり【煤籠り】
すすはきの時、病人・老人などが別室に移りこもること。〈[季]冬〉
すずこん‐しき【錫婚式】
(tin wedding)結婚10年記念祝賀の式。→結婚記念日(表)
すず‐さいこ【鈴柴胡】
ガガイモ科イケマ属の多年草。アジアの温帯に広く分布し、日本の山野にも自生する。高さ数十センチメートル。葉は対生し披針ひしん状線形。夏、葉腋に花序を出し、淡黄緑色の小花を多数つける。古名、ヒメカガミ。
すす‐さだけ【煤さ竹】
(→)煤男すすおとこに同じ。
すすし
(山陰地方で)(→)「すずき」に同じ。
すずし【生絹】
生糸きいとの織物で、練っていないもの。軽く薄くて紗しゃに似る。源氏物語空蝉「―なるひとへ」。日葡辞書「ススシ」↔練絹ねりぎぬ
すず‐し【錫師】
錫・鉛で茶壺・鉢などの器具を造る職人。
すずし・い【涼しい】
〔形〕[文]すず・し(シク)
①ほどよく冷やかである。暑苦しくなくすがすがしい。ひんやりして気持よい。〈[季]夏〉。万葉集10「秋風は―・しくなりぬ」。源氏物語若紫「すこし―・しき水の流れ」。「―・い風が吹く」
②物のさまがさわやかである。すっきりしている。澄んで清い。源氏物語常夏「秋の夜の月影―・しき程」。源氏物語蓬生「遣水かき払ひ、前栽のもとだちも―・しうしなしなどして」。日葡辞書「スズシュウ(立派に礼儀正しく)マウス」。好色一代男2「目のうち―・しく、おもくさ繁く見えて、どこともなうこのもし」。「―・い目もと」
③心がさわやかである。煩いがない。さっぱりしている。源氏物語若菜下「身を捨てむも惜しかるまじき齢どもになりにたるを、やうやう―・しく思ひ侍る」
④いさぎよい。太平記25「事の賾おぎろ、実に思ひ切つたる体かなと、先づ―・しくぞ見えたりける」
⑤厳としたさまである。きっぱりしている。恨之介「いづれも―・しく申されけるは、さも頼もしく聞えけり」
⑥潔白である。無関係である。浄瑠璃、淀鯉出世滝徳「恐らく―・しい此の新七に無い難つけて暇出させ」
⇒涼しい顔
⇒涼しき方
⇒涼しき道
⇒すずき【鈴木】
すずき‐もんど【鈴木主水】
江戸後期の武士。また、主水を主人公とする歌舞伎の通称。鈴木主水と江戸内藤新宿橋本屋の宿場女郎白糸との情死事件は、幕末期の流行歌謡に歌われて流布。これに鏡山の筋を合わせた「隅田川対高賀紋すみだがわついのかがもん」(3世桜田治助作)以後、同材を扱った歌舞伎脚本が作られた。( 〜1801)
⇒すずき【鈴木】
すずき‐よねわか【寿々木米若】
浪曲家。本名、藤田松平。新潟県生れ。当り芸「佐渡情話」は浪曲に民謡を取り入れ、最初の浪曲トーキー映画にもなった。(1899〜1979)
すす・ぐ【濯ぐ・洒ぐ・滌ぐ・漱ぐ】
〔他五〕
(古くは清音)
①水で洗い清める。万葉集16「机の島の小螺しただみを…早川に洗ひ―・き」。源氏物語橋姫「所せき人の御移香にて、えも―・ぎ捨てぬぞあまりなるや」。「洗濯物を―・ぐ」
②《漱》口をゆすぐ。うがいする。〈日本霊異記中訓釈〉。日葡辞書「クチヲススグ」
③けがれをきよめる。源氏物語槿「よろづに罪かろげなりし御有様ながら、この一つ事にてぞこの世のにごりを―・ぎ給はざらむ」。日葡辞書「ミミヲススイダ」
④(「雪ぐ」とも書く)汚名を除き払う。源氏物語夕霧「かの一夜ばかりの御うらみ文を、とらへ所にかこちて、えしも―・ぎ果て給はじと頼もしかりけり」。「恥を―・ぐ」
すず‐くしろ【鈴釧】
銅の腕輪の周縁に小鈴をつけたもの。古墳時代後期の遺物。
すず‐ぐち【鈴口】
①大名の屋敷などで、表と奥との境に赤い組緒のついた鈴を掛け、鈴をひき鳴らして用事を通ずる所。→鈴の間。
②亀頭の異称。
すず‐くら【篶倉】
篠竹すずたけで葺いた倉。散木奇歌集「―にふるきほしひぞつきもせぬ」
ずず‐ぐり【数珠繰り】
(→)「数珠子ずずご釣り」に同じ。
すずくれ‐ぐさ【涼暮草】
松の雅称。
すずくれ‐づき【涼暮月】
陰暦6月の異称。
すすけ【煤け】
すすけること。煤けて黒くなること。「―紙」
すす・ける【煤ける】
〔自下一〕[文]すす・く(下二)
①煤に染みて黒くなる。宇津保物語蔵開下「火桶の―・けたるに火わづかにおこしたるに」
②古ぼけて煤色になる。汚れて黒くなる。源氏物語末摘花「白き衣のいひしらず―・けたるに」
すず‐こ
(→)筋子すじこに同じ。
ずず‐ご【数珠子】
①ジュズダマの別称。
②数珠子釣りに用いる、ミミズなどをいくつも糸に通した餌。輪にして釣竿の先に結ぶ。
⇒ずずご‐づり【数珠子釣り】
ずずご‐づり【数珠子釣り】
数珠子2を用いてウナギ・ハゼなどを釣ること。ずずぐり。ずずぶし。千つなぎ。
⇒ずず‐ご【数珠子】
すす‐ごもり【煤籠り】
すすはきの時、病人・老人などが別室に移りこもること。〈[季]冬〉
すずこん‐しき【錫婚式】
(tin wedding)結婚10年記念祝賀の式。→結婚記念日(表)
すず‐さいこ【鈴柴胡】
ガガイモ科イケマ属の多年草。アジアの温帯に広く分布し、日本の山野にも自生する。高さ数十センチメートル。葉は対生し披針ひしん状線形。夏、葉腋に花序を出し、淡黄緑色の小花を多数つける。古名、ヒメカガミ。
すす‐さだけ【煤さ竹】
(→)煤男すすおとこに同じ。
すすし
(山陰地方で)(→)「すずき」に同じ。
すずし【生絹】
生糸きいとの織物で、練っていないもの。軽く薄くて紗しゃに似る。源氏物語空蝉「―なるひとへ」。日葡辞書「ススシ」↔練絹ねりぎぬ
すず‐し【錫師】
錫・鉛で茶壺・鉢などの器具を造る職人。
すずし・い【涼しい】
〔形〕[文]すず・し(シク)
①ほどよく冷やかである。暑苦しくなくすがすがしい。ひんやりして気持よい。〈[季]夏〉。万葉集10「秋風は―・しくなりぬ」。源氏物語若紫「すこし―・しき水の流れ」。「―・い風が吹く」
②物のさまがさわやかである。すっきりしている。澄んで清い。源氏物語常夏「秋の夜の月影―・しき程」。源氏物語蓬生「遣水かき払ひ、前栽のもとだちも―・しうしなしなどして」。日葡辞書「スズシュウ(立派に礼儀正しく)マウス」。好色一代男2「目のうち―・しく、おもくさ繁く見えて、どこともなうこのもし」。「―・い目もと」
③心がさわやかである。煩いがない。さっぱりしている。源氏物語若菜下「身を捨てむも惜しかるまじき齢どもになりにたるを、やうやう―・しく思ひ侍る」
④いさぎよい。太平記25「事の賾おぎろ、実に思ひ切つたる体かなと、先づ―・しくぞ見えたりける」
⑤厳としたさまである。きっぱりしている。恨之介「いづれも―・しく申されけるは、さも頼もしく聞えけり」
⑥潔白である。無関係である。浄瑠璃、淀鯉出世滝徳「恐らく―・しい此の新七に無い難つけて暇出させ」
⇒涼しい顔
⇒涼しき方
⇒涼しき道
すすき‐の‐まる【薄の丸】🔗⭐🔉
すすき‐の‐まる【薄の丸】
紋所の名。薄を輪わとして穂と葉を内側に描いたもの。
⇒すすき【薄・芒】
ばがぼん【薄伽梵・婆伽梵】🔗⭐🔉
ばがぼん【薄伽梵・婆伽梵】
(梵語bhagavat 福徳ある者、聖なる者の意。世尊と訳す)
①仏の尊称。特に、釈迦牟尼しゃかむにの尊称。婆伽婆ばぎゃば。栄華物語疑「―うせて人住まずなり」
②インドで、神仏・貴人の尊称。
はく‐うん【薄運】🔗⭐🔉
はく‐うん【薄運】
運にめぐまれないこと。ふしあわせ。不運。薄福。
はく‐うん【薄雲】🔗⭐🔉
はく‐うん【薄雲】
うすい雲。うすぐも。
はく‐ぎ【薄儀】🔗⭐🔉
はく‐ぎ【薄儀】
謝礼の謙譲語。わずかな礼物の意。薄謝。
はく‐ぐう【薄遇】🔗⭐🔉
はく‐ぐう【薄遇】
冷淡なもてなし。不親切な待遇。冷遇。
はく‐さい【薄才】🔗⭐🔉
はく‐さい【薄才】
才知のうすく少ないこと。また、自己の才能を謙遜していう語。菲才ひさい。
はく‐し【薄志】🔗⭐🔉
はく‐し【薄志】
①薄弱な志。軽薄な志。
②わずかな謝礼。寸志。「―を包む」
⇒はくし‐じゃっこう【薄志弱行】
はくし‐じゃっこう【薄志弱行】‥ジヤクカウ🔗⭐🔉
はくし‐じゃっこう【薄志弱行】‥ジヤクカウ
意志が薄弱で、事を断行する気力を欠くこと。
⇒はく‐し【薄志】
はっ‐か【薄荷】ハク‥🔗⭐🔉
はっ‐か【薄荷】ハク‥
①シソ科の多年草。山地に自生するが、香料植物として北海道などで大規模に栽培。夏・秋に葉腋に淡紅紫色の唇形花を群生。茎・葉共に薄荷油の原料となり、香料および矯味矯臭薬となる。漢方で消炎・鎮痛・健胃剤とする。メグサ。ミント。〈日葡辞書〉
はっか
 ②広くは、1のほか薄荷脳を含む同属植物数種の総称。セイヨウハッカ(英語名ペパーミント)、オランダハッカ(英語名スペアミント)がある。
③薄荷精・薄荷脳の略。
⇒はっか‐すい【薄荷水】
⇒はっか‐せい【薄荷精】
⇒はっか‐とう【薄荷糖】
⇒はっか‐のう【薄荷脳】
⇒はっか‐パイプ【薄荷パイプ】
⇒はっか‐ゆ【薄荷油】
②広くは、1のほか薄荷脳を含む同属植物数種の総称。セイヨウハッカ(英語名ペパーミント)、オランダハッカ(英語名スペアミント)がある。
③薄荷精・薄荷脳の略。
⇒はっか‐すい【薄荷水】
⇒はっか‐せい【薄荷精】
⇒はっか‐とう【薄荷糖】
⇒はっか‐のう【薄荷脳】
⇒はっか‐パイプ【薄荷パイプ】
⇒はっか‐ゆ【薄荷油】
 ②広くは、1のほか薄荷脳を含む同属植物数種の総称。セイヨウハッカ(英語名ペパーミント)、オランダハッカ(英語名スペアミント)がある。
③薄荷精・薄荷脳の略。
⇒はっか‐すい【薄荷水】
⇒はっか‐せい【薄荷精】
⇒はっか‐とう【薄荷糖】
⇒はっか‐のう【薄荷脳】
⇒はっか‐パイプ【薄荷パイプ】
⇒はっか‐ゆ【薄荷油】
②広くは、1のほか薄荷脳を含む同属植物数種の総称。セイヨウハッカ(英語名ペパーミント)、オランダハッカ(英語名スペアミント)がある。
③薄荷精・薄荷脳の略。
⇒はっか‐すい【薄荷水】
⇒はっか‐せい【薄荷精】
⇒はっか‐とう【薄荷糖】
⇒はっか‐のう【薄荷脳】
⇒はっか‐パイプ【薄荷パイプ】
⇒はっか‐ゆ【薄荷油】
はっか‐すい【薄荷水】ハク‥🔗⭐🔉
はっか‐すい【薄荷水】ハク‥
①粗く刻んだ薄荷の葉を蒸留してとった液。
②薄荷油に水を加えたもの。矯味矯臭薬や健胃・駆風・含嗽がんそう・罨法あんぽうに用いる。
⇒はっ‐か【薄荷】
はっか‐せい【薄荷精】ハク‥🔗⭐🔉
はっか‐せい【薄荷精】ハク‥
薄荷油とアルコールとを混合した無色透明の液。健胃・駆風剤。
⇒はっ‐か【薄荷】
はっか‐とう【薄荷糖】ハク‥タウ🔗⭐🔉
はっか‐とう【薄荷糖】ハク‥タウ
砂糖を煮固め、薄荷の香味を加えて製した菓子。
⇒はっ‐か【薄荷】
はっか‐のう【薄荷脳】ハク‥ナウ🔗⭐🔉
はっか‐のう【薄荷脳】ハク‥ナウ
薄荷油の固形成分。無色針状の結晶で、浸透性の香気がある。薬用。メントール。
⇒はっ‐か【薄荷】
はっか‐パイプ【薄荷パイプ】ハク‥🔗⭐🔉
はっか‐パイプ【薄荷パイプ】ハク‥
巻タバコのパイプに似たものに薄荷をつめたもの。吸って香りを味わう。
⇒はっ‐か【薄荷】
はっか‐ゆ【薄荷油】ハク‥🔗⭐🔉
はっか‐ゆ【薄荷油】ハク‥
薄荷の葉を乾燥・水蒸気蒸留して得た精油。主成分はメントール。無色透明または帯黄色。揮発性で芳香と辛味がある。清涼剤・香料となる。
⇒はっ‐か【薄荷】
はっ‐きゅう【薄給】ハクキフ🔗⭐🔉
はっ‐きゅう【薄給】ハクキフ
手薄い俸給。すくない給料。「―に甘んずる」
はっ‐こう【薄行】ハクカウ🔗⭐🔉
はっ‐こう【薄行】ハクカウ
軽薄なおこない。
はっ‐こう【薄幸・薄倖】ハクカウ🔗⭐🔉
はっ‐こう【薄幸・薄倖】ハクカウ
ふしあわせ。不運。不幸。「―の少女」
[漢]薄🔗⭐🔉
薄 字形
 筆順
筆順
 〔艹部13画/16画/常用/3986・4776〕
[
〔艹部13画/16画/常用/3986・4776〕
[ ] 字形
] 字形
 〔艹部13画/16画〕
〔音〕ハク(漢)
〔訓〕うすい・うすめる・うすまる・うすらぐ・うすれる・せまる・すすき
[意味]
①うすい。(対)厚。「薄氷・希薄」
②少ない。とぼしい。わずか。「薄給・薄謝・薄幸・薄情」
③あさはかである。「軽薄・浮薄」
④(へだたりを)うすくする。せまる。近づく。(同)迫。「薄暮・肉薄」
⑤草の名。すすき(=芒)。尾花。秋の七草の一つ。
[解字]
形声。「艹」+音符「溥」(=水が平らに広がる)。草木がすきまなく生え広がる意。転じて、すきまがつまる、うすい、などの意となる。
[下ツキ
希薄・軽薄・厚薄・剋薄・酷薄・浅薄・肉薄・菲薄・浮薄
〔艹部13画/16画〕
〔音〕ハク(漢)
〔訓〕うすい・うすめる・うすまる・うすらぐ・うすれる・せまる・すすき
[意味]
①うすい。(対)厚。「薄氷・希薄」
②少ない。とぼしい。わずか。「薄給・薄謝・薄幸・薄情」
③あさはかである。「軽薄・浮薄」
④(へだたりを)うすくする。せまる。近づく。(同)迫。「薄暮・肉薄」
⑤草の名。すすき(=芒)。尾花。秋の七草の一つ。
[解字]
形声。「艹」+音符「溥」(=水が平らに広がる)。草木がすきまなく生え広がる意。転じて、すきまがつまる、うすい、などの意となる。
[下ツキ
希薄・軽薄・厚薄・剋薄・酷薄・浅薄・肉薄・菲薄・浮薄
 筆順
筆順
 〔艹部13画/16画/常用/3986・4776〕
[
〔艹部13画/16画/常用/3986・4776〕
[ ] 字形
] 字形
 〔艹部13画/16画〕
〔音〕ハク(漢)
〔訓〕うすい・うすめる・うすまる・うすらぐ・うすれる・せまる・すすき
[意味]
①うすい。(対)厚。「薄氷・希薄」
②少ない。とぼしい。わずか。「薄給・薄謝・薄幸・薄情」
③あさはかである。「軽薄・浮薄」
④(へだたりを)うすくする。せまる。近づく。(同)迫。「薄暮・肉薄」
⑤草の名。すすき(=芒)。尾花。秋の七草の一つ。
[解字]
形声。「艹」+音符「溥」(=水が平らに広がる)。草木がすきまなく生え広がる意。転じて、すきまがつまる、うすい、などの意となる。
[下ツキ
希薄・軽薄・厚薄・剋薄・酷薄・浅薄・肉薄・菲薄・浮薄
〔艹部13画/16画〕
〔音〕ハク(漢)
〔訓〕うすい・うすめる・うすまる・うすらぐ・うすれる・せまる・すすき
[意味]
①うすい。(対)厚。「薄氷・希薄」
②少ない。とぼしい。わずか。「薄給・薄謝・薄幸・薄情」
③あさはかである。「軽薄・浮薄」
④(へだたりを)うすくする。せまる。近づく。(同)迫。「薄暮・肉薄」
⑤草の名。すすき(=芒)。尾花。秋の七草の一つ。
[解字]
形声。「艹」+音符「溥」(=水が平らに広がる)。草木がすきまなく生え広がる意。転じて、すきまがつまる、うすい、などの意となる。
[下ツキ
希薄・軽薄・厚薄・剋薄・酷薄・浅薄・肉薄・菲薄・浮薄
広辞苑に「薄」で始まるの検索結果 1-94。もっと読み込む