複数辞典一括検索+![]()
![]()
おどろ・く【驚く・愕く・駭く】🔗⭐🔉
おどろ・く【驚く・愕く・駭く】
〔自五〕
①はっとして目がさめる。万葉集4「夢いめの逢ひは苦しかりけり―・きてかき探れども手にも触れねば」。今昔物語集12「抱きて寝たるに―・きて児ちごを見るになし」
②注意・関心を呼びおこされる。はっとして気がつく。古今和歌集秋「秋来ぬと目にはさやかに見えねども風の音にぞ―・かれぬる」。源氏物語紅葉賀「こちやと宣へど―・かず」
③意外な事にあって心がさわぐ。びっくりする。また、感嘆する。伊勢物語「とみのこととて御文あり。―・きて見れば」。「事故の知らせに―・く」「演奏のすばらしさに―・いた」
⇒驚くなかれ
○驚くなかれおどろくなかれ
驚いてはいけないよ。これから驚くべきことを言うという前置きとして使う語。「―二人は実の兄弟だった」
⇒おどろ・く【驚く・愕く・駭く】
○驚くなかれおどろくなかれ🔗⭐🔉
○驚くなかれおどろくなかれ
驚いてはいけないよ。これから驚くべきことを言うという前置きとして使う語。「―二人は実の兄弟だった」
⇒おどろ・く【驚く・愕く・駭く】
おどろ・し【驚し】
〔形シク〕
驚くべきさまである。おどろおどろし。続日本紀34「―・しき事行ことわざなせそ」
おどろ‐の‐みち【棘路】
(「棘路きょくろ」の訓読)
①草木の乱れ茂っている道。
②公卿くぎょうの異称。
⇒おどろ【棘・荊棘】
おとわ【音羽】‥ハ
東京都文京区の一地区。護国寺の門前から江戸川橋に至る地域。
おとわ‐のぶこ【乙羽信子】‥ハ‥
女優。本名、新藤信子。鳥取県生れ。宝塚歌劇団を経て映画界入り。代表作「裸の島」など。(1924〜1994)
おとわ‐や【音羽屋】‥ハ‥
歌舞伎俳優尾上菊五郎とその一門の屋号。
おとわ‐やき【音羽焼】‥ハ‥
京都東山の音羽付近で作られた京焼。江戸前期の創始とされ、茶器などを焼き江戸中期まで続いた。
おとわ‐やま【音羽山】‥ハ‥
①京都市山科区と大津市との境をなす山。北稜は逢坂山に続く。山中に音羽川が発し北流。(歌枕)
②京都東山三十六峰の一つ。西側の山腹に清水寺があり、音羽の滝がかかる。紅葉の名所。清水寺の山号によるか。
おなヲナ
(ヲンナの約)娘。妻にもいう。狂言、眉目よし「―を呼べ」
おなあヲナア
(→)「おな」に同じ。「をなあさま」はその敬語表現。
オナー【honour】
(名誉・名声の意)ゴルフで、ティー‐ショットを先に打つ権利、またそれを持つ人。前ホールで最少打数の人がなる。
お‐ないぎ【御内儀】
他人の妻の尊敬語。近世前期、多く京都で町家の妻に用いたが、一般にも使われた。
おない‐どし【同い年】
(オナジトシの音便)年齢が同じであること。同年。
お‐なか【御中】
①(女房詞)食事。
②(女房詞)綿わた。やわやわ。
③(主として女性や子供が使う)腹。「―がすいた」「―をこわす」
④室町時代の武家の奥向きに奉仕する女中の役名。御中臈おちゅうろう。
⇒おなか‐いれ【御中入れ】
⇒おなか‐がしら【御中頭】
⇒おなか‐ごころ【御中心】
お‐なが【尾長】ヲ‥
①尾の長いこと。
②スズメ目カラス科の鳥。頭は黒色、背は灰色、腹は灰白色。翼と尾の大部分は美しい灰青色。尾は長い。低山帯や人家近くの樹林に営巣、昆虫や果実を食べる。群棲し、やかましい声で鳴く。東アジアとイベリア半島に分布。日本では本州東半にのみ分布するが、かつては西日本にもいた。〈饅頭屋本節用集〉
おなが
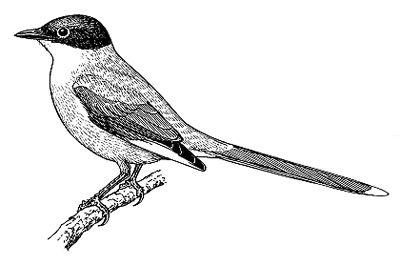 オナガ
提供:OPO
オナガ
提供:OPO
 →鳴声
提供:NHKサービスセンター
⇒おなが‐ざめ【尾長鮫】
⇒おなが‐ざる【尾長猿】
⇒おなが‐どり【尾長鳥】
おなか‐いれ【御中入れ】
(女房詞)
①昼食。
②綿入れ。
⇒お‐なか【御中】
おなか‐がしら【御中頭】
御中臈おちゅうろうの頭。
⇒お‐なか【御中】
おなか‐ごころ【御中心】
はらぐあい。
⇒お‐なか【御中】
おなが‐ざめ【尾長鮫】ヲ‥
オナガザメ科の海産軟骨魚の総称。サメ類の中では尾びれが最も長く、ネズミの尾に似ているためにネズミブカともいう。全長約4メートル。南日本に産。マオナガ・ニタリ・ハチワレなど。
⇒お‐なが【尾長】
おなが‐ざる【尾長猿】ヲ‥
サル目(霊長類)オナガザル科(狭鼻猿類)オナガザル属の哺乳類の総称。約20種があり、熱帯アフリカに分布。サバンナモンキー・ダイアナモンキーなど。
⇒お‐なが【尾長】
おなが‐どり【尾長鳥】ヲ‥
(→)長尾鶏ちょうびけいに同じ。
⇒お‐なが【尾長】
お‐ながれ【御流れ】
①主君や貴人から賜る盃の酒。また、酒席で敬意を表すために相手の盃を受けて飲む酒。狂言、松楪まつゆずりは「前世下された事は無けれども、―を下さるる」。「―頂戴」
②目上の人から不用となって与えられる物。お下がり。
③計画した事が中止となること。「集会が―になる」
お‐なぐさみ【御慰み】
その場のなぐさみになること。おたのしみ。皮肉の意でも用いる。「首尾よくいきましたら―」「とんだ―」
おな‐ご【女子】ヲナ‥
(ヲンナゴの約)
①女の子供。女児。狂言、粟田口「下京に妹が居りまらする。是にも―が一ぴきござあるが是も姪の内でござあらうずるか」
②女。婦人。浄瑠璃、堀川波鼓「―の道を教へ込み」
③女中。はしため。好色一代男7「高嶋屋の―によびかけられて」
⇒おなご‐おうぎ【女子扇】
⇒おなご‐ぎ【女子気】
⇒おなご‐しゅう【女子衆】
⇒おなご‐じょたい【女子所帯】
⇒おなご‐だけ【女子竹】
⇒おなご‐だて【女子達・女侠】
⇒おなご‐なおし【女子直し】
⇒おなご‐みず【女子水】
⇒おなご‐むすび【女子結び】
⇒おなご‐らし・い【女子らしい】
⇒おなご‐わざ【女子業】
おなご‐おうぎ【女子扇】ヲナ‥アフギ
女持ちの小さな扇。
⇒おな‐ご【女子】
おなご‐ぎ【女子気】ヲナ‥
女の心。女のせまい心。女のしとやかな心。
⇒おな‐ご【女子】
おなご‐しゅう【女子衆】ヲナ‥
(「おなごしゅ」「おなごし」とも)
①女たち。
②女中。
⇒おな‐ご【女子】
おなご‐じょたい【女子所帯】ヲナ‥
女だけで男のいない所帯。
⇒おな‐ご【女子】
おなご‐だけ【女子竹】ヲナ‥
メダケの別称。
⇒おな‐ご【女子】
おなご‐だて【女子達・女侠】ヲナ‥
女の侠客きょうかく。
⇒おな‐ご【女子】
おなご‐なおし【女子直し】ヲナ‥ナホシ
下女を引き上げて嫁とすること。
⇒おな‐ご【女子】
おなご‐みず【女子水】ヲナ‥ミヅ
軟水。↔男水おとこみず。
⇒おな‐ご【女子】
おなご‐むすび【女子結び】ヲナ‥
(→)「おんなむすび」に同じ。
⇒おな‐ご【女子】
おなご‐らし・い【女子らしい】ヲナ‥
〔形〕
①女としてふさわしいさまである。しとやかである。
②めめしい。男でありながら女のようである。日葡辞書「ヲナゴラシイヒト」
⇒おな‐ご【女子】
おなご‐わざ【女子業】ヲナ‥
女のする仕事。女にふさわしい仕事。
⇒おな‐ご【女子】
お‐なさけ【御情け】
哀れみ。思いやり。また、寵愛ちょうあい。「―で単位をもらう」「―を受ける」
おなじ【同じ】
(形容詞「おなじ」が体言化したもの)
[一]〔名〕
質・状態・程度などが同一であること。差異がないこと。「前に買った柄がらと―だ」「君と背丈が―になった」
[二]〔連体〕
同一の。同類の。同程度の。「―名前」「―成績」「彼の家とは―方向だ」「前回と―人を指名する」
[三]〔副〕
(「なら」と呼応して)どうせ。どっちみち。「―買うならもう少しましなものを買いなさい」
⇒おなじ‐まいまい【同蝸牛】
おな・じ【同じ】
〔形シク〕
体言に続く場合(殊に和文脈において)は「おなじき」よりも「おなじ」の形が多く用いられる。口語では「同じい」という形であるが、現在はほとんど使われず、連用形「おなじく」が残る。
①(二つ以上のものが質あるいは条件に)かわりがない。ちがいがない。差がない。万葉集15「君がむた行かましものを―・じこと後れて居おれど良きこともなし」。源氏物語桐壺「―・じほどそれより下らうの更衣たち」。「右に―・じく厳罰に処す」
②ひとつものである。同一である。万葉集18「あしひきの山は無くもが月見れば―・じき里を心隔てつ」。平家物語11「殿を―・じうして住み給へ」→おなじ(連体)
⇒同じ穴の貉
⇒同じ釜の飯を食う
⇒同じ流れを掬ぶ
⇒同じ星の下に生まれる
→鳴声
提供:NHKサービスセンター
⇒おなが‐ざめ【尾長鮫】
⇒おなが‐ざる【尾長猿】
⇒おなが‐どり【尾長鳥】
おなか‐いれ【御中入れ】
(女房詞)
①昼食。
②綿入れ。
⇒お‐なか【御中】
おなか‐がしら【御中頭】
御中臈おちゅうろうの頭。
⇒お‐なか【御中】
おなか‐ごころ【御中心】
はらぐあい。
⇒お‐なか【御中】
おなが‐ざめ【尾長鮫】ヲ‥
オナガザメ科の海産軟骨魚の総称。サメ類の中では尾びれが最も長く、ネズミの尾に似ているためにネズミブカともいう。全長約4メートル。南日本に産。マオナガ・ニタリ・ハチワレなど。
⇒お‐なが【尾長】
おなが‐ざる【尾長猿】ヲ‥
サル目(霊長類)オナガザル科(狭鼻猿類)オナガザル属の哺乳類の総称。約20種があり、熱帯アフリカに分布。サバンナモンキー・ダイアナモンキーなど。
⇒お‐なが【尾長】
おなが‐どり【尾長鳥】ヲ‥
(→)長尾鶏ちょうびけいに同じ。
⇒お‐なが【尾長】
お‐ながれ【御流れ】
①主君や貴人から賜る盃の酒。また、酒席で敬意を表すために相手の盃を受けて飲む酒。狂言、松楪まつゆずりは「前世下された事は無けれども、―を下さるる」。「―頂戴」
②目上の人から不用となって与えられる物。お下がり。
③計画した事が中止となること。「集会が―になる」
お‐なぐさみ【御慰み】
その場のなぐさみになること。おたのしみ。皮肉の意でも用いる。「首尾よくいきましたら―」「とんだ―」
おな‐ご【女子】ヲナ‥
(ヲンナゴの約)
①女の子供。女児。狂言、粟田口「下京に妹が居りまらする。是にも―が一ぴきござあるが是も姪の内でござあらうずるか」
②女。婦人。浄瑠璃、堀川波鼓「―の道を教へ込み」
③女中。はしため。好色一代男7「高嶋屋の―によびかけられて」
⇒おなご‐おうぎ【女子扇】
⇒おなご‐ぎ【女子気】
⇒おなご‐しゅう【女子衆】
⇒おなご‐じょたい【女子所帯】
⇒おなご‐だけ【女子竹】
⇒おなご‐だて【女子達・女侠】
⇒おなご‐なおし【女子直し】
⇒おなご‐みず【女子水】
⇒おなご‐むすび【女子結び】
⇒おなご‐らし・い【女子らしい】
⇒おなご‐わざ【女子業】
おなご‐おうぎ【女子扇】ヲナ‥アフギ
女持ちの小さな扇。
⇒おな‐ご【女子】
おなご‐ぎ【女子気】ヲナ‥
女の心。女のせまい心。女のしとやかな心。
⇒おな‐ご【女子】
おなご‐しゅう【女子衆】ヲナ‥
(「おなごしゅ」「おなごし」とも)
①女たち。
②女中。
⇒おな‐ご【女子】
おなご‐じょたい【女子所帯】ヲナ‥
女だけで男のいない所帯。
⇒おな‐ご【女子】
おなご‐だけ【女子竹】ヲナ‥
メダケの別称。
⇒おな‐ご【女子】
おなご‐だて【女子達・女侠】ヲナ‥
女の侠客きょうかく。
⇒おな‐ご【女子】
おなご‐なおし【女子直し】ヲナ‥ナホシ
下女を引き上げて嫁とすること。
⇒おな‐ご【女子】
おなご‐みず【女子水】ヲナ‥ミヅ
軟水。↔男水おとこみず。
⇒おな‐ご【女子】
おなご‐むすび【女子結び】ヲナ‥
(→)「おんなむすび」に同じ。
⇒おな‐ご【女子】
おなご‐らし・い【女子らしい】ヲナ‥
〔形〕
①女としてふさわしいさまである。しとやかである。
②めめしい。男でありながら女のようである。日葡辞書「ヲナゴラシイヒト」
⇒おな‐ご【女子】
おなご‐わざ【女子業】ヲナ‥
女のする仕事。女にふさわしい仕事。
⇒おな‐ご【女子】
お‐なさけ【御情け】
哀れみ。思いやり。また、寵愛ちょうあい。「―で単位をもらう」「―を受ける」
おなじ【同じ】
(形容詞「おなじ」が体言化したもの)
[一]〔名〕
質・状態・程度などが同一であること。差異がないこと。「前に買った柄がらと―だ」「君と背丈が―になった」
[二]〔連体〕
同一の。同類の。同程度の。「―名前」「―成績」「彼の家とは―方向だ」「前回と―人を指名する」
[三]〔副〕
(「なら」と呼応して)どうせ。どっちみち。「―買うならもう少しましなものを買いなさい」
⇒おなじ‐まいまい【同蝸牛】
おな・じ【同じ】
〔形シク〕
体言に続く場合(殊に和文脈において)は「おなじき」よりも「おなじ」の形が多く用いられる。口語では「同じい」という形であるが、現在はほとんど使われず、連用形「おなじく」が残る。
①(二つ以上のものが質あるいは条件に)かわりがない。ちがいがない。差がない。万葉集15「君がむた行かましものを―・じこと後れて居おれど良きこともなし」。源氏物語桐壺「―・じほどそれより下らうの更衣たち」。「右に―・じく厳罰に処す」
②ひとつものである。同一である。万葉集18「あしひきの山は無くもが月見れば―・じき里を心隔てつ」。平家物語11「殿を―・じうして住み給へ」→おなじ(連体)
⇒同じ穴の貉
⇒同じ釜の飯を食う
⇒同じ流れを掬ぶ
⇒同じ星の下に生まれる
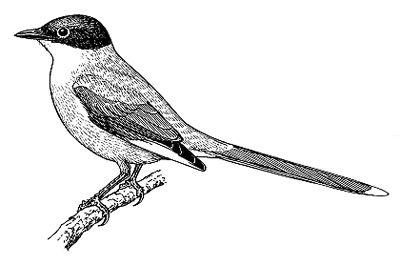 オナガ
提供:OPO
オナガ
提供:OPO
 →鳴声
提供:NHKサービスセンター
⇒おなが‐ざめ【尾長鮫】
⇒おなが‐ざる【尾長猿】
⇒おなが‐どり【尾長鳥】
おなか‐いれ【御中入れ】
(女房詞)
①昼食。
②綿入れ。
⇒お‐なか【御中】
おなか‐がしら【御中頭】
御中臈おちゅうろうの頭。
⇒お‐なか【御中】
おなか‐ごころ【御中心】
はらぐあい。
⇒お‐なか【御中】
おなが‐ざめ【尾長鮫】ヲ‥
オナガザメ科の海産軟骨魚の総称。サメ類の中では尾びれが最も長く、ネズミの尾に似ているためにネズミブカともいう。全長約4メートル。南日本に産。マオナガ・ニタリ・ハチワレなど。
⇒お‐なが【尾長】
おなが‐ざる【尾長猿】ヲ‥
サル目(霊長類)オナガザル科(狭鼻猿類)オナガザル属の哺乳類の総称。約20種があり、熱帯アフリカに分布。サバンナモンキー・ダイアナモンキーなど。
⇒お‐なが【尾長】
おなが‐どり【尾長鳥】ヲ‥
(→)長尾鶏ちょうびけいに同じ。
⇒お‐なが【尾長】
お‐ながれ【御流れ】
①主君や貴人から賜る盃の酒。また、酒席で敬意を表すために相手の盃を受けて飲む酒。狂言、松楪まつゆずりは「前世下された事は無けれども、―を下さるる」。「―頂戴」
②目上の人から不用となって与えられる物。お下がり。
③計画した事が中止となること。「集会が―になる」
お‐なぐさみ【御慰み】
その場のなぐさみになること。おたのしみ。皮肉の意でも用いる。「首尾よくいきましたら―」「とんだ―」
おな‐ご【女子】ヲナ‥
(ヲンナゴの約)
①女の子供。女児。狂言、粟田口「下京に妹が居りまらする。是にも―が一ぴきござあるが是も姪の内でござあらうずるか」
②女。婦人。浄瑠璃、堀川波鼓「―の道を教へ込み」
③女中。はしため。好色一代男7「高嶋屋の―によびかけられて」
⇒おなご‐おうぎ【女子扇】
⇒おなご‐ぎ【女子気】
⇒おなご‐しゅう【女子衆】
⇒おなご‐じょたい【女子所帯】
⇒おなご‐だけ【女子竹】
⇒おなご‐だて【女子達・女侠】
⇒おなご‐なおし【女子直し】
⇒おなご‐みず【女子水】
⇒おなご‐むすび【女子結び】
⇒おなご‐らし・い【女子らしい】
⇒おなご‐わざ【女子業】
おなご‐おうぎ【女子扇】ヲナ‥アフギ
女持ちの小さな扇。
⇒おな‐ご【女子】
おなご‐ぎ【女子気】ヲナ‥
女の心。女のせまい心。女のしとやかな心。
⇒おな‐ご【女子】
おなご‐しゅう【女子衆】ヲナ‥
(「おなごしゅ」「おなごし」とも)
①女たち。
②女中。
⇒おな‐ご【女子】
おなご‐じょたい【女子所帯】ヲナ‥
女だけで男のいない所帯。
⇒おな‐ご【女子】
おなご‐だけ【女子竹】ヲナ‥
メダケの別称。
⇒おな‐ご【女子】
おなご‐だて【女子達・女侠】ヲナ‥
女の侠客きょうかく。
⇒おな‐ご【女子】
おなご‐なおし【女子直し】ヲナ‥ナホシ
下女を引き上げて嫁とすること。
⇒おな‐ご【女子】
おなご‐みず【女子水】ヲナ‥ミヅ
軟水。↔男水おとこみず。
⇒おな‐ご【女子】
おなご‐むすび【女子結び】ヲナ‥
(→)「おんなむすび」に同じ。
⇒おな‐ご【女子】
おなご‐らし・い【女子らしい】ヲナ‥
〔形〕
①女としてふさわしいさまである。しとやかである。
②めめしい。男でありながら女のようである。日葡辞書「ヲナゴラシイヒト」
⇒おな‐ご【女子】
おなご‐わざ【女子業】ヲナ‥
女のする仕事。女にふさわしい仕事。
⇒おな‐ご【女子】
お‐なさけ【御情け】
哀れみ。思いやり。また、寵愛ちょうあい。「―で単位をもらう」「―を受ける」
おなじ【同じ】
(形容詞「おなじ」が体言化したもの)
[一]〔名〕
質・状態・程度などが同一であること。差異がないこと。「前に買った柄がらと―だ」「君と背丈が―になった」
[二]〔連体〕
同一の。同類の。同程度の。「―名前」「―成績」「彼の家とは―方向だ」「前回と―人を指名する」
[三]〔副〕
(「なら」と呼応して)どうせ。どっちみち。「―買うならもう少しましなものを買いなさい」
⇒おなじ‐まいまい【同蝸牛】
おな・じ【同じ】
〔形シク〕
体言に続く場合(殊に和文脈において)は「おなじき」よりも「おなじ」の形が多く用いられる。口語では「同じい」という形であるが、現在はほとんど使われず、連用形「おなじく」が残る。
①(二つ以上のものが質あるいは条件に)かわりがない。ちがいがない。差がない。万葉集15「君がむた行かましものを―・じこと後れて居おれど良きこともなし」。源氏物語桐壺「―・じほどそれより下らうの更衣たち」。「右に―・じく厳罰に処す」
②ひとつものである。同一である。万葉集18「あしひきの山は無くもが月見れば―・じき里を心隔てつ」。平家物語11「殿を―・じうして住み給へ」→おなじ(連体)
⇒同じ穴の貉
⇒同じ釜の飯を食う
⇒同じ流れを掬ぶ
⇒同じ星の下に生まれる
→鳴声
提供:NHKサービスセンター
⇒おなが‐ざめ【尾長鮫】
⇒おなが‐ざる【尾長猿】
⇒おなが‐どり【尾長鳥】
おなか‐いれ【御中入れ】
(女房詞)
①昼食。
②綿入れ。
⇒お‐なか【御中】
おなか‐がしら【御中頭】
御中臈おちゅうろうの頭。
⇒お‐なか【御中】
おなか‐ごころ【御中心】
はらぐあい。
⇒お‐なか【御中】
おなが‐ざめ【尾長鮫】ヲ‥
オナガザメ科の海産軟骨魚の総称。サメ類の中では尾びれが最も長く、ネズミの尾に似ているためにネズミブカともいう。全長約4メートル。南日本に産。マオナガ・ニタリ・ハチワレなど。
⇒お‐なが【尾長】
おなが‐ざる【尾長猿】ヲ‥
サル目(霊長類)オナガザル科(狭鼻猿類)オナガザル属の哺乳類の総称。約20種があり、熱帯アフリカに分布。サバンナモンキー・ダイアナモンキーなど。
⇒お‐なが【尾長】
おなが‐どり【尾長鳥】ヲ‥
(→)長尾鶏ちょうびけいに同じ。
⇒お‐なが【尾長】
お‐ながれ【御流れ】
①主君や貴人から賜る盃の酒。また、酒席で敬意を表すために相手の盃を受けて飲む酒。狂言、松楪まつゆずりは「前世下された事は無けれども、―を下さるる」。「―頂戴」
②目上の人から不用となって与えられる物。お下がり。
③計画した事が中止となること。「集会が―になる」
お‐なぐさみ【御慰み】
その場のなぐさみになること。おたのしみ。皮肉の意でも用いる。「首尾よくいきましたら―」「とんだ―」
おな‐ご【女子】ヲナ‥
(ヲンナゴの約)
①女の子供。女児。狂言、粟田口「下京に妹が居りまらする。是にも―が一ぴきござあるが是も姪の内でござあらうずるか」
②女。婦人。浄瑠璃、堀川波鼓「―の道を教へ込み」
③女中。はしため。好色一代男7「高嶋屋の―によびかけられて」
⇒おなご‐おうぎ【女子扇】
⇒おなご‐ぎ【女子気】
⇒おなご‐しゅう【女子衆】
⇒おなご‐じょたい【女子所帯】
⇒おなご‐だけ【女子竹】
⇒おなご‐だて【女子達・女侠】
⇒おなご‐なおし【女子直し】
⇒おなご‐みず【女子水】
⇒おなご‐むすび【女子結び】
⇒おなご‐らし・い【女子らしい】
⇒おなご‐わざ【女子業】
おなご‐おうぎ【女子扇】ヲナ‥アフギ
女持ちの小さな扇。
⇒おな‐ご【女子】
おなご‐ぎ【女子気】ヲナ‥
女の心。女のせまい心。女のしとやかな心。
⇒おな‐ご【女子】
おなご‐しゅう【女子衆】ヲナ‥
(「おなごしゅ」「おなごし」とも)
①女たち。
②女中。
⇒おな‐ご【女子】
おなご‐じょたい【女子所帯】ヲナ‥
女だけで男のいない所帯。
⇒おな‐ご【女子】
おなご‐だけ【女子竹】ヲナ‥
メダケの別称。
⇒おな‐ご【女子】
おなご‐だて【女子達・女侠】ヲナ‥
女の侠客きょうかく。
⇒おな‐ご【女子】
おなご‐なおし【女子直し】ヲナ‥ナホシ
下女を引き上げて嫁とすること。
⇒おな‐ご【女子】
おなご‐みず【女子水】ヲナ‥ミヅ
軟水。↔男水おとこみず。
⇒おな‐ご【女子】
おなご‐むすび【女子結び】ヲナ‥
(→)「おんなむすび」に同じ。
⇒おな‐ご【女子】
おなご‐らし・い【女子らしい】ヲナ‥
〔形〕
①女としてふさわしいさまである。しとやかである。
②めめしい。男でありながら女のようである。日葡辞書「ヲナゴラシイヒト」
⇒おな‐ご【女子】
おなご‐わざ【女子業】ヲナ‥
女のする仕事。女にふさわしい仕事。
⇒おな‐ご【女子】
お‐なさけ【御情け】
哀れみ。思いやり。また、寵愛ちょうあい。「―で単位をもらう」「―を受ける」
おなじ【同じ】
(形容詞「おなじ」が体言化したもの)
[一]〔名〕
質・状態・程度などが同一であること。差異がないこと。「前に買った柄がらと―だ」「君と背丈が―になった」
[二]〔連体〕
同一の。同類の。同程度の。「―名前」「―成績」「彼の家とは―方向だ」「前回と―人を指名する」
[三]〔副〕
(「なら」と呼応して)どうせ。どっちみち。「―買うならもう少しましなものを買いなさい」
⇒おなじ‐まいまい【同蝸牛】
おな・じ【同じ】
〔形シク〕
体言に続く場合(殊に和文脈において)は「おなじき」よりも「おなじ」の形が多く用いられる。口語では「同じい」という形であるが、現在はほとんど使われず、連用形「おなじく」が残る。
①(二つ以上のものが質あるいは条件に)かわりがない。ちがいがない。差がない。万葉集15「君がむた行かましものを―・じこと後れて居おれど良きこともなし」。源氏物語桐壺「―・じほどそれより下らうの更衣たち」。「右に―・じく厳罰に処す」
②ひとつものである。同一である。万葉集18「あしひきの山は無くもが月見れば―・じき里を心隔てつ」。平家物語11「殿を―・じうして住み給へ」→おなじ(連体)
⇒同じ穴の貉
⇒同じ釜の飯を食う
⇒同じ流れを掬ぶ
⇒同じ星の下に生まれる
広辞苑に「驚く」で始まるの検索結果 1-2。