複数辞典一括検索+![]()
![]()
こう‐ぼく【高木】カウ‥🔗⭐🔉
こう‐ぼく【高木】カウ‥
①高い木。普通、人の背丈以上のもの。
②〔生〕枝と明瞭に区別できる幹があり、樹下を人が立って通れる樹木。モミ・スギ・カシの類。喬木きょうぼく。↔低木。
⇒こうぼく‐げんかい【高木限界】
⇒こうぼく‐そう【高木層】
⇒こうぼく‐たい【高木帯】
⇒高木は風に折らる
こうぼく‐げんかい【高木限界】カウ‥🔗⭐🔉
こうぼく‐げんかい【高木限界】カウ‥
(→)樹木限界に同じ。
⇒こう‐ぼく【高木】
こうぼく‐そう【高木層】カウ‥🔗⭐🔉
こうぼく‐そう【高木層】カウ‥
森林の最上層を占め、高木が林冠を構成する層。
⇒こう‐ぼく【高木】
こうぼく‐たい【高木帯】カウ‥🔗⭐🔉
こうぼく‐たい【高木帯】カウ‥
植生分布帯の一つ。植物帯では低木帯の下で、高木が生育する。喬木帯。
⇒こう‐ぼく【高木】
○高木は風に折らるこうぼくはかぜにおらる
声望・信用のすぐれた者は、他からねたまれて、身を滅ぼしやすいことのたとえ。
⇒こう‐ぼく【高木】
○高木は風に折らるこうぼくはかぜにおらる🔗⭐🔉
○高木は風に折らるこうぼくはかぜにおらる
声望・信用のすぐれた者は、他からねたまれて、身を滅ぼしやすいことのたとえ。
⇒こう‐ぼく【高木】
こうほ‐こう【黄浦江】クワウ‥カウ
(Huangpu Jiang)中国、長江の支流。淀山湖に発源し、上海中心部で呉淞ウースン江(蘇州河)と合流、長江に入る。大型船舶の航行が可能で、水運が盛ん。
こうぼ‐さい【公募債】
不特定多数の投資家に応募を呼びかけて発行される債券。国債・政府保証債・事業債など。↔私募債
⇒こう‐ぼ【公募】
こうほ‐せい【候補生】
一定の修業を完了して、ある官職に登用される資格のある生徒。「士官―」
⇒こう‐ほ【候補】
こう‐ほね【河骨・川骨】カウ‥
①スイレン科の多年草。沼沢などに自生。根茎は太く横臥、水上に露出する。葉は長さ30センチメートルに及ぶ。沈水葉は薄く色も浅い。夏に、長い花柄を水面に出し、黄色の1花を開く。根茎は強壮・止血剤となる。かわほね。漢名、萍蓬草。〈[季]夏〉
こうほね
 ②紋所の名。コウホネの花と葉をとり合わせたもの。葵紋あおいもんに似る。
河骨
②紋所の名。コウホネの花と葉をとり合わせたもの。葵紋あおいもんに似る。
河骨
 こうほ‐ひつ【皇甫謐】クワウ‥
西晋の学者。字は士安。百家の書に通じ、自ら玄晏げんあん先生と号す。著「帝王世紀」「高士伝」「列女伝」「玄晏春秋」など。(215〜282)
こう‐ぼり【蝙蝠】カウ‥
(→)「こうもり」に同じ。
こう‐ほん【広本】クワウ‥
同一作品の伝本のうち、内容の多い方のもの。↔略本
こう‐ほん【校本】カウ‥
①伝本の校合きょうごうの結果を書き加えた本。「―万葉集」
②校合に際して比較に利用する本。↔底本
こう‐ほん【絖本】クワウ‥
書画をかくのに用いる絖ぬめ。また、絖にかいた書画。
こう‐ほん【稿本】カウ‥
①下書きの本。著述の草稿。草稿本。原稿本。
②手書きした本。
こう‐ぼん【香盆】カウ‥
香こうを盛る盆。
こ‐うま【小馬・子馬】
小さい馬。馬の子。〈[季]春〉
⇒こうま‐ざ【小馬座】
⇒小馬の朝いさみ
こう‐ま【黄麻】クワウ‥
⇒おうま。
⇒こうま‐し【黄麻紙】
ごう‐ま【格間】ガウ‥
格天井ごうてんじょうの、組子内の一区画。
ごう‐ま【降魔】ガウ‥
〔仏〕悪魔を降伏ごうぶくすること。
⇒ごうま‐の‐いん【降魔の印】
⇒ごうま‐の‐そう【降魔の相】
⇒ごうま‐の‐りけん【降魔の利剣】
ごう‐ま【業魔】ゴフ‥
〔仏〕悪業が心身を悩乱し正道を妨げることを悪魔にたとえていう語。
こう‐まい【貢米】
みつぎものの米。
こう‐まい【高邁】カウ‥
けだかく衆にすぐれていること。「―な精神」
ごう‐まい【豪邁】ガウ‥
気性が強く衆にすぐれていること。
こう‐まいり【講参り】カウマヰリ
講中こうじゅうをつくって神仏に参詣すること。好色一代女6「―の通し馬を引き込み」
こう‐まく【厚膜】
厚い膜。
⇒こうまく‐さいぼう【厚膜細胞】
⇒こうまく‐そしき【厚膜組織】
こう‐まく【硬膜】カウ‥
〔医〕脳脊髄膜のうち最も外層のもの。硬脳膜。
⇒こうまく‐じょうみゃくどう【硬膜静脈洞】
こうまく‐さいぼう【厚膜細胞】‥バウ
〔生〕(→)厚壁細胞に同じ。
⇒こう‐まく【厚膜】
こうまく‐じょうみゃくどう【硬膜静脈洞】カウ‥ジヤウ‥
頭蓋骨内の硬膜にある太い静脈。大脳と小脳からの血液を集めて頭蓋の外に導く。
⇒こう‐まく【硬膜】
こうまく‐そしき【厚膜組織】
〔生〕(→)厚壁組織に同じ。
⇒こう‐まく【厚膜】
こう‐まくら【香枕】カウ‥
香をたく装置のある枕。表面に蒔絵まきえを施してある。きゃら枕。
こうま‐ざ【小馬座】
(Equuleus ラテン)ペガスス座の南西にある小星座。10月上旬の夕刻に南中。駒座。
⇒こ‐うま【小馬・子馬】
こうま‐し【黄麻紙】クワウ‥
⇒おうまし
⇒こう‐ま【黄麻】
こう‐まつ【口沫】
はげしくものを言う時、口角こうかくから飛ばす沫あわ。
ごう‐まつ【劫末】ゴフ‥
〔仏〕この世の終り。↔劫初
ごう‐まつ【毫末】ガウ‥
(「毫」は細い毛の意)毛筋の先ぐらいのわずかなこと。ほんのすこし。「―の疑いもない」
こうほ‐ひつ【皇甫謐】クワウ‥
西晋の学者。字は士安。百家の書に通じ、自ら玄晏げんあん先生と号す。著「帝王世紀」「高士伝」「列女伝」「玄晏春秋」など。(215〜282)
こう‐ぼり【蝙蝠】カウ‥
(→)「こうもり」に同じ。
こう‐ほん【広本】クワウ‥
同一作品の伝本のうち、内容の多い方のもの。↔略本
こう‐ほん【校本】カウ‥
①伝本の校合きょうごうの結果を書き加えた本。「―万葉集」
②校合に際して比較に利用する本。↔底本
こう‐ほん【絖本】クワウ‥
書画をかくのに用いる絖ぬめ。また、絖にかいた書画。
こう‐ほん【稿本】カウ‥
①下書きの本。著述の草稿。草稿本。原稿本。
②手書きした本。
こう‐ぼん【香盆】カウ‥
香こうを盛る盆。
こ‐うま【小馬・子馬】
小さい馬。馬の子。〈[季]春〉
⇒こうま‐ざ【小馬座】
⇒小馬の朝いさみ
こう‐ま【黄麻】クワウ‥
⇒おうま。
⇒こうま‐し【黄麻紙】
ごう‐ま【格間】ガウ‥
格天井ごうてんじょうの、組子内の一区画。
ごう‐ま【降魔】ガウ‥
〔仏〕悪魔を降伏ごうぶくすること。
⇒ごうま‐の‐いん【降魔の印】
⇒ごうま‐の‐そう【降魔の相】
⇒ごうま‐の‐りけん【降魔の利剣】
ごう‐ま【業魔】ゴフ‥
〔仏〕悪業が心身を悩乱し正道を妨げることを悪魔にたとえていう語。
こう‐まい【貢米】
みつぎものの米。
こう‐まい【高邁】カウ‥
けだかく衆にすぐれていること。「―な精神」
ごう‐まい【豪邁】ガウ‥
気性が強く衆にすぐれていること。
こう‐まいり【講参り】カウマヰリ
講中こうじゅうをつくって神仏に参詣すること。好色一代女6「―の通し馬を引き込み」
こう‐まく【厚膜】
厚い膜。
⇒こうまく‐さいぼう【厚膜細胞】
⇒こうまく‐そしき【厚膜組織】
こう‐まく【硬膜】カウ‥
〔医〕脳脊髄膜のうち最も外層のもの。硬脳膜。
⇒こうまく‐じょうみゃくどう【硬膜静脈洞】
こうまく‐さいぼう【厚膜細胞】‥バウ
〔生〕(→)厚壁細胞に同じ。
⇒こう‐まく【厚膜】
こうまく‐じょうみゃくどう【硬膜静脈洞】カウ‥ジヤウ‥
頭蓋骨内の硬膜にある太い静脈。大脳と小脳からの血液を集めて頭蓋の外に導く。
⇒こう‐まく【硬膜】
こうまく‐そしき【厚膜組織】
〔生〕(→)厚壁組織に同じ。
⇒こう‐まく【厚膜】
こう‐まくら【香枕】カウ‥
香をたく装置のある枕。表面に蒔絵まきえを施してある。きゃら枕。
こうま‐ざ【小馬座】
(Equuleus ラテン)ペガスス座の南西にある小星座。10月上旬の夕刻に南中。駒座。
⇒こ‐うま【小馬・子馬】
こうま‐し【黄麻紙】クワウ‥
⇒おうまし
⇒こう‐ま【黄麻】
こう‐まつ【口沫】
はげしくものを言う時、口角こうかくから飛ばす沫あわ。
ごう‐まつ【劫末】ゴフ‥
〔仏〕この世の終り。↔劫初
ごう‐まつ【毫末】ガウ‥
(「毫」は細い毛の意)毛筋の先ぐらいのわずかなこと。ほんのすこし。「―の疑いもない」
 ②紋所の名。コウホネの花と葉をとり合わせたもの。葵紋あおいもんに似る。
河骨
②紋所の名。コウホネの花と葉をとり合わせたもの。葵紋あおいもんに似る。
河骨
 こうほ‐ひつ【皇甫謐】クワウ‥
西晋の学者。字は士安。百家の書に通じ、自ら玄晏げんあん先生と号す。著「帝王世紀」「高士伝」「列女伝」「玄晏春秋」など。(215〜282)
こう‐ぼり【蝙蝠】カウ‥
(→)「こうもり」に同じ。
こう‐ほん【広本】クワウ‥
同一作品の伝本のうち、内容の多い方のもの。↔略本
こう‐ほん【校本】カウ‥
①伝本の校合きょうごうの結果を書き加えた本。「―万葉集」
②校合に際して比較に利用する本。↔底本
こう‐ほん【絖本】クワウ‥
書画をかくのに用いる絖ぬめ。また、絖にかいた書画。
こう‐ほん【稿本】カウ‥
①下書きの本。著述の草稿。草稿本。原稿本。
②手書きした本。
こう‐ぼん【香盆】カウ‥
香こうを盛る盆。
こ‐うま【小馬・子馬】
小さい馬。馬の子。〈[季]春〉
⇒こうま‐ざ【小馬座】
⇒小馬の朝いさみ
こう‐ま【黄麻】クワウ‥
⇒おうま。
⇒こうま‐し【黄麻紙】
ごう‐ま【格間】ガウ‥
格天井ごうてんじょうの、組子内の一区画。
ごう‐ま【降魔】ガウ‥
〔仏〕悪魔を降伏ごうぶくすること。
⇒ごうま‐の‐いん【降魔の印】
⇒ごうま‐の‐そう【降魔の相】
⇒ごうま‐の‐りけん【降魔の利剣】
ごう‐ま【業魔】ゴフ‥
〔仏〕悪業が心身を悩乱し正道を妨げることを悪魔にたとえていう語。
こう‐まい【貢米】
みつぎものの米。
こう‐まい【高邁】カウ‥
けだかく衆にすぐれていること。「―な精神」
ごう‐まい【豪邁】ガウ‥
気性が強く衆にすぐれていること。
こう‐まいり【講参り】カウマヰリ
講中こうじゅうをつくって神仏に参詣すること。好色一代女6「―の通し馬を引き込み」
こう‐まく【厚膜】
厚い膜。
⇒こうまく‐さいぼう【厚膜細胞】
⇒こうまく‐そしき【厚膜組織】
こう‐まく【硬膜】カウ‥
〔医〕脳脊髄膜のうち最も外層のもの。硬脳膜。
⇒こうまく‐じょうみゃくどう【硬膜静脈洞】
こうまく‐さいぼう【厚膜細胞】‥バウ
〔生〕(→)厚壁細胞に同じ。
⇒こう‐まく【厚膜】
こうまく‐じょうみゃくどう【硬膜静脈洞】カウ‥ジヤウ‥
頭蓋骨内の硬膜にある太い静脈。大脳と小脳からの血液を集めて頭蓋の外に導く。
⇒こう‐まく【硬膜】
こうまく‐そしき【厚膜組織】
〔生〕(→)厚壁組織に同じ。
⇒こう‐まく【厚膜】
こう‐まくら【香枕】カウ‥
香をたく装置のある枕。表面に蒔絵まきえを施してある。きゃら枕。
こうま‐ざ【小馬座】
(Equuleus ラテン)ペガスス座の南西にある小星座。10月上旬の夕刻に南中。駒座。
⇒こ‐うま【小馬・子馬】
こうま‐し【黄麻紙】クワウ‥
⇒おうまし
⇒こう‐ま【黄麻】
こう‐まつ【口沫】
はげしくものを言う時、口角こうかくから飛ばす沫あわ。
ごう‐まつ【劫末】ゴフ‥
〔仏〕この世の終り。↔劫初
ごう‐まつ【毫末】ガウ‥
(「毫」は細い毛の意)毛筋の先ぐらいのわずかなこと。ほんのすこし。「―の疑いもない」
こうほ‐ひつ【皇甫謐】クワウ‥
西晋の学者。字は士安。百家の書に通じ、自ら玄晏げんあん先生と号す。著「帝王世紀」「高士伝」「列女伝」「玄晏春秋」など。(215〜282)
こう‐ぼり【蝙蝠】カウ‥
(→)「こうもり」に同じ。
こう‐ほん【広本】クワウ‥
同一作品の伝本のうち、内容の多い方のもの。↔略本
こう‐ほん【校本】カウ‥
①伝本の校合きょうごうの結果を書き加えた本。「―万葉集」
②校合に際して比較に利用する本。↔底本
こう‐ほん【絖本】クワウ‥
書画をかくのに用いる絖ぬめ。また、絖にかいた書画。
こう‐ほん【稿本】カウ‥
①下書きの本。著述の草稿。草稿本。原稿本。
②手書きした本。
こう‐ぼん【香盆】カウ‥
香こうを盛る盆。
こ‐うま【小馬・子馬】
小さい馬。馬の子。〈[季]春〉
⇒こうま‐ざ【小馬座】
⇒小馬の朝いさみ
こう‐ま【黄麻】クワウ‥
⇒おうま。
⇒こうま‐し【黄麻紙】
ごう‐ま【格間】ガウ‥
格天井ごうてんじょうの、組子内の一区画。
ごう‐ま【降魔】ガウ‥
〔仏〕悪魔を降伏ごうぶくすること。
⇒ごうま‐の‐いん【降魔の印】
⇒ごうま‐の‐そう【降魔の相】
⇒ごうま‐の‐りけん【降魔の利剣】
ごう‐ま【業魔】ゴフ‥
〔仏〕悪業が心身を悩乱し正道を妨げることを悪魔にたとえていう語。
こう‐まい【貢米】
みつぎものの米。
こう‐まい【高邁】カウ‥
けだかく衆にすぐれていること。「―な精神」
ごう‐まい【豪邁】ガウ‥
気性が強く衆にすぐれていること。
こう‐まいり【講参り】カウマヰリ
講中こうじゅうをつくって神仏に参詣すること。好色一代女6「―の通し馬を引き込み」
こう‐まく【厚膜】
厚い膜。
⇒こうまく‐さいぼう【厚膜細胞】
⇒こうまく‐そしき【厚膜組織】
こう‐まく【硬膜】カウ‥
〔医〕脳脊髄膜のうち最も外層のもの。硬脳膜。
⇒こうまく‐じょうみゃくどう【硬膜静脈洞】
こうまく‐さいぼう【厚膜細胞】‥バウ
〔生〕(→)厚壁細胞に同じ。
⇒こう‐まく【厚膜】
こうまく‐じょうみゃくどう【硬膜静脈洞】カウ‥ジヤウ‥
頭蓋骨内の硬膜にある太い静脈。大脳と小脳からの血液を集めて頭蓋の外に導く。
⇒こう‐まく【硬膜】
こうまく‐そしき【厚膜組織】
〔生〕(→)厚壁組織に同じ。
⇒こう‐まく【厚膜】
こう‐まくら【香枕】カウ‥
香をたく装置のある枕。表面に蒔絵まきえを施してある。きゃら枕。
こうま‐ざ【小馬座】
(Equuleus ラテン)ペガスス座の南西にある小星座。10月上旬の夕刻に南中。駒座。
⇒こ‐うま【小馬・子馬】
こうま‐し【黄麻紙】クワウ‥
⇒おうまし
⇒こう‐ま【黄麻】
こう‐まつ【口沫】
はげしくものを言う時、口角こうかくから飛ばす沫あわ。
ごう‐まつ【劫末】ゴフ‥
〔仏〕この世の終り。↔劫初
ごう‐まつ【毫末】ガウ‥
(「毫」は細い毛の意)毛筋の先ぐらいのわずかなこと。ほんのすこし。「―の疑いもない」
たかぎ【高木】🔗⭐🔉
たかぎ‐いちのすけ【高木市之助】🔗⭐🔉
たかぎ‐いちのすけ【高木市之助】
国文学者。愛知県生れ。東大卒。京城帝大・九大教授。旧套を脱した方法や着想で記紀・万葉などの文学性を追求。著「吉野の鮎」など。(1888〜1974)
⇒たかぎ【高木】
たかぎ‐かねひろ【高木兼寛】🔗⭐🔉
たかぎ‐かねひろ【高木兼寛】
衛生学者・軍医。日向(宮崎県)生れ。イギリス留学後、有志共立東京病院(東京慈恵会医大の前身)を設立。白米食から麦飯に替えて海軍の脚気を追放。1888年(明治21)日本で初の医学博士号を受ける。(1849〜1920)
⇒たかぎ【高木】
たかぎ‐しゅんざん【高木春山】🔗⭐🔉
たかぎ‐しゅんざん【高木春山】
江戸後期の本草家。名は以孝。島津家出入りの江戸目黒の豪商の家に生まれる。著「本草図説」は動植物などを精細な図入りで解説した200巻を越す大図鑑。( 〜1852)
⇒たかぎ【高木】
たかぎ‐せんえもん【高木仙右衛門】‥ヱ‥🔗⭐🔉
たかぎ‐せんえもん【高木仙右衛門】‥ヱ‥
長崎のキリスト教信者。1865年(慶応1)の隠れキリシタン復活時の当事者。迫害を受けたが、73年(明治6)キリシタン禁制の高札撤去後、浦上キリシタンを支えた。(1820〜1899)
⇒たかぎ【高木】
たかぎ‐ていじ【高木貞治】‥ヂ🔗⭐🔉
たかぎ‐ていじ【高木貞治】‥ヂ
数学者。岐阜県の人。東大教授。整数論における類体論に重要な寄与をし、日本の数学が国際的に認められる基礎を築いた。著書は、整数論・代数学・解析学・数学史等にわたる。文化勲章。(1875〜1960)
高木貞治
撮影:田村 茂
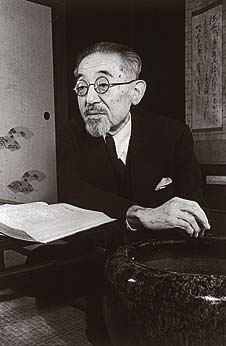 ⇒たかぎ【高木】
⇒たかぎ【高木】
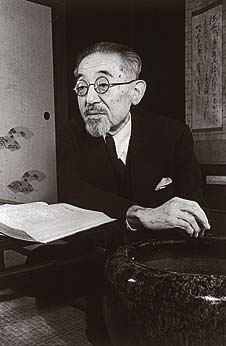 ⇒たかぎ【高木】
⇒たかぎ【高木】
○高木に遷るたかきにうつる🔗⭐🔉
○高木に遷るたかきにうつる
鶯が春になって、谷から出て高木にとびうつる。貫之集「氷とけなば鶯の―声を告げなむ」
⇒たか‐き【高木】
広辞苑に「高木」で始まるの検索結果 1-14。