複数辞典一括検索+![]()
![]()
広辞苑の検索結果 (27)
ご‐しょ【御所】🔗⭐🔉
ご‐しょ【御所】
①天皇の座所。また、その居所。禁中。内裏。また、天皇の敬称。平家物語11「―の御船には」。「京都―」
②上皇・三后・皇子の居所。また、それらの人の敬称。「東宮―」
③親王・将軍・大臣などの居所。また、それらの人の敬称。「花の―」
④御所風の略。浄瑠璃、傾城酒呑童子「供の女が頬かぶり、―のひんぬき」
⇒ごしょ‐がき【御所柿】
⇒ごしょ‐かずき【御所被衣】
⇒ごしょ‐がた【御所方】
⇒ごしょ‐かん【御所羹】
⇒ごしょ‐ぐるま【御所車】
⇒ごしょ‐ことば【御所詞】
⇒ごしょ‐ざくら【御所桜】
⇒ごしょ‐ざま【御所様】
⇒ごしょ‐ざむらい【御所侍】
⇒ごしょ‐そだち【御所育ち】
⇒ごしょ‐ぞめ【御所染】
⇒ごしょ‐ぢらし【御所散らし】
⇒ごしょ‐づくり【御所作り】
⇒ごしょ‐づとめ【御所勤め】
⇒ごしょ‐にんぎょう【御所人形】
⇒ごしょ‐ふう【御所風】
⇒ごしょ‐ぶぎょう【御所奉行】
⇒ごしょ‐まと【御所的】
⇒ごしょ‐むね【御所棟】
⇒ごしょ‐もよう【御所模様】
⇒ごしょ‐らくがん【御所落雁】
ごしょ‐がき【御所柿】🔗⭐🔉
ごしょ‐がき【御所柿】
(奈良県御所ごせ市、もと五所村から産したからいう)カキの一品種。実の形は扁平で縦の筋が四つあり、種少なく熟すれば深紅色となる。肉が柔らかでカキの品種中最も風味がよい。
ごしょがき
 ⇒ご‐しょ【御所】
⇒ご‐しょ【御所】
 ⇒ご‐しょ【御所】
⇒ご‐しょ【御所】
ごしょ‐かずき【御所被衣】‥カヅキ🔗⭐🔉
ごしょ‐かずき【御所被衣】‥カヅキ
御所染めの被衣。好色五人女3「―の取廻し」
⇒ご‐しょ【御所】
ごしょ‐がた【御所方】🔗⭐🔉
ごしょ‐がた【御所方】
御所に関係ある方々。また、御所の味方。ごしょざま。↔武家方。
⇒ご‐しょ【御所】
ごしょ‐かん【御所羹】🔗⭐🔉
ごしょ‐かん【御所羹】
寒天の中に、皮をむいて薄く輪切りにした蜜柑みかんを入れて固めたもの。
⇒ご‐しょ【御所】
ごしょ‐ぐるま【御所車】🔗⭐🔉
ごしょ‐ことば【御所詞】🔗⭐🔉
ごしょ‐ことば【御所詞】
室町時代以後、禁中で女房の間に使用された言葉。江戸時代に至り、ひろく幕府・大名の奥向きで用いられたものをもいう。女房詞。
⇒ご‐しょ【御所】
ごしょ‐ざくら【御所桜】🔗⭐🔉
ごしょ‐ざくら【御所桜】
桜の一品種。花は大形重弁で、5輪ずつむらがり咲く。
⇒ご‐しょ【御所】
ごしょざくらほりかわようち【御所桜堀川夜討】‥カハ‥🔗⭐🔉
ごしょざくらほりかわようち【御所桜堀川夜討】‥カハ‥
浄瑠璃。文耕堂・三好松洛合作の時代物。1737年(元文2)初演。土佐坊昌俊が源義経を堀河御所に襲撃したことを中心とし、義経・伊勢三郎・弁慶・静御前などに関する伝説を脚色。後に歌舞伎化。
ごしょ‐ざま【御所様】🔗⭐🔉
ごしょ‐ざま【御所様】
(→)「ごしょがた」に同じ。徒然草「その後ある―の古き女房のそぞろごと言はれしついでに」
⇒ご‐しょ【御所】
ごしょ‐ざむらい【御所侍】‥ザムラヒ🔗⭐🔉
ごしょ‐ざむらい【御所侍】‥ザムラヒ
上皇の御所や摂関の家などに仕えた侍。
⇒ご‐しょ【御所】
ごしょ‐そだち【御所育ち】🔗⭐🔉
ごしょ‐そだち【御所育ち】
御所で生い育ったこと。
⇒ご‐しょ【御所】
ごしょ‐ぞめ【御所染】🔗⭐🔉
ごしょ‐ぞめ【御所染】
染模様の一種。白地の絹に上品な散らし模様を配する。寛永(1624〜1644)頃、女院の御所で始められたのが諸方にひろまった。好色一代女1「―の時花はやりしも」
⇒ご‐しょ【御所】
ごしょ‐ぢらし【御所散らし】🔗⭐🔉
ごしょ‐ぢらし【御所散らし】
(→)御所染ごしょぞめに同じ。
⇒ご‐しょ【御所】
ごしょ‐づくり【御所作り】🔗⭐🔉
ごしょ‐づくり【御所作り】
①菊御作きくのぎょさくの別称。
②御所風の建築様式。
⇒ご‐しょ【御所】
ごしょ‐づとめ【御所勤め】🔗⭐🔉
ごしょ‐づとめ【御所勤め】
御所に仕えること。
⇒ご‐しょ【御所】
ごしょ‐にんぎょう【御所人形】‥ギヤウ🔗⭐🔉
ごしょ‐にんぎょう【御所人形】‥ギヤウ
(もと、京都の公卿の間に行われたからとも、西国大名が参勤交代の途次御所に伺候し、その返礼に拝領したからともいう)頭の大きな、体の丸々とした幼児をかたどった裸人形。享保(1716〜1736)の頃、京都で創製された。大内人形。拝領人形。御土産人形。
御所人形
 ⇒ご‐しょ【御所】
⇒ご‐しょ【御所】
 ⇒ご‐しょ【御所】
⇒ご‐しょ【御所】
ごしょのごろぞう【御所の五郎蔵】‥ザウ🔗⭐🔉
ごしょのごろぞう【御所の五郎蔵】‥ザウ
歌舞伎脚本「曾我綉侠御所染そがもようたてしのごしょぞめ」の通称。6幕。河竹黙阿弥作の世話物。1864年(元治1)初演。柳亭種彦の読本「浅間嶽面影草紙」を脚色したもの。
ごしょ‐ふう【御所風】🔗⭐🔉
ごしょ‐ふう【御所風】
①御所の風俗。公家の風俗。
②女の髪の結い方。下げ髪を巻きあげて笄こうがいで留めておき、笄を抜けば直ちに下げ髪となるようにしたもの。
御所風
 ⇒ご‐しょ【御所】
⇒ご‐しょ【御所】
 ⇒ご‐しょ【御所】
⇒ご‐しょ【御所】
ごしょ‐ぶぎょう【御所奉行】‥ギヤウ🔗⭐🔉
ごしょ‐ぶぎょう【御所奉行】‥ギヤウ
鎌倉・室町幕府の職名。営中の雑事を統すべつかさどった者。
⇒ご‐しょ【御所】
ごしょ‐まと【御所的】🔗⭐🔉
ごしょ‐まと【御所的】
室町時代、新年に将軍家の弓場で行われた弓技。
⇒ご‐しょ【御所】
ごしょ‐むね【御所棟】🔗⭐🔉
ごしょ‐むね【御所棟】
宮殿・社殿などで、獅子口のある棟。
⇒ご‐しょ【御所】
ごしょ‐もよう【御所模様】‥ヤウ🔗⭐🔉
ごしょ‐もよう【御所模様】‥ヤウ
王朝風の花や庭園などの文様。近世、それを簡略にした御所解ごしょどき文様が流行。
⇒ご‐しょ【御所】
ごしょ‐らくがん【御所落雁】🔗⭐🔉
ごしょ‐らくがん【御所落雁】
溶かした氷砂糖で糯米もちごめの挽粉を捏こねて製した干菓子。富山県井波の名産。長方形で紅色と白色がある。
⇒ご‐しょ【御所】
ごす‐さま【御所様】🔗⭐🔉
ごす‐さま【御所様】
摂家・大臣などの子女が、その父を呼ぶ語。ごすさん。
ごせ【御所】🔗⭐🔉
ごせ【御所】
奈良県西部、大阪府に接する市。葛城地方の中心都市。製薬・繊維工業が盛ん。古代史跡が多い。人口3万2千。
ごっ‐さん【御所様】🔗⭐🔉
ごっ‐さん【御所様】
①ゴスサマの転。
②茶屋の女主人または主人。
大辞林の検索結果 (25)
ご-しょ【御所】🔗⭐🔉
ご-しょ [1] 【御所】
(1)天皇・上皇・三后・皇子などのすまい。特に,天皇の御座所。古くは一定の場所だけではなく,その時々の居所をもいう。「東宮―」「―の御舟をはじめ参らせて人々の舟どもみな出だしつつ/平家 4」
(2){(1)}に住んでいる人。天皇・上皇・三后などを敬っていう語。「―も二位殿抱き参らせて/弁内侍日記」
(3)親王・大臣・将軍などのすまい。また,そこに住む人を敬っていう語。「或る公卿の―へ宮仕はんとて/沙石 8」
ごしょ-がき【御所柿・五所柿】🔗⭐🔉
ごしょ-がき [2] 【御所柿・五所柿】
カキの品種の一。奈良県御所(ゴセ)の原産という。果実は扁球形で,種が少なく,甘みが強い。大和(ヤマト)柿。
ごしょ-かずき【御所被】🔗⭐🔉
ごしょ-かずき ―カヅキ 【御所被】
近世,京都の御所の女官たちが用いた衣被(キヌカズキ){(1)}。また,それをまねたもの。
ごしょ-がた【御所方】🔗⭐🔉
ごしょ-がた 【御所方】
(1)宮廷に味方する側(ガワ)。天皇方。「楠兵衛正成と言ふ者,―になりて/太平記 3」
(2)宮廷に関係のある方々。公家(クゲ)や女官など。また,その家。ごしょざま。「年久しく―に宮仕ひせしが/浮世草子・五人女 3」
ごしょ-かん【御所羹】🔗⭐🔉
ごしょ-かん [2] 【御所羹】
寒天の中に薄く輪切りにしたミカンを入れて固めた和菓子。
ごしょ-ぐるま【御所車】🔗⭐🔉
ごしょ-ぐるま [3] 【御所車】
(1)牛車(ギツシヤ)の俗称。源氏車。
(2)家紋の一。「源氏車」に同じ。
ごしょ-ことば【御所詞】🔗⭐🔉
ごしょ-ことば [3] 【御所詞】
室町時代以降,宮中の女官の間に行われた特殊な言葉。
→女房詞(ニヨウボウコトバ)
ごしょ-ざくら【御所桜】🔗⭐🔉
ごしょ-ざくら [3] 【御所桜】
サトザクラの一種。花は大形で八重咲き。
ごしょ-ざむらい【御所侍】🔗⭐🔉
ごしょ-ざむらい ―ザムラヒ 【御所侍】
禁中・院の御所・摂家に仕えた身分の低い侍。ごしょさぶらい。
ごしょ-ぞめ【御所染(め)】🔗⭐🔉
ごしょ-ぞめ [0] 【御所染(め)】
寛永(1624-1644)頃,女院の御所で好んで染められ,官女などに賜った染め物。また,その染め方。これを模したものが各地で流行したという。
ごしょ-づくり【御所作り・御所造り】🔗⭐🔉
ごしょ-づくり [3] 【御所作り・御所造り】
(1)菊一文字(キクイチモンジ)の異名。御所鍛(ギタ)い。
(2)御所風の家の造り。
ごしょ-どき-もよう【御所解(き)模様】🔗⭐🔉
ごしょ-どき-もよう ―モヤウ [5] 【御所解(き)模様】
和服の模様の一。御殿や欄干・檜扇(ヒオウギ)・四季の花や木などを散らした多彩で華麗な模様。
ごしょ-にんぎょう【御所人形】🔗⭐🔉
ごしょ-にんぎょう ―ギヤウ [3] 【御所人形】
幼児の裸人形。大きな頭に小さな目鼻立ちで,丸々と太り,肌は胡粉(ゴフン)塗りで白い。江戸時代には,御所方が諸大名への贈答に用いた。大内人形。お土産人形。拝領人形。伊豆蔵(イズクラ)人形。
ごしょ-ふう【御所風】🔗⭐🔉
ごしょ-ふう 【御所風】
(1)(町人や武士の風俗・様式に対して)御所めいていること。優美で上品なこと。
(2)江戸初期の女性の髪形。束ねた髪を根の周りに巻き付け,一本の笄(コウガイ)でとめたもの。御所風髷(ワゲ)。
御所風(2)
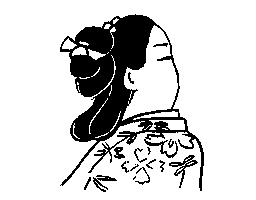 [図]
[図]
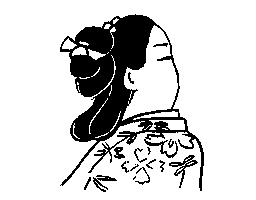 [図]
[図]
ごしょ-ぶぎょう【御所奉行】🔗⭐🔉
ごしょ-ぶぎょう ―ギヤウ [3] 【御所奉行】
鎌倉・室町幕府の職名。将軍の寺社参詣のことや年中行事など,営中の諸事をつかさどった。
ごしょ-まと【御所的】🔗⭐🔉
ごしょ-まと 【御所的】
室町時代,正月に将軍の御所で行なった弓技。
ごしょ-むね【御所棟】🔗⭐🔉
ごしょ-むね [0] 【御所棟】
端に獅子口(シシグチ)のある大棟。
ごしょ-もよう【御所模様】🔗⭐🔉
ごしょ-もよう ―ヤウ [3] 【御所模様】
御所風の上品な模様。
ごしょ-らくがん【御所落雁】🔗⭐🔉
ごしょ-らくがん [4] 【御所落雁】
干菓子の一。溶いた氷砂糖ともち米の粉で製した落雁。長方形で紅・白がある。富山県井波町の銘菓。
ごしょざくらほりかわようち【御所桜堀川夜討】🔗⭐🔉
ごしょざくらほりかわようち ―ホリカハヨウチ 【御所桜堀川夜討】
人形浄瑠璃,時代物の一。文耕堂・三好松洛作。1737年初演。通称「堀川夜討」。「平家物語」「義経記」などの土佐坊昌俊(シヨウシユン)が堀川御所を襲撃したことを中心とし,義経・伊勢三郎・弁慶・静御前などの伝説を加えて脚色。
ごしょのごろぞう【御所の五郎蔵】🔗⭐🔉
ごしょのごろぞう ―ゴロザウ 【御所の五郎蔵】
歌舞伎「曾我綉侠御所染(ソガモヨウタテシノゴシヨゾメ)」の通称。河竹黙阿弥作。1864年江戸市村座初演。柳亭種彦の読本「浅間嶽面影双紙(アサマガタケオモカゲソウシ)」を脚色したもの。
ごす-さま【御所様】🔗⭐🔉
ごす-さま 【御所様】
〔「ごす」は「ごしょ」の転〕
摂家・大臣家などの子女が,父を敬って呼ぶ語。ごっさん。
ごせ【御所】🔗⭐🔉
ごせ 【御所】
奈良県西部の市。江戸初期,桑山氏の城下町。大和売薬・大和絣(ガスリ)で知られた。古代の遺跡が多い。
ごっ-さん【御所様】🔗⭐🔉
ごっ-さん 【御所様】
(1)「ごすさま」の転。
(2)「ごてさん(御亭様)」の転。
ごしょ【御所】(和英)🔗⭐🔉
ごしょ【御所】
an Imperial Palace.
広辞苑+大辞林に「御所」で始まるの検索結果。