複数辞典一括検索+![]()
![]()
【支】🔗⭐🔉
【支】
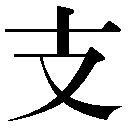 4画 支部 [五年]
区点=2757 16進=3B59 シフトJIS=8E78
《常用音訓》シ/ささ…える
《音読み》 シ
4画 支部 [五年]
区点=2757 16進=3B59 シフトJIS=8E78
《常用音訓》シ/ささ…える
《音読み》 シ
 〈zh
〈zh 〉
《訓読み》 わかれ/えだ/ささえる(ささふ)/ささえ(ささへ)/わかつ/つかえ(つかへ)
《名付け》 えだ・なか・もろ・ゆた
《意味》
〉
《訓読み》 わかれ/えだ/ささえる(ささふ)/ささえ(ささへ)/わかつ/つかえ(つかへ)
《名付け》 えだ・なか・もろ・ゆた
《意味》
 {名}わかれ。えだ。本からえだのようにわかれて出たもの。小さいもの。〈同義語〉→枝。〈対語〉→幹(みき)・→本(もと)。「支部」「支隊」「分支」
{名}わかれ。えだ。本からえだのようにわかれて出たもの。小さいもの。〈同義語〉→枝。〈対語〉→幹(みき)・→本(もと)。「支部」「支隊」「分支」
 {名}手足。▽肢シに当てた用法。胴体を幹(みき)とすれば、手足はえだにあたるので、支・肢という。「四支(=四肢)」「惰其四支=ソノ四支ヲ惰ル」〔→孟子〕
{名}手足。▽肢シに当てた用法。胴体を幹(みき)とすれば、手足はえだにあたるので、支・肢という。「四支(=四肢)」「惰其四支=ソノ四支ヲ惰ル」〔→孟子〕
 {動・名}ささえる(ササフ)。ささえ(ササヘ)。Y型のえだを当ててささえる。つっかい棒。「支柱」「支持」
{動・名}ささえる(ササフ)。ささえ(ササヘ)。Y型のえだを当ててささえる。つっかい棒。「支柱」「支持」
 シス{動}わかつ。財源からわけて金を出す。元金をわけて支払う。〈対語〉→収。「支出」「支付(支払う)」
シス{動}わかつ。財源からわけて金を出す。元金をわけて支払う。〈対語〉→収。「支出」「支付(支払う)」
 {名}子ネ・丑ウシ・寅トラ・卯ウ・辰タツ・巳ミ・午ウマ・未ヒツジ・申サル・酉トリ・戌イヌ・亥イの十二支。もと十二進法の数詞で、月日や年を数えるのに用いた。▽干(みき)に対して支(えだ)と名づけたもの。
〔国〕
{名}子ネ・丑ウシ・寅トラ・卯ウ・辰タツ・巳ミ・午ウマ・未ヒツジ・申サル・酉トリ・戌イヌ・亥イの十二支。もと十二進法の数詞で、月日や年を数えるのに用いた。▽干(みき)に対して支(えだ)と名づけたもの。
〔国〕 「支那シナ」の略。
「支那シナ」の略。 つかえ(ツカヘ)。さしさわり。
《解字》
つかえ(ツカヘ)。さしさわり。
《解字》
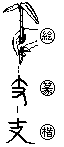 会意。支は「竹の枝+又(手)」で、手に一本のえだを持つさまを示す。
《単語家族》
岐キ(わかれ)
会意。支は「竹の枝+又(手)」で、手に一本のえだを持つさまを示す。
《単語家族》
岐キ(わかれ) 枝(えだ)などと同系。また、解(別々にわかれる)とも近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
枝(えだ)などと同系。また、解(別々にわかれる)とも近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
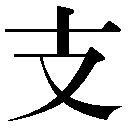 4画 支部 [五年]
区点=2757 16進=3B59 シフトJIS=8E78
《常用音訓》シ/ささ…える
《音読み》 シ
4画 支部 [五年]
区点=2757 16進=3B59 シフトJIS=8E78
《常用音訓》シ/ささ…える
《音読み》 シ
 〈zh
〈zh 〉
《訓読み》 わかれ/えだ/ささえる(ささふ)/ささえ(ささへ)/わかつ/つかえ(つかへ)
《名付け》 えだ・なか・もろ・ゆた
《意味》
〉
《訓読み》 わかれ/えだ/ささえる(ささふ)/ささえ(ささへ)/わかつ/つかえ(つかへ)
《名付け》 えだ・なか・もろ・ゆた
《意味》
 {名}わかれ。えだ。本からえだのようにわかれて出たもの。小さいもの。〈同義語〉→枝。〈対語〉→幹(みき)・→本(もと)。「支部」「支隊」「分支」
{名}わかれ。えだ。本からえだのようにわかれて出たもの。小さいもの。〈同義語〉→枝。〈対語〉→幹(みき)・→本(もと)。「支部」「支隊」「分支」
 {名}手足。▽肢シに当てた用法。胴体を幹(みき)とすれば、手足はえだにあたるので、支・肢という。「四支(=四肢)」「惰其四支=ソノ四支ヲ惰ル」〔→孟子〕
{名}手足。▽肢シに当てた用法。胴体を幹(みき)とすれば、手足はえだにあたるので、支・肢という。「四支(=四肢)」「惰其四支=ソノ四支ヲ惰ル」〔→孟子〕
 {動・名}ささえる(ササフ)。ささえ(ササヘ)。Y型のえだを当ててささえる。つっかい棒。「支柱」「支持」
{動・名}ささえる(ササフ)。ささえ(ササヘ)。Y型のえだを当ててささえる。つっかい棒。「支柱」「支持」
 シス{動}わかつ。財源からわけて金を出す。元金をわけて支払う。〈対語〉→収。「支出」「支付(支払う)」
シス{動}わかつ。財源からわけて金を出す。元金をわけて支払う。〈対語〉→収。「支出」「支付(支払う)」
 {名}子ネ・丑ウシ・寅トラ・卯ウ・辰タツ・巳ミ・午ウマ・未ヒツジ・申サル・酉トリ・戌イヌ・亥イの十二支。もと十二進法の数詞で、月日や年を数えるのに用いた。▽干(みき)に対して支(えだ)と名づけたもの。
〔国〕
{名}子ネ・丑ウシ・寅トラ・卯ウ・辰タツ・巳ミ・午ウマ・未ヒツジ・申サル・酉トリ・戌イヌ・亥イの十二支。もと十二進法の数詞で、月日や年を数えるのに用いた。▽干(みき)に対して支(えだ)と名づけたもの。
〔国〕 「支那シナ」の略。
「支那シナ」の略。 つかえ(ツカヘ)。さしさわり。
《解字》
つかえ(ツカヘ)。さしさわり。
《解字》
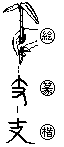 会意。支は「竹の枝+又(手)」で、手に一本のえだを持つさまを示す。
《単語家族》
岐キ(わかれ)
会意。支は「竹の枝+又(手)」で、手に一本のえだを持つさまを示す。
《単語家族》
岐キ(わかれ) 枝(えだ)などと同系。また、解(別々にわかれる)とも近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
枝(えだ)などと同系。また、解(別々にわかれる)とも近い。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
漢字源 ページ 1934 での【支】単語。