複数辞典一括検索+![]()
![]()
【投錨】🔗⭐🔉
【投錨】
トウビョウ いかりを水の中に投げ入れる。船をとめること。〈対語〉抜錨バツビョウ。
【投擲】🔗⭐🔉
【投擲】
トウテキ  なげうつ。ほうり出す。〈類義語〉抛擲ホウテキ。
なげうつ。ほうり出す。〈類義語〉抛擲ホウテキ。 遠くまで投げる。「投擲競技」
遠くまで投げる。「投擲競技」
 なげうつ。ほうり出す。〈類義語〉抛擲ホウテキ。
なげうつ。ほうり出す。〈類義語〉抛擲ホウテキ。 遠くまで投げる。「投擲競技」
遠くまで投げる。「投擲競技」
【投簪】🔗⭐🔉
【投簪】
トウシン・シンヲトウズ 役人をやめる。『投伝トウデン・投笏トウコツ』▽「簪」は、冠をとめるかんざし。「伝」は、役人の身分を示す証明書。「笏」は、役人が持つしゃく。
【抖】🔗⭐🔉
【抖】
 7画
7画  部
区点=5721 16進=5935 シフトJIS=9D54
《音読み》 トウ
部
区点=5721 16進=5935 シフトJIS=9D54
《音読み》 トウ /ツ
/ツ 〈d
〈d u〉
《訓読み》 ふるえる(ふるふ)
《意味》
{動}ふるえる(フルフ)。ぶるぶるとふるえる。「抖戦トウセン(ふるえる)」「抖膝トウシツ(ひざを貧乏ゆすりさせる)」
《解字》
形声。「手+音符斗」。
u〉
《訓読み》 ふるえる(ふるふ)
《意味》
{動}ふるえる(フルフ)。ぶるぶるとふるえる。「抖戦トウセン(ふるえる)」「抖膝トウシツ(ひざを貧乏ゆすりさせる)」
《解字》
形声。「手+音符斗」。
 7画
7画  部
区点=5721 16進=5935 シフトJIS=9D54
《音読み》 トウ
部
区点=5721 16進=5935 シフトJIS=9D54
《音読み》 トウ /ツ
/ツ 〈d
〈d u〉
《訓読み》 ふるえる(ふるふ)
《意味》
{動}ふるえる(フルフ)。ぶるぶるとふるえる。「抖戦トウセン(ふるえる)」「抖膝トウシツ(ひざを貧乏ゆすりさせる)」
《解字》
形声。「手+音符斗」。
u〉
《訓読み》 ふるえる(ふるふ)
《意味》
{動}ふるえる(フルフ)。ぶるぶるとふるえる。「抖戦トウセン(ふるえる)」「抖膝トウシツ(ひざを貧乏ゆすりさせる)」
《解字》
形声。「手+音符斗」。
【把】🔗⭐🔉
【把】
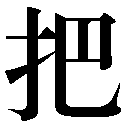 7画
7画  部 [常用漢字]
区点=3936 16進=4744 シフトJIS=9463
《常用音訓》ハ
《音読み》 ハ
部 [常用漢字]
区点=3936 16進=4744 シフトJIS=9463
《常用音訓》ハ
《音読み》 ハ /ヘ
/ヘ 〈b
〈b ・b
・b 〉
《訓読み》 にぎる/とる
《意味》
〉
《訓読み》 にぎる/とる
《意味》
 {動}にぎる。とる。手のひらをあててにぎる。にぎって持つ。「左手把秦王之袖=左手ヲモテ秦王ノ袖ヲ把ル」〔→史記〕
{動}にぎる。とる。手のひらをあててにぎる。にぎって持つ。「左手把秦王之袖=左手ヲモテ秦王ノ袖ヲ把ル」〔→史記〕
 {単位}ひとにぎりの量をあらわす単位。▽昔は半かかえを把といったこともある。「一把柴イッパノサイ(いちわのしば)」「拱把之桐梓=拱把ノ桐梓」〔→孟子〕
{単位}ひとにぎりの量をあらわす単位。▽昔は半かかえを把といったこともある。「一把柴イッパノサイ(いちわのしば)」「拱把之桐梓=拱把ノ桐梓」〔→孟子〕
 {前}処置する対象を、もちあげて示すことば。「欲把西湖比西子=西湖ヲ把ツテ西子ニ比セント欲ス」〔→蘇軾〕
{前}処置する対象を、もちあげて示すことば。「欲把西湖比西子=西湖ヲ把ツテ西子ニ比セント欲ス」〔→蘇軾〕
 {名}とって。にぎりて。「把手ハシュ」
《解字》
会意兼形声。巴ハは、人がうつ伏せて腹ばいになるさま。腹や手などの面をおし当てる意を含む。把は「手+音符巴」で、手のひらをぴたりとあててにぎること。
《類義》
→取
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{名}とって。にぎりて。「把手ハシュ」
《解字》
会意兼形声。巴ハは、人がうつ伏せて腹ばいになるさま。腹や手などの面をおし当てる意を含む。把は「手+音符巴」で、手のひらをぴたりとあててにぎること。
《類義》
→取
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
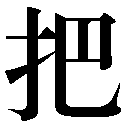 7画
7画  部 [常用漢字]
区点=3936 16進=4744 シフトJIS=9463
《常用音訓》ハ
《音読み》 ハ
部 [常用漢字]
区点=3936 16進=4744 シフトJIS=9463
《常用音訓》ハ
《音読み》 ハ /ヘ
/ヘ 〈b
〈b ・b
・b 〉
《訓読み》 にぎる/とる
《意味》
〉
《訓読み》 にぎる/とる
《意味》
 {動}にぎる。とる。手のひらをあててにぎる。にぎって持つ。「左手把秦王之袖=左手ヲモテ秦王ノ袖ヲ把ル」〔→史記〕
{動}にぎる。とる。手のひらをあててにぎる。にぎって持つ。「左手把秦王之袖=左手ヲモテ秦王ノ袖ヲ把ル」〔→史記〕
 {単位}ひとにぎりの量をあらわす単位。▽昔は半かかえを把といったこともある。「一把柴イッパノサイ(いちわのしば)」「拱把之桐梓=拱把ノ桐梓」〔→孟子〕
{単位}ひとにぎりの量をあらわす単位。▽昔は半かかえを把といったこともある。「一把柴イッパノサイ(いちわのしば)」「拱把之桐梓=拱把ノ桐梓」〔→孟子〕
 {前}処置する対象を、もちあげて示すことば。「欲把西湖比西子=西湖ヲ把ツテ西子ニ比セント欲ス」〔→蘇軾〕
{前}処置する対象を、もちあげて示すことば。「欲把西湖比西子=西湖ヲ把ツテ西子ニ比セント欲ス」〔→蘇軾〕
 {名}とって。にぎりて。「把手ハシュ」
《解字》
会意兼形声。巴ハは、人がうつ伏せて腹ばいになるさま。腹や手などの面をおし当てる意を含む。把は「手+音符巴」で、手のひらをぴたりとあててにぎること。
《類義》
→取
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
{名}とって。にぎりて。「把手ハシュ」
《解字》
会意兼形声。巴ハは、人がうつ伏せて腹ばいになるさま。腹や手などの面をおし当てる意を含む。把は「手+音符巴」で、手のひらをぴたりとあててにぎること。
《類義》
→取
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
漢字源 ページ 1802。