複数辞典一括検索+![]()
![]()
【佐吏】🔗⭐🔉
【佐吏】
サリ 上役をたすける役人。属官。
【佐車】🔗⭐🔉
【佐車】
サシャ 君主が乗る、予備の車。〈類義語〉副車・弐車ジシャ。
【佐幕】🔗⭐🔉
【佐幕】
サバク  野営している陣中で将軍をたすける。
野営している陣中で将軍をたすける。 〔国〕江戸時代末期、勤皇に対して、幕府をたすけ武家政治の維持に同調したこと。また、その一派。
〔国〕江戸時代末期、勤皇に対して、幕府をたすけ武家政治の維持に同調したこと。また、その一派。
 野営している陣中で将軍をたすける。
野営している陣中で将軍をたすける。 〔国〕江戸時代末期、勤皇に対して、幕府をたすけ武家政治の維持に同調したこと。また、その一派。
〔国〕江戸時代末期、勤皇に対して、幕府をたすけ武家政治の維持に同調したこと。また、その一派。
【佐久間象山】🔗⭐🔉
【佐久間象山】
サクマショウザン〔日〕〈人名〉1811〜64 江戸時代の儒学者。信濃シナノ(長野県)の松代マツシロの人。名は啓、象山は号で、ゾウザンと読む説もある。佐藤一斎に朱子学を学び、江戸に塾を開いた。のち、蘭学ランガク・兵学を学び、開国論を唱えた。また、和魂洋才をといた。勝海舟・吉田松陰らは門弟。
【佐藤一斎】🔗⭐🔉
【佐藤一斎】
サトウイッサイ〔日〕〈人名〉1772〜1859 江戸時代後期の儒学者。名は坦タン、号は一斎・愛日楼。朱子学と陽明学を兼ねおさめ、昌平黌ショウヘイコウの儒官となり幕政にも参与した。著に『言志四録』『近思録欄外書』などがある。
【作】🔗⭐🔉
【作】
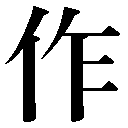 7画 人部 [二年]
区点=2678 16進=3A6E シフトJIS=8DEC
【做】異体字異体字
7画 人部 [二年]
区点=2678 16進=3A6E シフトJIS=8DEC
【做】異体字異体字
 11画 人部
区点=4886 16進=5076 シフトJIS=98F4
《常用音訓》サ/サク/つく…る
《音読み》 サク
11画 人部
区点=4886 16進=5076 シフトJIS=98F4
《常用音訓》サ/サク/つく…る
《音読み》 サク
 /サ
/サ
 〈zu
〈zu ・zu
・zu 〉〈zu
〉〈zu 〉
《訓読み》 つくる/なす/なる/おきる(おく)/おこる
《名付け》 あり・つくり・つくる・とも・なお・なり・ふか
《意味》
〉
《訓読み》 つくる/なす/なる/おきる(おく)/おこる
《名付け》 あり・つくり・つくる・とも・なお・なり・ふか
《意味》
 {動}つくる。新たに工夫してつくり出す。「創作」「述而不作=述ベテ作ラズ」〔→論語〕「作離騒=離騒ヲ作ル」〔→史記〕
{動}つくる。新たに工夫してつくり出す。「創作」「述而不作=述ベテ作ラズ」〔→論語〕「作離騒=離騒ヲ作ル」〔→史記〕
 {動}なす。する。「作為」「動作」
{動}なす。する。「作為」「動作」
 {動}なる。変化してその状態になる。「翻手作雲覆手雨=手ヲ翻セバ雲ト作リ手ヲ覆セバ雨」〔→杜甫〕
{動}なる。変化してその状態になる。「翻手作雲覆手雨=手ヲ翻セバ雲ト作リ手ヲ覆セバ雨」〔→杜甫〕
 {動}おきる(オク)。おき出す。働く。「蚤作而夜思=蚤ク作キテ夜思フ」〔→柳宗元〕
{動}おきる(オク)。おき出す。働く。「蚤作而夜思=蚤ク作キテ夜思フ」〔→柳宗元〕
 {動}おこる。動作がおこる。生じてくる。「発作」「有聖人作=聖人ノ作ル有リ」〔→韓非〕
{動}おこる。動作がおこる。生じてくる。「発作」「有聖人作=聖人ノ作ル有リ」〔→韓非〕
 {名}つくったもの。「傑作」
〔国〕作物のできぐあい。「作柄サクガラ」「平年作」
《解字》
会意兼形声。乍サクは、刀で素材に切れ目を入れるさまを描いた象形文字。急激な動作であることから、たちまちにの意の副詞に専用するようになったため、作の字で人為を加える、動作をするの意をあらわすようになった。作は「人+音符乍サ」。
《類義》
→造・→建
《異字同訓》
つくる。 作る「米を作る。規則を作る。小説を作る。まぐろを刺身に作る。生け作り」造る「船を造る。庭園を造る。酒を造る」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
{名}つくったもの。「傑作」
〔国〕作物のできぐあい。「作柄サクガラ」「平年作」
《解字》
会意兼形声。乍サクは、刀で素材に切れ目を入れるさまを描いた象形文字。急激な動作であることから、たちまちにの意の副詞に専用するようになったため、作の字で人為を加える、動作をするの意をあらわすようになった。作は「人+音符乍サ」。
《類義》
→造・→建
《異字同訓》
つくる。 作る「米を作る。規則を作る。小説を作る。まぐろを刺身に作る。生け作り」造る「船を造る。庭園を造る。酒を造る」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
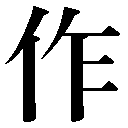 7画 人部 [二年]
区点=2678 16進=3A6E シフトJIS=8DEC
【做】異体字異体字
7画 人部 [二年]
区点=2678 16進=3A6E シフトJIS=8DEC
【做】異体字異体字
 11画 人部
区点=4886 16進=5076 シフトJIS=98F4
《常用音訓》サ/サク/つく…る
《音読み》 サク
11画 人部
区点=4886 16進=5076 シフトJIS=98F4
《常用音訓》サ/サク/つく…る
《音読み》 サク
 /サ
/サ
 〈zu
〈zu ・zu
・zu 〉〈zu
〉〈zu 〉
《訓読み》 つくる/なす/なる/おきる(おく)/おこる
《名付け》 あり・つくり・つくる・とも・なお・なり・ふか
《意味》
〉
《訓読み》 つくる/なす/なる/おきる(おく)/おこる
《名付け》 あり・つくり・つくる・とも・なお・なり・ふか
《意味》
 {動}つくる。新たに工夫してつくり出す。「創作」「述而不作=述ベテ作ラズ」〔→論語〕「作離騒=離騒ヲ作ル」〔→史記〕
{動}つくる。新たに工夫してつくり出す。「創作」「述而不作=述ベテ作ラズ」〔→論語〕「作離騒=離騒ヲ作ル」〔→史記〕
 {動}なす。する。「作為」「動作」
{動}なす。する。「作為」「動作」
 {動}なる。変化してその状態になる。「翻手作雲覆手雨=手ヲ翻セバ雲ト作リ手ヲ覆セバ雨」〔→杜甫〕
{動}なる。変化してその状態になる。「翻手作雲覆手雨=手ヲ翻セバ雲ト作リ手ヲ覆セバ雨」〔→杜甫〕
 {動}おきる(オク)。おき出す。働く。「蚤作而夜思=蚤ク作キテ夜思フ」〔→柳宗元〕
{動}おきる(オク)。おき出す。働く。「蚤作而夜思=蚤ク作キテ夜思フ」〔→柳宗元〕
 {動}おこる。動作がおこる。生じてくる。「発作」「有聖人作=聖人ノ作ル有リ」〔→韓非〕
{動}おこる。動作がおこる。生じてくる。「発作」「有聖人作=聖人ノ作ル有リ」〔→韓非〕
 {名}つくったもの。「傑作」
〔国〕作物のできぐあい。「作柄サクガラ」「平年作」
《解字》
会意兼形声。乍サクは、刀で素材に切れ目を入れるさまを描いた象形文字。急激な動作であることから、たちまちにの意の副詞に専用するようになったため、作の字で人為を加える、動作をするの意をあらわすようになった。作は「人+音符乍サ」。
《類義》
→造・→建
《異字同訓》
つくる。 作る「米を作る。規則を作る。小説を作る。まぐろを刺身に作る。生け作り」造る「船を造る。庭園を造る。酒を造る」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
{名}つくったもの。「傑作」
〔国〕作物のできぐあい。「作柄サクガラ」「平年作」
《解字》
会意兼形声。乍サクは、刀で素材に切れ目を入れるさまを描いた象形文字。急激な動作であることから、たちまちにの意の副詞に専用するようになったため、作の字で人為を加える、動作をするの意をあらわすようになった。作は「人+音符乍サ」。
《類義》
→造・→建
《異字同訓》
つくる。 作る「米を作る。規則を作る。小説を作る。まぐろを刺身に作る。生け作り」造る「船を造る。庭園を造る。酒を造る」
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→故事成語
漢字源 ページ 228。