複数辞典一括検索+![]()
![]()
【碧漢】🔗⭐🔉
【碧漢】
ヘキカン 青空と銀河。天をさしていうことば。▽「漢」は、天漢(天の川)。
【碧殿】🔗⭐🔉
【碧殿】
ヘキデン  青緑色をした家。特に、俗世をはなれた人の住む家のこと。
青緑色をした家。特に、俗世をはなれた人の住む家のこと。 碧玉ヘキギョクで飾られたりっぱな御殿。
碧玉ヘキギョクで飾られたりっぱな御殿。
 青緑色をした家。特に、俗世をはなれた人の住む家のこと。
青緑色をした家。特に、俗世をはなれた人の住む家のこと。 碧玉ヘキギョクで飾られたりっぱな御殿。
碧玉ヘキギョクで飾られたりっぱな御殿。
【碧緑】🔗⭐🔉
【碧緑】
ヘキリョク 深緑色。
【碧澗】🔗⭐🔉
【碧澗】
ヘキカン 青々とした水をたたえた谷川。
【碧潭】🔗⭐🔉
【碧潭】
ヘキタン 水が深く青緑色に見えるふち。
【碧羅】🔗⭐🔉
【碧羅】
ヘキラ 青緑色の薄い絹。また、それでできた着物。「碧羅冠子穏犀簪=碧羅ノ冠子ハ犀簪ニ穏ヘラル」〔和凝〕
【碧蘚】🔗⭐🔉
【碧蘚】
ヘキセン 青緑色をしたこけ。『碧苔ヘキタイ』
【碧巌】🔗⭐🔉
【碧巌】
ヘキガン 青緑色の岩。こけのはえている岩。
【碧巌録】🔗⭐🔉
【碧巌録】
ヘキガンロク〈書物〉一〇巻。宋ソウの僧、圜悟エンゴ(1063〜1135)の著。1125年に成立。参禅の教典。「碧巌」とは、圜悟のいた湖南省夾山キョウザンの霊泉院の方丈にかけられてあった額の文字を採ったもの。本則と頌ショウの部分は雪門宗の僧雪竇セットウ(980〜1052)の作で、圜悟が学僧に教えるために雪竇の作から百則を選んで、解説や批評をつけた。日本には鎌倉時代から伝えられ、五山版以来何回も出版されて解説書も多い。『仏果圜悟禅師碧巌録』が正式の書名、禅家では『碧巌集』と呼んでいる。
【磑】🔗⭐🔉
【磑】
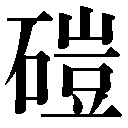 15画 石部
区点=6686 16進=6276 シフトJIS=E1F4
《音読み》 ガイ(グ
15画 石部
区点=6686 16進=6276 シフトJIS=E1F4
《音読み》 ガイ(グ イ)
イ) /ゲ
/ゲ 〈w
〈w i〉
《訓読み》 うす/つむ/しろい(しろし)
《意味》
i〉
《訓読み》 うす/つむ/しろい(しろし)
《意味》

 {名}うす。みぞをつけた石と石をすりあわせて、穀物などをごりごりと粉にする道具。ひきうす。石うす。
{名}うす。みぞをつけた石と石をすりあわせて、穀物などをごりごりと粉にする道具。ひきうす。石うす。
 {動}つむ。ごりごりした面をあわせて、高くつみ重ねる。
{動}つむ。ごりごりした面をあわせて、高くつみ重ねる。
 {形}しろい(シロシ)。よごれをこすりとったようにしろい。▽皚ガイに当てた用法。
{形}しろい(シロシ)。よごれをこすりとったようにしろい。▽皚ガイに当てた用法。
 「磑磑ガイガイ」とは、(イ)ごりごりしてかたいさま。「行積氷之磑磑兮=積氷ノ磑磑タルヲ行ク」〔→後漢書〕(ロ)雪などのしろいさま。(ハ)高くそびえるさま。〈同義語〉皚皚。
《解字》
会意兼形声。「石+音符豈ガイ(がらがらと音を出す、きしる)」。
《単語家族》
剴ガイ(ごりごりと切る)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
「磑磑ガイガイ」とは、(イ)ごりごりしてかたいさま。「行積氷之磑磑兮=積氷ノ磑磑タルヲ行ク」〔→後漢書〕(ロ)雪などのしろいさま。(ハ)高くそびえるさま。〈同義語〉皚皚。
《解字》
会意兼形声。「石+音符豈ガイ(がらがらと音を出す、きしる)」。
《単語家族》
剴ガイ(ごりごりと切る)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
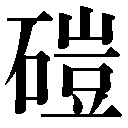 15画 石部
区点=6686 16進=6276 シフトJIS=E1F4
《音読み》 ガイ(グ
15画 石部
区点=6686 16進=6276 シフトJIS=E1F4
《音読み》 ガイ(グ イ)
イ) /ゲ
/ゲ 〈w
〈w i〉
《訓読み》 うす/つむ/しろい(しろし)
《意味》
i〉
《訓読み》 うす/つむ/しろい(しろし)
《意味》

 {名}うす。みぞをつけた石と石をすりあわせて、穀物などをごりごりと粉にする道具。ひきうす。石うす。
{名}うす。みぞをつけた石と石をすりあわせて、穀物などをごりごりと粉にする道具。ひきうす。石うす。
 {動}つむ。ごりごりした面をあわせて、高くつみ重ねる。
{動}つむ。ごりごりした面をあわせて、高くつみ重ねる。
 {形}しろい(シロシ)。よごれをこすりとったようにしろい。▽皚ガイに当てた用法。
{形}しろい(シロシ)。よごれをこすりとったようにしろい。▽皚ガイに当てた用法。
 「磑磑ガイガイ」とは、(イ)ごりごりしてかたいさま。「行積氷之磑磑兮=積氷ノ磑磑タルヲ行ク」〔→後漢書〕(ロ)雪などのしろいさま。(ハ)高くそびえるさま。〈同義語〉皚皚。
《解字》
会意兼形声。「石+音符豈ガイ(がらがらと音を出す、きしる)」。
《単語家族》
剴ガイ(ごりごりと切る)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
「磑磑ガイガイ」とは、(イ)ごりごりしてかたいさま。「行積氷之磑磑兮=積氷ノ磑磑タルヲ行ク」〔→後漢書〕(ロ)雪などのしろいさま。(ハ)高くそびえるさま。〈同義語〉皚皚。
《解字》
会意兼形声。「石+音符豈ガイ(がらがらと音を出す、きしる)」。
《単語家族》
剴ガイ(ごりごりと切る)と同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
漢字源 ページ 3123。