複数辞典一括検索+![]()
![]()
【菜】🔗⭐🔉
【菜食】🔗⭐🔉
【菜食】
サイショク  野菜類だけの質素な食事をする。
野菜類だけの質素な食事をする。 肉食に対して、主に野菜を常食とすること。「菜食主義」
肉食に対して、主に野菜を常食とすること。「菜食主義」
 野菜類だけの質素な食事をする。
野菜類だけの質素な食事をする。 肉食に対して、主に野菜を常食とすること。「菜食主義」
肉食に対して、主に野菜を常食とすること。「菜食主義」
【菜根】🔗⭐🔉
【菜根】
サイコン  野菜の根。
野菜の根。 転じて、質素な食事。
転じて、質素な食事。
 野菜の根。
野菜の根。 転じて、質素な食事。
転じて、質素な食事。
【菜茹】🔗⭐🔉
【菜茹】
サイジョ 野菜。あおもの。▽「茹」は、柔らかい菜。
【菜圃】🔗⭐🔉
【菜圃】
サイホ 野菜ばたけ。『菜園サイエン・菜畦サイケイ』
【菜羹】🔗⭐🔉
【菜羹】
サイコウ 野菜のあつもの。蔬羹ソコウ。
【菜根譚】🔗⭐🔉
【菜根譚】
サイコンタン〈書物〉二巻。明ミン末の洪応明コウオウメイの著。成立年代不明。著者は四川シセン省の人で明末の1573〜1620年ごろの人らしい。「菜根」とはまずい食物を意味し、宋ソウの儒者汪革オウカクの「人間はいつも菜根をかじっていたら、万事がうまくいく」という語から、書名をとったもの。世俗に対する批判、処世・交友の道、閑居の楽しみなどがのべられているが、主として儒教的倫理観によりながら、道教・仏教の思想もとり入れられ、わかりやすい通俗的な処世訓の書となっている。中国でよりも、むしろ日本で広く読まれた本で、1822年に刊行されて以来、多くの注釈書が出され、特に禅僧の間で愛読されて来た。『菜根談』とも書く。
漢字源 ページ 3777。
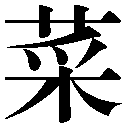 11画 艸部 [四年]
区点=2658 16進=3A5A シフトJIS=8DD8
《常用音訓》サイ/な
《音読み》 サイ
11画 艸部 [四年]
区点=2658 16進=3A5A シフトJIS=8DD8
《常用音訓》サイ/な
《音読み》 サイ
 〈c
〈c i〉
《訓読み》 な
《名付け》 な
《意味》
i〉
《訓読み》 な
《名付け》 な
《意味》
 {名}な。葉・くきを食用とする草本類の総称。つみな。なっぱ。「野菜」「蔬菜ソサイ」
{名}な。葉・くきを食用とする草本類の総称。つみな。なっぱ。「野菜」「蔬菜ソサイ」
 {名}な。草の名。種から菜種油をとる。あぶらな。「菜子(なたね)」
{名}な。草の名。種から菜種油をとる。あぶらな。「菜子(なたね)」
 {名}副食物。おかず。また、料理。「菜館」「惣菜ソウザイ」
《解字》
会意兼形声。「艸+音符采サイ(=採。つみとる)」。つみなのこと。
《熟語》
{名}副食物。おかず。また、料理。「菜館」「惣菜ソウザイ」
《解字》
会意兼形声。「艸+音符采サイ(=採。つみとる)」。つみなのこと。
《熟語》