複数辞典一括検索+![]()
![]()
【蕾】🔗⭐🔉
【蕾】
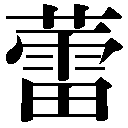 16画 艸部
区点=7318 16進=6932 シフトJIS=E551
《音読み》 ライ
16画 艸部
区点=7318 16進=6932 シフトJIS=E551
《音読み》 ライ
 〈l
〈l i〉
《訓読み》 つぼみ
《意味》
{名}つぼみ。いくつも重なった花のつぼみ。
《解字》
会意兼形声。「艸+音符雷(かさなって集まる)」
i〉
《訓読み》 つぼみ
《意味》
{名}つぼみ。いくつも重なった花のつぼみ。
《解字》
会意兼形声。「艸+音符雷(かさなって集まる)」
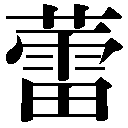 16画 艸部
区点=7318 16進=6932 シフトJIS=E551
《音読み》 ライ
16画 艸部
区点=7318 16進=6932 シフトJIS=E551
《音読み》 ライ
 〈l
〈l i〉
《訓読み》 つぼみ
《意味》
{名}つぼみ。いくつも重なった花のつぼみ。
《解字》
会意兼形声。「艸+音符雷(かさなって集まる)」
i〉
《訓読み》 つぼみ
《意味》
{名}つぼみ。いくつも重なった花のつぼみ。
《解字》
会意兼形声。「艸+音符雷(かさなって集まる)」
【薐】🔗⭐🔉
【薐】
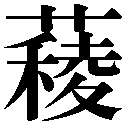 16画 艸部
区点=7319 16進=6933 シフトJIS=E552
《音読み》 リョウ
16画 艸部
区点=7319 16進=6933 シフトJIS=E552
《音読み》 リョウ /リン
/リン /ロウ
/ロウ
 〈l
〈l ng〉
《意味》
「菠薐ハリョウ」とは、野菜の名。ほうれんそう。▽ホウレンは、唐宋トウソウ音ホリンのなまったもの。
《解字》
形声。「艸+音符稜ロウ」。
ng〉
《意味》
「菠薐ハリョウ」とは、野菜の名。ほうれんそう。▽ホウレンは、唐宋トウソウ音ホリンのなまったもの。
《解字》
形声。「艸+音符稜ロウ」。
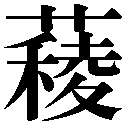 16画 艸部
区点=7319 16進=6933 シフトJIS=E552
《音読み》 リョウ
16画 艸部
区点=7319 16進=6933 シフトJIS=E552
《音読み》 リョウ /リン
/リン /ロウ
/ロウ
 〈l
〈l ng〉
《意味》
「菠薐ハリョウ」とは、野菜の名。ほうれんそう。▽ホウレンは、唐宋トウソウ音ホリンのなまったもの。
《解字》
形声。「艸+音符稜ロウ」。
ng〉
《意味》
「菠薐ハリョウ」とは、野菜の名。ほうれんそう。▽ホウレンは、唐宋トウソウ音ホリンのなまったもの。
《解字》
形声。「艸+音符稜ロウ」。
【薩】🔗⭐🔉
【薩】
 17画 艸部
区点=2707 16進=3B27 シフトJIS=8E46
《音読み》 サツ
17画 艸部
区点=2707 16進=3B27 シフトJIS=8E46
《音読み》 サツ /サチ
/サチ 〈s
〈s 〉
《意味》
〉
《意味》
 {動}あまねく衆生シュジョウをすくう。済度サイド。また、仏道修行をして悟りを得る。
{動}あまねく衆生シュジョウをすくう。済度サイド。また、仏道修行をして悟りを得る。
 〔仏〕「菩薩ボサツ」とは、仏につぐ地位にある有徳の修行者。▽梵語ボンゴの音訳。
《解字》
梵語ボンゴの音訳に当てた字で、もと薛セツと書いたが、のち、薩と書くようになった。
《熟語》
→下付・中付語
〔仏〕「菩薩ボサツ」とは、仏につぐ地位にある有徳の修行者。▽梵語ボンゴの音訳。
《解字》
梵語ボンゴの音訳に当てた字で、もと薛セツと書いたが、のち、薩と書くようになった。
《熟語》
→下付・中付語
 17画 艸部
区点=2707 16進=3B27 シフトJIS=8E46
《音読み》 サツ
17画 艸部
区点=2707 16進=3B27 シフトJIS=8E46
《音読み》 サツ /サチ
/サチ 〈s
〈s 〉
《意味》
〉
《意味》
 {動}あまねく衆生シュジョウをすくう。済度サイド。また、仏道修行をして悟りを得る。
{動}あまねく衆生シュジョウをすくう。済度サイド。また、仏道修行をして悟りを得る。
 〔仏〕「菩薩ボサツ」とは、仏につぐ地位にある有徳の修行者。▽梵語ボンゴの音訳。
《解字》
梵語ボンゴの音訳に当てた字で、もと薛セツと書いたが、のち、薩と書くようになった。
《熟語》
→下付・中付語
〔仏〕「菩薩ボサツ」とは、仏につぐ地位にある有徳の修行者。▽梵語ボンゴの音訳。
《解字》
梵語ボンゴの音訳に当てた字で、もと薛セツと書いたが、のち、薩と書くようになった。
《熟語》
→下付・中付語
【藉】🔗⭐🔉
【藉】
 17画 艸部
区点=7320 16進=6934 シフトJIS=E553
《音読み》
17画 艸部
区点=7320 16進=6934 シフトJIS=E553
《音読み》  シャ
シャ /ジャ
/ジャ 〈ji
〈ji 〉/
〉/ セキ
セキ /ジャク
/ジャク 〈j
〈j 〉
《訓読み》 しく/かりる(かる)/よる/かす/ふむ
《意味》
〉
《訓読み》 しく/かりる(かる)/よる/かす/ふむ
《意味》

 {動}しく。草やむしろをしく。また、下にしいて、その上にすわったり、ねたりする。〈同義語〉→籍。「枕藉チンシャ(下にしいて枕マクラにする)」「藉之用茅=コレヲ藉クニ茅ヲ用フ」〔→易経〕
{動}しく。草やむしろをしく。また、下にしいて、その上にすわったり、ねたりする。〈同義語〉→籍。「枕藉チンシャ(下にしいて枕マクラにする)」「藉之用茅=コレヲ藉クニ茅ヲ用フ」〔→易経〕
 {動}かりる(カル)。よる。下地を設けてそれにたよる。また、かりて用いる。お陰をこうむる。「馮藉ヒョウシャ(たよる)」「藉端生事=端ヲ藉リテ事ヲ生ズ」「藉口シャコウ」
{動}かりる(カル)。よる。下地を設けてそれにたよる。また、かりて用いる。お陰をこうむる。「馮藉ヒョウシャ(たよる)」「藉端生事=端ヲ藉リテ事ヲ生ズ」「藉口シャコウ」
 {動}かす。かさねてやる。つけ加える。〈同義語〉→借。「藉手=手ヲ藉ス」
{動}かす。かさねてやる。つけ加える。〈同義語〉→借。「藉手=手ヲ藉ス」
 {名}下にしくしきもの。〈類義語〉→席。
{名}下にしくしきもの。〈類義語〉→席。
 {動}間にクッションをしきこむ。間に理由・口実やゆとりを設けてやわらげる。大目にみる。なぐさめる。「慰藉イシャ」「藉之以楽=コレヲ藉ムルニ楽ヲモッテス」〔→左伝〕
{動}間にクッションをしきこむ。間に理由・口実やゆとりを設けてやわらげる。大目にみる。なぐさめる。「慰藉イシャ」「藉之以楽=コレヲ藉ムルニ楽ヲモッテス」〔→左伝〕

 {動}たがやす。すきをさしこんで、土をかえす。「藉田セキデン」
{動}たがやす。すきをさしこんで、土をかえす。「藉田セキデン」
 {動}ふむ。下にしいてふむ。「狼藉ロウゼキ(おおかみがふみにじったように乱れる)」
《解字》
会意兼形声。下部の字(音セキ)は「耒(すき)+音符昔セキ」から成り、すきを地表の下にしきこんで土をすき、おこした土を上に重ねること。藉はそれを音符とし、艸(くさ)を加えた字で、草むしろを下にしきこんで、その上にのること。
《単語家族》
昔(日がしき重なる→むかし)
{動}ふむ。下にしいてふむ。「狼藉ロウゼキ(おおかみがふみにじったように乱れる)」
《解字》
会意兼形声。下部の字(音セキ)は「耒(すき)+音符昔セキ」から成り、すきを地表の下にしきこんで土をすき、おこした土を上に重ねること。藉はそれを音符とし、艸(くさ)を加えた字で、草むしろを下にしきこんで、その上にのること。
《単語家族》
昔(日がしき重なる→むかし) 籍セキ(下にしいて上へ重ねて積む竹札)
籍セキ(下にしいて上へ重ねて積む竹札) 席(下にしいて、上へのるしきもの)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
席(下にしいて、上へのるしきもの)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 17画 艸部
区点=7320 16進=6934 シフトJIS=E553
《音読み》
17画 艸部
区点=7320 16進=6934 シフトJIS=E553
《音読み》  シャ
シャ /ジャ
/ジャ 〈ji
〈ji 〉/
〉/ セキ
セキ /ジャク
/ジャク 〈j
〈j 〉
《訓読み》 しく/かりる(かる)/よる/かす/ふむ
《意味》
〉
《訓読み》 しく/かりる(かる)/よる/かす/ふむ
《意味》

 {動}しく。草やむしろをしく。また、下にしいて、その上にすわったり、ねたりする。〈同義語〉→籍。「枕藉チンシャ(下にしいて枕マクラにする)」「藉之用茅=コレヲ藉クニ茅ヲ用フ」〔→易経〕
{動}しく。草やむしろをしく。また、下にしいて、その上にすわったり、ねたりする。〈同義語〉→籍。「枕藉チンシャ(下にしいて枕マクラにする)」「藉之用茅=コレヲ藉クニ茅ヲ用フ」〔→易経〕
 {動}かりる(カル)。よる。下地を設けてそれにたよる。また、かりて用いる。お陰をこうむる。「馮藉ヒョウシャ(たよる)」「藉端生事=端ヲ藉リテ事ヲ生ズ」「藉口シャコウ」
{動}かりる(カル)。よる。下地を設けてそれにたよる。また、かりて用いる。お陰をこうむる。「馮藉ヒョウシャ(たよる)」「藉端生事=端ヲ藉リテ事ヲ生ズ」「藉口シャコウ」
 {動}かす。かさねてやる。つけ加える。〈同義語〉→借。「藉手=手ヲ藉ス」
{動}かす。かさねてやる。つけ加える。〈同義語〉→借。「藉手=手ヲ藉ス」
 {名}下にしくしきもの。〈類義語〉→席。
{名}下にしくしきもの。〈類義語〉→席。
 {動}間にクッションをしきこむ。間に理由・口実やゆとりを設けてやわらげる。大目にみる。なぐさめる。「慰藉イシャ」「藉之以楽=コレヲ藉ムルニ楽ヲモッテス」〔→左伝〕
{動}間にクッションをしきこむ。間に理由・口実やゆとりを設けてやわらげる。大目にみる。なぐさめる。「慰藉イシャ」「藉之以楽=コレヲ藉ムルニ楽ヲモッテス」〔→左伝〕

 {動}たがやす。すきをさしこんで、土をかえす。「藉田セキデン」
{動}たがやす。すきをさしこんで、土をかえす。「藉田セキデン」
 {動}ふむ。下にしいてふむ。「狼藉ロウゼキ(おおかみがふみにじったように乱れる)」
《解字》
会意兼形声。下部の字(音セキ)は「耒(すき)+音符昔セキ」から成り、すきを地表の下にしきこんで土をすき、おこした土を上に重ねること。藉はそれを音符とし、艸(くさ)を加えた字で、草むしろを下にしきこんで、その上にのること。
《単語家族》
昔(日がしき重なる→むかし)
{動}ふむ。下にしいてふむ。「狼藉ロウゼキ(おおかみがふみにじったように乱れる)」
《解字》
会意兼形声。下部の字(音セキ)は「耒(すき)+音符昔セキ」から成り、すきを地表の下にしきこんで土をすき、おこした土を上に重ねること。藉はそれを音符とし、艸(くさ)を加えた字で、草むしろを下にしきこんで、その上にのること。
《単語家族》
昔(日がしき重なる→むかし) 籍セキ(下にしいて上へ重ねて積む竹札)
籍セキ(下にしいて上へ重ねて積む竹札) 席(下にしいて、上へのるしきもの)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
席(下にしいて、上へのるしきもの)などと同系。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
漢字源 ページ 3864。