複数辞典一括検索+![]()
![]()
【不知其子視其友】🔗⭐🔉
【不知其子視其友】
ソノコヲシラザレバソノトモヲミヨ〈故事〉その子のことがわからないときは、その子の友人を見ればわかる。ある人間の善悪は、その人間の交友関係を見ればわかる。〔→荀子〕
【与其有諾責也寧有已怨】🔗⭐🔉
【与其有諾責也寧有已怨】
ソノダクセキアランヨリハムシロイエンアレ〈故事〉承諾したことを果たさなくて人からうらまれるよりは、むしろ要求をことわってうらまれるほうがよい。〔→礼記〕
【其思】🔗⭐🔉
【其思】
キシ〈人名〉春秋時代、楚ソの賢人其思革子カクシのこと。成王が賢人を募ったとき応ずる途上死に直面、同行の賢人戸文子コブンシ・叔衍子シュクエンシの犠牲によりひとり王のもとに至る。
【具】🔗⭐🔉
【具】
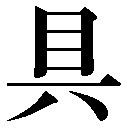 8画 八部 [三年]
区点=2281 16進=3671 シフトJIS=8BEF
《常用音訓》グ
《音読み》 グ
8画 八部 [三年]
区点=2281 16進=3671 シフトJIS=8BEF
《常用音訓》グ
《音読み》 グ /ク
/ク 〈j
〈j 〉
《訓読み》 そなわる(そなはる)/そなえる(そなふ)/つぶさに/ともに
《名付け》 とも
《意味》
〉
《訓読み》 そなわる(そなはる)/そなえる(そなふ)/つぶさに/ともに
《名付け》 とも
《意味》
 {動}そなわる(ソナハル)。そなえる(ソナフ)。おぜんだてがそろう。必要な物をそろえる。「具備」「令既具未布=令既ニ具ハリテ未ダ布カズ」〔→史記〕
{動}そなわる(ソナハル)。そなえる(ソナフ)。おぜんだてがそろう。必要な物をそろえる。「具備」「令既具未布=令既ニ具ハリテ未ダ布カズ」〔→史記〕
 {動}そなわる(ソナハル)。そなえる(ソナフ)。いちおう形をそなえる。どうにか数だけそろえる。「具数(頭数だけそろえる)」「冉牛閔子顔淵、則具体而微=冉牛閔子顔淵ハ、則チ体ヲ具ヘテ微ナリ」〔→孟子〕
{動}そなわる(ソナハル)。そなえる(ソナフ)。いちおう形をそなえる。どうにか数だけそろえる。「具数(頭数だけそろえる)」「冉牛閔子顔淵、則具体而微=冉牛閔子顔淵ハ、則チ体ヲ具ヘテ微ナリ」〔→孟子〕
 {名}仕事のためそろえておく用具。「道具」
{名}仕事のためそろえておく用具。「道具」
 {副}つぶさに。具体的に。こまごまと。欠けめなくひとそろい。「具答之=具ニコレニ答フ」〔→陶潜〕
{副}つぶさに。具体的に。こまごまと。欠けめなくひとそろい。「具答之=具ニコレニ答フ」〔→陶潜〕
 {副}ともに。あれもこれも。
《解字》
{副}ともに。あれもこれも。
《解字》
 会意。上部は鼎カナエの形、下部に両手を添えて、食物を鼎にそろえてさし出すさまを示す。そろえる、ひとそろい、そろえた用具などの意を含む。
《類義》
→備
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
会意。上部は鼎カナエの形、下部に両手を添えて、食物を鼎にそろえてさし出すさまを示す。そろえる、ひとそろい、そろえた用具などの意を含む。
《類義》
→備
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
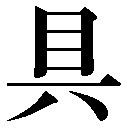 8画 八部 [三年]
区点=2281 16進=3671 シフトJIS=8BEF
《常用音訓》グ
《音読み》 グ
8画 八部 [三年]
区点=2281 16進=3671 シフトJIS=8BEF
《常用音訓》グ
《音読み》 グ /ク
/ク 〈j
〈j 〉
《訓読み》 そなわる(そなはる)/そなえる(そなふ)/つぶさに/ともに
《名付け》 とも
《意味》
〉
《訓読み》 そなわる(そなはる)/そなえる(そなふ)/つぶさに/ともに
《名付け》 とも
《意味》
 {動}そなわる(ソナハル)。そなえる(ソナフ)。おぜんだてがそろう。必要な物をそろえる。「具備」「令既具未布=令既ニ具ハリテ未ダ布カズ」〔→史記〕
{動}そなわる(ソナハル)。そなえる(ソナフ)。おぜんだてがそろう。必要な物をそろえる。「具備」「令既具未布=令既ニ具ハリテ未ダ布カズ」〔→史記〕
 {動}そなわる(ソナハル)。そなえる(ソナフ)。いちおう形をそなえる。どうにか数だけそろえる。「具数(頭数だけそろえる)」「冉牛閔子顔淵、則具体而微=冉牛閔子顔淵ハ、則チ体ヲ具ヘテ微ナリ」〔→孟子〕
{動}そなわる(ソナハル)。そなえる(ソナフ)。いちおう形をそなえる。どうにか数だけそろえる。「具数(頭数だけそろえる)」「冉牛閔子顔淵、則具体而微=冉牛閔子顔淵ハ、則チ体ヲ具ヘテ微ナリ」〔→孟子〕
 {名}仕事のためそろえておく用具。「道具」
{名}仕事のためそろえておく用具。「道具」
 {副}つぶさに。具体的に。こまごまと。欠けめなくひとそろい。「具答之=具ニコレニ答フ」〔→陶潜〕
{副}つぶさに。具体的に。こまごまと。欠けめなくひとそろい。「具答之=具ニコレニ答フ」〔→陶潜〕
 {副}ともに。あれもこれも。
《解字》
{副}ともに。あれもこれも。
《解字》
 会意。上部は鼎カナエの形、下部に両手を添えて、食物を鼎にそろえてさし出すさまを示す。そろえる、ひとそろい、そろえた用具などの意を含む。
《類義》
→備
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
会意。上部は鼎カナエの形、下部に両手を添えて、食物を鼎にそろえてさし出すさまを示す。そろえる、ひとそろい、そろえた用具などの意を含む。
《類義》
→備
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
漢字源 ページ 419。