複数辞典一括検索+![]()
![]()
【里俗】🔗⭐🔉
【里俗】
リゾク =俚俗。村のならわし。いなかである地方の風俗のこと。
【里程】🔗⭐🔉
【里程】
リテイ  距離を里であらわしたもの。
距離を里であらわしたもの。 二地点間の道のり。
二地点間の道のり。
 距離を里であらわしたもの。
距離を里であらわしたもの。 二地点間の道のり。
二地点間の道のり。
【里魁】🔗⭐🔉
【里魁】
リカイ 後漢・南宋ナンソウの制度で、里の長。
【里塾】🔗⭐🔉
【里塾】
リジュク 村の学校。村塾。村学。
【里諺】🔗⭐🔉
【里諺】
リゲン =俚諺。民間で用いられていることわざ。〈類義語〉野諺ヤゲン。
【里{俚}謡】🔗⭐🔉
【里{俚}謡】
リヨウ 民間で歌われるはやりうた。
【重】🔗⭐🔉
【重】
 9画 里部 [三年]
区点=2937 16進=3D45 シフトJIS=8F64
《常用音訓》ジュウ/チョウ/え/おも…い/かさ…なる/かさ…ねる
《音読み》 ジュウ(ヂュウ)
9画 里部 [三年]
区点=2937 16進=3D45 シフトJIS=8F64
《常用音訓》ジュウ/チョウ/え/おも…い/かさ…なる/かさ…ねる
《音読み》 ジュウ(ヂュウ) /チョウ
/チョウ 〈zh
〈zh ng〉〈ch
ng〉〈ch ng〉
《訓読み》 え/おもい(おもし)/おもさ/おもんずる(おもんず)/かさなる/かさねる(かさぬ)
《名付け》 あつ・あつし・いかし・え・おもし・かさぬ・かず・かたし・しげ・しげし・しげる・のぶ・ふさ
《意味》
ng〉
《訓読み》 え/おもい(おもし)/おもさ/おもんずる(おもんず)/かさなる/かさねる(かさぬ)
《名付け》 あつ・あつし・いかし・え・おもし・かさぬ・かず・かたし・しげ・しげし・しげる・のぶ・ふさ
《意味》
 {形・名}おもい(オモシ)。おもさ。↓の方向に力が加わった状態。↓の方向の力が底面に加わった感じ。おもみ。〈対語〉→軽。「軽重ケイチョウ/ケイジュウ(おもさ)」「重量」「重一鈞オモサイッキン」
{形・名}おもい(オモシ)。おもさ。↓の方向に力が加わった状態。↓の方向の力が底面に加わった感じ。おもみ。〈対語〉→軽。「軽重ケイチョウ/ケイジュウ(おもさ)」「重量」「重一鈞オモサイッキン」
 {形}おもい(オモシ)。病気・罪・声・やり方などがおもい。おもおもしい。てあつい。「厳重」「慎重」「重濁」「重賄之=重クコレニ賄ス」〔→左伝〕「君子不重則不威=君子ハ重カラザレバスナハチ威アラズ」〔→論語〕
{形}おもい(オモシ)。病気・罪・声・やり方などがおもい。おもおもしい。てあつい。「厳重」「慎重」「重濁」「重賄之=重クコレニ賄ス」〔→左伝〕「君子不重則不威=君子ハ重カラザレバスナハチ威アラズ」〔→論語〕
 {動}おもんずる(オモンズ)。たいせつなものとして敬い扱う。おもくみる。転じて、はばかる。▽この訓は「おもみす」の転じたもの。「尊重」「重社稷=社稷ヲ重ンズ」〔→礼記〕
{動}おもんずる(オモンズ)。たいせつなものとして敬い扱う。おもくみる。転じて、はばかる。▽この訓は「おもみす」の転じたもの。「尊重」「重社稷=社稷ヲ重ンズ」〔→礼記〕
 {動・形}かさなる。かさねる(カサヌ)。上へおいて下におもみをかける。層をなしてかさなったさま。▽平声に読む。「重複チョウフク」「重畳チョウジョウ」
{動・形}かさなる。かさねる(カサヌ)。上へおいて下におもみをかける。層をなしてかさなったさま。▽平声に読む。「重複チョウフク」「重畳チョウジョウ」
 {単位}下をおさえて上にかさなった物を数えることば。▽平声に読む。〈類義語〉→層ソウ。「万重山バンチョウノヤマ(いくえにもかさなった山)」
〔国〕かさなった物を数えることば。え。「七重八重ナナエヤエ」
《解字》
{単位}下をおさえて上にかさなった物を数えることば。▽平声に読む。〈類義語〉→層ソウ。「万重山バンチョウノヤマ(いくえにもかさなった山)」
〔国〕かさなった物を数えることば。え。「七重八重ナナエヤエ」
《解字》
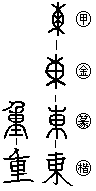 会意兼形声。東トウは、心棒がつきぬけた袋を描いた象形文字で、つきとおすの意を含む。重は「人が土の上にたったさま+音符東」で、人体のおもみが↓型につきぬけて、地上の一点にかかることを示す。→東
《単語家族》
動(トンと足ぶみして↓型におもみをかける)
会意兼形声。東トウは、心棒がつきぬけた袋を描いた象形文字で、つきとおすの意を含む。重は「人が土の上にたったさま+音符東」で、人体のおもみが↓型につきぬけて、地上の一点にかかることを示す。→東
《単語家族》
動(トンと足ぶみして↓型におもみをかける) 衝ショウ(↓型につきあたる)と同系。
《類義》
申は、下の物をおしのばすこと。累ルイは、ごろごろとつみかさねること。襲は、かさねて二重にすること。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
衝ショウ(↓型につきあたる)と同系。
《類義》
申は、下の物をおしのばすこと。累ルイは、ごろごろとつみかさねること。襲は、かさねて二重にすること。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
 9画 里部 [三年]
区点=2937 16進=3D45 シフトJIS=8F64
《常用音訓》ジュウ/チョウ/え/おも…い/かさ…なる/かさ…ねる
《音読み》 ジュウ(ヂュウ)
9画 里部 [三年]
区点=2937 16進=3D45 シフトJIS=8F64
《常用音訓》ジュウ/チョウ/え/おも…い/かさ…なる/かさ…ねる
《音読み》 ジュウ(ヂュウ) /チョウ
/チョウ 〈zh
〈zh ng〉〈ch
ng〉〈ch ng〉
《訓読み》 え/おもい(おもし)/おもさ/おもんずる(おもんず)/かさなる/かさねる(かさぬ)
《名付け》 あつ・あつし・いかし・え・おもし・かさぬ・かず・かたし・しげ・しげし・しげる・のぶ・ふさ
《意味》
ng〉
《訓読み》 え/おもい(おもし)/おもさ/おもんずる(おもんず)/かさなる/かさねる(かさぬ)
《名付け》 あつ・あつし・いかし・え・おもし・かさぬ・かず・かたし・しげ・しげし・しげる・のぶ・ふさ
《意味》
 {形・名}おもい(オモシ)。おもさ。↓の方向に力が加わった状態。↓の方向の力が底面に加わった感じ。おもみ。〈対語〉→軽。「軽重ケイチョウ/ケイジュウ(おもさ)」「重量」「重一鈞オモサイッキン」
{形・名}おもい(オモシ)。おもさ。↓の方向に力が加わった状態。↓の方向の力が底面に加わった感じ。おもみ。〈対語〉→軽。「軽重ケイチョウ/ケイジュウ(おもさ)」「重量」「重一鈞オモサイッキン」
 {形}おもい(オモシ)。病気・罪・声・やり方などがおもい。おもおもしい。てあつい。「厳重」「慎重」「重濁」「重賄之=重クコレニ賄ス」〔→左伝〕「君子不重則不威=君子ハ重カラザレバスナハチ威アラズ」〔→論語〕
{形}おもい(オモシ)。病気・罪・声・やり方などがおもい。おもおもしい。てあつい。「厳重」「慎重」「重濁」「重賄之=重クコレニ賄ス」〔→左伝〕「君子不重則不威=君子ハ重カラザレバスナハチ威アラズ」〔→論語〕
 {動}おもんずる(オモンズ)。たいせつなものとして敬い扱う。おもくみる。転じて、はばかる。▽この訓は「おもみす」の転じたもの。「尊重」「重社稷=社稷ヲ重ンズ」〔→礼記〕
{動}おもんずる(オモンズ)。たいせつなものとして敬い扱う。おもくみる。転じて、はばかる。▽この訓は「おもみす」の転じたもの。「尊重」「重社稷=社稷ヲ重ンズ」〔→礼記〕
 {動・形}かさなる。かさねる(カサヌ)。上へおいて下におもみをかける。層をなしてかさなったさま。▽平声に読む。「重複チョウフク」「重畳チョウジョウ」
{動・形}かさなる。かさねる(カサヌ)。上へおいて下におもみをかける。層をなしてかさなったさま。▽平声に読む。「重複チョウフク」「重畳チョウジョウ」
 {単位}下をおさえて上にかさなった物を数えることば。▽平声に読む。〈類義語〉→層ソウ。「万重山バンチョウノヤマ(いくえにもかさなった山)」
〔国〕かさなった物を数えることば。え。「七重八重ナナエヤエ」
《解字》
{単位}下をおさえて上にかさなった物を数えることば。▽平声に読む。〈類義語〉→層ソウ。「万重山バンチョウノヤマ(いくえにもかさなった山)」
〔国〕かさなった物を数えることば。え。「七重八重ナナエヤエ」
《解字》
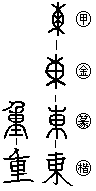 会意兼形声。東トウは、心棒がつきぬけた袋を描いた象形文字で、つきとおすの意を含む。重は「人が土の上にたったさま+音符東」で、人体のおもみが↓型につきぬけて、地上の一点にかかることを示す。→東
《単語家族》
動(トンと足ぶみして↓型におもみをかける)
会意兼形声。東トウは、心棒がつきぬけた袋を描いた象形文字で、つきとおすの意を含む。重は「人が土の上にたったさま+音符東」で、人体のおもみが↓型につきぬけて、地上の一点にかかることを示す。→東
《単語家族》
動(トンと足ぶみして↓型におもみをかける) 衝ショウ(↓型につきあたる)と同系。
《類義》
申は、下の物をおしのばすこと。累ルイは、ごろごろとつみかさねること。襲は、かさねて二重にすること。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
衝ショウ(↓型につきあたる)と同系。
《類義》
申は、下の物をおしのばすこと。累ルイは、ごろごろとつみかさねること。襲は、かさねて二重にすること。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
→主要人名
漢字源 ページ 4566。