複数辞典一括検索+![]()
![]()
【閉門】🔗⭐🔉
【閉門】
ヘイモン  モンヲトザス・モンヲトズ門をしめる。〈対語〉開門。「閉門鶏犬不爾留=門ヲ閉ザシ鶏犬ナンジラヲ留メズ」〔→梅尭臣〕
モンヲトザス・モンヲトズ門をしめる。〈対語〉開門。「閉門鶏犬不爾留=門ヲ閉ザシ鶏犬ナンジラヲ留メズ」〔→梅尭臣〕 〔国〕江戸時代、武士・僧侶ソウリョに科した刑の一つ。五十日間、または百日間、門を閉じてとじこもらせ、客の出入りも許さないもの。
〔国〕江戸時代、武士・僧侶ソウリョに科した刑の一つ。五十日間、または百日間、門を閉じてとじこもらせ、客の出入りも許さないもの。
 モンヲトザス・モンヲトズ門をしめる。〈対語〉開門。「閉門鶏犬不爾留=門ヲ閉ザシ鶏犬ナンジラヲ留メズ」〔→梅尭臣〕
モンヲトザス・モンヲトズ門をしめる。〈対語〉開門。「閉門鶏犬不爾留=門ヲ閉ザシ鶏犬ナンジラヲ留メズ」〔→梅尭臣〕 〔国〕江戸時代、武士・僧侶ソウリョに科した刑の一つ。五十日間、または百日間、門を閉じてとじこもらせ、客の出入りも許さないもの。
〔国〕江戸時代、武士・僧侶ソウリョに科した刑の一つ。五十日間、または百日間、門を閉じてとじこもらせ、客の出入りも許さないもの。
【閉息】🔗⭐🔉
【閉息】
ヘイソク 息をころす。
【閉塞】🔗⭐🔉
【閉塞】
ヘイソク  閉じふさぐ。閉じて通じないようにすること。
閉じふさぐ。閉じて通じないようにすること。 閉ざされてふさがる。
閉ざされてふさがる。
 閉じふさぐ。閉じて通じないようにすること。
閉じふさぐ。閉じて通じないようにすること。 閉ざされてふさがる。
閉ざされてふさがる。
【閉関】🔗⭐🔉
【閉関】
ヘイカン・カンヲトザス  関所を閉ざして通行できないようにする。
関所を閉ざして通行できないようにする。 門を閉じて客にあわない。閉じこもって俗世との交際をやめる。「迢逓嵩高下、帰来且閉関=迢逓タリ嵩高ノ下、帰来シテシバラク関ヲ閉ザス」〔→王維〕
門を閉じて客にあわない。閉じこもって俗世との交際をやめる。「迢逓嵩高下、帰来且閉関=迢逓タリ嵩高ノ下、帰来シテシバラク関ヲ閉ザス」〔→王維〕
 関所を閉ざして通行できないようにする。
関所を閉ざして通行できないようにする。 門を閉じて客にあわない。閉じこもって俗世との交際をやめる。「迢逓嵩高下、帰来且閉関=迢逓タリ嵩高ノ下、帰来シテシバラク関ヲ閉ザス」〔→王維〕
門を閉じて客にあわない。閉じこもって俗世との交際をやめる。「迢逓嵩高下、帰来且閉関=迢逓タリ嵩高ノ下、帰来シテシバラク関ヲ閉ザス」〔→王維〕
【閉蔵】🔗⭐🔉
【閉蔵】
ヘイゾウ  物をしまいこむ。
物をしまいこむ。 知られないようにかくす。
知られないようにかくす。 冬にあたるとされる、陰暦十月・十一月・十二月の三か月のこと。▽生気がとじこもって外に出ない時節の意。
冬にあたるとされる、陰暦十月・十一月・十二月の三か月のこと。▽生気がとじこもって外に出ない時節の意。
 物をしまいこむ。
物をしまいこむ。 知られないようにかくす。
知られないようにかくす。 冬にあたるとされる、陰暦十月・十一月・十二月の三か月のこと。▽生気がとじこもって外に出ない時節の意。
冬にあたるとされる、陰暦十月・十一月・十二月の三か月のこと。▽生気がとじこもって外に出ない時節の意。
【閉蟄】🔗⭐🔉
【閉蟄】
ヘイチツ 啓蟄ケイチツに対して、冬期になって虫類が土の中にとじこもること。冬ごもり。
【閉鎖】🔗⭐🔉
【閉鎖】
ヘイサ  門などを閉じる。
門などを閉じる。 閉じて活動をやめさせること。
閉じて活動をやめさせること。
 門などを閉じる。
門などを閉じる。 閉じて活動をやめさせること。
閉じて活動をやめさせること。
【開】🔗⭐🔉
【開】
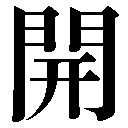 12画 門部 [三年]
区点=1911 16進=332B シフトJIS=8A4A
《常用音訓》カイ/あ…く/あ…ける/ひら…く/ひら…ける
《音読み》 カイ
12画 門部 [三年]
区点=1911 16進=332B シフトJIS=8A4A
《常用音訓》カイ/あ…く/あ…ける/ひら…く/ひら…ける
《音読み》 カイ /カイ/ケ
/カイ/ケ 〈k
〈k i〉
《訓読み》 あく/あける/ひらく/ひらける(ひらく)/ひらき
《名付け》 さく・はる・はるき・ひら・ひらかす・ひらき・ひらく
《意味》
i〉
《訓読み》 あく/あける/ひらく/ひらける(ひらく)/ひらき
《名付け》 さく・はる・はるき・ひら・ひらかす・ひらき・ひらく
《意味》
 {動}ひらく。ひらける(ヒラク)。門・出入り口など、閉じたものを広げあける。また、閉じているものがあく。〈対語〉→閉ヘイ・→闔コウ。〈類義語〉→啓ケイ。「開口=口ヲ開ク」「開花」「切開」「天門開闔=天ノ門開闔ス」〔→老子〕
{動}ひらく。ひらける(ヒラク)。門・出入り口など、閉じたものを広げあける。また、閉じているものがあく。〈対語〉→閉ヘイ・→闔コウ。〈類義語〉→啓ケイ。「開口=口ヲ開ク」「開花」「切開」「天門開闔=天ノ門開闔ス」〔→老子〕
 {動}ひらく。埋もれたものを掘りおこす。すておかれたものをおこしてひらく。「開発」「開墾」「開辺=辺ヲ開ク」
{動}ひらく。埋もれたものを掘りおこす。すておかれたものをおこしてひらく。「開発」「開墾」「開辺=辺ヲ開ク」
 {動}物事をはじめる。はじまる。「開端=端ヲ開ク」「開始」「開春」
{動}物事をはじめる。はじまる。「開端=端ヲ開ク」「開始」「開春」
 {動}しばったものをときはなす。「開放」「開釈無辜=無辜ヲ開釈ス」〔→書経〕
{動}しばったものをときはなす。「開放」「開釈無辜=無辜ヲ開釈ス」〔→書経〕
 {動}離れる。また、離れて間があく。「離開」
{動}離れる。また、離れて間があく。「離開」
 {動・形}ひらける(ヒラク)。あけすけになる。あけすけであるさま。開放的で明るい。「開朗」「開明」
{動・形}ひらける(ヒラク)。あけすけになる。あけすけであるさま。開放的で明るい。「開朗」「開明」
 {動}あけすけに外に出す。ひろげる。「展開」「開列」「開筵=筵ヲ開ク」
{動}あけすけに外に出す。ひろげる。「展開」「開列」「開筵=筵ヲ開ク」
 {動}ひらく。数学で、乗根を出して示す。「開平(平方根を出す)」
{動}ひらく。数学で、乗根を出して示す。「開平(平方根を出す)」
 {動}じゃまなものをおしのけてとる。「開除」
{動}じゃまなものをおしのけてとる。「開除」
 {動}〔俗〕動かす。動きはじめる。「開動カイトン」「開車カイチョ(発車)」
{動}〔俗〕動かす。動きはじめる。「開動カイトン」「開車カイチョ(発車)」
 {動}〔俗〕湯がわく。湯をわかす。「開水カイシュイ(わいた湯)」
{動}〔俗〕湯がわく。湯をわかす。「開水カイシュイ(わいた湯)」
 {単位}印刷用紙の全紙の大きさを基準にし、それの何分の一にあたるかによって、紙の大きさをあらわすことば。きり。「四開(全紙の四分の一の大きさ)」
〔国〕
{単位}印刷用紙の全紙の大きさを基準にし、それの何分の一にあたるかによって、紙の大きさをあらわすことば。きり。「四開(全紙の四分の一の大きさ)」
〔国〕 ひらき。会や宴会を閉じること。▽「閉」を忌んでいう。「お開きにする」
ひらき。会や宴会を閉じること。▽「閉」を忌んでいう。「お開きにする」 ひらき。あいた隔たり。間隔や差。「十メートルの開き」
ひらき。あいた隔たり。間隔や差。「十メートルの開き」 ひらき。魚の身を切りさいて干したもの。
《解字》
ひらき。魚の身を切りさいて干したもの。
《解字》
 会意。門のかんぬきを両手ではずして、門をあけるさま、または「門+幵(平等に並んだ姿)」で、とびらを左右平等にひらくことを示す。
《単語家族》
凱ガイ(明るくひらけた)と同系。啓ケイとも縁が近い。
《類義》
披ヒは、垂れた物を片よせてひらくこと。闢ヘキは、とびらを左右におしあけること。排ハイは、じゃま物を左右におしのけること。廓カクは、うつろにして空間をあけること。放は、両方にあけはなつ意。啓は、閉じたものをあけること。撥ハツは、くっついたものを分離させること。
《異字同訓》
あく/あける。 →明
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
会意。門のかんぬきを両手ではずして、門をあけるさま、または「門+幵(平等に並んだ姿)」で、とびらを左右平等にひらくことを示す。
《単語家族》
凱ガイ(明るくひらけた)と同系。啓ケイとも縁が近い。
《類義》
披ヒは、垂れた物を片よせてひらくこと。闢ヘキは、とびらを左右におしあけること。排ハイは、じゃま物を左右におしのけること。廓カクは、うつろにして空間をあけること。放は、両方にあけはなつ意。啓は、閉じたものをあけること。撥ハツは、くっついたものを分離させること。
《異字同訓》
あく/あける。 →明
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
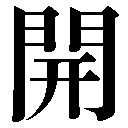 12画 門部 [三年]
区点=1911 16進=332B シフトJIS=8A4A
《常用音訓》カイ/あ…く/あ…ける/ひら…く/ひら…ける
《音読み》 カイ
12画 門部 [三年]
区点=1911 16進=332B シフトJIS=8A4A
《常用音訓》カイ/あ…く/あ…ける/ひら…く/ひら…ける
《音読み》 カイ /カイ/ケ
/カイ/ケ 〈k
〈k i〉
《訓読み》 あく/あける/ひらく/ひらける(ひらく)/ひらき
《名付け》 さく・はる・はるき・ひら・ひらかす・ひらき・ひらく
《意味》
i〉
《訓読み》 あく/あける/ひらく/ひらける(ひらく)/ひらき
《名付け》 さく・はる・はるき・ひら・ひらかす・ひらき・ひらく
《意味》
 {動}ひらく。ひらける(ヒラク)。門・出入り口など、閉じたものを広げあける。また、閉じているものがあく。〈対語〉→閉ヘイ・→闔コウ。〈類義語〉→啓ケイ。「開口=口ヲ開ク」「開花」「切開」「天門開闔=天ノ門開闔ス」〔→老子〕
{動}ひらく。ひらける(ヒラク)。門・出入り口など、閉じたものを広げあける。また、閉じているものがあく。〈対語〉→閉ヘイ・→闔コウ。〈類義語〉→啓ケイ。「開口=口ヲ開ク」「開花」「切開」「天門開闔=天ノ門開闔ス」〔→老子〕
 {動}ひらく。埋もれたものを掘りおこす。すておかれたものをおこしてひらく。「開発」「開墾」「開辺=辺ヲ開ク」
{動}ひらく。埋もれたものを掘りおこす。すておかれたものをおこしてひらく。「開発」「開墾」「開辺=辺ヲ開ク」
 {動}物事をはじめる。はじまる。「開端=端ヲ開ク」「開始」「開春」
{動}物事をはじめる。はじまる。「開端=端ヲ開ク」「開始」「開春」
 {動}しばったものをときはなす。「開放」「開釈無辜=無辜ヲ開釈ス」〔→書経〕
{動}しばったものをときはなす。「開放」「開釈無辜=無辜ヲ開釈ス」〔→書経〕
 {動}離れる。また、離れて間があく。「離開」
{動}離れる。また、離れて間があく。「離開」
 {動・形}ひらける(ヒラク)。あけすけになる。あけすけであるさま。開放的で明るい。「開朗」「開明」
{動・形}ひらける(ヒラク)。あけすけになる。あけすけであるさま。開放的で明るい。「開朗」「開明」
 {動}あけすけに外に出す。ひろげる。「展開」「開列」「開筵=筵ヲ開ク」
{動}あけすけに外に出す。ひろげる。「展開」「開列」「開筵=筵ヲ開ク」
 {動}ひらく。数学で、乗根を出して示す。「開平(平方根を出す)」
{動}ひらく。数学で、乗根を出して示す。「開平(平方根を出す)」
 {動}じゃまなものをおしのけてとる。「開除」
{動}じゃまなものをおしのけてとる。「開除」
 {動}〔俗〕動かす。動きはじめる。「開動カイトン」「開車カイチョ(発車)」
{動}〔俗〕動かす。動きはじめる。「開動カイトン」「開車カイチョ(発車)」
 {動}〔俗〕湯がわく。湯をわかす。「開水カイシュイ(わいた湯)」
{動}〔俗〕湯がわく。湯をわかす。「開水カイシュイ(わいた湯)」
 {単位}印刷用紙の全紙の大きさを基準にし、それの何分の一にあたるかによって、紙の大きさをあらわすことば。きり。「四開(全紙の四分の一の大きさ)」
〔国〕
{単位}印刷用紙の全紙の大きさを基準にし、それの何分の一にあたるかによって、紙の大きさをあらわすことば。きり。「四開(全紙の四分の一の大きさ)」
〔国〕 ひらき。会や宴会を閉じること。▽「閉」を忌んでいう。「お開きにする」
ひらき。会や宴会を閉じること。▽「閉」を忌んでいう。「お開きにする」 ひらき。あいた隔たり。間隔や差。「十メートルの開き」
ひらき。あいた隔たり。間隔や差。「十メートルの開き」 ひらき。魚の身を切りさいて干したもの。
《解字》
ひらき。魚の身を切りさいて干したもの。
《解字》
 会意。門のかんぬきを両手ではずして、門をあけるさま、または「門+幵(平等に並んだ姿)」で、とびらを左右平等にひらくことを示す。
《単語家族》
凱ガイ(明るくひらけた)と同系。啓ケイとも縁が近い。
《類義》
披ヒは、垂れた物を片よせてひらくこと。闢ヘキは、とびらを左右におしあけること。排ハイは、じゃま物を左右におしのけること。廓カクは、うつろにして空間をあけること。放は、両方にあけはなつ意。啓は、閉じたものをあけること。撥ハツは、くっついたものを分離させること。
《異字同訓》
あく/あける。 →明
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
会意。門のかんぬきを両手ではずして、門をあけるさま、または「門+幵(平等に並んだ姿)」で、とびらを左右平等にひらくことを示す。
《単語家族》
凱ガイ(明るくひらけた)と同系。啓ケイとも縁が近い。
《類義》
披ヒは、垂れた物を片よせてひらくこと。闢ヘキは、とびらを左右におしあけること。排ハイは、じゃま物を左右におしのけること。廓カクは、うつろにして空間をあけること。放は、両方にあけはなつ意。啓は、閉じたものをあけること。撥ハツは、くっついたものを分離させること。
《異字同訓》
あく/あける。 →明
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
漢字源 ページ 4686。