複数辞典一括検索+![]()
![]()
【魯縞】🔗⭐🔉
【魯縞】
ロコウ 魯の国に産する、薄く、しまの細かい白絹。
【魯粛】🔗⭐🔉
【魯粛】
ロシュク〈人名〉172〜217 三国時代、呉の建国の功臣。東城トウジョウ(安徽アンキ省)の人。字アザナは子敬。孫権ソンケンに仕えて曹操ソウソウを赤壁セキヘキに破った。
【魯迅】🔗⭐🔉
【魯迅】
ロジン〈人名〉1881〜1936 清シン末民国初の文学者。浙江セッコウ省紹興ショウコウの人。姓名は周樹人、字アザナは予才、魯迅は筆名。明治の末、日本に留学。のち、中国の文化革命の先頭にたって、思想・文学、また、文字改革などに大きな影響を及ぼした。著に『狂人日記』『阿Q正伝』などがある。
【魯班】🔗⭐🔉
【魯班】
ロハン〈人名〉春秋時代、魯ロのすぐれた大工。公輸班コウシュハンのことともいわれる。後世、大工の神様としてまつられた。魯般とも。
【鮗】🔗⭐🔉
【鮗】
 16画 魚部 〔国〕
区点=8228 16進=723C シフトJIS=E9BA
《訓読み》 このしろ
《意味》
このしろ海にすむ魚の一種。背は青く、黒い斑点ハンテンが並び、腹は白い。
《解字》
会意。「魚+冬」。冬のころが、しゅんになる魚であることをあらわす。
16画 魚部 〔国〕
区点=8228 16進=723C シフトJIS=E9BA
《訓読み》 このしろ
《意味》
このしろ海にすむ魚の一種。背は青く、黒い斑点ハンテンが並び、腹は白い。
《解字》
会意。「魚+冬」。冬のころが、しゅんになる魚であることをあらわす。
 16画 魚部 〔国〕
区点=8228 16進=723C シフトJIS=E9BA
《訓読み》 このしろ
《意味》
このしろ海にすむ魚の一種。背は青く、黒い斑点ハンテンが並び、腹は白い。
《解字》
会意。「魚+冬」。冬のころが、しゅんになる魚であることをあらわす。
16画 魚部 〔国〕
区点=8228 16進=723C シフトJIS=E9BA
《訓読み》 このしろ
《意味》
このしろ海にすむ魚の一種。背は青く、黒い斑点ハンテンが並び、腹は白い。
《解字》
会意。「魚+冬」。冬のころが、しゅんになる魚であることをあらわす。
【鮓】🔗⭐🔉
【鮓】
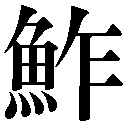 16画 魚部
区点=8224 16進=7238 シフトJIS=E9B6
《音読み》 サ
16画 魚部
区点=8224 16進=7238 シフトJIS=E9B6
《音読み》 サ /シャ
/シャ 〈zh
〈zh 〉
《訓読み》 すし
《意味》
〉
《訓読み》 すし
《意味》
 {名}すし。塩・糟カスなどにつけ、発酵させて酸味をつけた魚。また、飯を発酵させてすっぱくなった中に魚をつけこんだ保存食。▽華南・東南アジアに広く行われた。
{名}すし。塩・糟カスなどにつけ、発酵させて酸味をつけた魚。また、飯を発酵させてすっぱくなった中に魚をつけこんだ保存食。▽華南・東南アジアに広く行われた。
 {名}海にすむ魚の一種。かさを広げたような形をしている。くらげ。
〔国〕すし。(イ)酢につけた魚。(ロ)酢・塩で味をつけた飯に、魚肉や野菜などをまぜたもの。また、酢をした飯をにぎって、その上に魚や貝類の肉をのせたもの。鮨スシ。
《解字》
形声。「魚+音符乍サ」。
《単語家族》
酢サ(す)
{名}海にすむ魚の一種。かさを広げたような形をしている。くらげ。
〔国〕すし。(イ)酢につけた魚。(ロ)酢・塩で味をつけた飯に、魚肉や野菜などをまぜたもの。また、酢をした飯をにぎって、その上に魚や貝類の肉をのせたもの。鮨スシ。
《解字》
形声。「魚+音符乍サ」。
《単語家族》
酢サ(す) 醋(す)と同系。
醋(す)と同系。
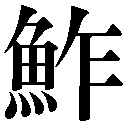 16画 魚部
区点=8224 16進=7238 シフトJIS=E9B6
《音読み》 サ
16画 魚部
区点=8224 16進=7238 シフトJIS=E9B6
《音読み》 サ /シャ
/シャ 〈zh
〈zh 〉
《訓読み》 すし
《意味》
〉
《訓読み》 すし
《意味》
 {名}すし。塩・糟カスなどにつけ、発酵させて酸味をつけた魚。また、飯を発酵させてすっぱくなった中に魚をつけこんだ保存食。▽華南・東南アジアに広く行われた。
{名}すし。塩・糟カスなどにつけ、発酵させて酸味をつけた魚。また、飯を発酵させてすっぱくなった中に魚をつけこんだ保存食。▽華南・東南アジアに広く行われた。
 {名}海にすむ魚の一種。かさを広げたような形をしている。くらげ。
〔国〕すし。(イ)酢につけた魚。(ロ)酢・塩で味をつけた飯に、魚肉や野菜などをまぜたもの。また、酢をした飯をにぎって、その上に魚や貝類の肉をのせたもの。鮨スシ。
《解字》
形声。「魚+音符乍サ」。
《単語家族》
酢サ(す)
{名}海にすむ魚の一種。かさを広げたような形をしている。くらげ。
〔国〕すし。(イ)酢につけた魚。(ロ)酢・塩で味をつけた飯に、魚肉や野菜などをまぜたもの。また、酢をした飯をにぎって、その上に魚や貝類の肉をのせたもの。鮨スシ。
《解字》
形声。「魚+音符乍サ」。
《単語家族》
酢サ(す) 醋(す)と同系。
醋(す)と同系。
漢字源 ページ 5084。