複数辞典一括検索+![]()
![]()
【両髦】🔗⭐🔉
【両髦】
リョウボウ 幼児の髪型の名。左右にわけて両方にたらす。▽父母に仕える子の髪型とされる。
【両頭蛇】🔗⭐🔉
【両頭蛇】
リョウトウダ  前後に頭があるという蛇ヘビ。これを見ると死ぬという。
前後に頭があるという蛇ヘビ。これを見ると死ぬという。 頭が二つ並んでいるという蛇。
頭が二つ並んでいるという蛇。
 前後に頭があるという蛇ヘビ。これを見ると死ぬという。
前後に頭があるという蛇ヘビ。これを見ると死ぬという。 頭が二つ並んでいるという蛇。
頭が二つ並んでいるという蛇。
【並】🔗⭐🔉
【並】
 8画 一部 [六年]
区点=4234 16進=4A42 シフトJIS=95C0
【竝】旧字旧字
8画 一部 [六年]
区点=4234 16進=4A42 シフトJIS=95C0
【竝】旧字旧字
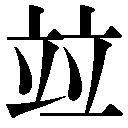 10画 立部
区点=6777 16進=636D シフトJIS=E28D
《常用音訓》ヘイ/な…み/なら…びに/なら…ぶ/なら…べる
《音読み》 ヘイ
10画 立部
区点=6777 16進=636D シフトJIS=E28D
《常用音訓》ヘイ/な…み/なら…びに/なら…ぶ/なら…べる
《音読み》 ヘイ /ビョウ(ビャウ)
/ビョウ(ビャウ) 〈b
〈b ng〉
《訓読み》 ならべる/ならぶ/ならびに/なみ
《名付け》 なみ・なめ・ならぶ・み・みつ
《意味》
ng〉
《訓読み》 ならべる/ならぶ/ならびに/なみ
《名付け》 なみ・なめ・ならぶ・み・みつ
《意味》
 ヘイス{動・形}ならぶ。ならんでいる。また、そのさま。「並立」
ヘイス{動・形}ならぶ。ならんでいる。また、そのさま。「並立」
 {接続}ならびに。「A並B」とは、「AおよびB」の意。また文章の前後二節の間に用い、それと同様に、それと同時に、の意をあらわすことば。
{接続}ならびに。「A並B」とは、「AおよびB」の意。また文章の前後二節の間に用い、それと同様に、それと同時に、の意をあらわすことば。
 {副}ならびに。みな一様に。「並受其福=並ビニ其ノ福ヲ受ク」〔→詩経〕
〔国〕
{副}ならびに。みな一様に。「並受其福=並ビニ其ノ福ヲ受ク」〔→詩経〕
〔国〕 なみ。程度が普通であること。
なみ。程度が普通であること。 なみ。そのものと同類であること。「世間並み」
《解字》
なみ。そのものと同類であること。「世間並み」
《解字》
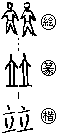 会意。人が地上にたった姿を示す立の字を二つならべて、同じようにならぶさまを示したもの。同じように横にならぶこと。略して並と書く。また、併ヘイに通じる。
《類義》
併は、一つにあわさること。双ソウは、二つ対をなすこと。比は、くっついてならぶこと。配は、くっついて対をなすこと。排は、左右に開いてならぶこと。偶グウは、二つでペアをなすこと。例は、同列に並ぶもの。較は、つきあわせること。譬は、たとえてならべること。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
会意。人が地上にたった姿を示す立の字を二つならべて、同じようにならぶさまを示したもの。同じように横にならぶこと。略して並と書く。また、併ヘイに通じる。
《類義》
併は、一つにあわさること。双ソウは、二つ対をなすこと。比は、くっついてならぶこと。配は、くっついて対をなすこと。排は、左右に開いてならぶこと。偶グウは、二つでペアをなすこと。例は、同列に並ぶもの。較は、つきあわせること。譬は、たとえてならべること。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
 8画 一部 [六年]
区点=4234 16進=4A42 シフトJIS=95C0
【竝】旧字旧字
8画 一部 [六年]
区点=4234 16進=4A42 シフトJIS=95C0
【竝】旧字旧字
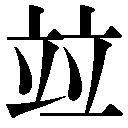 10画 立部
区点=6777 16進=636D シフトJIS=E28D
《常用音訓》ヘイ/な…み/なら…びに/なら…ぶ/なら…べる
《音読み》 ヘイ
10画 立部
区点=6777 16進=636D シフトJIS=E28D
《常用音訓》ヘイ/な…み/なら…びに/なら…ぶ/なら…べる
《音読み》 ヘイ /ビョウ(ビャウ)
/ビョウ(ビャウ) 〈b
〈b ng〉
《訓読み》 ならべる/ならぶ/ならびに/なみ
《名付け》 なみ・なめ・ならぶ・み・みつ
《意味》
ng〉
《訓読み》 ならべる/ならぶ/ならびに/なみ
《名付け》 なみ・なめ・ならぶ・み・みつ
《意味》
 ヘイス{動・形}ならぶ。ならんでいる。また、そのさま。「並立」
ヘイス{動・形}ならぶ。ならんでいる。また、そのさま。「並立」
 {接続}ならびに。「A並B」とは、「AおよびB」の意。また文章の前後二節の間に用い、それと同様に、それと同時に、の意をあらわすことば。
{接続}ならびに。「A並B」とは、「AおよびB」の意。また文章の前後二節の間に用い、それと同様に、それと同時に、の意をあらわすことば。
 {副}ならびに。みな一様に。「並受其福=並ビニ其ノ福ヲ受ク」〔→詩経〕
〔国〕
{副}ならびに。みな一様に。「並受其福=並ビニ其ノ福ヲ受ク」〔→詩経〕
〔国〕 なみ。程度が普通であること。
なみ。程度が普通であること。 なみ。そのものと同類であること。「世間並み」
《解字》
なみ。そのものと同類であること。「世間並み」
《解字》
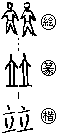 会意。人が地上にたった姿を示す立の字を二つならべて、同じようにならぶさまを示したもの。同じように横にならぶこと。略して並と書く。また、併ヘイに通じる。
《類義》
併は、一つにあわさること。双ソウは、二つ対をなすこと。比は、くっついてならぶこと。配は、くっついて対をなすこと。排は、左右に開いてならぶこと。偶グウは、二つでペアをなすこと。例は、同列に並ぶもの。較は、つきあわせること。譬は、たとえてならべること。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
会意。人が地上にたった姿を示す立の字を二つならべて、同じようにならぶさまを示したもの。同じように横にならぶこと。略して並と書く。また、併ヘイに通じる。
《類義》
併は、一つにあわさること。双ソウは、二つ対をなすこと。比は、くっついてならぶこと。配は、くっついて対をなすこと。排は、左右に開いてならぶこと。偶グウは、二つでペアをなすこと。例は、同列に並ぶもの。較は、つきあわせること。譬は、たとえてならべること。
《熟語》
→熟語
→下付・中付語
漢字源 ページ 80。