複数辞典一括検索+![]()
![]()
広辞苑の検索結果 (5)
けんにん【建仁】🔗⭐🔉
けんにん【建仁】
[文選]鎌倉前期、土御門つちみかど天皇朝の年号。辛酉革命により、正治3年2月13日(1201年3月19日)改元。建仁4年2月20日(1204年3月23日)元久に改元。
⇒けんにん‐じ【建仁寺】
⇒けんにんじ‐がき【建仁寺垣】
⇒けんにんじ‐りゅう【建仁寺流】
けんにん‐じ【建仁寺】🔗⭐🔉
けんにん‐じ【建仁寺】
①京都市東山区にある臨済宗建仁寺派の大本山。山号は東山。建仁2年(1202)栄西の創建。当初は天台・真言・禅の兼学寺院。室町時代は京都五山の一つで五山文学の中心。戦国末期に恵瓊えけいが復興。
②建仁寺垣の略。
⇒けんにん【建仁】
けんにんじ‐がき【建仁寺垣】🔗⭐🔉
けんにんじ‐がき【建仁寺垣】
竹垣の一種。四つ割竹を皮を外にして平たく並べ、竹の押縁おしぶちを横にとりつけ、縄で結んだ垣。建仁寺で初めて造ったという。建仁寺。けんねんじ。
建仁寺垣
 ⇒けんにん【建仁】
⇒けんにん【建仁】
 ⇒けんにん【建仁】
⇒けんにん【建仁】
けんにんじ‐りゅう【建仁寺流】‥リウ🔗⭐🔉
けんにんじ‐りゅう【建仁寺流】‥リウ
〔建〕大工技術の一流派に対する呼称。建仁寺建立に始まるためという。↔四天王寺流
⇒けんにん【建仁】
けんねん‐じ【建仁寺】🔗⭐🔉
けんねん‐じ【建仁寺】
①ケンニンジの訛。
②⇒けんねじ
大辞林の検索結果 (6)
けんにん【建仁】🔗⭐🔉
けんにん 【建仁】
年号(1201.2.13-1204.2.20)。正治の後,元久の前。土御門(ツチミカド)天皇の代。
けんにん-じ【建仁寺】🔗⭐🔉
けんにん-じ 【建仁寺】
京都市東山区にある臨済宗建仁寺派の本山。山号は東山。1202年(建仁2)源頼家の寄進をうけ,栄西を開山として創建。天台・真言兼修の道場であったが,蘭渓道隆の時代に純粋の禅宗寺院となった。けんねんじ。
けんにんじ-がき【建仁寺垣】🔗⭐🔉
けんにんじ-がき [5] 【建仁寺垣】
竹垣の一。四つ割り竹を皮を外にしてすき間なく並べ,竹の押縁で押さえて棕梠(シユロ)縄で結んだもの。建仁寺の竹垣がはじまりとされる。
建仁寺垣
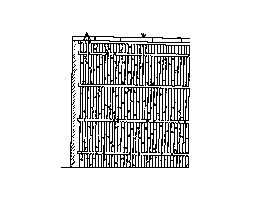 [図]
[図]
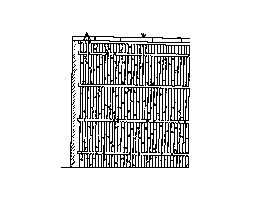 [図]
[図]
けんにんじ-は【建仁寺派】🔗⭐🔉
けんにんじ-は 【建仁寺派】
臨済宗の一派。京都の建仁寺を本山とし,栄西を祖とする。千光派。
けんにんじ-りゅう【建仁寺流】🔗⭐🔉
けんにんじ-りゅう ―リウ 【建仁寺流】
近世,主として禅宗様の建築技術を継承してきたと伝える大工の流派。
けんねん-じ【建仁寺】🔗⭐🔉
けんねん-じ 【建仁寺】
「けんにんじ」の転。
広辞苑+大辞林に「建仁」で始まるの検索結果。