複数辞典一括検索+![]()
![]()
おし-どり ヲシ― [2] 【鴛鴦】🔗⭐🔉
おし-どり ヲシ― [2] 【鴛鴦】
(1)カモ目カモ科の水鳥。繁殖期の雄は橙色のイチョウの葉形の飾り羽をもち,非常に美しい。雌は灰褐色に斑(マダラ)のある地味な鳥。暗い池や小川の木陰などを好み,山地の水辺に近い木の空洞に巣をつくる。シベリア・朝鮮・中国・日本に分布。[季]冬。
(2)仲がよくて,いつも一緒にいる男女のたとえ。「―夫婦」
〔オシドリは繁殖期になると雄は美しい羽毛となりつがいで行動するが,実際にはつがいは毎年新しくつくられる〕
→鴛鴦(エンオウ)の契り
(3)近世の女性の髪形の一。(ア)島田髷(マゲ)の変形。雌雄の二形ある。上方で一六,七歳の少女が結う。(イ)江戸末期,江戸で結われたもの。髷の部分が御盥(オタライ)に似る。
鴛鴦(1)
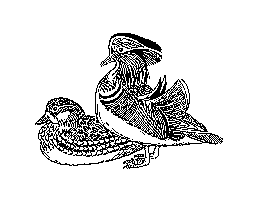 [図]
[図]
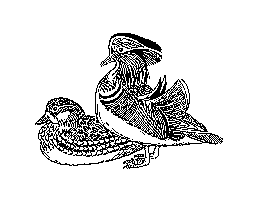 [図]
[図]
おしどり-の ヲシ― 【鴛鴦の】 (枕詞)🔗⭐🔉
おしどり-の ヲシ― 【鴛鴦の】 (枕詞)
同音の「惜し」,また水に浮くところから「うき」にかかる。「―惜しき吾が身は君がまにまに/万葉 4505」「―うきねの床や荒ぬらむ/千載(冬)」
おし-なが・す [4] 【押(し)流す】 (動サ五[四])🔗⭐🔉
おし-なが・す [4] 【押(し)流す】 (動サ五[四])
(1)激しい勢いで流し去る。「濁流が家を―・した」
(2)(比喩的に)時流・時勢など周囲の情勢が大きな影響を及ぼす。多く,受け身形で使う。「時流に―・される」
[可能] おしながせる
おじ-な・し ヲヂ― 【怯し】 (形ク)🔗⭐🔉
おじ-な・し ヲヂ― 【怯し】 (形ク)
(1)意気地がない。おくびょうだ。「―・き事する舟人にもあるかな/竹取」
(2)劣っている。「―・きや我に劣れる人を多み/仏足石歌」
おし-な・ぶ 【押し並ぶ・押し靡ぶ】 (動バ下二)🔗⭐🔉
おし-な・ぶ 【押し並ぶ・押し靡ぶ】 (動バ下二)
(1)一面になびかせる。押しならす。「秋の穂をしのに―・べ置く露の/万葉 2256」
(2)すべてを同じ状態にする。「さきにやけにし憎所(ニクドコロ),こたみは―・ぶるなりけり/蜻蛉(下)」
(3)普通である。世間並みである。「―・べたらぬ心ざしの程を御覧じ知らば/源氏(若紫)」
大辞林 ページ 140247。