複数辞典一括検索+![]()
![]()
きり-かか・る [4] 【切り掛(か)る・斬り掛(か)る】 (動ラ五[四])🔗⭐🔉
きり-かか・る [4] 【切り掛(か)る・斬り掛(か)る】 (動ラ五[四])
(1)刃物を振り上げて切ろうとする。「太刀を振りかざして―・る」
(2)切りはじめる。また,切る行動を途中までする。「布を―・ったところで,電話に出る」
きり-かき [0] 【切(り)欠き】🔗⭐🔉
きり-かき [0] 【切(り)欠き】
(1)接合のために材料の一部を切り取ってできた穴・溝・段付きなどの部分。集中応力が現れやすい。
(2)材料力学の強度試験で,試験片の縁に切り込みを入れた箇所。
(3)流量の測定のため,堰板(セキイタ)に三角形または四角形の切り口をつけたもの。
きりかき-かっしゃ ―クワツ― [5] 【切(り)欠き滑車】🔗⭐🔉
きりかき-かっしゃ ―クワツ― [5] 【切(り)欠き滑車】
枠の一部分が開閉できるようになっていて,ロープの途中からでもかけられるようにした滑車。
きり-がくれ [3] 【霧隠れ】🔗⭐🔉
きり-がくれ [3] 【霧隠れ】
霧におおわれて姿・形が見えなくなること。
きりがくれ-さいぞう ―サイザウ 【霧隠才蔵】🔗⭐🔉
きりがくれ-さいぞう ―サイザウ 【霧隠才蔵】
真田(サナダ)十勇士の一人。伊賀流忍術の名人として猿飛佐助とともに活躍。
きり-かけ [0] 【切(り)掛け・切(り)懸け】🔗⭐🔉
きり-かけ [0] 【切(り)掛け・切(り)懸け】
(1)物を切る途中,また途中まで切ったもの。
(2)柱の間に,板を横によろい戸のように張った板塀。目隠し用のもので,中庭の坪などに立てた。
(3){(2)}のように作った,室内用の衝立(ツイタテ)。たてきりかけ。
(4)御幣(ゴヘイ)につける紙四手(カミシデ)。
(5)指物(サシモノ)の一。紙四手に似たもの。
切り掛け(2)
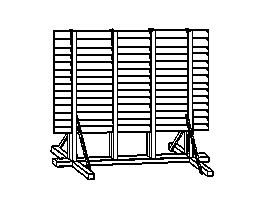 [図]
[図]
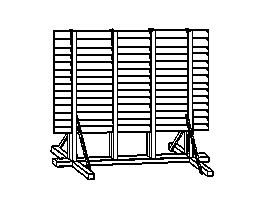 [図]
[図]
きりかけ-づくり [5] 【切(り)掛け作り・切(り)掛け造り】🔗⭐🔉
きりかけ-づくり [5] 【切(り)掛け作り・切(り)掛け造り】
刺身の作り方の一。切り身の皮側に切れ目が残るように,一刃おきに切り離すような切り方。
きり-か・ける [0][4] 【切(り)掛ける・斬り掛ける】 (動カ下一)[文]カ下二 きりか・く🔗⭐🔉
きり-か・ける [0][4] 【切(り)掛ける・斬り掛ける】 (動カ下一)[文]カ下二 きりか・く
(1)切りはじめる。また,途中まで切る。「―・けて,やめる」
(2)刃物を振るって,切ろうとして立ち向かう。切りつける。「いやといはば―・けんず/浄瑠璃・博多小女郎(上)」
(3)切ったものを他のものにかける。多く首を獄門などにかけさらす際にいう。「戦場にしてうたるる大衆千余人,少々は般若寺の門の前に―・け/平家 5」
(4)鑽(キ)り火を他へ向けてうちかける。「三つの清火を―・け―・け/浄瑠璃・唐船噺」
大辞林 ページ 142561。