複数辞典一括検索+![]()
![]()
しょう シヤウ [1] 【鉦】🔗⭐🔉
しょう シヤウ [1] 【鉦】
銅,または銅の合金で作った平たい円盆形の打楽器。直径12センチメートルから20センチメートルぐらいまでのものがあり,撞木(シユモク)または桴(バチ)で打つ。伏せ鉦(ガネ)・摺り鉦(ちゃんぎり)・鉦鼓(シヨウコ)などの種類がある。「―を打つ」
しょう [1] 【頌】🔗⭐🔉
しょう [1] 【頌】
(1)人の功績や人柄をほめたたえることば。
(2)「詩経」の六義(リクギ)の一。漢詩の内容による分類の一つで,宗廟(ソウビヨウ)で歌われる先祖の徳をたたえる歌。
しょう [1] 【衝】🔗⭐🔉
しょう [1] 【衝】
(1)通路。また,重要な地点。
(2)重要な立場。大切な役目。
(3)太陽と外惑星との黄経の差が一八〇度となる現象およびその時刻。外惑星はこの時刻の近くで地球に最も接近する。
→合(ゴウ)
――に当た・る🔗⭐🔉
――に当た・る
(1)重要な地点になっている。「交通の―・る」
(2)重要な役目を受け持つ。「外交の―・る」
しょう シヤウ [1] 【請】🔗⭐🔉
しょう シヤウ [1] 【請】
(1)お願いすること。要請。「医師,―を受けて病める者のもとへ行く道に/今昔 10」
(2)律令制で,五位以上の貴族などに与えられた刑法上の特典。
しょう シヤウ [1] 【賞】🔗⭐🔉
しょう シヤウ [1] 【賞】
人の功績に対して与えられるほうび。「―にはいる」
しょう セウ [1] 【礁】🔗⭐🔉
しょう セウ [1] 【礁】
海面付近,あるいは水深20メートル以浅にある岩石または珊瑚(サンゴ)礁などからなる海底の突起部。
しょう [1] 【鍾】🔗⭐🔉
しょう [1] 【鍾】
中国漢代に盛行した酒器。円壺形の金属製のもの。
しょう セウ [1] 【簫】🔗⭐🔉
しょう セウ [1] 【簫】
中国の竹製縦笛。竹管一本(指孔あり)の洞簫(尺八型)と,長短数本(指孔なし)を一組にした排簫(パンパイプ型)の二種がある。
→洞簫(ドウシヨウ)
→排簫(ハイシヨウ)
→簫[音声]
しょう [1] 【鐘】🔗⭐🔉
しょう [1] 【鐘】
(1)かね。つりがね。つきがね。
(2)中国古代の楽器。銅または青銅製で,周代のものは扁平な釣り鐘状。上部に棒状のつり手,胴に乳首状の隆起がつく。相似形のものを大きさの順にかけ並べて一組にしたものを編鐘といい,音階をなす打楽器として用いた。
鐘(2)
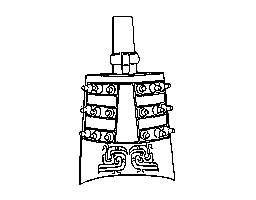 [図]
[図]
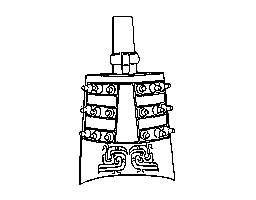 [図]
[図]
大辞林 ページ 146419。