複数辞典一括検索+![]()
![]()
ちゃ-せん [0] 【茶筅・茶筌】🔗⭐🔉
ちゃ-せん [0] 【茶筅・茶筌】
(1)抹茶をたてる時,泡をたてたり,練ったりするのに用いる竹製の具。10センチメートルほどの竹筒の半分以上を細く割って穂にしたもの。白竹・青竹・煤竹(ススダケ)などを用い,種類が多い。
(2)〔茶筅を売り歩いたからという〕
江戸時代,竹細工などをした人々の称。賤民視されていた。
(3)「茶筅髪(ガミ)」の略。
茶筅(1)
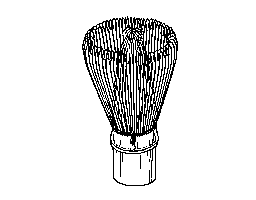 [図]
[図]
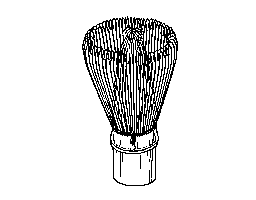 [図]
[図]
ちゃせん-かざり [4] 【茶筅飾り】🔗⭐🔉
ちゃせん-かざり [4] 【茶筅飾り】
茶の湯の点前(テマエ)の一。茶巾(チヤキン)・茶筅・茶杓(チヤシヤク)を水指(ミズサシ)のふたの上にのせ,前に茶入れを入れた茶碗を置く。名物の茶碗や新茶碗や拝領の水指を用いるときに行う。
ちゃせん-がみ [0][2] 【茶筅髪】🔗⭐🔉
ちゃせん-がみ [0][2] 【茶筅髪】
〔髷(マゲ)が茶筅に似るところから〕
(1)男子の髪形の一。室町末頃に始まる。髪を頭頂で束ね,根元から組み緒などで巻き立て,先を巻き残したもの。巻いた部分が柄で,先が穂である茶筅に見える。
(2)女子の髪形の一。切り髪{(1)}に似て,髷が茶筅状であるもの。江戸時代,京坂の未亡人が結った。
茶筅髪(1)
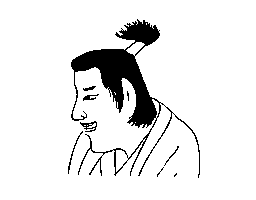 [図]
[図]
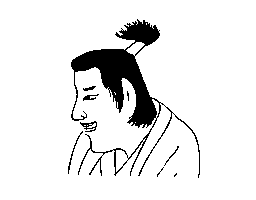 [図]
[図]
ちゃせん-ぎり [0] 【茶筅切り】🔗⭐🔉
ちゃせん-ぎり [0] 【茶筅切り】
野菜の飾り切りの一。両端または一端を残して縦に細かく包丁を入れる切り方。ナス・ゴボウなどに用いる。
ちゃせん-し [2] 【茶筅師】🔗⭐🔉
ちゃせん-し [2] 【茶筅師】
茶筅の製造を業とする人。
ちゃせん-しだ [4] 【茶筅羊歯】🔗⭐🔉
ちゃせん-しだ [4] 【茶筅羊歯】
チャセンシダ科の常緑性シダ植物。多く山地の岩上または樹幹上に生える。葉は根茎から叢生(ソウセイ)し,長さ約20センチメートル。葉柄は細く暗褐色。胞子嚢(ホウシノウ)群は広線形で裏面の脈上につく。
ちゃせん-ずれ [0] 【茶筅擦れ】🔗⭐🔉
ちゃせん-ずれ [0] 【茶筅擦れ】
茶碗の部分の名。茶をたてるとき茶筅が当たる部分。見所の一つ。また,茶筅が当たって生じたきずをいう場合もある。
ちゃせん-そでがき [4] 【茶筅袖垣】🔗⭐🔉
ちゃせん-そでがき [4] 【茶筅袖垣】
竹を筋違いに組み,その上部を縦に編んだ袖垣。
ちゃせん-たて [2] 【茶筅立て】🔗⭐🔉
ちゃせん-たて [2] 【茶筅立て】
茶筅を立てておく器具。金属・陶製の印章状のもの。野点(ノダテ)に用いる。
大辞林 ページ 149290。