複数辞典一括検索+![]()
![]()
ひき-らか 【低らか】 (形動ナリ)🔗⭐🔉
ひき-らか 【低らか】 (形動ナリ)
「ひきやか」に同じ。「丈―なる衆の/宇治拾遺 2」
ひ-きり [3] 【火鑽り・火切り・燧】🔗⭐🔉
ひ-きり [3] 【火鑽り・火切り・燧】
よく乾燥したタブやスギなどを台木(火鑽り臼(ウス))とし,木の棒(火鑽り杵(ギネ))をあてて激しくもみ合わせ火をおこすこと。また,その道具。
ひきり-うす [4] 【火鑽り臼】🔗⭐🔉
ひきり-うす [4] 【火鑽り臼】
火をおこす道具の一。火鑽り杵(ギネ)を垂直に立て,これを急速度で回転させ,摩擦熱で発火させる。弥生時代のものが登呂(トロ)遺跡から出土。
ひきり-ぎね [4] 【火鑽り杵】🔗⭐🔉
ひきり-ぎね [4] 【火鑽り杵】
火鑽り臼(ウス)と組み合わせて火をおこす道具。
→火鑽り臼
ひ-ぎり [0] 【日切り】🔗⭐🔉
ひ-ぎり [0] 【日切り】
日数を限って定めること。日限。期限。「―の注文お急ぎ合点(ガテン)/安愚楽鍋(魯文)」
ひ-ぎり [1] 【緋桐】🔗⭐🔉
ひ-ぎり [1] 【緋桐】
クマツヅラ科の落葉低木。東南アジア・インド原産。観賞用に暖地で栽培。葉は大きく,形はキリの葉に似る。夏から秋に,枝頂に大形の円錐花序を立て朱赤色の花を多数つける。トウギリ。漢名, 桐。
桐。
 桐。
桐。
ひき-りょう ―リヤウ [0] 【引両】🔗⭐🔉
ひき-りょう ―リヤウ [0] 【引両】
家紋の一。輪の中に一〜三本の太い横線を引いたもの。新田氏・足利氏などの家紋。輪のないものや,縦線のものもある。
引両
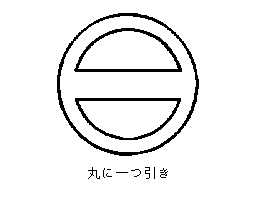 [図]
[図]
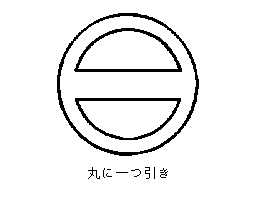 [図]
[図]
ひ-ぎれ [0] 【日切れ】🔗⭐🔉
ひ-ぎれ [0] 【日切れ】
期限の切れること。
ひぎれ-ほうあん ―ハフ― [4] 【日切れ法案】🔗⭐🔉
ひぎれ-ほうあん ―ハフ― [4] 【日切れ法案】
時限法の期限延長のための法律案,特定の期日に開始すべき施策に関する法律案,予算と関係する法律案など,一定期日までの成立が不可欠とされる法律案。
ひき-わけ [0] 【引(き)分け】🔗⭐🔉
ひき-わけ [0] 【引(き)分け】
(1)試合や勝負事で,勝負がつかないまま終わらせること。「―に終わる」「―試合」
(2)平安時代,陰暦八月の駒牽(コマヒキ)のとき,諸国から献上された馬を上皇・皇太子などに分けること。
ひきわけ-ど [4] 【引(き)分け戸】🔗⭐🔉
ひきわけ-ど [4] 【引(き)分け戸】
一本の溝にはめて左右に引いて開けるようにした引き戸。両引き戸。
大辞林 ページ 152788。