複数辞典一括検索+![]()
![]()
み-くまの 【三熊野】🔗⭐🔉
み-くまの 【三熊野】
「熊野三山(クマノサンザン)」に同じ。
み-くまり 【水分り】🔗⭐🔉
み-くまり 【水分り】
〔「み」は「水」,「くまり」は「配り」の意〕
(1)山から流れ出る水が分岐する所。分水嶺(ブンスイレイ)。「―に坐す皇神等(スメガミタチ)の前に白さく/祝詞(祈年祭)」
(2)水を分けること。水を調節すること。
みくまり-じんじゃ [5] 【水分神社】🔗⭐🔉
みくまり-じんじゃ [5] 【水分神社】
水分神を祀(マツ)った神社。雨乞いの対象となることもあった。中古以降,「みくまり」を「みこもり(御子守)」と解し,子供を守り育てる神としても信仰された。
みくまり-の-かみ 【水分神】🔗⭐🔉
みくまり-の-かみ 【水分神】
日本神話で,流水の分配をつかさどる神。古事記に天之水分神・国之水分神の二神が見える。
みくら-じま 【御蔵島】🔗⭐🔉
みくら-じま 【御蔵島】
伊豆七島の一。火山島。海食崖の発達が著しい。全島シイ・ツゲの原生林でおおわれる。
み-くら・べる [0][4] 【見比べる・見較べる】 (動バ下一)[文]バ下二 みくら・ぶ🔗⭐🔉
み-くら・べる [0][4] 【見比べる・見較べる】 (動バ下一)[文]バ下二 みくら・ぶ
(1)二つ以上のものをそれぞれ見てくらべる。「しげしげと二人の顔を―・べる」
(2)比較して考える。比較検討する。「商品を―・べる」「データを―・べる」
み-くり [0] 【実栗・三稜草】🔗⭐🔉
み-くり [0] 【実栗・三稜草】
ミクリ科の多年草。溝や浅い池に生える。葉は根生し,長い線形。夏,花茎の先が分枝し,上方に雄性の,下方に雌性の頭状花序をつける。花後,緑色球形の栗に似た集合果をつける。
実栗
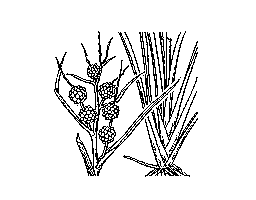 [図]
[図]
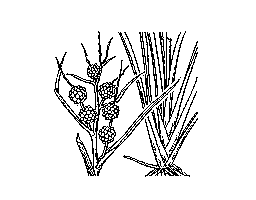 [図]
[図]
みくり-の-すだれ 【三稜の簾】🔗⭐🔉
みくり-の-すだれ 【三稜の簾】
ミクリの茎を干して編んだ簾。
み-くりや 【御厨】🔗⭐🔉
み-くりや 【御厨】
(1)古代・中世,供御(クゴ)・供祭用の魚介類・果物類を調進するために設けられた所領。内膳司所属のもの,伊勢神宮所属のものが著名。
(2)神に供える食物を調理する所。
み-ぐるし・い [4] 【見苦しい】 (形)[文]シク みぐる・し🔗⭐🔉
み-ぐるし・い [4] 【見苦しい】 (形)[文]シク みぐる・し
(1)(物の外観や人間の行為・態度などが)見ていていやになる様子だ。みにくい。みっともない。「―・いごみの山」「―・い負け方」
(2)見づらい。見るのが困難だ。「月頃目をいみじう煩ひ給ひて,よろづ治し尽させ給ひけれど,猶いと―・しくて/栄花(玉のむら菊)」
[派生] ――げ(形動)――さ(名)
大辞林 ページ 155002。