複数辞典一括検索+![]()
![]()
もち-の-き [1] 【黐の木】🔗⭐🔉
もち-の-き [1] 【黐の木】
モチノキ科の常緑高木。山野に自生。また,庭木ともする。葉は楕円形で,厚い革質。雌雄異株。初夏,葉腋に黄緑色の小花をつける。秋,球形の液果が赤く熟す。材は細工物用,樹皮からは鳥黐(トリモチ)を取る。トリモチノキ。モチ。冬青(トウセイ)。
〔「黐の花」は [季]夏〕
もち-の-つき 【望の月】🔗⭐🔉
もち-の-つき 【望の月】
満月。十五夜の月。もちづき。
もち-の-ひ 【望の日】🔗⭐🔉
もち-の-ひ 【望の日】
陰暦一五日。満月の日。「―に出でにし月の高々に/万葉 3005」
もち-の-ふだ 【餅の札】🔗⭐🔉
もち-の-ふだ 【餅の札】
江戸時代,年末に乞食などが家々から餅を請い,もらった家の門柱にそのしるしとしてはった札。「弱法師わが門ゆるせ―(其角)/猿蓑」
もち-のり [0][2] 【餅糊】🔗⭐🔉
もち-のり [0][2] 【餅糊】
餅をつぶして練ってつくった糊。粘着力が強く,細工物などに用いた。
もち-ば [3] 【持(ち)場】🔗⭐🔉
もち-ば [3] 【持(ち)場】
受け持ちの場所。担当の部署。「―につく」「―を守る」
もち-はこび [0] 【持(ち)運び】🔗⭐🔉
もち-はこび [0] 【持(ち)運び】
もちはこぶこと。運搬。「―に便利がいい」
もち-はこ・ぶ [4][0] 【持(ち)運ぶ】 (動バ五[四])🔗⭐🔉
もち-はこ・ぶ [4][0] 【持(ち)運ぶ】 (動バ五[四])
物を持って,他の場所へ移す。運搬する。「荷物を―・ぶ」
[可能] もちはこべる
もち-はだ [0] 【餅肌・餅膚】🔗⭐🔉
もち-はだ [0] 【餅肌・餅膚】
つきたての餅のように,色が白くなめらかでふっくらとした肌。「―の美人」
もち-ばな [0] 【餅花】🔗⭐🔉
もち-ばな [0] 【餅花】
柳の枝などに,小さく丸めた餅や米の粉のだんごをたくさん付けたもの。農作物の豊作や財宝が多くなるように祈って小正月に神棚に飾る。繭の形に作ったものを繭玉という。餅の花。[季]新年。《―や灯立て壁の影/其角》
餅花
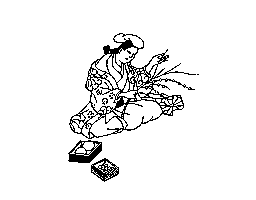 [図]
[図]
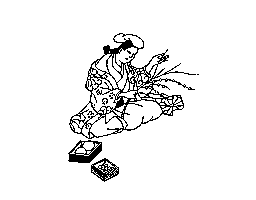 [図]
[図]
もちばな-いり [4] 【餅花煎り】🔗⭐🔉
もちばな-いり [4] 【餅花煎り】
正月の餅花をとっておき,二月の涅槃会(ネハンエ)のときに煎(イ)って供物とするもの。餅をあられのように切って用いることもある。
大辞林 ページ 155661。