複数辞典一括検索+![]()
![]()
やつ-はし [2] 【八つ橋】🔗⭐🔉
やつ-はし [2] 【八つ橋】
(1)庭園の池などで,幅の狭い板を数枚ジグザグに並べて架けた橋。
(2)和菓子の一。精白米粉を湯でこねて,砂糖・肉桂で味・香りをつけ蒸したものを,薄くのばして切ったもの。二つ折りにして餡(アン)を入れたものや,鉄板で焼いて煎餅にしたものがある。京都聖護院の名物。
(3)「八つ橋織り」の略。
(4)〔近世に「八橋流」の略から転じて〕
琴のこと。
八つ橋(1)
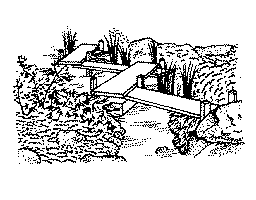 [図]
[図]
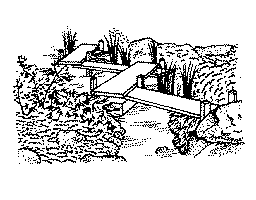 [図]
[図]
やつはし-おり [0] 【八つ橋織(り)】🔗⭐🔉
やつはし-おり [0] 【八つ橋織(り)】
表繻子(シユス)と裏繻子の組織を格子状に配した絹織物。もと,仙台藩の特産。羽織裏・夜具・コートなどに用いる。
やつはし-の 【八つ橋の】 (枕詞)🔗⭐🔉
やつはし-の 【八つ橋の】 (枕詞)
「伊勢物語」の「そこを八橋といひけるは,水ゆく川の蜘蛛手(クモデ)なれば,橋を八つわたせるによりてなむ八橋といひける」の文から「くもで」にかかる。物思いの多いことのたとえ。「うちわたし長き心は―くもでに思ふことは絶えせじ/後撰(恋一)」
やっぱし [3] (副)🔗⭐🔉
やっぱし [3] (副)
「やっぱり」の転。「―だめだった」「是でも―懲(コ)りねえのさ/洒落本・深川手習草紙」
やつはし-けんぎょう ―ケンゲウ 【八橋検校】🔗⭐🔉
やつはし-けんぎょう ―ケンゲウ 【八橋検校】
(1614-1685) 俗箏(ゾクソウ)(箏曲)八橋流の開祖。磐城平(一説に豊前小倉)の人。中年まで京坂で三味線・胡弓の名手として活躍。のちに江戸で法水に筑紫箏(ツクシゴト)を学び,それを改編して箏組歌一三曲と段物(「六段」など)三曲を編作曲して俗箏を創始した。
やつはし-りゅう ―リウ 【八橋流】🔗⭐🔉
やつはし-りゅう ―リウ 【八橋流】
箏曲の流派の一。俗箏(ゾクソウ)の最初の流派。一七世紀中葉に,八橋検校(ケンギヨウ)が筑紫箏(ツクシゴト)を改編して創始。一七世紀末以降,生田流はじめ多くの分派が生じ,それらの隆盛の中で,八橋流の称は次第に衰退した。末流の一部が信州松代の真田家に伝存する。
大辞林 ページ 155910。