複数辞典一括検索+![]()
![]()
かる・う【担ふ】🔗⭐🔉
かる・う カルフ 【担ふ】 (動ハ四)
背負う。「―・ワセテコイ/ロドリゲス」
かるか🔗⭐🔉
かるか
先込めの鉄砲で,銃身に弾丸を込めたり,銃身を掃除したりするのに用いる鉄製の細長い棒。 杖(サクジヨウ)。「―をひん抜て,鉄砲を腰にひつばさけて/雑兵物語」
〔(ポルトガル)calcadorからともいう〕
→火縄銃
杖(サクジヨウ)。「―をひん抜て,鉄砲を腰にひつばさけて/雑兵物語」
〔(ポルトガル)calcadorからともいう〕
→火縄銃
 杖(サクジヨウ)。「―をひん抜て,鉄砲を腰にひつばさけて/雑兵物語」
〔(ポルトガル)calcadorからともいう〕
→火縄銃
杖(サクジヨウ)。「―をひん抜て,鉄砲を腰にひつばさけて/雑兵物語」
〔(ポルトガル)calcadorからともいう〕
→火縄銃
かるかや-の【刈る萱の】🔗⭐🔉
かるかや-の 【刈る萱の】 (枕詞)
萱の穂の意から「ほに出づ」に,また,刈り取ったカヤは乱れやすいので「乱る」にかかる。「―ほに出て物を言はねども/古今六帖 6」
かる-かん【軽羹】🔗⭐🔉
かる-かん [0] 【軽羹】
蒸し菓子の一。ヤマノイモをすりおろして, 粉(シンコ)や蕎麦粉(ソバコ)・砂糖と練り合わせて蒸したもの。鹿児島県の銘菓。
粉(シンコ)や蕎麦粉(ソバコ)・砂糖と練り合わせて蒸したもの。鹿児島県の銘菓。
 粉(シンコ)や蕎麦粉(ソバコ)・砂糖と練り合わせて蒸したもの。鹿児島県の銘菓。
粉(シンコ)や蕎麦粉(ソバコ)・砂糖と練り合わせて蒸したもの。鹿児島県の銘菓。
かる-の-いち【軽の市】🔗⭐🔉
かる-の-いち 【軽の市】
上代,軽の地で開かれた市。
→軽
かる-の-おおいらつめ【軽大郎女】🔗⭐🔉
かる-の-おおいらつめ ―オホイラツメ 【軽大郎女】
允恭(インギヨウ)天皇の皇女。同母の兄軽皇子(カルノミコ)との近親相姦を伝える記紀の悲劇的歌謡物語の女主人公。古事記では,流刑の軽皇子を追って伊予に行き,そこで心中したと伝え,日本書紀では,太子である軽皇子に代わって伊予に流されたとされる。衣通郎女(ソトオリノイラツメ)。
かる-の-みこ【軽皇子・軽王】🔗⭐🔉
かる-の-みこ 【軽皇子・軽王】
允恭(インギヨウ)天皇の皇子。太子であったが,同母の妹軽大郎女(カルノオオイラツメ)との近親相姦が発覚して失脚。古事記では,伊予に流され,その地で軽大郎女とともに心中したと伝え,日本書紀では,臣下に背かれ,穴穂皇子(アナホノミコ)(安康天皇)の軍に囲まれ自殺したとされる。
かる-み【軽み】🔗⭐🔉
かる・む【軽む】🔗⭐🔉
かる・む 【軽む】
〔「かろむ」の転〕
■一■ (動マ四)
軽くなる。「罪―・ませ給はめ/源氏(玉鬘)」
■二■ (動マ下二)
(1)軽くする。「身のくるしみを―・めたまへ/こんてむつすむん地」
(2)軽んずる。あなどる。「人に―・めあなづらるるに/源氏(乙女)」
かるめ-きん【軽目金】🔗⭐🔉
かるめ-きん [0] 【軽目金】
摩滅のため量目の減った小判や一分金。かるめ。
かる-も【枯る草】🔗⭐🔉
かる-も 【枯る草】
枯れ草。「秋の野の―が下に月もりて/夫木 27」
かるも-かく【枯る草掻く】🔗⭐🔉
かるも-かく 【枯る草掻く】 (枕詞)
猪(イノシシ)が枯れ草を集め寝床にするところから,「猪(イ)」または「い」を含む語にかかる。かるもかき。「―ゐな野の原の仮枕/続古今(羇旅)」
かる-もの【軽物】🔗⭐🔉
かる-もの 【軽物】
〔目方の軽い物の意〕
絹布類の称。「―も人要すばかりの物は少少有り/今昔 28」
かる-やか【軽やか】🔗⭐🔉
かる-やか [2] 【軽やか】 (形動)[文]ナリ
「かろやか」に同じ。「―な足取り」
かる-やき【軽焼(き)】🔗⭐🔉
かる-やき [0] 【軽焼(き)】
「軽焼き煎餅(センベイ)」の略。
かる-ゆき【軽行き】🔗⭐🔉
かる-ゆき 【軽行き】 (形動)
たやすく事が運ぶさま。手軽。「一人を金一角に定めおきしは―なる呼物也/浮世草子・一代女 1」
かるら【迦楼羅】🔗⭐🔉
かるら-えん【迦楼羅炎】🔗⭐🔉
かるら-えん [3] 【迦楼羅炎】
迦楼羅の口から吐く火炎。不動明王の光背はこれをあしらったもの。
かるら-ほう【迦楼羅法】🔗⭐🔉
かるら-ほう ―ホフ [0] 【迦楼羅法】
密教で,迦楼羅を本尊として,病苦・風雨・落雷などの災いを除くために行う修法。
かる-らか【軽らか】🔗⭐🔉
かる-らか 【軽らか】 (形動ナリ)
「かろらか」に同じ。「―にはひ渡り/源氏(胡蝶)」
大辞林に「−がる」で始まるの検索結果 1-21。
 a「金翅(コンジ)鳥」の意〕
(1)仏典にみえる想像上の大鳥。金色で鷲(ワシ)に似ていて,口から火を吐き,竜を取って食うとされる。仏教を守護する天竜八部衆の一。密教では,衆生を救うために梵天が化した姿とする。がるら。
a「金翅(コンジ)鳥」の意〕
(1)仏典にみえる想像上の大鳥。金色で鷲(ワシ)に似ていて,口から火を吐き,竜を取って食うとされる。仏教を守護する天竜八部衆の一。密教では,衆生を救うために梵天が化した姿とする。がるら。
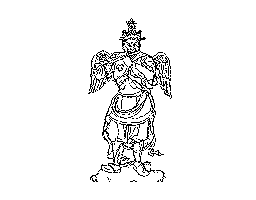 [図]
[図]