複数辞典一括検索+![]()
![]()
しい【尿】🔗⭐🔉
しい 【尿】
〔幼児語〕
小便。おしっこ。
しい【椎】🔗⭐🔉
しい シヒ [1] 【椎】
ブナ科の常緑高木。ツブラジイ・スダジイの総称。関東以西の暖地に自生し,大木・古木となる。葉は革質で長円形。雌雄同株。果実はどんぐり状で食用になる。材は建材・家具材,椎茸の原木などとする。樹皮は染色に用いる。シイノキ。シイガシ。
し-い【尸位】🔗⭐🔉
し-い ― [1] 【尸位】
〔「書経(五子之歌)」による。人が尸(カタシロ)として,仮に神霊の位につく意〕
才能も人徳もないのにいたずらに位についていること。「―素餐(ソサン)」
[1] 【尸位】
〔「書経(五子之歌)」による。人が尸(カタシロ)として,仮に神霊の位につく意〕
才能も人徳もないのにいたずらに位についていること。「―素餐(ソサン)」
 [1] 【尸位】
〔「書経(五子之歌)」による。人が尸(カタシロ)として,仮に神霊の位につく意〕
才能も人徳もないのにいたずらに位についていること。「―素餐(ソサン)」
[1] 【尸位】
〔「書経(五子之歌)」による。人が尸(カタシロ)として,仮に神霊の位につく意〕
才能も人徳もないのにいたずらに位についていること。「―素餐(ソサン)」
し-い【四夷】🔗⭐🔉
し-い [1] 【四夷】
漢民族が中国の周囲の異民族をさしていう語。東夷・西戎(セイジユウ)・南蛮・北狄(ホクテキ)の総称。転じて服従しない四方の民。
し-い【四位】🔗⭐🔉
し-い ― [1] 【四位】
位階の第四番目。正四位・従四位の総称。
[1] 【四位】
位階の第四番目。正四位・従四位の総称。
 [1] 【四位】
位階の第四番目。正四位・従四位の総称。
[1] 【四位】
位階の第四番目。正四位・従四位の総称。
し-い【四囲】🔗⭐🔉
し-い ― [1] 【四囲】 (名)スル
(1)四方をとり囲むこと。「高嶽之れを―す/日本風景論(重昂)」
(2)まわり。周囲。「―の情勢」
[1] 【四囲】 (名)スル
(1)四方をとり囲むこと。「高嶽之れを―す/日本風景論(重昂)」
(2)まわり。周囲。「―の情勢」
 [1] 【四囲】 (名)スル
(1)四方をとり囲むこと。「高嶽之れを―す/日本風景論(重昂)」
(2)まわり。周囲。「―の情勢」
[1] 【四囲】 (名)スル
(1)四方をとり囲むこと。「高嶽之れを―す/日本風景論(重昂)」
(2)まわり。周囲。「―の情勢」
し-い【四維】🔗⭐🔉
し-い ― [1] 【四維】
(1)〔「維」は隅(スミ)の意〕
艮(ウシトラ)(北東)・巽(タツミ)(南東)・坤(ヒツジサル)(南西)・乾(イヌイ)(北西)の四つの方位。
(2)〔「管子(牧民)」による。「維」は大綱の意〕
国家を維持するのに必要な四つの基本的な事柄。礼・義・廉・恥をいう。
[1] 【四維】
(1)〔「維」は隅(スミ)の意〕
艮(ウシトラ)(北東)・巽(タツミ)(南東)・坤(ヒツジサル)(南西)・乾(イヌイ)(北西)の四つの方位。
(2)〔「管子(牧民)」による。「維」は大綱の意〕
国家を維持するのに必要な四つの基本的な事柄。礼・義・廉・恥をいう。
 [1] 【四維】
(1)〔「維」は隅(スミ)の意〕
艮(ウシトラ)(北東)・巽(タツミ)(南東)・坤(ヒツジサル)(南西)・乾(イヌイ)(北西)の四つの方位。
(2)〔「管子(牧民)」による。「維」は大綱の意〕
国家を維持するのに必要な四つの基本的な事柄。礼・義・廉・恥をいう。
[1] 【四維】
(1)〔「維」は隅(スミ)の意〕
艮(ウシトラ)(北東)・巽(タツミ)(南東)・坤(ヒツジサル)(南西)・乾(イヌイ)(北西)の四つの方位。
(2)〔「管子(牧民)」による。「維」は大綱の意〕
国家を維持するのに必要な四つの基本的な事柄。礼・義・廉・恥をいう。
し-い【旨意】🔗⭐🔉
し-い [1] 【旨意】
考え。意図。「何等の―も,秩序も,趣味も無くて/金色夜叉(紅葉)」
し-い【私意】🔗⭐🔉
し-い [1] 【私意】
(1)自分の考え。私見。
(2)私情を交えた不公平な考え。「毫も―なし/花柳春話(純一郎)」
し-い【思惟】🔗⭐🔉
し-い ― [1] 【思惟】 (名)スル
(1)考えること。思考。しゆい。「其―する所甚だ卑下にして/明六雑誌 19」
(2)〔仏〕「しゆい(思惟)」に同じ。
(3)〔哲〕「思考(シコウ){(2)}」に同じ。
[1] 【思惟】 (名)スル
(1)考えること。思考。しゆい。「其―する所甚だ卑下にして/明六雑誌 19」
(2)〔仏〕「しゆい(思惟)」に同じ。
(3)〔哲〕「思考(シコウ){(2)}」に同じ。
 [1] 【思惟】 (名)スル
(1)考えること。思考。しゆい。「其―する所甚だ卑下にして/明六雑誌 19」
(2)〔仏〕「しゆい(思惟)」に同じ。
(3)〔哲〕「思考(シコウ){(2)}」に同じ。
[1] 【思惟】 (名)スル
(1)考えること。思考。しゆい。「其―する所甚だ卑下にして/明六雑誌 19」
(2)〔仏〕「しゆい(思惟)」に同じ。
(3)〔哲〕「思考(シコウ){(2)}」に同じ。
し-い【施為】🔗⭐🔉
し-い ― [1] 【施為】
ほどこし行うこと。行為。
[1] 【施為】
ほどこし行うこと。行為。
 [1] 【施為】
ほどこし行うこと。行為。
[1] 【施為】
ほどこし行うこと。行為。
し-い【恣意・肆意】🔗⭐🔉
し-い [1] 【恣意・肆意】
(1)その時々の気ままな思いつき。自分勝手な考え。「会長の―によって方針が左右される」
(2)物事の関係が偶然的であること。「言語の―性」
し-い【徙移】🔗⭐🔉
し-い [1] 【徙移】
移ること。移動。移徙。
し-い【詩意】🔗⭐🔉
し-い [1] 【詩意】
詩の心。詩の意味。
しい🔗⭐🔉
しい [1] (感)
(1)動物を追う語。しっ。
(2)人を制する語。しっ。「―,人が来るぞ」
(3)あざ笑う声を表す語。「―と笑ひけるなり/平治(下・古活字本)」
(4)呼び掛ける語。もしもし。「是に言葉をかけて見う,―,―,申/狂言・鼻取相撲」
し・い🔗⭐🔉
し・い (接尾)
〔形容詞型活用([文]シク し)〕
名詞や動詞の未然形,畳語などに付いて,形容詞をつくる。そういうさまである,そう感じられる,という意を表す。「おとな―・い」「喜ば―・い」「毒々―・い」「にくにく―・い」
しい-か【詩歌】🔗⭐🔉
しい-か [1] 【詩歌】
〔「しか(詩歌)」の慣用読み〕
(1)和歌・俳句・詩など韻文の総称。
(2)和歌と漢詩。「―管弦の遊び」
しいか-あわせ【詩歌合】🔗⭐🔉
しいか-あわせ ―アハセ [4] 【詩歌合】
数名が左右に分かれ,同じ題について詠じた和歌と漢詩をくらべ合わせて優劣を判定したもの。
しい-がし【椎樫】🔗⭐🔉
しい-がし シヒ― [1] 【椎樫】
シイの別名。
しいがもと【椎本】🔗⭐🔉
しいがもと シヒガモト 【椎本】
源氏物語の巻名。第四六帖。宇治十帖の一。
しいがもと【椎本】🔗⭐🔉
しいがもと シヒガモト 【椎本】
姓氏の一。
しいがもと-さいまろ【椎本才麿】🔗⭐🔉
しいがもと-さいまろ シヒガモト― 【椎本才麿】
(1656-1738) 江戸前・中期の俳人。本名,谷八郎右衛門。大和国宇陀の人。西武門,のち西鶴門。青年期に江戸で芭蕉らと親交,のち大坂俳壇の中心となる。著「椎の葉」
し-いき【市域】🔗⭐🔉
し-いき ― キ [1] 【市域】
市の区域。
キ [1] 【市域】
市の区域。
 キ [1] 【市域】
市の区域。
キ [1] 【市域】
市の区域。
し-いぎ【四威儀】🔗⭐🔉
し-いぎ ― ギ [2] 【四威儀】
〔仏〕「四儀(シギ)」に同じ。
ギ [2] 【四威儀】
〔仏〕「四儀(シギ)」に同じ。
 ギ [2] 【四威儀】
〔仏〕「四儀(シギ)」に同じ。
ギ [2] 【四威儀】
〔仏〕「四儀(シギ)」に同じ。
しい-ぎゃく【弑逆】🔗⭐🔉
しい-ぎゃく [0] 【弑逆】 (名)スル
「しぎゃく(弑逆)」の慣用読み。「君父を―する/日本開化小史(卯吉)」
し-いく【飼育】🔗⭐🔉
し-いく [0] 【飼育】 (名)スル
家畜などを養い育てること。「乳牛を―する」
しいく【飼育】🔗⭐🔉
しいく 【飼育】
短編小説。大江健三郎作。1958年(昭和33)「文学界」に発表。山村に不時着した黒人兵を獣のように飼育する村人たちを,子供の眼を通して描く。
しい-けいざい【思惟経済】🔗⭐🔉
しい-けいざい シ ― [3] 【思惟経済】
⇒思考経済(シコウケイザイ)
― [3] 【思惟経済】
⇒思考経済(シコウケイザイ)
 ― [3] 【思惟経済】
⇒思考経済(シコウケイザイ)
― [3] 【思惟経済】
⇒思考経済(シコウケイザイ)
しい-ごと【誣言】🔗⭐🔉
しい-ごと シヒ― [2][0] 【誣言】
事実を曲げて言うこと。作りごと。讒言(ザンゲン)。「君が世にめずらしき―に/浴泉記(喜美子)」
しいさあ🔗⭐🔉
しいさあ [0]
〔獅子さんの意〕
沖縄で,魔よけとして家屋の屋根の四方にとりつける焼物の唐獅子像。
しい-ざかな【強い肴】🔗⭐🔉
しい-ざかな シヒ― [3] 【強い肴】
懐石料理で,酒をさらに客に勧めるために,本来の献立に加えて出す肴。進め肴。
しい-し【四至】🔗⭐🔉
しい-し [1] 【四至】
〔「しし(四至)」の慣用読み〕
古代・中世において,荘園や寺域などの東西南北の境界。
しい-じ【四時】🔗⭐🔉
しい-じ [1] 【四時】
「しじ(四時)」の慣用読み。
しい-しば【椎柴】🔗⭐🔉
しい-しば シヒ― 【椎柴】
(1)椎の小枝。また,椎。「わが折敷ける嶺の―/新古今(羇旅)」
(2)〔椎を染料としたことから〕
喪服。喪服の色。「―に変へぬを歎く涙もて深くぞ袖の色を染めつる/新千載(哀傷)」
しい-しゅ【旨趣】🔗⭐🔉
しい-しゅ 【旨趣】
「ししゅ(旨趣)」の慣用読み。「心の底に―を残すべきに非ず/平家 2」
し-い・ず【為出づ】🔗⭐🔉
し-い・ず ―イヅ 【為出づ】 (動ダ下二)
(1)作り上げる。やり遂げる。「嫗よろづにしありきて其の折の事皆―・でつ/宇津保(俊蔭)」
(2)事をする。しでかす。「なかなかなること―・でたる/紫式部日記」
(3)し始める。「その世の物語―・で侍りていと堪へがたく/源氏(玉鬘)」
しい・する【弑する】🔗⭐🔉
しい・する [3] 【弑する】 (動サ変)[文]サ変 しい・す
〔「しする(弑)」の慣用読み〕
主君・親など目上の人を殺す。「誰か其君を―・するを欲せん/日本開化小史(卯吉)」
しい-せい【恣意性】🔗⭐🔉
しい-せい [0] 【恣意性】
〔(フランス) arbitraire〕
ソシュールの用語。言語記号の音声面(能記)と意味内容面(所記)との間には自然な結びつきが存在しないこと。
しい-そさん【尸位素餐】🔗⭐🔉
しい-そさん シ ― [1] 【尸位素餐】
〔漢書(朱雲伝)〕
才能も人徳もないのに位についていて,むなしく俸禄を食(ハ)むこと。
― [1] 【尸位素餐】
〔漢書(朱雲伝)〕
才能も人徳もないのに位についていて,むなしく俸禄を食(ハ)むこと。
 ― [1] 【尸位素餐】
〔漢書(朱雲伝)〕
才能も人徳もないのに位についていて,むなしく俸禄を食(ハ)むこと。
― [1] 【尸位素餐】
〔漢書(朱雲伝)〕
才能も人徳もないのに位についていて,むなしく俸禄を食(ハ)むこと。
しい-たけ【椎茸】🔗⭐🔉
しい-たけ シヒ― [1] 【椎茸】
(1)担子菌類ハラタケ目のきのこ。ナラ・クヌギ・シイ・クリ・カシなどの枯れ木に生えるが,人工栽培もされる。傘は径6〜10センチメートル。肉質で弾性があり,上面は淡褐色から黒褐色。食用。乾物は香りが高い。[季]秋。
(2)「椎茸髱(タボ)」の略。
しいたけ-たぼ【椎茸髱】🔗⭐🔉
しいたけ-たぼ シヒ― [5] 【椎茸髱】
江戸時代,御殿女中の髪形の一。椎茸の傘状に左右の鬢(ビン)を張り出した髱。また,その髪形の御殿女中。
しいた・げる【虐げる】🔗⭐🔉
しいた・げる シヒタゲル [4] 【虐げる】 (動ガ下一)[文]ガ下二 しひた・ぐ
〔「しへたぐ」の転〕
むごい扱いをして苦しめる。虐待(ギヤクタイ)する。「領民を―・げる」「動物を―・げる」
し-いだ・す【為出だす】🔗⭐🔉
し-いだ・す 【為出だす】 (動サ四)
(1)作って形のあるものにする。また,事を成し遂げる。「白鑞(ロウ)をわかして…海・山・亀・月,いろを尽して―・す/宇津保(吹上・上)」「打手は向うたりといへどもさせる―・したる事も候はず/平家 6」
(2)事件などを引き起こす。ある状況にする。「かかる態(ワザ)を―・して量らんをばいかにかはすべき/今昔 28」
(3)し始める。初めてする。「唐土の烏曹といふ者,博棊(バクギ)といふ事を―・せしより/仮名草子・浮世物語」
しいたぶ-たい【椎椨帯】🔗⭐🔉
しいたぶ-たい [0] 【椎椨帯】
温帯の山麓帯のこと。シイ・タブノキなどの照葉樹林が発達するのでいう。
し-いち【視位置】🔗⭐🔉
し-いち ― チ [2] 【視位置】
天球上における天体の見かけの位置。地球の中心から見たある時刻の天体の幾何学的位置に年周光行差などの補正をしたもの。天体暦に記載。
チ [2] 【視位置】
天球上における天体の見かけの位置。地球の中心から見たある時刻の天体の幾何学的位置に年周光行差などの補正をしたもの。天体暦に記載。
 チ [2] 【視位置】
天球上における天体の見かけの位置。地球の中心から見たある時刻の天体の幾何学的位置に年周光行差などの補正をしたもの。天体暦に記載。
チ [2] 【視位置】
天球上における天体の見かけの位置。地球の中心から見たある時刻の天体の幾何学的位置に年周光行差などの補正をしたもの。天体暦に記載。
しいちろく-じけん【四・一六事件】🔗⭐🔉
しいちろく-じけん 【四・一六事件】
1929年(昭和4)4月16日,前年の三・一五事件に引き続き,田中義一内閣によって行われた日本共産党員大量検挙事件。よんいちろくじけん。
しい-つ・ける【強い付ける】🔗⭐🔉
しい-つ・ける シヒ― [4] 【強い付ける】 (動カ下一)[文]カ下二 しひつ・く
無理やり勧める。「無暗にワイン(酒)ばかし―・けて居たが/当世書生気質(逍遥)」
し-いっし【視一視】🔗⭐🔉
し-いっし [2] 【視一視】
じっと見つめること。「瞳を定めて能く之を―すれば/世路日記(香水)」
しい-て【強いて】🔗⭐🔉
しい-て シヒ― [1] 【強いて】 (副)
〔動詞「強いる」の連用形に助詞「て」の付いた語〕
(1)困難や反対などを押し切って,物事を行うさま。むりに。むりやり。「嫌なら,―することはない」
(2)むしょうに。むやみに。「はらからの君たちよりも―悲しとおぼえ給ひけり/源氏(柏木)」
しい-てき【恣意的】🔗⭐🔉
しい-てき [0] 【恣意的】 (形動)
その時々の思いつきで物事を判断するさま。「―な解釈」
しいな【粃・秕】🔗⭐🔉
しいな シヒナ [0] 【粃・秕】
(1)十分に実っていない籾(モミ)。殻ばかりで,中に実のない籾。しいなせ。しいだ。
(2)果実のよく実っていないもの。また,中身のからっぽなもの。
しいな【椎名】🔗⭐🔉
しいな シヒナ 【椎名】
姓氏の一。
しいな-りんぞう【椎名麟三】🔗⭐🔉
しいな-りんぞう シヒナリンザウ 【椎名麟三】
(1911-1973) 小説家。兵庫県生まれ。本名,大坪昇。実存主義を基調とする作風で,のちキリスト教に入信。小説「深夜の酒宴」「永遠なる序章」「自由の彼方で」「懲役人の告発」など。
しい-なり【椎形・椎像】🔗⭐🔉
しい-なり シヒ― [0] 【椎形・椎像】
先のとがった当世兜(トウセイカブト)。形が椎の実に似ているのでいう。
しい-の-しょうしょう【四位少将】🔗⭐🔉
しい-の-しょうしょう シ ―セウシヤウ 【四位少将】
(1)四位の位に進んだ近衛府の少将。通常,少将は五位相当であり名誉とされた。
(2)謡曲「通小町(カヨイコマチ)」中の深草の少将のこと。
―セウシヤウ 【四位少将】
(1)四位の位に進んだ近衛府の少将。通常,少将は五位相当であり名誉とされた。
(2)謡曲「通小町(カヨイコマチ)」中の深草の少将のこと。
 ―セウシヤウ 【四位少将】
(1)四位の位に進んだ近衛府の少将。通常,少将は五位相当であり名誉とされた。
(2)謡曲「通小町(カヨイコマチ)」中の深草の少将のこと。
―セウシヤウ 【四位少将】
(1)四位の位に進んだ近衛府の少将。通常,少将は五位相当であり名誉とされた。
(2)謡曲「通小町(カヨイコマチ)」中の深草の少将のこと。
しい-の-み【椎の実】🔗⭐🔉
しい-の-み シヒ― [1] 【椎の実】
(1)椎の果実。形はどんぐり状で,食べられる。[季]秋。
(2)幼い男子の陰茎。また,その年齢の男子。「まだ―だから役に立たねえ/人情本・娘消息」
しいのみ-ふで【椎の実筆】🔗⭐🔉
しいのみ-ふで シヒ― [4] 【椎の実筆】
太書き用の筆。穂が椎の実に似る。
椎の実筆
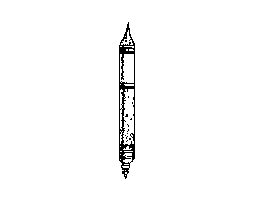 [図]
[図]
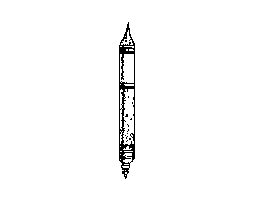 [図]
[図]
しいば【椎葉】🔗⭐🔉
しいば シヒバ 【椎葉】
宮崎県北西部,耳川上流の九州山地にある山村。平家落人の伝説や民謡「稗搗(ヒエツキ)節」で知られる。また,上椎葉ダムがある。
しいら【 ・
・ 】🔗⭐🔉
】🔗⭐🔉
しいら [0][1] 【 ・
・ 】
スズキ目の海魚。全長約1.5メートル。体は著しく側扁し,目の後方の上部から尾部にかけて長い背びれをもつ。体色は背面が青緑色,腹面は黄色を帯びた銀白色で,体側に小黒点が散在する。食用。全世界の暖海に分布。マンビキ。
】
スズキ目の海魚。全長約1.5メートル。体は著しく側扁し,目の後方の上部から尾部にかけて長い背びれをもつ。体色は背面が青緑色,腹面は黄色を帯びた銀白色で,体側に小黒点が散在する。食用。全世界の暖海に分布。マンビキ。

 " src="/%E5%A4%A7%E8%BE%9E%E6%9E%97/binary/mono_180658_1088_256_200.bmp" />
[図]
" src="/%E5%A4%A7%E8%BE%9E%E6%9E%97/binary/mono_180658_1088_256_200.bmp" />
[図]
 ・
・ 】
スズキ目の海魚。全長約1.5メートル。体は著しく側扁し,目の後方の上部から尾部にかけて長い背びれをもつ。体色は背面が青緑色,腹面は黄色を帯びた銀白色で,体側に小黒点が散在する。食用。全世界の暖海に分布。マンビキ。
】
スズキ目の海魚。全長約1.5メートル。体は著しく側扁し,目の後方の上部から尾部にかけて長い背びれをもつ。体色は背面が青緑色,腹面は黄色を帯びた銀白色で,体側に小黒点が散在する。食用。全世界の暖海に分布。マンビキ。

 " src="/%E5%A4%A7%E8%BE%9E%E6%9E%97/binary/mono_180658_1088_256_200.bmp" />
[図]
" src="/%E5%A4%A7%E8%BE%9E%E6%9E%97/binary/mono_180658_1088_256_200.bmp" />
[図]
しいら-づけ【 漬(け)】🔗⭐🔉
漬(け)】🔗⭐🔉
しいら-づけ [0] 【 漬(け)】
竹の束を海面に浮かべ,石俵などにつないで定置したもの。物陰に集まるシイラの習性を利用して漁獲する。また,その漁法。
漬(け)】
竹の束を海面に浮かべ,石俵などにつないで定置したもの。物陰に集まるシイラの習性を利用して漁獲する。また,その漁法。
 漬け
漬け
 漬け" src="/%E5%A4%A7%E8%BE%9E%E6%9E%97/binary/mono_180661_1344_256_200.bmp" />
[図]
漬け" src="/%E5%A4%A7%E8%BE%9E%E6%9E%97/binary/mono_180661_1344_256_200.bmp" />
[図]
 漬(け)】
竹の束を海面に浮かべ,石俵などにつないで定置したもの。物陰に集まるシイラの習性を利用して漁獲する。また,その漁法。
漬(け)】
竹の束を海面に浮かべ,石俵などにつないで定置したもの。物陰に集まるシイラの習性を利用して漁獲する。また,その漁法。
 漬け
漬け
 漬け" src="/%E5%A4%A7%E8%BE%9E%E6%9E%97/binary/mono_180661_1344_256_200.bmp" />
[図]
漬け" src="/%E5%A4%A7%E8%BE%9E%E6%9E%97/binary/mono_180661_1344_256_200.bmp" />
[図]
し・いる【強いる】🔗⭐🔉
し・いる シヒル [2] 【強いる】 (動ア上一)[文]ハ上二 し・ふ
相手の気持ちを無視してむりにさせる。むりにおしつける。強制する。「酒を―・いる」「…に無理を―・いる」「苦戦を―・いられている」
→強いて
し・いる【誣いる】🔗⭐🔉
し・いる シヒル [2] 【誣いる】 (動ア上一)[文]ハ上二 し・ふ
〔「強いる」と同源〕
事実を曲げていう。ありもしない事を述べて,人を悪くいう。「そをかくまで―・ふるは/浴泉記(喜美子)」
し・いる【癈いる】🔗⭐🔉
し・いる シヒル [2] 【癈いる】 (動ア上一)[文]ハ上二 し・ふ
目や耳の感覚を失う。「耳の―・いるほど鋭く響く/奇遇(四迷)」「両眼―・イマシマシテ/日葡」「耳―・イテ/日葡」
しい・る🔗⭐🔉
しい・る シヒル (動ラ下二)
ふくれていたものがしぼむ。「御腹ただ―・れに―・れて/栄花(浦々の別)」
し-いれ【仕入れ】🔗⭐🔉
し-いれ [0] 【仕入れ】
(1)商品・原材料などを仕入れること。「―帳」
(2)しこむこと。訓練すること。「元来女郎と野郎は凡夫の生いたちの―から違ふた物なり/浮世草子・禁短気」
しいれ-さき【仕入れ先】🔗⭐🔉
しいれ-さき [0] 【仕入れ先】
商品・原材料などの仕入れをする相手方。
しいれ-もの【仕入れ物】🔗⭐🔉
しいれ-もの [0] 【仕入れ物】
(1)仕入れた品物。
(2)出来合いの品。既製品。
し-い・れる【仕入れる】🔗⭐🔉
し-い・れる [3] 【仕入れる】 (動ラ下一)[文]ラ下二 しい・る
(1)販売のための商品や製造・加工のための原料を買いこむ。「問屋から―・れる」
(2)物事を自分のものとして取りいれる。「新しい情報を―・れる」
(3)訓練する。しこむ。「長崎水右衛門が―・れたる鼠づかひの藤兵衛/浮世草子・胸算用 1」
し-いん【子音】🔗⭐🔉
し-いん [0] 【子音】
〔consonant〕
言語音の分類の一。発音に際して発音器官のどこかで閉鎖,摩擦・せばめなど,呼気の妨げがある音。声帯の振動を伴うか否かにより,有声子音(g, z, d, b など)と無声子音(k, s, t, p など)に分けられる。父音。しおん。
⇔母音
しいん-こうたい【子音交替】🔗⭐🔉
しいん-こうたい ―カウ― [4] 【子音交替】
子音の音韻変化にかかわる諸現象。調音点・調音様式・音源の三点から整理し得る。日本語では,ミラ→ニラ,ヘミ→ヘビ,タレ→ダレなどがそれぞれの例となる。子音推移。
→母音(ボイン)交替
し-いん【子院・支院・枝院】🔗⭐🔉
し-いん ― ン [1][0] 【子院・支院・枝院】
(1)「塔頭(タツチユウ)」に同じ。
(2)本寺に属する寺院。末寺。
ン [1][0] 【子院・支院・枝院】
(1)「塔頭(タツチユウ)」に同じ。
(2)本寺に属する寺院。末寺。
 ン [1][0] 【子院・支院・枝院】
(1)「塔頭(タツチユウ)」に同じ。
(2)本寺に属する寺院。末寺。
ン [1][0] 【子院・支院・枝院】
(1)「塔頭(タツチユウ)」に同じ。
(2)本寺に属する寺院。末寺。
し-いん【四韻】🔗⭐🔉
し-いん ― ン [0][1] 【四韻】
律詩のこと。四か所で韻を踏むのでいう。「―の詩(ウタ)なめりき/宇津保(嵯峨院)」
ン [0][1] 【四韻】
律詩のこと。四か所で韻を踏むのでいう。「―の詩(ウタ)なめりき/宇津保(嵯峨院)」
 ン [0][1] 【四韻】
律詩のこと。四か所で韻を踏むのでいう。「―の詩(ウタ)なめりき/宇津保(嵯峨院)」
ン [0][1] 【四韻】
律詩のこと。四か所で韻を踏むのでいう。「―の詩(ウタ)なめりき/宇津保(嵯峨院)」
し-いん【市隠】🔗⭐🔉
し-いん [1] 【市隠】
公の仕事につかず,市井(シセイ)にひっそりと住むこと。また,その人。「東京―仮名垣魯文戯著/安愚楽鍋(魯文)」
し-いん【死因】🔗⭐🔉
し-いん [0] 【死因】
人が死に至った原因。
しいん-しょぶん【死因処分】🔗⭐🔉
しいん-しょぶん [4] 【死因処分】
行為者の死亡によって効力が発生する法律行為。遺言・死因贈与など。死因行為。死後行為。死後処分。
⇔生前処分
しいん-ぞうよ【死因贈与】🔗⭐🔉
しいん-ぞうよ [4] 【死因贈与】
贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与契約。
しいん-ぎぞうざい【私印偽造罪】🔗⭐🔉
しいん-ぎぞうざい ―ギザウ― [0]-[2] 【私印偽造罪】
行使の目的で他人の印章や署名を偽造する犯罪。
し-いん【試飲】🔗⭐🔉
し-いん [0] 【試飲】 (名)スル
(味の良否を知るために)酒類や飲料などをためしに飲むこと。
し-いん【資蔭】🔗⭐🔉
し-いん [0] 【資蔭】
父祖の勲功によって官職に就くこと。
しいん-と🔗⭐🔉
しいん-と [0] (副)スル
物音一つせず,静まりかえっているさま。「場内は―静まりかえった」
しい【四囲の情勢】(和英)🔗⭐🔉
しい【四囲の情勢】
circumstances;surroundings.
しい【思惟する】(和英)🔗⭐🔉
しい【恣意的な(に)】(和英)🔗⭐🔉
しい【恣意的な(に)】
arbitrary(-ily).→英和
しいか【詩歌】(和英)🔗⭐🔉
しいか【詩歌】
Chinese and Japanese poetry (漢詩と和歌);→英和
poetry (散文に対して).
しいたけ【椎茸】(和英)🔗⭐🔉
しいたけ【椎茸】
a shiitake;amushroom.→英和
しいて【強いて…させる】(和英)🔗⭐🔉
しいて【強いて…させる】
force[compel]to do.〜頼む press one's request.〜…とおっしゃれば if you insist.
しいる【強いる】(和英)🔗⭐🔉
しいれ【仕入れ】(和英)🔗⭐🔉
しいん【子音】(和英)🔗⭐🔉
しいん【子音】
aconsonant.→英和
しいん【死因】(和英)🔗⭐🔉
しいん【死因】
the cause of a person's death.
大辞林に「しい」で始まるの検索結果 1-98。