複数辞典一括検索+![]()
![]()
てら【寺】🔗⭐🔉
てら [2][0] 【寺】
〔朝鮮語チョルからという〕
(1)(ア)本堂などの建物を備え,僧尼が居住して,法事や修行を行うための施設。私的な性格の強い庵や特定の修行を目的とする道場に対し,一定の設備を持つ,より正式な宗教施設。伽藍(ガラン)。精舎(シヨウジヤ)。(イ)各種の仏教上の建物や施設の呼称。
(2)寺の住職。寺の僧。「さる―のなづみ給ひ三年切て銀三貫目にして/浮世草子・一代女 2」
(3)「寺子屋」に同じ。「―に上げて手習をさすれども/仮名草子・浮世物語」
(4)博打(バクチ)を開帳する宿。また,寺銭。「―の銭皆はり込み/浄瑠璃・夏祭」
(5)(比叡山延暦寺を「山」というのに対して)園城寺(オンジヨウジ)(三井寺)の称。寺門。
テラ tera
tera 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
テラ [1]  tera
tera 単位に冠して,10
単位に冠して,10
 すなわち一兆を表す語。記号 T
すなわち一兆を表す語。記号 T
 tera
tera 単位に冠して,10
単位に冠して,10
 すなわち一兆を表す語。記号 T
すなわち一兆を表す語。記号 T
て-ら🔗⭐🔉
て-ら (連語)
〔「ているは」の転。話し言葉でのくだけた言い方。上に来る語によって「でら」ともなる〕
感動を込めて,あるいはとがめる口調などで,「ている」の意を表す。…ているなあ。…ているよ。てらあ。「夕日に照らされて,教会の尖塔があんなに光っ―」「君の答えは間違っ―」「空には赤とんぼがあんなに飛んでら」
て-らあ🔗⭐🔉
て-らあ (連語)
〔連語「ている」に終助詞「わ」の付いた「ているわ」の転。上に来る語によっては「でらあ」となる。話し言葉でのくだけた言い方に用いられる〕
動作・状態を,さげすんだりひやかしたりする気持ちを込めて述べるのに用いられる。「あんなこと言っ―」「そんなこと,だれでも知っ―」「女の子なんかと遊んでらあ」
てらい【衒い】🔗⭐🔉
てらい テラヒ [2][0] 【衒い】
てらうこと。ひけらかすこと。「―のない素直な文体」
てら-い【寺井】🔗⭐🔉
てら-い ― 【寺井】
寺にある井戸。「もののふの八十娘子(ヤソオトメ)らが汲みまがふ―の上の堅香子(カタカゴ)の花/万葉 4143」
【寺井】
寺にある井戸。「もののふの八十娘子(ヤソオトメ)らが汲みまがふ―の上の堅香子(カタカゴ)の花/万葉 4143」
 【寺井】
寺にある井戸。「もののふの八十娘子(ヤソオトメ)らが汲みまがふ―の上の堅香子(カタカゴ)の花/万葉 4143」
【寺井】
寺にある井戸。「もののふの八十娘子(ヤソオトメ)らが汲みまがふ―の上の堅香子(カタカゴ)の花/万葉 4143」
てら-いり【寺入り】🔗⭐🔉
てら-いり [0] 【寺入り】
(1)寺子屋に入門すること。また,その子供。「して―はこのお子でござりますか/浄瑠璃・菅原」
(2)戦いに敗れた者・罪人などが治外法権であった寺に逃げこみ,罪を免れたこと。また,失火などの過失を犯した者が,寺にこもって謹慎したこと。
てら・う【衒う】🔗⭐🔉
てら・う テラフ [2][0] 【衒う】 (動ワ五[ハ四])
〔「照らふ」の意〕
(1)ことさらに才能や知識をひけらかす。また,実際以上によく見せかける。「学識を―・う」「奇を―・う」
(2)誇る。みせびらかす。「人―・ふ馬の八匹(ヤツギ)は惜しけくもなし/日本書紀(雄略)」
てら-うけ【寺請】🔗⭐🔉
てら-うけ [0] 【寺請】
(1)江戸幕府がキリシタン禁圧の一環として設けた一種の登録制度。一人一人の民衆を特定の寺院の檀家とし,寺院に自寺の檀家であることを証明させたもの。キリシタン根絶後は一般庶民に対する支配監察のための制度として機能した。寺檀制度。檀家制度。
(2)「寺請状」の略。
てらうけ-じょう【寺請状】🔗⭐🔉
てらうけ-じょう ―ジヤウ [0][4] 【寺請状】
寺請制度に基づいて檀那寺が檀徒に対して発行する文書。当初は仏教徒であることを証明するために用いられたが,のちには民衆の移動・旅行・就業に際して提出を要求される一種の身分証明書となった。寺請証文。寺証文。宗旨手形。
てらうけ-しょうもん【寺請証文】🔗⭐🔉
てらうけ-しょうもん [5] 【寺請証文】
「寺請状」に同じ。
てらうち【寺内】🔗⭐🔉
てらうち 【寺内】
姓氏の一。
てらうち-ひさいち【寺内寿一】🔗⭐🔉
てらうち-ひさいち 【寺内寿一】
(1879-1946) 軍人。陸軍元帥。山口県生まれ。二・二六事件後,広田内閣の陸相。1941年(昭和16)南方軍総司令官。敗戦後サイゴンで死亡。
てらうち-まさたけ【寺内正毅】🔗⭐🔉
てらうち-まさたけ 【寺内正毅】
(1852-1919) 政治家。陸軍大将・元帥。長州藩出身。第一次桂内閣に入閣,以後陸相を歴任。1910年(明治43)初代朝鮮総督。16年(大正5)組閣して,シベリア出兵を断行,世論の批判を受け,米騒動により総辞職した。
てらお【寺尾】🔗⭐🔉
てらお テラヲ 【寺尾】
姓氏の一。
てらお-ひさし【寺尾寿】🔗⭐🔉
てらお-ひさし テラヲ― 【寺尾寿】
(1855-1923) 天文学者。福岡県生まれ。東大卒。東京天文台初代台長となり,編暦・測地学などに業績を残す。東京物理学校(現東京理科大学)の創設者の一人。
てら-おくり【寺送り】🔗⭐🔉
てら-おくり [3] 【寺送り】
死者の位牌(イハイ)・遺物を寺に納めること。
てら-おとこ【寺男】🔗⭐🔉
てら-おとこ ―ヲトコ [3] 【寺男】
寺で雑役をする男。
てら-かた【寺方】🔗⭐🔉
てら-かた [0] 【寺方】
〔「てらがた」とも〕
(1)寺に関係のあること。また,その人々。
(2)寺院の僧侶。
てらかど【寺門】🔗⭐🔉
てらかど 【寺門】
姓氏の一。
てらかど-せいけん【寺門静軒】🔗⭐🔉
てらかど-せいけん 【寺門静軒】
(1796-1868) 幕末の漢詩人。名は良,字(アザナ)は子温,通称,弥五左衛門。江戸で私塾を開く。「無用之人」の自覚のもとに著した,漢文の戯書,「江戸繁昌記」が幕府の出版取り締まりに触れ,のち諸国を放浪。
てら-がね【寺鐘】🔗⭐🔉
てら-がね [2] 【寺鐘】
歌舞伎の鳴り物の一。本吊鐘(ホンツリガネ)などを続けて鳴らすもの。
てら-がまえ【寺構え】🔗⭐🔉
てら-がまえ ―ガマヘ [3] 【寺構え】
寺院建築の構造。また,寺院風なつくり。
てら-こ【寺子】🔗⭐🔉
てら-こ [0] 【寺子】
寺子屋で学んでいる子供。「数多ある―の内/浄瑠璃・菅原」
てらこ-や【寺子屋】🔗⭐🔉
てらこ-や [0] 【寺子屋】
(1)江戸時代の庶民のための初等教育機関。武士・僧侶・医者・神職などが師となり,手習い・読み方・そろばんなどを教えた。寺。寺屋。
(2)浄瑠璃「菅原伝授手習鑑(テナライカガミ)」の四段目の通称。寺子屋を開きながら菅原道真の子菅秀才をかくまう武部源蔵夫婦と,自分の子を秀才の身代わりにする松王丸夫婦の悲劇。
てら-こしょう【寺小姓】🔗⭐🔉
てら-こしょう ―コシヤウ [3] 【寺小姓】
寺にあって,雑用をした少年。男色の相手となるものが多かった。時に,少女が勤めていることもあった。稚児。寺若衆。
テラ-コッタ (イタリア) terracotta
(イタリア) terracotta 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
テラ-コッタ [3]  (イタリア) terracotta
(イタリア) terracotta 〔焼いた土の意〕
良質の粘土を焼いて作った素焼きの塑像や器。古くから作られ,メソポタミア・エジプトなどの遺跡から発掘される。古代ギリシャのタナグラ人形は特に有名。現在でも彫刻や建築装飾の材料として用いられる。
〔焼いた土の意〕
良質の粘土を焼いて作った素焼きの塑像や器。古くから作られ,メソポタミア・エジプトなどの遺跡から発掘される。古代ギリシャのタナグラ人形は特に有名。現在でも彫刻や建築装飾の材料として用いられる。
 (イタリア) terracotta
(イタリア) terracotta 〔焼いた土の意〕
良質の粘土を焼いて作った素焼きの塑像や器。古くから作られ,メソポタミア・エジプトなどの遺跡から発掘される。古代ギリシャのタナグラ人形は特に有名。現在でも彫刻や建築装飾の材料として用いられる。
〔焼いた土の意〕
良質の粘土を焼いて作った素焼きの塑像や器。古くから作られ,メソポタミア・エジプトなどの遺跡から発掘される。古代ギリシャのタナグラ人形は特に有名。現在でも彫刻や建築装飾の材料として用いられる。
てら-ごもり【寺籠り】🔗⭐🔉
てら-ごもり [3] 【寺籠り】
寺にこもって祈念すること。
てらさ・う【照らさふ・衒さふ】🔗⭐🔉
てらさ・う テラサフ 【照らさふ・衒さふ】 (動ハ四)
〔動詞「てらす(照らす)」に助動詞「ふ」が付いたものから〕
物をはっきり見せるようにする。みせびらかす。てらう。「里ごとに―・ひあるけど人も咎めず/万葉 4130」
てらさか【寺坂】🔗⭐🔉
てらさか 【寺坂】
姓氏の一。
てらさか-きちえもん【寺坂吉右衛門】🔗⭐🔉
てらさか-きちえもん ―キチ モン 【寺坂吉右衛門】
(1665-1747) 赤穂浪士の一人。名は信行。吉田兼亮の歩卒。討ち入り後,浅野本家へ事件を通報。のち自首したが,不問に付された。
モン 【寺坂吉右衛門】
(1665-1747) 赤穂浪士の一人。名は信行。吉田兼亮の歩卒。討ち入り後,浅野本家へ事件を通報。のち自首したが,不問に付された。
 モン 【寺坂吉右衛門】
(1665-1747) 赤穂浪士の一人。名は信行。吉田兼亮の歩卒。討ち入り後,浅野本家へ事件を通報。のち自首したが,不問に付された。
モン 【寺坂吉右衛門】
(1665-1747) 赤穂浪士の一人。名は信行。吉田兼亮の歩卒。討ち入り後,浅野本家へ事件を通報。のち自首したが,不問に付された。
てらさき【寺崎】🔗⭐🔉
てらさき 【寺崎】
姓氏の一。
てらさき-こうぎょう【寺崎広業】🔗⭐🔉
てらさき-こうぎょう ―クワウゲフ 【寺崎広業】
(1866-1919) 日本画家。秋田生まれ。東京美術学校教授。狩野派,のち四条風・大和絵風を学び,南画に新風を吹き込む。作「渓四題」「瀟湘八景」など。
てら-ざむらい【寺侍】🔗⭐🔉
てら-ざむらい ―ザムラヒ [3] 【寺侍】
江戸時代,門跡寺院など格式の高い寺に仕え,警護・寺務などにあたった武士。
てらし-あわ・す【照らし合(わ)す】🔗⭐🔉
てらし-あわ・す ―アハス [5] 【照らし合(わ)す】
■一■ (動サ五[四])
「照らし合わせる」に同じ。「資料と―・してみる」
■二■ (動サ下二)
⇒てらしあわせる
てらし-あわ・せる【照らし合(わ)せる】🔗⭐🔉
てらし-あわ・せる ―アハセル [6][0] 【照らし合(わ)せる】 (動サ下一)[文]サ下二 てらしあは・す
二つ以上のものの異同などを調べるため,見比べる。照合する。「台帳と在庫品とを―・せる」
てらし-だ・す【照らし出す】🔗⭐🔉
てらし-だ・す [0][4] 【照らし出す】 (動サ五[四])
光を当ててはっきり現す。「ヘッドライトが人影を―・す」
[可能] てらしだせる
てらしま【寺島】🔗⭐🔉
てらしま 【寺島】
姓氏の一。
てらしま-りょうあん【寺島良安】🔗⭐🔉
てらしま-りょうあん ―リヤウアン 【寺島良安】
江戸中期の古医方家。大坂の人。字(アザナ)は尚順。号,杏林堂。法橋(ホツキヨウ)に叙せられた。和漢の学問に通じ,「和漢三才図会」を編纂。ほかに「三才諸神本記」「済宝記」など。生没年未詳。
てらじま【寺島】🔗⭐🔉
てらじま 【寺島】
姓氏の一。
てらじま-むねのり【寺島宗則】🔗⭐🔉
てらじま-むねのり 【寺島宗則】
(1832-1893) 幕末・明治時代の外交官・政治家。薩摩藩出身。薩英戦争後,渡英,帰国して松木弘安の名で幕府に仕えた。維新後参議・外務卿を歴任,条約改正交渉に当たった。
てら-しょうがつ【寺正月】🔗⭐🔉
てら-しょうがつ ―シヤウグワツ [3] 【寺正月】
寺方の年始回り。一般に正月四日。坊主礼(ボウズレイ)。
てら-じょうもん【寺証文】🔗⭐🔉
てら-じょうもん [3] 【寺証文】
「寺請状(テラウケジヨウ)」に同じ。
テラス terrace; (フランス) terrasse
terrace; (フランス) terrasse 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
テラス [1]  terrace; (フランス) terrasse
terrace; (フランス) terrasse (1)段々になっている台地。段丘。
(2)建物から床と同じ高さで庭や街路に向けて張り出した部分。露台。
(3)登山で,岩壁の途中などの,狭い棚状の場所。
(4)体育館の床の上に張り出した通路または観覧席。
(1)段々になっている台地。段丘。
(2)建物から床と同じ高さで庭や街路に向けて張り出した部分。露台。
(3)登山で,岩壁の途中などの,狭い棚状の場所。
(4)体育館の床の上に張り出した通路または観覧席。
 terrace; (フランス) terrasse
terrace; (フランス) terrasse (1)段々になっている台地。段丘。
(2)建物から床と同じ高さで庭や街路に向けて張り出した部分。露台。
(3)登山で,岩壁の途中などの,狭い棚状の場所。
(4)体育館の床の上に張り出した通路または観覧席。
(1)段々になっている台地。段丘。
(2)建物から床と同じ高さで庭や街路に向けて張り出した部分。露台。
(3)登山で,岩壁の途中などの,狭い棚状の場所。
(4)体育館の床の上に張り出した通路または観覧席。
テラス-ハウス🔗⭐🔉
テラス-ハウス [4]
〔和 terrace+house〕
各戸が専用の庭をもった連続住宅。
てら・す【照らす】🔗⭐🔉
てら・す [0][2] 【照らす】 (動サ五[四])
(1)光を当てて明るくする。輝くようにする。古くは光に限らず,玉・紅葉・美しい容貌などにも用いた。「闇を―・す灯台」「月に―・された庭」「山―・す秋の黄葉(モミチ)の散らまく惜しも/万葉 1517」
(2)基準になるものと引き比べる。参照する。「法に―・す」
(3)てれさせる。恥をかかせる。「吉原にふるといふ言葉あれば,深川に―・すといふ言葉あり/洒落本・古契三娼」
〔「照る」に対する他動詞〕
[可能] てらせる
[慣用] 肝胆相―
てら-せん【寺銭】🔗⭐🔉
てら-せん [0][2] 【寺銭】
博打(バクチ)で,賭場の貸し主に支払う金。動いた金の額に応じて支払う。てらぜに。てら。
テラゾー (イタリア) terrazzo
(イタリア) terrazzo 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
テラゾー [2]  (イタリア) terrazzo
(イタリア) terrazzo 大理石や類似の石材の砕石を白色セメントに混ぜて固め,磨いて大理石のように仕上げた人造石。人造大理石。
大理石や類似の石材の砕石を白色セメントに混ぜて固め,磨いて大理石のように仕上げた人造石。人造大理石。
 (イタリア) terrazzo
(イタリア) terrazzo 大理石や類似の石材の砕石を白色セメントに混ぜて固め,磨いて大理石のように仕上げた人造石。人造大理石。
大理石や類似の石材の砕石を白色セメントに混ぜて固め,磨いて大理石のように仕上げた人造石。人造大理石。
てらだ【寺田】🔗⭐🔉
てらだ 【寺田】
姓氏の一。
てらだ-とらひこ【寺田寅彦】🔗⭐🔉
てらだ-とらひこ 【寺田寅彦】
(1878-1935) 物理学者・随筆家。東京生まれ。筆名は吉村冬彦・藪柑子(ヤブコウジ)など。東大教授。物理学・地球物理学・地震学・気象学・海洋学などの研究に従事するかたわら,夏目漱石に師事し「団栗」「竜舌蘭」など写生文や小品に新生面をひらいた。代表随筆集「冬彦集」「藪柑子集」「万華鏡」
てらだや-そうどう【寺田屋騒動】🔗⭐🔉
てらだや-そうどう ―サウドウ 【寺田屋騒動】
1862年,京都伏見にある船宿寺田屋で,薩摩藩の尊攘派,有馬新七らが島津久光の命を受けた同藩の藩士に殺害された事件。尊攘派と公武合体派との対立による。
てら-ち【寺地】🔗⭐🔉
てら-ち [0] 【寺地】
寺の敷地。寺の土地。
てら-つつき【寺啄】🔗⭐🔉
てら-つつき 【寺啄】
キツツキの異名。「―花の心をしらんとて花を一ふさつつきだしたれ/沙石 5」
てら-てら🔗⭐🔉
てら-てら [1] (副)スル
(1)つやがあって光るさま。「―したはげ頭」「髪は薄いが,櫛に―と艶が見えた/婦系図(鏡花)」
(2)日や月などが照り輝くさま。「薄い日影が―照した/田舎教師(花袋)」
〔「―に」などの場合,アクセントは [0]〕
てらどまり【寺泊】🔗⭐🔉
てらどまり 【寺泊】
新潟県中部,新信濃川河口にある漁業の町。古くは北陸街道の宿駅,佐渡への渡津として繁栄した。
てら-なっとう【寺納豆】🔗⭐🔉
てら-なっとう [3] 【寺納豆】
豆・麹に塩水を加えて発酵させた食品。古くから寺院で作られた。浜納豆など。唐(カラ)納豆。
てらにし【寺西】🔗⭐🔉
てらにし 【寺西】
姓氏の一。
てらにし-かんしん【寺西閑心】🔗⭐🔉
てらにし-かんしん 【寺西閑心】
江戸初期の侠客。赤坂氷川で六法組の侠客一三人を斬り,下野へ逃れた。生没年未詳。
てらのひがし-いせき【寺野東遺跡】🔗⭐🔉
てらのひがし-いせき ― セキ 【寺野東遺跡】
栃木県小山市にある旧石器時代から平安時代の複合集落遺跡。縄文後期に祭祀が行われた環状盛土遺構や水場遺構が発掘された。
セキ 【寺野東遺跡】
栃木県小山市にある旧石器時代から平安時代の複合集落遺跡。縄文後期に祭祀が行われた環状盛土遺構や水場遺構が発掘された。
 セキ 【寺野東遺跡】
栃木県小山市にある旧石器時代から平安時代の複合集落遺跡。縄文後期に祭祀が行われた環状盛土遺構や水場遺構が発掘された。
セキ 【寺野東遺跡】
栃木県小山市にある旧石器時代から平安時代の複合集落遺跡。縄文後期に祭祀が行われた環状盛土遺構や水場遺構が発掘された。
テラピア (ラテン) Tilapia
(ラテン) Tilapia 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
テラピア [0]  (ラテン) Tilapia
(ラテン) Tilapia (1)スズキ目カワスズメ科の淡水魚の総称。アフリカ東部の原産。五〇〇種以上が知られる。雌が卵を口中で保護し孵化させる種が多い。ティラピア。
(2){(1)}の一種。全長約35センチメートル。体は長楕円形で側扁し,クロダイに似る。熱帯魚で成長が早く,温泉地などに移入され養殖される。刺身などにして美味。イズミダイ・チカダイの名で市場にでる。ナイルカワスズメ。
テラピア(2)
(1)スズキ目カワスズメ科の淡水魚の総称。アフリカ東部の原産。五〇〇種以上が知られる。雌が卵を口中で保護し孵化させる種が多い。ティラピア。
(2){(1)}の一種。全長約35センチメートル。体は長楕円形で側扁し,クロダイに似る。熱帯魚で成長が早く,温泉地などに移入され養殖される。刺身などにして美味。イズミダイ・チカダイの名で市場にでる。ナイルカワスズメ。
テラピア(2)
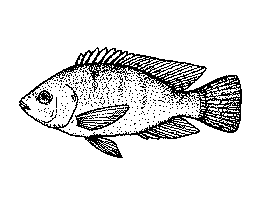 [図]
[図]
 (ラテン) Tilapia
(ラテン) Tilapia (1)スズキ目カワスズメ科の淡水魚の総称。アフリカ東部の原産。五〇〇種以上が知られる。雌が卵を口中で保護し孵化させる種が多い。ティラピア。
(2){(1)}の一種。全長約35センチメートル。体は長楕円形で側扁し,クロダイに似る。熱帯魚で成長が早く,温泉地などに移入され養殖される。刺身などにして美味。イズミダイ・チカダイの名で市場にでる。ナイルカワスズメ。
テラピア(2)
(1)スズキ目カワスズメ科の淡水魚の総称。アフリカ東部の原産。五〇〇種以上が知られる。雌が卵を口中で保護し孵化させる種が多い。ティラピア。
(2){(1)}の一種。全長約35センチメートル。体は長楕円形で側扁し,クロダイに似る。熱帯魚で成長が早く,温泉地などに移入され養殖される。刺身などにして美味。イズミダイ・チカダイの名で市場にでる。ナイルカワスズメ。
テラピア(2)
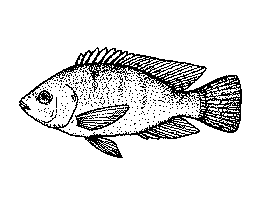 [図]
[図]
てら-ぶぎょう【寺奉行】🔗⭐🔉
てら-ぶぎょう ―ブギヤウ [3] 【寺奉行】
室町幕府の職名。寺院に関する事をつかさどるもの。
てら-ほうし【寺法師】🔗⭐🔉
テラマイシン Terramycin
Terramycin 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
テラマイシン [3]  Terramycin
Terramycin 抗生物質テトラサイクリンの一。オキシテトラサイクリンの商標名。
抗生物質テトラサイクリンの一。オキシテトラサイクリンの商標名。
 Terramycin
Terramycin 抗生物質テトラサイクリンの一。オキシテトラサイクリンの商標名。
抗生物質テトラサイクリンの一。オキシテトラサイクリンの商標名。
てら-まいり【寺参り】🔗⭐🔉
てら-まいり ―マ リ [3] 【寺参り】
寺院に出かけ,法会(ホウエ)・墓参・参拝などを行うこと。てらもうで。
リ [3] 【寺参り】
寺院に出かけ,法会(ホウエ)・墓参・参拝などを行うこと。てらもうで。
 リ [3] 【寺参り】
寺院に出かけ,法会(ホウエ)・墓参・参拝などを行うこと。てらもうで。
リ [3] 【寺参り】
寺院に出かけ,法会(ホウエ)・墓参・参拝などを行うこと。てらもうで。
てら-まち【寺町】🔗⭐🔉
てら-まち [0] 【寺町】
寺院の多く集まった一画。
てら-めぐり【寺巡り】🔗⭐🔉
てら-めぐり [3] 【寺巡り】
方々の寺を巡拝すること。
てら-もうで【寺詣で】🔗⭐🔉
てら-もうで ―マウデ [3] 【寺詣で】
「寺参(テラマイ)り」に同じ。
てら-や【寺屋】🔗⭐🔉
てら-や 【寺屋】
「寺子屋(テラコヤ)」に同じ。「また,この娘は―から戻りが遅い/浄瑠璃・妹背山」
てらやま【寺山】🔗⭐🔉
てらやま 【寺山】
姓氏の一。
てらやま-しゅうじ【寺山修司】🔗⭐🔉
てらやま-しゅうじ ―シウジ 【寺山修司】
(1935-1983) 歌人・劇作家。青森県生まれ。早大中退。歌人として出発,劇団「天井桟敷(サジキ)」を設立,前衛演劇活動を展開。歌集「空には本」「血と麦」,劇作「青森県のせむし男」など。
テラリウム terrarium
terrarium 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
テラリウム [3]  terrarium
terrarium (1)陸性の小動物を飼育する容器。
(2)園芸で,密閉されたガラス器や小口のガラス瓶などの中で,小形の植物を栽培する方法。植物は室内光で光合成を行う。
(1)陸性の小動物を飼育する容器。
(2)園芸で,密閉されたガラス器や小口のガラス瓶などの中で,小形の植物を栽培する方法。植物は室内光で光合成を行う。
 terrarium
terrarium (1)陸性の小動物を飼育する容器。
(2)園芸で,密閉されたガラス器や小口のガラス瓶などの中で,小形の植物を栽培する方法。植物は室内光で光合成を行う。
(1)陸性の小動物を飼育する容器。
(2)園芸で,密閉されたガラス器や小口のガラス瓶などの中で,小形の植物を栽培する方法。植物は室内光で光合成を行う。
テラ-ローシャ (ポルトガル) terra roxa
(ポルトガル) terra roxa 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
テラ-ローシャ [3]  (ポルトガル) terra roxa
(ポルトガル) terra roxa 〔「赤い土」の意〕
玄武岩質の火山岩が風化して出来た赤色の土壌。ブラジル高原の南部に広く分布。肥沃でコーヒー栽培に適する。
〔「赤い土」の意〕
玄武岩質の火山岩が風化して出来た赤色の土壌。ブラジル高原の南部に広く分布。肥沃でコーヒー栽培に適する。
 (ポルトガル) terra roxa
(ポルトガル) terra roxa 〔「赤い土」の意〕
玄武岩質の火山岩が風化して出来た赤色の土壌。ブラジル高原の南部に広く分布。肥沃でコーヒー栽培に適する。
〔「赤い土」の意〕
玄武岩質の火山岩が風化して出来た赤色の土壌。ブラジル高原の南部に広く分布。肥沃でコーヒー栽培に適する。
テラ-ロッサ (イタリア) terra rossa
(イタリア) terra rossa 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
テラ-ロッサ [3]  (イタリア) terra rossa
(イタリア) terra rossa 〔赤い土の意〕
石灰岩が風化してできる赤褐色の土壌。炭酸カルシウムが溶出し,そのあとに残った鉄・アルミニウムの水酸化物,粘土などから成る。地中海沿岸地方に多い。
〔赤い土の意〕
石灰岩が風化してできる赤褐色の土壌。炭酸カルシウムが溶出し,そのあとに残った鉄・アルミニウムの水酸化物,粘土などから成る。地中海沿岸地方に多い。
 (イタリア) terra rossa
(イタリア) terra rossa 〔赤い土の意〕
石灰岩が風化してできる赤褐色の土壌。炭酸カルシウムが溶出し,そのあとに残った鉄・アルミニウムの水酸化物,粘土などから成る。地中海沿岸地方に多い。
〔赤い土の意〕
石灰岩が風化してできる赤褐色の土壌。炭酸カルシウムが溶出し,そのあとに残った鉄・アルミニウムの水酸化物,粘土などから成る。地中海沿岸地方に多い。
てら-わかしゅ【寺若衆】🔗⭐🔉
てら-わかしゅ [3][4] 【寺若衆】
「寺小姓(テラコシヨウ)」に同じ。
テランセラ (ラテン) Telanthera
(ラテン) Telanthera 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
テランセラ [2]  (ラテン) Telanthera
(ラテン) Telanthera ヒユ科の多年草。ブラジル原産。高さ10センチメートル内外。よく分枝し,葉は秋に黄または紅色になる。秋の毛氈(モウセン)花壇に利用。模様
ヒユ科の多年草。ブラジル原産。高さ10センチメートル内外。よく分枝し,葉は秋に黄または紅色になる。秋の毛氈(モウセン)花壇に利用。模様 (モヨウビユ)。
(モヨウビユ)。
 (ラテン) Telanthera
(ラテン) Telanthera ヒユ科の多年草。ブラジル原産。高さ10センチメートル内外。よく分枝し,葉は秋に黄または紅色になる。秋の毛氈(モウセン)花壇に利用。模様
ヒユ科の多年草。ブラジル原産。高さ10センチメートル内外。よく分枝し,葉は秋に黄または紅色になる。秋の毛氈(モウセン)花壇に利用。模様 (モヨウビユ)。
(モヨウビユ)。
て-ランプ【手―】🔗⭐🔉
て-ランプ [2] 【手―】
取っ手のある小さいランプ。
てら【寺】(和英)🔗⭐🔉
てら【寺】
a (Buddhist) temple.
てらい【衒い】(和英)🔗⭐🔉
てらい【衒い】
何の〜もなく unpretentiously.
てらう【衒う】(和英)🔗⭐🔉
てらう【衒う】
[誇示]show off;make a show of;be pedantic (学問を).
てらおとこ【寺男】(和英)🔗⭐🔉
てらおとこ【寺男】
a sexton.→英和
テラコッタ(和英)🔗⭐🔉
テラコッタ
terra-cotta.
てらこや【寺子屋】(和英)🔗⭐🔉
てらこや【寺子屋】
a private elementary school.
てらしあわせる【照らし合わせる】(和英)🔗⭐🔉
てらしあわせる【照らし合わせる】
⇒照合.
てらす【照らす】(和英)🔗⭐🔉
てらせん【寺銭】(和英)🔗⭐🔉
てらせん【寺銭】
a banker's fee (賭博の).
てらてら(和英)🔗⭐🔉
てらてら
〜する be bright[shiny].
大辞林に「てら」で始まるの検索結果 1-87。もっと読み込む