複数辞典一括検索+![]()
![]()
なめ【白痢】🔗⭐🔉
なめ 【白痢】
「びゃくり(白痢)」に同じ。[和名抄]
なめ【滑】🔗⭐🔉
なめ [2] 【滑】
(1)(登山用語)平滑な岩の上を少量の水が流れている所。
(2)なめらかなこと。また,ぬるぬるしたもの。「葛の根を舂(ツ)き,その汁の―を取りて/古事記(中訓)」
なめ【嘗め】🔗⭐🔉
なめ [2] 【嘗め】
(1)なめること。「ひと―なめてみる」
(2)貴人に薬を勧めるとき,あらかじめなめて毒味をすること。また,その役。「両宮の―にはおもと薬師一人参るなり/建武年中行事」
なめ【無礼】🔗⭐🔉
なめ [0] 【無礼】 (形動)[文]ナリ
〔形容詞「なめし」の語幹から〕
無礼なさま。「されど―なる言葉を咎め玉はず/うたかたの記(鴎外)」
なめ-いし【大理石】🔗⭐🔉
なめ-いし [2] 【大理石】
〔なめらかな石の意〕
大理石(ダイリセキ)。
なめ-かた【縵面形】🔗⭐🔉
なめ-かた 【縵面形】
銭を投げて,なめ(裏)が出るか,かた(表)が出るかを当てて勝ち負けを争う賭博。
なめくじ【蛞蝓】🔗⭐🔉
なめくじ ナメクヂ [3] 【蛞蝓】
(1)ナメクジ科およびコウラナメクジ科に属する陸生巻貝の総称。貝殻が全くないか,または退化している。体は円筒形で,頭部に二対の触角をもつ。後方の大触角の先端は目となる。体表は粘液におおわれ,はうと粘液の跡が残る。雌雄同体。多湿な環境を好み,農作物を食害する。塩をかけると体内の水分が出て縮む。なめくじら。なめくじり。[季]夏。
(2)ナメクジ科の陸生巻貝。体長約6センチメートル。無殻で,体表は淡褐色に小黒点が散在し,三条の暗褐色縦帯が走る。アジアに広く分布。
なめくじ-うお【蛞蝓魚】🔗⭐🔉
なめくじ-うお ナメクヂウヲ [4] 【蛞蝓魚】
原索動物頭索綱に属する小形で細長い動物。全長4.5センチメートル前後。原索動物の中では脊椎動物に最も近いと考えられている。背びれ・尾びれなどをもつが,骨がないこと,赤血球がないことなど魚類とは異なる。
なめくじら【蛞蝓】🔗⭐🔉
なめくじら ナメクヂラ [3] 【蛞蝓】
ナメクジの異名。[季]夏。
なめくじり【蛞蝓】🔗⭐🔉
なめくじり ナメクヂリ [3] 【蛞蝓】
ナメクジの異名。[季]夏。《五月雨に家ふり捨てて―/凡兆》
なめ-げ【無礼気】🔗⭐🔉
なめ-げ 【無礼気】 (形動ナリ)
〔形容詞「なめし」の語幹に接尾語「げ」のついたもの〕
無礼なさま。無作法に見えるさま。「せばき所に侍れば―なる事や侍らむ/源氏(帚木)」
なめ-こ【滑子】🔗⭐🔉
なめ-こ [3][0] 【滑子】
(1)担子菌類ハラタケ目のきのこ。天然には秋季,ブナの枯れ木・切り株などに群生し,かさの直径は2センチメートルから10センチメートルほど。表面は粘質物でおおわれる。きわめて美味で栽培もされる。味噌汁の具や大根おろしとあえたりして食べる。
(2)榎茸(エノキタケ)のこと。
滑子(1)
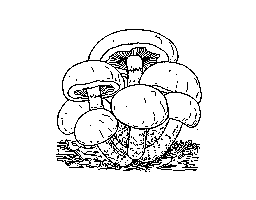 [図]
[図]
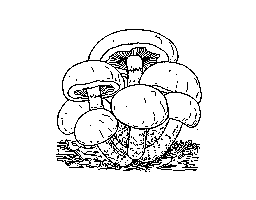 [図]
[図]
なめし【鞣】🔗⭐🔉
なめし [3][0] 【鞣】
皮をなめすこと。また,なめした革。
なめし-がわ【鞣革】🔗⭐🔉
なめし-がわ ―ガハ [0] 【鞣革】
(1)なめした革。つくりかわ。レザー。
(2)(「韋」と書く)漢字の部首の一。「韓」「 」の「韋」の部分。皮(けがわ)・革(つくりかわ)と区別していう。
」の「韋」の部分。皮(けがわ)・革(つくりかわ)と区別していう。
 」の「韋」の部分。皮(けがわ)・革(つくりかわ)と区別していう。
」の「韋」の部分。皮(けがわ)・革(つくりかわ)と区別していう。
な-めし【菜飯】🔗⭐🔉
な-めし [1] 【菜飯】
刻んだ青菜を炊き込んだ塩味の飯。また,炊き上げた飯に,刻んで塩味をつけた青菜を混ぜたもの。[季]春。《さみどりの―が出来てかぐはしや/虚子》
なめ・し【無礼し】🔗⭐🔉
なめ・し 【無礼し】 (形ク)
礼を欠いている。無礼である。無作法である。「いと―・しと思ひけれど心ざしはいやまさりけり/伊勢 105」
なめ・す【鞣す】🔗⭐🔉
なめ・す [2] 【鞣す】 (動サ五[四])
動物の皮をなめし革にする。動物の皮から皮下組織などを除いてから,クロムなめし剤・植物タンニンなめし剤などで処理し,皮を構成するタンパク質の腐敗を防ぎ,耐水性・耐熱性・耐磨耗性を与える。「シカの皮を―・す」
なめ-ずり【舐めずり】🔗⭐🔉
なめ-ずり ―ヅリ [4][0] 【舐めずり】
なめずること。「舌―」
なめ-ず・る【舐めずる】🔗⭐🔉
なめ-ず・る ―ヅル [3] 【舐めずる】 (動ラ五[四])
舌で,唇をなめまわす。「跡から,跡から子供を産んで…―・るばかりにして,愛し育てる/放浪(泡鳴)」「舌を―・り/霊異記(中訓注)」
なめ-そ🔗⭐🔉
なめ-そ
瀬戸内海地方で,漁師の恐れる怪魚の名。サメの一種かといわれ,これに船を追い越されるときは,鉈(ナタ)で断ち切らないと船が沈むという。めっそう。
なめた-がれい【なめた鰈】🔗⭐🔉
なめた-がれい ―ガレヒ [4] 【なめた鰈】
ババガレイの別名。
なめ-たけ【滑茸】🔗⭐🔉
なめ-たけ [2] 【滑茸】
エノキタケの別名。
なめ-つく・す【舐め尽(く)す・嘗め尽(く)す】🔗⭐🔉
なめ-つく・す [4][0] 【舐め尽(く)す・嘗め尽(く)す】 (動サ五[四])
(1)全部なめてしまう。
(2)(炎を舌にたとえて)建物などを全部燃やす。「山火事は麓(フモト)の町を―・した」
なめ-て【並めて】🔗⭐🔉
なめ-て 【並めて】 (副)
「なべて(並)」に同じ。「吹く風の―梢にあたるかなかばかり人の惜しむ桜に/山家(春)」
なめ-まわ・す【舐め回す】🔗⭐🔉
なめ-まわ・す ―マハス [4] 【舐め回す】 (動サ五[四])
舌であちらこちらをなめる。すみずみまでなめる。「唇を―・す」
なめ-みそ【嘗め味噌】🔗⭐🔉
なめ-みそ [0][3] 【嘗め味噌】
魚・肉・野菜などを入れて調味してあり,そのまま副食とする味噌。調味用のものに対していう。金山寺味噌・鯛味噌など。
なめ-もの【嘗め物】🔗⭐🔉
なめ-もの [2][0] 【嘗め物】
嘗め味噌・ひしお・塩辛などの副食物の総称。
なめ-ら【滑ら】🔗⭐🔉
なめ-ら 【滑ら】
水などですべりやすいこと。なめらか。「下は―の溜り池/浄瑠璃・祇園女御九重錦」
なめら-ふぐ【滑河豚】🔗⭐🔉
なめら-ふぐ [4] 【滑河豚】
マフグの別名。
なめら-か【滑らか】🔗⭐🔉
なめら-か [2] 【滑らか】 (形動)[文]ナリ
(1)表面が平らですべすべしているさま。つるつるしているさま。また,すべりやすいさま。「―な肌」「―な斜面」「表面を―に削る」「蒼苔路―にして/和漢朗詠(秋)」
(2)物事がよどみなく運ぶさま。すらすらと進むさま。「ヨットが湖面を―に進む」「―な口調で話す」
[派生] ――さ(名)
な めり🔗⭐🔉
めり🔗⭐🔉
な めり (連語)
〔断定の助動詞「なり」の連体形に推量の助動詞「めり」の付いたものの撥音便の形「なんめり」の撥音「ん」が表記されなかったもの〕
…であるとみえる。…であるようだ。「子となり給ふべき人―
めり (連語)
〔断定の助動詞「なり」の連体形に推量の助動詞「めり」の付いたものの撥音便の形「なんめり」の撥音「ん」が表記されなかったもの〕
…であるとみえる。…であるようだ。「子となり給ふべき人― めり/竹取」「それは横笛も吹きなし―
めり/竹取」「それは横笛も吹きなし― めりかし/枕草子 218」
めりかし/枕草子 218」
 めり (連語)
〔断定の助動詞「なり」の連体形に推量の助動詞「めり」の付いたものの撥音便の形「なんめり」の撥音「ん」が表記されなかったもの〕
…であるとみえる。…であるようだ。「子となり給ふべき人―
めり (連語)
〔断定の助動詞「なり」の連体形に推量の助動詞「めり」の付いたものの撥音便の形「なんめり」の撥音「ん」が表記されなかったもの〕
…であるとみえる。…であるようだ。「子となり給ふべき人― めり/竹取」「それは横笛も吹きなし―
めり/竹取」「それは横笛も吹きなし― めりかし/枕草子 218」
めりかし/枕草子 218」
なめりかわ【滑川】🔗⭐🔉
なめりかわ ナメリカハ 【滑川】
富山県中部,富山湾に面する市。越中売薬で知られる製薬業や漁業が盛ん。沖合いはホタルイカ群遊海面。
なめ・る【滑る】🔗⭐🔉
なめ・る 【滑る】 (動ラ四)
ぬるりとすべる。なめらかである。「苔は―・りて足もたまらず/謡曲・石橋」
な・める【嘗める・舐める】🔗⭐🔉
な・める [2] 【嘗める・舐める】 (動マ下一)[文]マ下二 な・む
(1)物の表面を,舌の先で触れる。また,物を口の中にいれて舌の上でとかす。《舐》「猫が前足を―・める」「あめを―・める」
(2)少量ずつ味わいながら飲む。「酒をちびちび―・める」
(3)経験する。「世の辛酸を―・める」「苦杯を―・める」「苦汁を―・める」「甘露ヲ―・ムル/日葡」
(4)隈(クマ)なく及ぶ。「火は商店街を―・めつくした」「―・めるように見る」
(5)人を馬鹿にして無礼な態度をとる。あなどる。「相手を―・めてかかる」
〔(5)は「無礼(ナメ)」の動詞化〕
な-めん【名面】🔗⭐🔉
な-めん 【名面】
名前。名跡(ミヨウゼキ)。
なめんだら🔗⭐🔉
なめんだら (形動ナリ)
無秩序なさま。でたらめ。「畿内近国の勢馳せ集まつて,在々所々―に/御伽草子・鴉鷺合戦」
なめし【鞣皮】(和英)🔗⭐🔉
なめす【鞣す】(和英)🔗⭐🔉
なめす【鞣す】
tan.→英和
大辞林に「なめ」で始まるの検索結果 1-42。