複数辞典一括検索+![]()
![]()
べん【弁(瓣)】🔗⭐🔉
べん [1] 【弁(瓣)】
(1)花びら。花弁。「五―の椿」
(2)「弁膜」に同じ。
(3)管などを流れる気体や液体の出入りや流れの方向を調節する装置。バルブ。
べん【弁(辯)】🔗⭐🔉
べん [1] 【弁(辯)】
(1)話すこと。説明すること。また,話しぶり。「立候補の―」「気障(キザ)な―を揮(フル)ひながら/社会百面相(魯庵)」
(2)地方名のあとに付けて,その地方独特の言葉遣いであることを表す。「津軽―」
べん【便】🔗⭐🔉
べん [1] 【便】
■一■ (名・形動)[文]ナリ
都合のよいこと。便利なこと。また,そのさま。「交通の―がいい」「運輸頗る―なり/八十日間世界一周(忠之助)」
■二■ (名)
大便と小便。特に,大便をいう。「―の検査」
ベン Gottfried Benn
Gottfried Benn 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
ベン  Gottfried Benn
Gottfried Benn (1886-1956) ドイツの詩人・医師。表現主義から出発し,ニヒリズムの克服をめぐって変貌を重ねた。詩集「モルグ」「肉」「静力学的詩篇」,エッセー「プトレマイオス家の人々」,自伝「二重生活」など。
(1886-1956) ドイツの詩人・医師。表現主義から出発し,ニヒリズムの克服をめぐって変貌を重ねた。詩集「モルグ」「肉」「静力学的詩篇」,エッセー「プトレマイオス家の人々」,自伝「二重生活」など。
 Gottfried Benn
Gottfried Benn (1886-1956) ドイツの詩人・医師。表現主義から出発し,ニヒリズムの克服をめぐって変貌を重ねた。詩集「モルグ」「肉」「静力学的詩篇」,エッセー「プトレマイオス家の人々」,自伝「二重生活」など。
(1886-1956) ドイツの詩人・医師。表現主義から出発し,ニヒリズムの克服をめぐって変貌を重ねた。詩集「モルグ」「肉」「静力学的詩篇」,エッセー「プトレマイオス家の人々」,自伝「二重生活」など。
ベン John Venn
John Venn 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
べんあ【弁阿】🔗⭐🔉
べんあ 【弁阿】
⇒弁長(ベンチヨウ)
へん-あつ【変圧】🔗⭐🔉
へん-あつ [0] 【変圧】 (名)スル
圧力を変えること。特に,電圧を変えること。
べん-い【便衣】🔗⭐🔉
べん-い [1] 【便衣】
(中国で,式服・礼服などに対して)丈を短く袖を細くして動きやすくした服。普段着。平服。便服。
べんい-たい【便衣隊】🔗⭐🔉
べんい-たい [0] 【便衣隊】
日中戦争時,中国で平服を着て敵地に潜入し,各種の宣伝や暗殺・破壊・襲撃などを行なった中国人の特殊部隊。
べん-い【便意】🔗⭐🔉
べん-い [1] 【便意】
大便がしたくなる気持ち。「―を催す」
へん-いき【変域】🔗⭐🔉
へん-いき ― キ [0] 【変域】
関数で,変数のとり得る値の範囲。定義域。
キ [0] 【変域】
関数で,変数のとり得る値の範囲。定義域。
 キ [0] 【変域】
関数で,変数のとり得る値の範囲。定義域。
キ [0] 【変域】
関数で,変数のとり得る値の範囲。定義域。
へん-うるし【辺漆】🔗⭐🔉
へん-うるし [3] 【辺漆】
半夏(ハンゲ)から秋の彼岸ごろまでの約九〇日の間に採取した生漆(キウルシ)。初めの二〇日間のものを初辺,終わりの二〇日間のものを遅辺,中ほどのものを辺掻(ヘンカキ)または盛(サカ)り物・盛り辺と呼ぶ。
→辺掻
へん-うん【片雲】🔗⭐🔉
へん-うん [0] 【片雲】
ちぎれ雲。一片の雲。一かけらの雲。「―の風にさそはれて漂泊の思ひやまず/奥の細道」
へん-えい【片影】🔗⭐🔉
へん-えい [0] 【片影】
(1)物のわずかな影。姿のほんの一部分。
(2)人の性格などの一面。「父の―を伺わせる」
べん-えき【便益】🔗⭐🔉
べん-えき [0] 【便益】
便利で有益なこと。都合のよいこと。「―をはかる」「―施設」
べんえん【弁円】🔗⭐🔉
べんえん ベン ン 【弁円】
(1202-1280) 鎌倉時代の臨済宗の僧。諱(イミナ)は円爾(エンニ)。諡号(シゴウ)は聖一国師。駿河の人。1235年宋に渡り,帰国後は九州に禅法を広め,藤原道家の招きで上洛して東福寺開山となる。鎌倉の寿福寺,京都の建仁寺に歴住。東福寺派の祖。
ン 【弁円】
(1202-1280) 鎌倉時代の臨済宗の僧。諱(イミナ)は円爾(エンニ)。諡号(シゴウ)は聖一国師。駿河の人。1235年宋に渡り,帰国後は九州に禅法を広め,藤原道家の招きで上洛して東福寺開山となる。鎌倉の寿福寺,京都の建仁寺に歴住。東福寺派の祖。
 ン 【弁円】
(1202-1280) 鎌倉時代の臨済宗の僧。諱(イミナ)は円爾(エンニ)。諡号(シゴウ)は聖一国師。駿河の人。1235年宋に渡り,帰国後は九州に禅法を広め,藤原道家の招きで上洛して東福寺開山となる。鎌倉の寿福寺,京都の建仁寺に歴住。東福寺派の祖。
ン 【弁円】
(1202-1280) 鎌倉時代の臨済宗の僧。諱(イミナ)は円爾(エンニ)。諡号(シゴウ)は聖一国師。駿河の人。1235年宋に渡り,帰国後は九州に禅法を広め,藤原道家の招きで上洛して東福寺開山となる。鎌倉の寿福寺,京都の建仁寺に歴住。東福寺派の祖。
へんか-そしき【変化組織】🔗⭐🔉
へんか-そしき ―クワ― [4] 【変化組織】
三原組織を変化させたり組み合わせたりして作り出した織物組織。畝(ウネ)織り・斜子(ナナコ)織りなど。
へんか-りつ【変化率】🔗⭐🔉
へんか-りつ ―クワ― [3] 【変化率】
〔数〕
⇒微分係数(ビブンケイスウ)
べん-か【卞和】🔗⭐🔉
べん-か ―クワ 【卞和】
中国,戦国時代の楚の人。粗玉(アラタマ)を楚の山中に得, 王に献じたがただの石だとされて左足を切られ,次の武王には右足を切られた。文王が位につくと,和(カ)は粗玉を抱いて哭(コク)すること三日三晩。文王の問いに,疑われたことを悲しんでいるのだと答えた。文王は粗玉を磨かせてみると果たして立派な璧(タマ)であった。この璧を「和氏(カシ)の璧」といった。またのち,趙王がこの璧を所有し,秦の昭王が一五の城と交換しようと言ったので,「連城の璧」ともいう。
王に献じたがただの石だとされて左足を切られ,次の武王には右足を切られた。文王が位につくと,和(カ)は粗玉を抱いて哭(コク)すること三日三晩。文王の問いに,疑われたことを悲しんでいるのだと答えた。文王は粗玉を磨かせてみると果たして立派な璧(タマ)であった。この璧を「和氏(カシ)の璧」といった。またのち,趙王がこの璧を所有し,秦の昭王が一五の城と交換しようと言ったので,「連城の璧」ともいう。
 王に献じたがただの石だとされて左足を切られ,次の武王には右足を切られた。文王が位につくと,和(カ)は粗玉を抱いて哭(コク)すること三日三晩。文王の問いに,疑われたことを悲しんでいるのだと答えた。文王は粗玉を磨かせてみると果たして立派な璧(タマ)であった。この璧を「和氏(カシ)の璧」といった。またのち,趙王がこの璧を所有し,秦の昭王が一五の城と交換しようと言ったので,「連城の璧」ともいう。
王に献じたがただの石だとされて左足を切られ,次の武王には右足を切られた。文王が位につくと,和(カ)は粗玉を抱いて哭(コク)すること三日三晩。文王の問いに,疑われたことを悲しんでいるのだと答えた。文王は粗玉を磨かせてみると果たして立派な璧(タマ)であった。この璧を「和氏(カシ)の璧」といった。またのち,趙王がこの璧を所有し,秦の昭王が一五の城と交換しようと言ったので,「連城の璧」ともいう。
べん-が【 河】🔗⭐🔉
河】🔗⭐🔉
べん-が 【 河】
⇒通済渠(ツウサイキヨ)
河】
⇒通済渠(ツウサイキヨ)
 河】
⇒通済渠(ツウサイキヨ)
河】
⇒通済渠(ツウサイキヨ)
べん-かい【弁解】🔗⭐🔉
べん-かい [0] 【弁解】 (名)スル
言いわけをすること。言いわけ。「いまさら―してもはじまらない」「―の余地はない」
へん-かき【辺掻】🔗⭐🔉
へん-かき [0] 【辺掻】
辺漆(ヘンウルシ)のうち,七月半ばごろから九月初めごろまで,盛夏の四〇〜五〇日間に採取した最上品質の生漆(キウルシ)。盛(サカ)り物。盛り辺。
へんかく-かつよう【変格活用】🔗⭐🔉
へんかく-かつよう ―クワツ― [5] 【変格活用】
動詞の活用形式のうち,その語形変化が特殊あるいはやや特殊で,四(五)段活用・二段活用・一段活用と異なるもの。口語では,カ行(「来る」)・サ行(「する」)の二種があり,文語では,カ行(「来(ク)」)・サ行(「す」)・ナ行(「死ぬ・往(イ)ぬ」)・ラ行(「有り・居り・侍り・いまそがり」)の四種がある。
⇔正格活用
へんかく-けい【偏角計】🔗⭐🔉
へんかく-けい [0] 【偏角計】
地磁気の偏角を測定する装置。地理的子午線を天体観測から求めるための望遠鏡と磁針とを組み合わせたもの。
べん-がく【勉学】🔗⭐🔉
べん-がく [0] 【勉学】 (名)スル
学問に励むこと。熱心に学ぶこと。勉強。「―にいそしむ」
ベンガジ Benghazi
Benghazi 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
ベンガジ  Benghazi
Benghazi リビア北東部の地中海に臨む港湾都市。石油開発により発展。精油・食品工業が盛ん。
リビア北東部の地中海に臨む港湾都市。石油開発により発展。精油・食品工業が盛ん。
 Benghazi
Benghazi リビア北東部の地中海に臨む港湾都市。石油開発により発展。精油・食品工業が盛ん。
リビア北東部の地中海に臨む港湾都市。石油開発により発展。精油・食品工業が盛ん。
ベンガラ (オランダ) Bengala
(オランダ) Bengala 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
ベンガラ [0]  (オランダ) Bengala
(オランダ) Bengala (1)〔インドのベンガル地方で産したことから。「弁柄」「紅殻」とも書く〕
赤色顔料の一。酸化鉄(III)(Fe
(1)〔インドのベンガル地方で産したことから。「弁柄」「紅殻」とも書く〕
赤色顔料の一。酸化鉄(III)(Fe O
O )を主成分とし,着色力・耐久性が強い。塗料やガラス・金属板の研磨剤などに用いる。鉄丹。べにがら。
(2){(1)}のような暗く黄がかった赤色。
(3)「ベンガラ縞」の略。
)を主成分とし,着色力・耐久性が強い。塗料やガラス・金属板の研磨剤などに用いる。鉄丹。べにがら。
(2){(1)}のような暗く黄がかった赤色。
(3)「ベンガラ縞」の略。
 (オランダ) Bengala
(オランダ) Bengala (1)〔インドのベンガル地方で産したことから。「弁柄」「紅殻」とも書く〕
赤色顔料の一。酸化鉄(III)(Fe
(1)〔インドのベンガル地方で産したことから。「弁柄」「紅殻」とも書く〕
赤色顔料の一。酸化鉄(III)(Fe O
O )を主成分とし,着色力・耐久性が強い。塗料やガラス・金属板の研磨剤などに用いる。鉄丹。べにがら。
(2){(1)}のような暗く黄がかった赤色。
(3)「ベンガラ縞」の略。
)を主成分とし,着色力・耐久性が強い。塗料やガラス・金属板の研磨剤などに用いる。鉄丹。べにがら。
(2){(1)}のような暗く黄がかった赤色。
(3)「ベンガラ縞」の略。
ベンガラ-じま【―縞】🔗⭐🔉
ベンガラ-じま [0] 【―縞】
江戸時代,ベンガル地方から輸入した縞織物。また,それを模した織物。多くはたて縞で,綿あるいは綿と絹の交ぜ織り。ベンガラ。
ベンガラ-つむぎ【―紬】🔗⭐🔉
ベンガラ-つむぎ [5] 【―紬】
ベンガラ縞の紬。
ベンガラ-ぬり【―塗(り)】🔗⭐🔉
ベンガラ-ぬり [0] 【―塗(り)】
ベンガラを塗ること。また,塗った物。
ベンガル Bengal
Bengal 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
ベンガル  Bengal
Bengal (1)インド北東部,ガンジス川とブラマプトラ川下流のデルタ地帯。地味豊かで,ジュート・米の産が多い。インド独立に際し,東パキスタン(現在のバングラデシュ)とインド(ウエストベンガル州)とに分割。
(2)ネコの一品種。アメリカ原産。短毛種で毛質は光沢があり,大きくはっきりした斑を持つ。彫りの深い顔立ちと筋肉質の体にたくましい四肢が特徴。
(1)インド北東部,ガンジス川とブラマプトラ川下流のデルタ地帯。地味豊かで,ジュート・米の産が多い。インド独立に際し,東パキスタン(現在のバングラデシュ)とインド(ウエストベンガル州)とに分割。
(2)ネコの一品種。アメリカ原産。短毛種で毛質は光沢があり,大きくはっきりした斑を持つ。彫りの深い顔立ちと筋肉質の体にたくましい四肢が特徴。
 Bengal
Bengal (1)インド北東部,ガンジス川とブラマプトラ川下流のデルタ地帯。地味豊かで,ジュート・米の産が多い。インド独立に際し,東パキスタン(現在のバングラデシュ)とインド(ウエストベンガル州)とに分割。
(2)ネコの一品種。アメリカ原産。短毛種で毛質は光沢があり,大きくはっきりした斑を持つ。彫りの深い顔立ちと筋肉質の体にたくましい四肢が特徴。
(1)インド北東部,ガンジス川とブラマプトラ川下流のデルタ地帯。地味豊かで,ジュート・米の産が多い。インド独立に際し,東パキスタン(現在のバングラデシュ)とインド(ウエストベンガル州)とに分割。
(2)ネコの一品種。アメリカ原産。短毛種で毛質は光沢があり,大きくはっきりした斑を持つ。彫りの深い顔立ちと筋肉質の体にたくましい四肢が特徴。
ベンガル-ご【―語】🔗⭐🔉
ベンガル-ご [0] 【―語】
バングラデシュの公用語。インド-ヨーロッパ語族,インド-イラン語派に属す。
→ベンガル語[音声]
ベンガル-ぼだいじゅ【―菩提樹】🔗⭐🔉
ベンガル-ぼだいじゅ [6] 【―菩提樹】
バニヤンの和名。
ベンガル-やまねこ【―山猫】🔗⭐🔉
ベンガル-やまねこ [5] 【―山猫】
ネコ科の哺乳類。頭胴長60センチメートル内外。森林や丘陵地にすみ,鳥や小形の哺乳類を捕食する。アジア東南部に分布。ツシマヤマネコは本種の一亜種。
ベンガル-わん【―湾】🔗⭐🔉
ベンガル-わん 【―湾】
インド洋北東部,インド半島とインドシナ半島との間にある海域。
べん-かん【弁官】🔗⭐🔉
べん-かん ―クワン [0] 【弁官】
律令制において,太政官を構成する機構の一。太政官とその管轄下の諸官司・諸国とを結んでその行政指揮運営の実際をつかさどった。左弁官・右弁官に分かれ,それぞれ大中少の弁(おおともい)があった。おおともいのつかさ。
べん-かん【冕冠】🔗⭐🔉
べん-かん ―クワン [0] 【冕冠】
天子が儀礼の際にかぶる冠。珠玉をひもで連ねた冕旒(ベンリユウ)を前または前後に垂らした冕板(ベンバン)が,冠の頂にのる。玉冠。冕。
冕冠
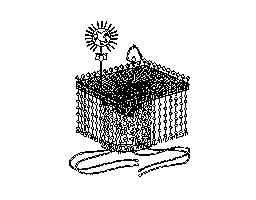 [図]
[図]
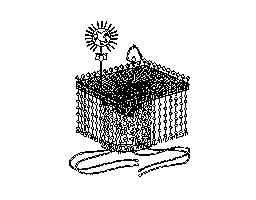 [図]
[図]
べん-き【抃喜】🔗⭐🔉
べん-き [1] 【抃喜】
手を打って喜ぶこと。非常に喜ぶこと。「―措く能はざるなり/日乗(荷風)」
べん-き【便器】🔗⭐🔉
べん-き [1] 【便器】
大小便をする器。おまる。おかわ。
べん-ぎ【便宜】🔗⭐🔉
べん-ぎ [1] 【便宜】 (名・形動)[文]ナリ
(1)都合のよいこと。便利のよいこと。また,そのさま。びんぎ。「菓子の類を売る者ありて頗る―なり/八十日間世界一周(忠之助)」
(2)その時々に応じたやり方。特別なはからい。「―をはかる」
べんぎ-さいりょう【便宜裁量】🔗⭐🔉
べんぎ-さいりょう ―リヤウ [4] 【便宜裁量】
裁量行為の際,一定の範囲内で行政庁の自由な判断が許されること。自由裁量。
⇔法規裁量
べんぎ-しゅぎ【便宜主義】🔗⭐🔉
べんぎ-しゅぎ [4] 【便宜主義】
根本的な処置をせず,その時々に応じた間に合わせで済ますやり方。
べんぎ-じょう【便宜上】🔗⭐🔉
べんぎ-じょう ―ジヤウ [0] 【便宜上】
そのほうが都合がよいという事情。
べんぎ-ちせきせん【便宜置籍船】🔗⭐🔉
べんぎ-ちせきせん [0] 【便宜置籍船】
船籍を実際の船主の国ではなく,税金や人件費節減などのために他の国に置いている船舶。置籍船。
べんぎ-てき【便宜的】🔗⭐🔉
べんぎ-てき [0] 【便宜的】 (形動)
ものごとを間に合わせに一時しのぎにするさま。「―な処置」
べん-きょう【勉強】🔗⭐🔉
べん-きょう ―キヤウ [0] 【勉強】 (名)スル
(1)学問や技芸を学ぶこと。学習。「―部屋」「おそくまで―している」
(2)ある目的のための修業や経験をすること。「何事も―だと思ってやってみる」
(3)(商人が)商品の値段を安くして売ること。「―しますのでお買い下さい」
(4)物事にはげむこと。努力すること。「職業に―する精神あること/西国立志編(正直)」
(5)気が進まないことをしかたなくすること。「―して櫓を揺しゐたれば/甲子夜話」
〔(4)が原義〕
べんきょう-か【勉強家】🔗⭐🔉
べんきょう-か ―キヤウ― [0] 【勉強家】
熱心に仕事・学業などにはげむ人。勉強人。
ベングリオン David Ben-Gurion
David Ben-Gurion 🔗⭐🔉
🔗⭐🔉
ベングリオン  David Ben-Gurion
David Ben-Gurion (1886-1973) イスラエルの政治家・シオニズム運動家。ポーランド生まれ。イスラエル共和国の独立を宣言し,初代首相兼国防相となった。
(1886-1973) イスラエルの政治家・シオニズム運動家。ポーランド生まれ。イスラエル共和国の独立を宣言し,初代首相兼国防相となった。
 David Ben-Gurion
David Ben-Gurion (1886-1973) イスラエルの政治家・シオニズム運動家。ポーランド生まれ。イスラエル共和国の独立を宣言し,初代首相兼国防相となった。
(1886-1973) イスラエルの政治家・シオニズム運動家。ポーランド生まれ。イスラエル共和国の独立を宣言し,初代首相兼国防相となった。
へんけい-きん【変形菌】🔗⭐🔉
へんけい-きん [0] 【変形菌】
菌類と原虫類の性質を備える植物界の一門。胞子は発芽してアメーバ状細胞を生じ,集合して運動性のある変形体となり,のちに胞子嚢(ノウ)または子実体を作る。ムラサキホコリカビ・ツノホコリカビなど。粘菌(ネンキン)。
へんけい-たい【変形体】🔗⭐🔉
へんけい-たい [0] 【変形体】
変形菌の生活体。細胞壁のない大きな原形質塊で,アメーバ運動や著しい原形質流動を行う。
べん-けい【鞭刑】🔗⭐🔉
べん-けい [0] 【鞭刑】
鞭(ムチ)で打つ刑罰。笞(チ)刑。
べんけい【弁慶】🔗⭐🔉
べんけい 【弁慶】
(1)(?-1189) 平安末・鎌倉初期の僧。「吾妻鏡」「義経記」などの伝えるところによれば,熊野の別当の子で比叡山西塔で修行し武蔵坊と称して武勇を好んだ。のち,源義経に仕えた。義経の奥州落ちに従い,安宅関,衣川の合戦などでの武勇は能・歌舞伎などに多く脚色された。
(2)〔弁慶が強かったところから〕
強いもの,強がる者のたとえ。「内―」
(3)〔弁慶が七つ道具を背負った姿,あるいは体中に矢を受けた姿になぞらえていう〕
竹筒に穴をあけ,その穴に勝手道具や団扇などを差すようにしたもの。また,花かんざしなどを差しておく藁(ワラ)を束ねたものにもいう。
(4)たいこもち。幇間(ホウカン)。「判官(キヤク)へいろ
 と讒(コミズ)をいうて,ほかへ導く―衆も有よし/洒落本・秘事真告」
(5)「弁慶縞」の略。
と讒(コミズ)をいうて,ほかへ導く―衆も有よし/洒落本・秘事真告」
(5)「弁慶縞」の略。

 と讒(コミズ)をいうて,ほかへ導く―衆も有よし/洒落本・秘事真告」
(5)「弁慶縞」の略。
と讒(コミズ)をいうて,ほかへ導く―衆も有よし/洒落本・秘事真告」
(5)「弁慶縞」の略。
べんけい-がに【弁慶蟹】🔗⭐🔉
べんけい-がに [3] 【弁慶蟹】
カニの一種。甲はほぼ四角形で幅約3センチメートル。鋏脚と甲の前半分は赤みがかるが残りは青黒色。河口付近の湿地などにすむ。本州中部以南に分布。
べんけい-じま【弁慶縞】🔗⭐🔉
べんけい-じま [0] 【弁慶縞】
縞柄の一。茶と紺など二色の色糸をたて・よこ双方に用いて同じ幅の碁盤模様に織ったもの。弁慶格子。弁慶。
→格子縞
べんけい-じょうし【弁慶上使】🔗⭐🔉
べんけい-じょうし ―ジヤウ― 【弁慶上使】
人形浄瑠璃「御所桜堀川夜討」三段目の切の通称。弁慶が義経の正妻京(卿)の君の首受け取りの上使となり,わが娘信夫(シノブ)を身代わりとする節。
べんけい-そう【弁慶草】🔗⭐🔉
べんけい-そう ―サウ [0] 【弁慶草】
ベンケイソウ科の多年草。山野に自生し,栽培もされる。全体に多肉質で白緑色。茎は高さ約50センチメートルで,楕円形の葉を対生。夏,茎頂に淡紅色の小花多数が散房状につく。古名イキクサ。[季]秋。《雨つよし―も土に伏し/杉田久女》
弁慶草
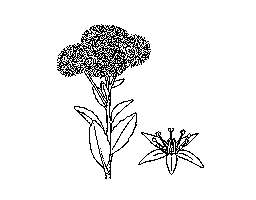 [図]
[図]
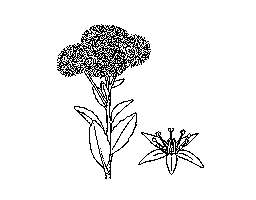 [図]
[図]
べんけい-そう-か【弁慶草科】🔗⭐🔉
べんけい-そう-か ―サウクワ [0] 【弁慶草科】
双子葉植物離弁花類の一科。世界に三五属一三〇〇種あり,ほとんど多年草。乾燥地帯や岩上に生育し,葉は多肉質でしばしば無性生殖を行う。コモチマンネングサ・イワレンゲ・ミセバヤ・カランコエなど。
べんけい【 京】🔗⭐🔉
京】🔗⭐🔉
べんけい 【 京】
中国,河南省開封(カイホウ)の古称。
京】
中国,河南省開封(カイホウ)の古称。
 京】
中国,河南省開封(カイホウ)の古称。
京】
中国,河南省開封(カイホウ)の古称。
べん-こ【便壺】🔗⭐🔉
べん-こ [1] 【便壺】
便器。
べん-ご【弁護】🔗⭐🔉
べん-ご [1] 【弁護】 (名)スル
その人のために申し開きをして,その立場を護ること。その人の利益となることを主張して助けること。「無実を信じて―(を)する」
べんご-し【弁護士】🔗⭐🔉
べんご-し [3] 【弁護士】
当事者その他関係人の依頼または官公署の委嘱によって,訴訟事件・非訟事件・行政庁に対する不服申し立て事件に関する行為,その他一般の法律事務を行うことを職務とする者。弁護士法に定める一定の資格を有し,日本弁護士連合会の備える弁護士名簿に登録されなければならない。
へんこう-けい【偏光計】🔗⭐🔉
へんこう-けい ―クワウ― [0] 【偏光計】
旋光性物質の旋光度を測る装置。ニコル-プリズムを用いたものなどがある。検糖計も偏光計の一種。
へんこう-し【偏光子】🔗⭐🔉
へんこう-し ―クワウ― [3] 【偏光子】
自然光を偏光に変える素子。結晶の複屈折を利用したニコル-プリズムや偏光板などが用いられる。
へんこう-めん【偏光面】🔗⭐🔉
へんこう-めん ―クワウ― [3] 【偏光面】
光波の進行方向と磁場ベクトルあるいは電場ベクトルの振動方向とを含む面。
べん-こう【弁口】🔗⭐🔉
べん-こう [0] 【弁口】
口のきき方。言い方。しゃべり方。また,口のきき方がうまいこと。
べん-こう【弁巧】🔗⭐🔉
べん-こう ―カウ [0] 【弁巧】
言い回しの巧みなこと。口先のうまいこと。「―に載せられて/鉄仮面(涙香)」
べんこう-ざい【弁甲材】🔗⭐🔉
べんこう-ざい ベンカフ― [3] 【弁甲材】
木造船用材。杉丸太を太鼓落としに削(ハツ)ったもの。宮崎県の飫肥(オビ)杉が有名。
へんこう-せい【変光星】🔗⭐🔉
へんこう-せい ヘンクワウ― [3][0] 【変光星】
みかけの明るさが変化する恒星。食変光星・脈動変光星・不規則変光星などがある。
へん-こく【辺国】🔗⭐🔉
へん-こく [0] 【辺国】
〔「へんごく」とも〕
都から遠く離れた地。辺地。
べん【弁】(和英)🔗⭐🔉
べん【便】(和英)🔗⭐🔉
べんい【便意を催す】(和英)🔗⭐🔉
べんい【便意を催す】
want to relieve oneself.
べんえき【便益】(和英)🔗⭐🔉
べんえき【便益】
⇒便宜.
べんかい【弁解】(和英)🔗⭐🔉
べんがく【勉学】(和英)🔗⭐🔉
べんがく【勉学】
⇒勉強.
べんき【便器】(和英)🔗⭐🔉
べんぎ【便宜】(和英)🔗⭐🔉
べんぎ【便宜】
a convenience;→英和
facilities(設備).〜を計る help;→英和
givefacilities.〜上 for convenience' sake.
べんきょう【勉強】(和英)🔗⭐🔉
べんきょう【勉強】
study;→英和
work;→英和
a lesson (課業).→英和
〜する study;work (hard);sellcheap (安く売る).‖勉強家 a hard worker.勉強部屋 a study.
べんけい【弁慶の泣き所】(和英)🔗⭐🔉
べんけい【弁慶の泣き所】
an Achilles' heel.弁慶縞 checks;<米>checkers.
べんけいそう【弁慶草】(和英)🔗⭐🔉
べんけいそう【弁慶草】
《植》an orpin(e).
べんご【弁護】(和英)🔗⭐🔉
大辞林に「べん」で始まるの検索結果 1-86。もっと読み込む