複数辞典一括検索+![]()
![]()
どう【堂】🔗⭐🔉
どう ダウ 【堂】
■一■ [1][0] (名)
(1)神仏をまつる建物。
(2)多くの人の集まる建物。
(3)客に接したり,礼楽を行なったりする所。正殿。
■二■ (接尾)
屋号・雅号,または建物の名などにつけて用いる。「静嘉―」「哲学―」
どう=に入(イ)・る🔗⭐🔉
――に入(イ)・る
〔「堂に升(ノボ)り室に入らず」から〕
学問や技術が奥深いところまで進んでいる。転じて,物事に習熟している。身についている。「―・った挨拶」
どう=に升(ノボ)り室(シツ)に入らず🔗⭐🔉
――に升(ノボ)り室(シツ)に入らず
〔「論語(先進)」。孔子が子路の学問について,建物には登ったがその奥にある部屋にはまだ入っていないと評したことから〕
学問や技芸は上達したが,いまだ奥義を究めていないことのたとえ。
どう-う【堂宇】🔗⭐🔉
どう-う ダウ― [1] 【堂宇】
〔「宇」はのきの意〕
堂の建物。
どう-おう【堂奥】🔗⭐🔉
どう-おう ダウアウ [0] 【堂奥】
(1)堂の奥まった所。
(2)学問・芸術などの奥深いところ。奥義。蘊奥(ウンノウ)。「―にはいる」
どう-か【堂下】🔗⭐🔉
どう-か ダウ― [1] 【堂下】
堂の下。
どうがしま-おんせん【堂ヶ島温泉】🔗⭐🔉
どうがしま-おんせん ダウガシマヲンセン 【堂ヶ島温泉】
(1)箱根七湯の一。神奈川県箱根町,早川沿いにある。食塩泉。
(2)静岡県賀茂郡西伊豆町堂ヶ島にある温泉。硫酸塩泉。
どう-こ【堂鼓】🔗⭐🔉
どう-こ ダウ― [1] 【堂鼓】
中国で,主に武劇に用いる太鼓の一種。四本足の台上にのせて棒で打ち鳴らす。唐鼓。
どう-ごう【堂号】🔗⭐🔉
どう-ごう ダウガウ [3] 【堂号】
「堂」のつく雅号・屋号など。
どう-ごもり【堂籠り】🔗⭐🔉
どう-ごもり ダウ― [3] 【堂籠り】
寺の堂にこもること。
どう-しき【胴敷・堂敷】🔗⭐🔉
どう-しき [0] ドウ― 【胴敷】 ・ ダウ― 【堂敷】
博打(バクチ)をやる座敷。ばくち場。ばくち宿。
どうじま【堂島】🔗⭐🔉
どうじま ダウジマ 【堂島】
(1)大阪市北区と福島区にまたがる堂島川北岸のビジネス地区。元禄年間(1688-1704)に新開,米市場が開かれ,その後幕府官許の市場として発展し,江戸時代の全国米相場の中心となった。
(2)「堂島下駄」の略。
どうじま-げた【堂島下駄】🔗⭐🔉
どうじま-げた ダウジマ― [4] 【堂島下駄】
くり歯の表付きの下駄。表を鉄鋲(テツビヨウ)で打ち付けたものもある。堂島。
堂島下駄
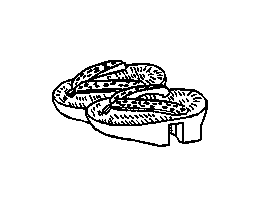 [図]
[図]
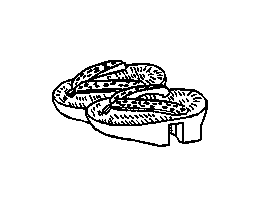 [図]
[図]
どうじま-べいこくとりひきじょ【堂島米穀取引所】🔗⭐🔉
どうじま-べいこくとりひきじょ ダウジマ― 【堂島米穀取引所】
1893年(明治26)大阪堂島に設立された米穀取引所。江戸時代以来栄えた米市場の後身で,1876年設立の大阪堂島米商会所が改称されたもの。1939年(昭和14)配給制度導入のため閉鎖。
どう-しゃ【堂舎】🔗⭐🔉
どう-しゃ ダウ― [1] 【堂舎】
〔「とうじゃ」「どうじゃ」とも。「堂」は大きな家,「舎」は小さな家〕
大小の建物。特に社寺の建物。「一山の―」
どう-しゅ【堂衆】🔗⭐🔉
どう-しゅ ダウ― [1][0] 【堂衆】
⇒どうしゅう(堂衆)
どう-しゅう【堂衆】🔗⭐🔉
どう-しゅう ダウ― [0] 【堂衆】
〔「どうしゅ」「どうじゅ」とも〕
(1)寺院内の諸堂において雑役にあたった下級の僧侶。「山上には―・学生不快の事いできて/平家 2」
(2)真宗の本山や別院で法儀をつとめた役僧。
どう-じょう【堂上】🔗⭐🔉
どう-じょう ダウジヤウ [0] 【堂上】
〔古くは「とうしょう」「どうしょう」とも〕
(1)昇殿を許された公卿・殿上人の総称。公家。堂上方。
⇔地下(ジゲ)
(2){(1)}の官人を出す家柄の総称。室町以降は摂家・清華・大臣家以外の公家の家格として狭義に用いることがあり,これを特に平堂上と呼ぶ。
(3)堂の上。「数万の軍旅は―堂下になみ居たれども/平家 6」
(4)清涼殿南廂の殿上の間に上ること。昇殿。「将軍―の後,帯刀の役人は皆中門の外に敷皮を布(シイ)て列居す/太平記 40」
どうじょう-かぞく【堂上華族】🔗⭐🔉
どうじょう-かぞく ダウジヤウクワ― [5] 【堂上華族】
明治維新後華族となったもののうち,もと公家の家柄のもの。
どうじょう-かた【堂上方】🔗⭐🔉
どうじょう-かた ダウジヤウ― [0] 【堂上方】
「堂上{(1)}」に同じ。
どうじょう-け【堂上家】🔗⭐🔉
どうじょう-け ダウジヤウ― [3] 【堂上家】
「堂上{(2)}」に同じ。
どうじょう-てん【堂上点】🔗⭐🔉
どうじょう-てん ダウジヤウ― [3] 【堂上点】
⇒博士家点(ハカセケテン)
どうじょう-は【堂上派】🔗⭐🔉
どうじょう-は ダウジヤウ― 【堂上派】
江戸時代の和歌の一派。二条家歌学を受け継いだ細川幽斎から古今伝授を受けた宮廷歌人の系統。智仁親王・中院通勝・烏丸光広・三条西実条・飛鳥井雅章など。
⇔地下(ジゲ)派
どうじょう-れんが【堂上連歌】🔗⭐🔉
どうじょう-れんが ダウジヤウ― [5] 【堂上連歌】
宮廷で行われた連歌。特に鎌倉・南北朝時代に宮廷貴族の間で行われたものをいう。
⇔地下(ジゲ)連歌
どう-たつ【堂達】🔗⭐🔉
どう-たつ ダウ― [0] 【堂達】
七僧の一。法会や受戒の際,導師に願文などを伝達する役僧。
どう-ちょう【堂頭】🔗⭐🔉
どう-ちょう ダウテウ [0] 【堂頭】
禅宗で,寺の住職。また,住職や長老の居所。方丈。どうとう。
どう-とう【堂塔】🔗⭐🔉
どう-とう ダウタフ [0] 【堂塔】
堂と塔。仏堂や仏塔など。
どうとう-がらん【堂塔伽藍】🔗⭐🔉
どうとう-がらん ダウタフ― [0] 【堂塔伽藍】
堂と塔と伽藍。寺院の中の建物の総称。
どう-とう【堂頭】🔗⭐🔉
どう-とう ダウ― [0] 【堂頭】
⇒どうちょう(堂頭)
どう-どう【堂堂】🔗⭐🔉
どう-どう ダウダウ [0][3] 【堂堂】 (ト|タル)[文]形動タリ
(1)いかめしく立派なさま。「威風―」「―たる偉容」「―の行進」
(2)恐れず立派に行うさま。「正々―」「―と意見を発表する」
(3)こそこそせず公然と行うさま。「白昼―と銀行に押し入る」
どうどう=の陣(ジン)🔗⭐🔉
――の陣(ジン)
〔孫子(軍争)〕
陣容が整い意気盛んな軍陣。
どう-どうじ【堂童子】🔗⭐🔉
どう-どうじ ダウ― 【堂童子】
(1)寺院で雑事に従事する年少のしもべ。「―とて俗なん入りて仏供・灯明奉る/今昔 11」
(2)宮中で法会などの行われる際,花籠(ケコ)を配る役の者。蔵人および五位以上の公家の子息の中から選ばれた。
どうどう-めぐり【堂堂巡り・堂堂回り】🔗⭐🔉
どうどう-めぐり ダウダウ― [5] 【堂堂巡り・堂堂回り】 (名)スル
(1)祈願のため,社寺の堂の周りをまわること。
(2)思考・議論などが同じことの繰り返しだけで少しも先へ進まないこと。「話し合いは―するばかりだ」
(3)国会などの議会の採決で,全議員が順々に演壇上にある投票箱に投票すること。
(4)遊戯の一。手をつなぎ丸い輪を作って一か所をぐるぐるまわるもの。
どうもと【堂本】🔗⭐🔉
どうもと ダウモト 【堂本】
姓氏の一。
どうもと-いんしょう【堂本印象】🔗⭐🔉
どうもと-いんしょう ダウモトインシヤウ 【堂本印象】
(1891-1975) 日本画家。京都生まれ。本名,三之助。伝統的日本画に近代的作風を吹き込み,戦後は抽象的な画風に転じた。
どう-もり【堂守(り)】🔗⭐🔉
どう-もり ダウ― [4] 【堂守(り)】
堂の番をすること。また,堂の番人。「―の小草ながめつ夏の月/蕪村句集」
どう【堂】(和英)🔗⭐🔉
どうどうめぐり【堂々巡りをする(議会で)】(和英)🔗⭐🔉
どうどうめぐり【堂々巡りをする(議会で)】
go (a)round for voting;(議論が) go round and round in circles.
大辞林に「堂」で始まるの検索結果 1-40。