複数辞典一括検索+![]()
![]()
うん【暈】🔗⭐🔉
うん [1] 【暈】
太陽や月の周囲に現れる輪状の光。大気の上層にある氷晶の細片が光線を屈折・反射するために生じる現象。ひがさ。かさ。
うん-げん【繧繝・暈繝】🔗⭐🔉
うん-げん [0] 【繧繝・暈繝】
ぼかしによらず,同系統の色を淡色から濃色に並列して色彩の濃淡の変化をあらわす彩色法。紅・青・緑・紫などの色を多く使う。朝鮮の古墳壁画などに見られ,奈良前期に日本に伝来,建築・工芸・仏画などに用いられた。繧繝彩色(ウンゲンザイシキ)。
うん-こう【暈光】🔗⭐🔉
うん-こう ―クワウ [0] 【暈光】
グロー放電の際に発する光。グロー。
うん-しょく【暈色】🔗⭐🔉
うん-しょく [0] 【暈色】
鉱物の表面に現れる虹(ニジ)のような色。多くは結晶面や劈開(ヘキカイ)面に沿って二次的にできた透明な薄膜によって生ずる。
かさ【暈】🔗⭐🔉
かさ [1] 【暈】
太陽・月の周囲にできる光の輪。巻層雲などの微細な氷晶からできた雲を通して太陽や月を見たときに現れる光の屈折現象。俗に風雨の前兆とされる。ハロー。うん。「月に―がかかる」
くま-どり【隈取り・暈取り】🔗⭐🔉
くま-どり [0][4] 【隈取り・暈取り】 (名)スル
(1)色をつけて,ある部分をきわ立たせること。「目のまわりを―する」
(2)日本画で,墨や色をぼかして,遠近・高低・凹凸などを表すこと。暈染(ウンゼン)。
(3)歌舞伎で,超人的な英雄や敵役,神仏の化身,鬼畜などの役柄を誇張するために施す独特の化粧法。紅・藍・墨・黛赭(タイシヤ)などの顔料を用いて顔を彩色する。筋隈・剥身(ムキミ)隈・一本隈・公家荒(クゲアレ)・猿隈などがある。
隈取り(3)=1
 [図]
隈取り(3)=2
[図]
隈取り(3)=2
 [図]
隈取り(3)=3
[図]
隈取り(3)=3
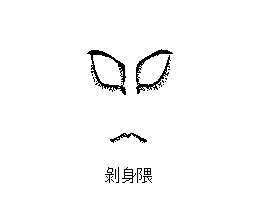 [図]
隈取り(3)=4
[図]
隈取り(3)=4
 [図]
[図]
 [図]
隈取り(3)=2
[図]
隈取り(3)=2
 [図]
隈取り(3)=3
[図]
隈取り(3)=3
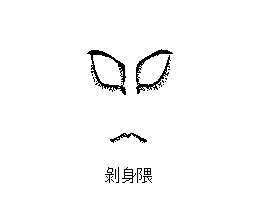 [図]
隈取り(3)=4
[図]
隈取り(3)=4
 [図]
[図]
くま-ど・る【隈取る・暈取る】🔗⭐🔉
くま-ど・る [3] 【隈取る・暈取る】 (動ラ五[四])
(1)絵画,特に日本画で,遠近・高低などを表すため,墨や絵の具でさかい目をぼかす。くまをとる。「山の端を―・る旭日の色/戸隠山紀行(美妙)」
(2)役者が役柄に応じて,くまどりをする。「―・って恐ろしい顔につくる」
ぼかし【暈し】🔗⭐🔉
ぼかし [3] 【暈し】
(1)ぼかすこと。
(2)日本画の技法。色を次第に濃くしたり薄くしたりして陰影をつけるもの。
ぼかし-ぞめ【暈し染(め)】🔗⭐🔉
ぼかし-ぞめ [0] 【暈し染(め)】
色を濃色から淡色へ,また隣り合う二つの色の境目をぼかして染める方法。曙(アケボノ)染め・裾濃(スソゴ)など。
ぼかし-ぬい【暈し繍】🔗⭐🔉
ぼかし-ぬい ―ヌヒ [0] 【暈し繍】
日本刺繍(シシユウ)の技法の一。ぼかしを針目の粗密や糸の濃淡によって表す方法。
ぼか・す【暈す】🔗⭐🔉
ぼか・す [2] 【暈す】 (動サ五[四])
(1)色の境目や輪郭をはっきりさせないようにする。
(2)話・内容などをはっきりさせないであいまいにする。「人数を―・す」
[可能] ぼかせる
ぼ・く【惚く・暈く】🔗⭐🔉
ぼ・ける【暈ける】🔗⭐🔉
ぼ・ける [2] 【暈ける】 (動カ下一)[文]カ下二 ぼ・く
〔「ぼける(惚)」と同源〕
色や形がはっきりしなくなる。ぼやける。「輪郭が―・ける」「ピントが―・ける」
ぼかし【暈し】(和英)🔗⭐🔉
ぼかし【暈し】
shading (off).
ぼかす【暈す】(和英)🔗⭐🔉
ぼかす【暈す】
shade off.態度を〜 take an ambiguous attitude.
大辞林に「暈」で始まるの検索結果 1-17。