複数辞典一括検索+![]()
![]()
広辞苑の検索結果 (17)
うん‐おう【暈滃】‥ヲウ🔗⭐🔉
うん‐おう【暈滃】‥ヲウ
(ウンノウと連声)ぼかし。
⇒うんおう‐しき【暈滃式】
うんおう‐しき【暈滃式】‥ヲウ‥🔗⭐🔉
うんおう‐しき【暈滃式】‥ヲウ‥
地図における地表の起伏の表現の仕方の一つで、等高線に直角に多数の細く短い線を描く方法。けば。↔暈渲式うんせんしき
暈滃式
 ⇒うん‐おう【暈滃】
⇒うん‐おう【暈滃】
 ⇒うん‐おう【暈滃】
⇒うん‐おう【暈滃】
うん‐げん【繧繝・暈繝】🔗⭐🔉
うん‐げん【繧繝・暈繝】
(古くはウゲンとも)同色系統の濃淡を段層的に表し、さらにこれと対比的な他の色調の濃淡を組み合わせることによって、一種の立体感や装飾的効果を生みだす彩色法。唐代の中国で完成、日本では奈良時代から平安時代にかけて仏像・仏画の彩色装飾、建築・工芸品の彩色文様や染織に応用され、独特の発達をとげた。
⇒うんげん‐くもがた【繧繝雲形】
⇒うんげん‐にしき【繧繝錦】
⇒うんげん‐ばし【繧繝端】
⇒うんげん‐べり【繧繝縁】
うん‐しょく【暈色】🔗⭐🔉
うん‐しょく【暈色】
鉱物の内部または表面に見られる虹のような色。虹色。
うん‐せん【暈渲】🔗⭐🔉
うん‐せん【暈渲】
(「渲」は淡墨のぼかし)ぼかし。くまどり。
⇒うんせん‐しき【暈渲式】
うんせん‐しき【暈渲式】🔗⭐🔉
うんせん‐しき【暈渲式】
地図における地表起伏の表現の仕方の一つで、地表の高低を彩色の濃淡で表す方法。直照光線式と斜照光線式とがある。ぼかし。↔暈滃式うんおうしき
暈渲式
 ⇒うん‐せん【暈渲】
⇒うん‐せん【暈渲】
 ⇒うん‐せん【暈渲】
⇒うん‐せん【暈渲】
うん‐のう【暈滃】‥ヲウ🔗⭐🔉
うん‐のう【暈滃】‥ヲウ
⇒うんおう
かさ【暈】🔗⭐🔉
かさ【暈】
〔天〕(halo)太陽または月の周囲に見える光の輪。光が、微細な氷の結晶から成る雲で反射・屈折を受ける結果生じる。広義には光冠をも含む。うん(暈)。光環。ハロー。「月に―がかかる」
暈
撮影:高橋健司


くま‐どり【隈取り・暈取り】🔗⭐🔉
くま‐どり【隈取り・暈取り】
①くまどること。彩色を加え、ぼかすこと。
②絵画で、遠近・高低・凹凸などを表現するため、墨や彩色の濃淡によってぼかしを加えること。
③歌舞伎や中国の京劇などにおける特殊な化粧法。正義・悪・超人的な力などをもつ役柄を強調するため、紅・青・墨などの絵具で一定の型に顔面を彩色すること。→隈くま(図)。
⇒くまどり‐ふで【隈取り筆】
くま‐ど・る【隈取る・暈取る】🔗⭐🔉
くま‐ど・る【隈取る・暈取る】
〔他五〕
①彩色で濃淡をつける。境目をぼかす。為兼集「雲の色は―・る墨の移し絵に」
②顔を紅・墨などでいろどる。特に、俳優が顔の隈取りをする。浄瑠璃、源平布引滝「つらを―・り隠せしは」
ぼかし【暈し】🔗⭐🔉
ぼかし【暈し】
①ぼかすこと。ぼかしたもの。
②ある色が濃から淡へと次第に変化してゆくように描く絵画の技法。隈取くまどりの一種。
⇒ぼかし‐ぞめ【暈し染め】
⇒ぼかし‐ぬい【暈し繍い】
ぼかし‐ぞめ【暈し染め】🔗⭐🔉
ぼかし‐ぞめ【暈し染め】
地色の一部をぼかして染めること。
⇒ぼかし【暈し】
ぼかし‐ぬい【暈し繍い】‥ヌヒ🔗⭐🔉
ぼかし‐ぬい【暈し繍い】‥ヌヒ
刺繍ししゅうで、針目の粗密・長短などにより、または種々の色糸を用いて濃淡をつける方法。
⇒ぼかし【暈し】
ぼか・す【暈す】🔗⭐🔉
ぼか・す【暈す】
〔他五〕
①色の濃淡のさかい目をはっきりさせないで、だんだんに淡くする。「輪郭を―・す」
②表現をあいまいにして、内容をぼんやりとさせる。ぼやかす。「要点を―・していう」
ぼ・ける【惚ける・呆ける・暈ける】🔗⭐🔉
ぼ・ける【惚ける・呆ける・暈ける】
〔自下一〕
(ホケルの転)
①頭の働きや感覚などがにぶくなる。ぼんやりする。もうろくする。「年のせいで―・ける」
②(「暈ける」と書く)色が薄れてはっきりしなくなる。色がさめる。また、物の輪郭がぼやける。「ピントが―・ける」「論点が―・ける」
[漢]暈🔗⭐🔉
暈 字形
 〔日(曰)部9画/13画/5884・5A74〕
〔音〕ウン(呉)(漢)
〔訓〕かさ・ぼかす
[意味]
①日・月・灯火の周囲にうすく現れる光の輪。かさ。「月暈・日暈」
②ぼかし。日・月のかさのように、周辺に向かってしだいに色をぼかす。「暈繝うんげん」
③目がまわる。めまい。「眩暈げんうん」
〔日(曰)部9画/13画/5884・5A74〕
〔音〕ウン(呉)(漢)
〔訓〕かさ・ぼかす
[意味]
①日・月・灯火の周囲にうすく現れる光の輪。かさ。「月暈・日暈」
②ぼかし。日・月のかさのように、周辺に向かってしだいに色をぼかす。「暈繝うんげん」
③目がまわる。めまい。「眩暈げんうん」
 〔日(曰)部9画/13画/5884・5A74〕
〔音〕ウン(呉)(漢)
〔訓〕かさ・ぼかす
[意味]
①日・月・灯火の周囲にうすく現れる光の輪。かさ。「月暈・日暈」
②ぼかし。日・月のかさのように、周辺に向かってしだいに色をぼかす。「暈繝うんげん」
③目がまわる。めまい。「眩暈げんうん」
〔日(曰)部9画/13画/5884・5A74〕
〔音〕ウン(呉)(漢)
〔訓〕かさ・ぼかす
[意味]
①日・月・灯火の周囲にうすく現れる光の輪。かさ。「月暈・日暈」
②ぼかし。日・月のかさのように、周辺に向かってしだいに色をぼかす。「暈繝うんげん」
③目がまわる。めまい。「眩暈げんうん」
大辞林の検索結果 (17)
うん【暈】🔗⭐🔉
うん [1] 【暈】
太陽や月の周囲に現れる輪状の光。大気の上層にある氷晶の細片が光線を屈折・反射するために生じる現象。ひがさ。かさ。
うん-げん【繧繝・暈繝】🔗⭐🔉
うん-げん [0] 【繧繝・暈繝】
ぼかしによらず,同系統の色を淡色から濃色に並列して色彩の濃淡の変化をあらわす彩色法。紅・青・緑・紫などの色を多く使う。朝鮮の古墳壁画などに見られ,奈良前期に日本に伝来,建築・工芸・仏画などに用いられた。繧繝彩色(ウンゲンザイシキ)。
うん-こう【暈光】🔗⭐🔉
うん-こう ―クワウ [0] 【暈光】
グロー放電の際に発する光。グロー。
うん-しょく【暈色】🔗⭐🔉
うん-しょく [0] 【暈色】
鉱物の表面に現れる虹(ニジ)のような色。多くは結晶面や劈開(ヘキカイ)面に沿って二次的にできた透明な薄膜によって生ずる。
かさ【暈】🔗⭐🔉
かさ [1] 【暈】
太陽・月の周囲にできる光の輪。巻層雲などの微細な氷晶からできた雲を通して太陽や月を見たときに現れる光の屈折現象。俗に風雨の前兆とされる。ハロー。うん。「月に―がかかる」
くま-どり【隈取り・暈取り】🔗⭐🔉
くま-どり [0][4] 【隈取り・暈取り】 (名)スル
(1)色をつけて,ある部分をきわ立たせること。「目のまわりを―する」
(2)日本画で,墨や色をぼかして,遠近・高低・凹凸などを表すこと。暈染(ウンゼン)。
(3)歌舞伎で,超人的な英雄や敵役,神仏の化身,鬼畜などの役柄を誇張するために施す独特の化粧法。紅・藍・墨・黛赭(タイシヤ)などの顔料を用いて顔を彩色する。筋隈・剥身(ムキミ)隈・一本隈・公家荒(クゲアレ)・猿隈などがある。
隈取り(3)=1
 [図]
隈取り(3)=2
[図]
隈取り(3)=2
 [図]
隈取り(3)=3
[図]
隈取り(3)=3
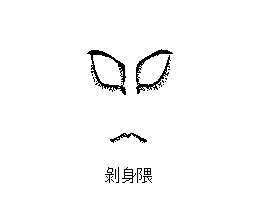 [図]
隈取り(3)=4
[図]
隈取り(3)=4
 [図]
[図]
 [図]
隈取り(3)=2
[図]
隈取り(3)=2
 [図]
隈取り(3)=3
[図]
隈取り(3)=3
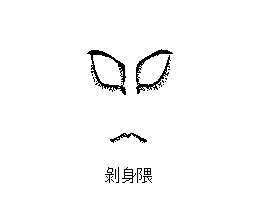 [図]
隈取り(3)=4
[図]
隈取り(3)=4
 [図]
[図]
くま-ど・る【隈取る・暈取る】🔗⭐🔉
くま-ど・る [3] 【隈取る・暈取る】 (動ラ五[四])
(1)絵画,特に日本画で,遠近・高低などを表すため,墨や絵の具でさかい目をぼかす。くまをとる。「山の端を―・る旭日の色/戸隠山紀行(美妙)」
(2)役者が役柄に応じて,くまどりをする。「―・って恐ろしい顔につくる」
ぼかし【暈し】🔗⭐🔉
ぼかし [3] 【暈し】
(1)ぼかすこと。
(2)日本画の技法。色を次第に濃くしたり薄くしたりして陰影をつけるもの。
ぼかし-ぞめ【暈し染(め)】🔗⭐🔉
ぼかし-ぞめ [0] 【暈し染(め)】
色を濃色から淡色へ,また隣り合う二つの色の境目をぼかして染める方法。曙(アケボノ)染め・裾濃(スソゴ)など。
ぼかし-ぬい【暈し繍】🔗⭐🔉
ぼかし-ぬい ―ヌヒ [0] 【暈し繍】
日本刺繍(シシユウ)の技法の一。ぼかしを針目の粗密や糸の濃淡によって表す方法。
ぼか・す【暈す】🔗⭐🔉
ぼか・す [2] 【暈す】 (動サ五[四])
(1)色の境目や輪郭をはっきりさせないようにする。
(2)話・内容などをはっきりさせないであいまいにする。「人数を―・す」
[可能] ぼかせる
ぼ・く【惚く・暈く】🔗⭐🔉
ぼ・ける【暈ける】🔗⭐🔉
ぼ・ける [2] 【暈ける】 (動カ下一)[文]カ下二 ぼ・く
〔「ぼける(惚)」と同源〕
色や形がはっきりしなくなる。ぼやける。「輪郭が―・ける」「ピントが―・ける」
ぼかし【暈し】(和英)🔗⭐🔉
ぼかし【暈し】
shading (off).
ぼかす【暈す】(和英)🔗⭐🔉
ぼかす【暈す】
shade off.態度を〜 take an ambiguous attitude.
広辞苑+大辞林に「暈」で始まるの検索結果。