複数辞典一括検索+![]()
![]()
いかり【錨・碇】🔗⭐🔉
いかり [0] 【錨・碇】
〔海中の石を意味する古語「いくり」と同源か〕
(1)綱や鎖をつけて水底に投下し,これによって船をその場所に停止させておく船具。古代から中世には石または石と木を組み合わせた木碇を使ったが,近世以後,鉄製となる。
(2)緒の端につけるいかり形の器具。物にかけて引き寄せたり,つなぎとめたりするのに用いる。「―の緒/枕草子 89」
(3)家紋の一。{(1)}を図案化したもの。
いかり-そう【碇草】🔗⭐🔉
いかり-そう ―サウ [0] 【碇草】
メギ科の多年草。山地に自生する。高さ約30センチメートル。葉は複葉。春,碇の形に似た淡紫色の四弁の花を下向きにつける。茎や葉を干して強壮・強精薬とする。
碇草
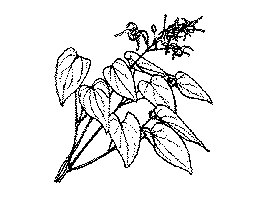 [図]
[図]
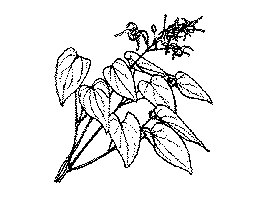 [図]
[図]
いかり-づな【碇綱】🔗⭐🔉
いかり-づな [3] 【碇綱】
碇を船に結びつける綱。苧綱(カラムシヅナ)が主に用いられた。
いかり-てんま【碇伝馬】🔗⭐🔉
いかり-てんま [4] 【碇伝馬】
端舟(ハシブネ)の一。碇の上げ下げのときに使用される小舟。
いかり-なわ【碇縄】🔗⭐🔉
いかり-なわ ―ナハ [3] 【碇縄】
「碇綱(イカリヅナ)」に同じ。「苦し」「いかで」を言い出すための序詞としても用いる。「沖つ島とまる小舟の―/新続古今(恋五)」
いかり-ぼうふう【碇防風】🔗⭐🔉
いかり-ぼうふう ―バウ― [4] 【碇防風】
ハマボウフウの茎の端を裂いて碇の形に似せたもの。刺身のつまにする。
いかり-ぼし【錨星・碇星】🔗⭐🔉
いかり-ぼし [3] 【錨星・碇星】
カシオペア座の W 形の五星を碇に見たてた和名。瀬戸内海地方から東北地方にかけて分布する呼称。山形星。
いかり-もり【碇銛】🔗⭐🔉
いかり-もり [3] 【碇銛】
捕鯨に用いる銛の一種。先の左右に突起があって碇のように見える。
いかりがせき【碇ヶ関】🔗⭐🔉
いかりがせき 【碇ヶ関】
青森県南部,南津軽郡の村。津軽三関の一つである碇ヶ関,食塩泉の碇ヶ関温泉がある。
いかりとももり【碇知盛】🔗⭐🔉
いかりとももり 【碇知盛】
人形浄瑠璃「義経千本桜」二段目の通称。渡海屋銀平に身をやつした平知盛が義経を討とうとするが果たせず,碇綱を体に巻きつけ岩の上から入水する豪快悲壮な場面。
てい-はく【停泊・碇泊】🔗⭐🔉
てい-はく [0] 【停泊・碇泊】 (名)スル
船が碇(イカリ)をおろしてとまること。ふながかり。
大辞林に「碇」で始まるの検索結果 1-11。